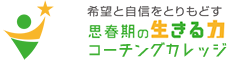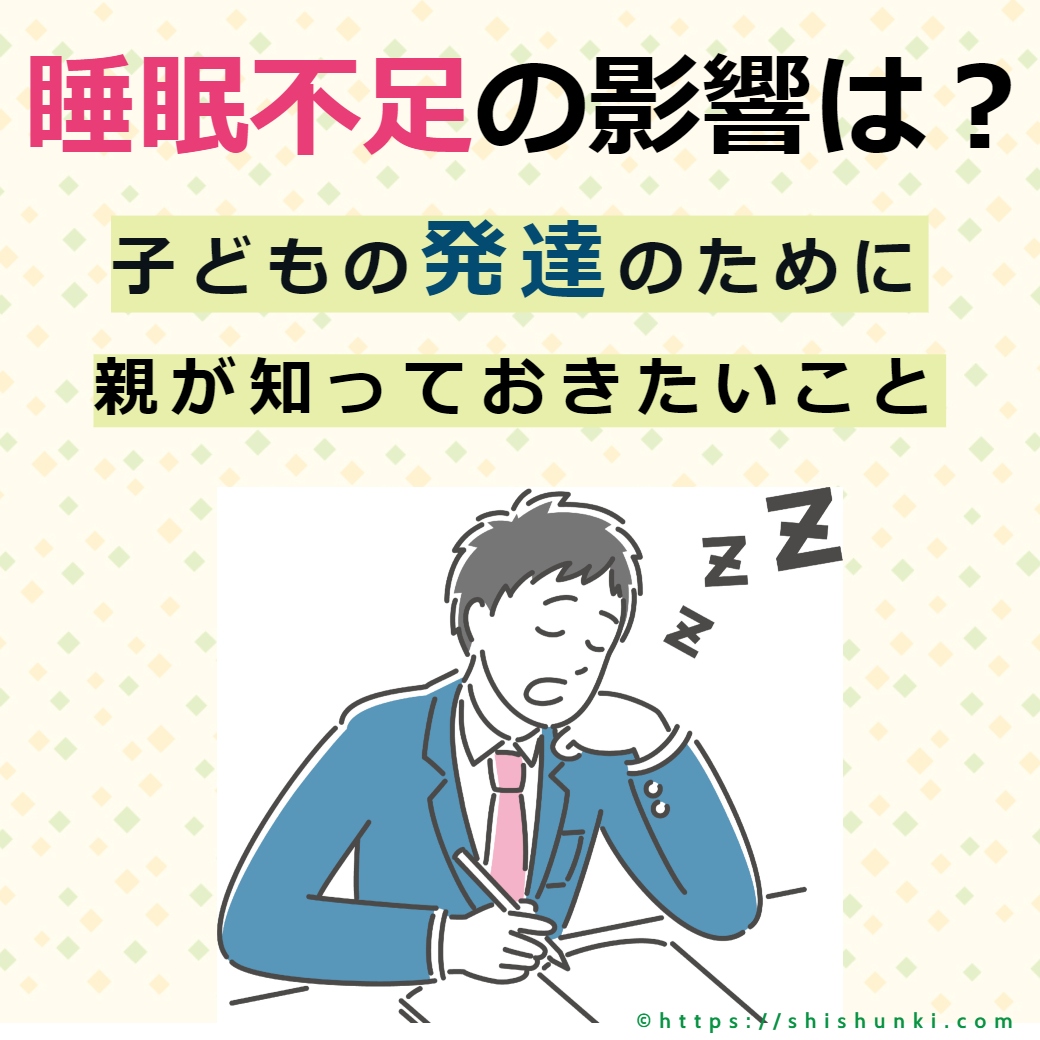同じ失敗を繰り返す子:親のNG対応、効果的な対応

同じ失敗を繰り返す子どもには、どう対応していますか?
親だってついイライラして「何度言ったらわかるの?」と言いたくなりますが、実際には、その言葉を繰り返しても改善には繋がらないのでもったいないですね。
そんな時にNG対応と効果的な対応を知っていると、無駄なイライラ時間を減らせます 🙂
学校に行く時もそうですし、友達と遊びに行く時にも遅刻が多いんです。
「もっと早くから準備しなさい」と口を酸っぱく言っても治りません
あまり遅刻が多いと、相手から信頼されなくなるのがもったいないですね。
ママ友のお子さんは、小さい頃から忘れ物が多くて、それも何度注意しても変わらないそうです。
そのママ友とも、子どもが同じ失敗を繰り返すのがなぜなのか、全くわからないね、と話してます。
同じ失敗を繰り返されると、「また⁉ 👿 👿 」と言いたくなりますよね。
特に思春期の子どもに多いのが、「時間に間に合わない」「忘れ物」「勉強を計画的にできない」という失敗を繰り返すことです。
結果として「遅刻」「困る、叱られる、他者に借りる」「成績上がらず」で、本人にも周りにもまずい影響が及んでしまいます。
一方では「もういい加減にして」とイライラする自分もいるので
時によって対応もバラバラで、自分でもまずいな~とは思ってるんですが、どうしたら良いのかわからないんです 🙁
子どもが自分の失敗経験から学んでくれれば一番いいですね。
それを待てる親の余裕も必要です。
ただ、いつもどの子でもそれができるか・・というと、現実では、ただ見守っている・待っているだけではどんどん失敗が続くだけになるケースもそれなりにあります。
親がただ待っていることで状況が悪化したり、子どもの自己肯定感が下がって改善の意欲まで失われてしまうのでは残念です。
子どもが同じ失敗を繰り返す時にも、その子なりのワケがあります。
そのワケを紐解いてみると、今どう対応したらいいのかが見えてきます
では「同じ失敗を繰り返す」時のワケと親の対応について、ご一緒に見てみましょう 🙂
目次
同じ失敗を繰り返す時に、子どもの中で起きていること
子どもが同じ失敗を繰り返す時に起きていることの最も多い5つです。
同じ失敗を繰り返す時に起きていること
ⅰ やることの重要性や必要性を感じてないのであれば、改善しようとするモチベーション不足です。
失敗による影響をあまり深く捉えてないので、「そんなに大したことじゃない」と捉えているので、改善しようとはしない状態です。
失敗の影響とメリット/デメリットがはっきりと分かる事が必要です。
ⅱ 自分ができてないとは認めてないなら、改善しようとはしませんね
今の状態で困ってないとか、本当はやる気になればできるとか、他の人や物事のせいだと、本人なりの言い訳があります。
今の状態が「失敗」だという理解と、失敗を繰り返すことのリスクが分かることが必要です。
また、失敗を重く捉えすぎたり、怒られるのが怖すぎて、失敗に向き合えない、認められないこともあります。
失敗の捉え方をリフォームしたり、安心できるコミュニケーションで関わることが必要です。
ⅲ やり方が分からないパターンは結構多いです。
誰でも「今のままだとまずい」と感じていても、代わりに何をしたら良いのかが、具体的にわかってないと代えられないものです。
抽象的なアドバイスが役に立たないことが多いのと同じです。
 また、「やり方」だけを指示されても、それがその子に合ってなかったり、なぜそのやり方が良いのかがわかってないと、応用が効かないので続きません。
また、「やり方」だけを指示されても、それがその子に合ってなかったり、なぜそのやり方が良いのかがわかってないと、応用が効かないので続きません。
例えば勉強方法も、お父さんや上の子には効果的だったやり方が、下の子にも同じように有効だとは限らないのです。
その子に合う勉強方法を見つけたことで、成績が2段階もアップしたという事例もたくさんあります。
その子に合う具体的な方法を、その子が見つけられるように関わることが必要です。
ⅳ 失敗の後、とりあえず謝ったので終わりにしている子は、それ以降改善を考えることがないので、同じ失敗を繰り返すことになります。
自己肯定感が低過ぎたり、怒られるのが怖い子は、「とりあえず今のこの場を凌ぐこと」に精一杯になるからです。
安心できるコミュニケーションで対応したり、自己肯定感を育てることが必要です。
ⅴ 落ち込むけど反省はしないパターンには要注意です。
 シュンとしているから反省しているのかと思っていても、本人は「自分はだめだ」とか「なんで失敗したんだろう」とぐるぐるしているだけのこともあるからです。
シュンとしているから反省しているのかと思っていても、本人は「自分はだめだ」とか「なんで失敗したんだろう」とぐるぐるしているだけのこともあるからです。
「どうせ私は全部ダメですよ」とキレるのも、このパターンの変形です。
いくら落ち込んで自分を責めてもキレても、次の行動が変わらなければ失敗が減ることはないのです。
失敗を重大なこととして捉えずに、失敗の中にある失敗要因と成功要因を分けて捉えられるようになる必要があります。
同じ「失敗を繰り返す」でも、それぞれ必要な対応って違うんですね
親のNG対応には気をつけて!
上記のの「同じ失敗を繰り返す時に、子どもの中で起きていること」がわかると、以下の対応がNGなことがよくわかります。
子どもに何度も同じ失敗をされたら、親だってカリカリします。
 ただ、その勢いのまま子どもに何かを言ったら、子どもは言葉の内容の前に、声のトーンや表情の方に先に反応します。
ただ、その勢いのまま子どもに何かを言ったら、子どもは言葉の内容の前に、声のトーンや表情の方に先に反応します。
「攻撃された」と感じれば、本能的に身構えるので、言葉が中に入っていきづらくなってしまいます。
また、人は感情的に来られれば、自分も感情的な反応が先に起こります。
子どもも感情的になり、更にそれに反応して親も感情的になり・・・という、かなり残念なパターンになってしまうのです
(T_T)
感情を抑えられない時には、一度タイムを取って落ち着いてからで大丈夫です。
その方がずっとお互いによいコミュニケーションができるようになります
(^^)
Ⅱ抽象的にアドバイスするのは、あまり望む結果につながりません。
例えば子育てで「もっと子どもに寄り添って」と言われても、具体的にどうしたら良いのかわからないのと同じです。
分からなければ自分で工夫することになりますが、NGの「甘やかす」「言いなりになる」との違いもわからないこともありますね。
 そうなると知らぬ間にそちらに偏ってしまって、より状況を悪化しまうことも珍しくないのと同じです。:-|
そうなると知らぬ間にそちらに偏ってしまって、より状況を悪化しまうことも珍しくないのと同じです。:-|
Ⅲ行動だけ指示するのも、長い目で見れば、失敗を繰り返すことから抜け出せる確立も低くなります。
誰かから適切な行動を教えてもらうだけでは、自分で応用が効かないからです。
また、思春期の子は特に納得感が大事ですし、行動だけ指示されるのは「コントロールされている」と強く反発します。
大事なのはその子が自分でその行動を導き出せるようになることなので、親としては失敗から改善策を子どもが見つけられるように関わるのがおすすめです。
Ⅳ人格否定や脅しを使うと、子どもの成長を妨げてしまいます。
人格否定「怠け者」「ルーズ」は、子どもの自己肯定感を下げるだけになりますので、いちばん大事な「やる気」が失われてしまいます。
「どうせ」という口癖の子には要注意です。
 また、「~~しないと✕✕になるよ」というのは、恐怖で人を動かそうとする脅しになります。
また、「~~しないと✕✕になるよ」というのは、恐怖で人を動かそうとする脅しになります。
親としては「そうならないようにね」と言うメッセージのつもりでも、相手にはその応援の気持が伝わりにくいのです。
脅されれば、嫌な結末を避けようとその時は行動するかもしれませんが、✕✕という嫌なイメージがそのことと一緒に記憶されてしまいます。
長い目で見れば、その行動をするのが億劫になることさえあります。
特に怖がり・慎重な子には気をつけたい言い回しです。
どうせなら、「~~すれば〇〇になるよ」と、良い未来やメリットを伝えるほうが効果的です。
Ⅴ他の子と比べるのは、子ども、特に思春期の子どもには最も嫌がられます。
ただでさて、勉強や部活/習い事であれこれ順位をつけられることの多い時期です。
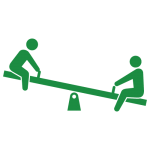 さらに思春期には同級生と自分を比べることで、自分を把握しようとする本能もあります。
さらに思春期には同級生と自分を比べることで、自分を把握しようとする本能もあります。
既に十分に比較したりされたりして、ほとんどの場合には自分がイマイチだと思っていることにばかり、自分で注目しているのが思春期です。
さらに他者からダメ出しのように他人と比べられるのはかなりヘビーです。
それよりも、その子個人として、「ここを改善するともっと良くなる」、「自由にやれる力が増える」などと、成長やメリットを表現するほうがずっと効果的です
(^^)
それに「行動の指示」が多かったかも。
自分の方にも気をつけるポイントがあると今分かってよかったです
はい、私もまさにそうでした
(^^)>
自分のコミュニケーションパターンを変えた時に、子どもの反応が変わったのでびっくりしちゃいました
同じ失敗を繰り返す子に必要な3つの対応と順番
では次に、同じ失敗を繰り返す子への対応について、具体的に見てみましょう!
先程の「同じ失敗を繰り返す時に、子どもの中で起きていること」の中身を分類すると、大きく3つに分けられます。
子どもが同じ失敗を繰り返すことから抜け出すチェックポイント
(1)失敗に向き合えるような状態を作る
(2)同じ失敗の繰り返しから抜け出そうとするモチベーションを呼び覚ます
(3)具体的な失敗から抜け出す方法を見つける
そしてこのチェックするポイントの順番も大事です。
(1)→(2)→(3)の順になります。
失敗に向き合えないなら、そもそも同しようもないですね。
そして失敗したとわかってても、改善にやる気がなければ、改善する方法を考えさせようとしてもやらないでしょう 🙄
そうなんです 🙂
この3つを分けて対応しないと、いくら頑張っても結果がでなくてがっかりしちゃいます。
3つの順番で整えていくと、うんとスムーズに運びます
現実を変えるのは、最終的には行動です。
いくら何十時間、もんもんと考えていても、現実は変わりません。
そして行動の原動力はモチベーション=気持ちです。
 「変わろう」「変わらなくちゃ」と思った時に、人は新しい行動をします。
「変わろう」「変わらなくちゃ」と思った時に、人は新しい行動をします。
そして「変わろう」と思うには、現状に向き合うことが必要なのです。
現実を把握する → 変えようと思う → 行動する
この順番でチェックしてみれば、どこに詰まりがあるのかわかります。
そうすれば、順に必要な対応をすることができるので、改善がスムーズに進みます
(^^)/
よくあるNG対応は、(1)(2)を抜かして(3)の方法だけを、行動の指示ですることです。
それだと同じ失敗を繰り返す時に、子どもの中で起きていることの全てが置き去りになってしまうので、頑張っても状況が変わらないままになったり、その時だけの改善で終わってしまったりになりますので、気をつけたいポイントです。
(1)子どもが失敗に向き合えるような状態を作る
「失敗に向き合う」というのは、自分の失敗だ、と一つの事実として受け止めて、その内容について意識を向けることです。
 「向き合えない」は失敗が起きていることや、その内容に意識を向けることさえできない状態のことです。
「向き合えない」は失敗が起きていることや、その内容に意識を向けることさえできない状態のことです。
子どもが失敗に向き合えないパターンには以下の3つのパターンがあります。
もともと慎重で怒られることが怖かったり、感情的に怒られた経験が多いか強くあった場合には、このパターンになります。
「失敗とした」と認めると怒られることになると思えば、その土俵に上がりたくない無意識が抵抗します。
 時には反射的に怒られるのを避けようと「謝る」「キレる」こともありますが、その場合には自分の失敗そのものを振り返る余裕はありません :-
時には反射的に怒られるのを避けようと「謝る」「キレる」こともありますが、その場合には自分の失敗そのものを振り返る余裕はありません :-
やたら自分のせいじゃないと言い張ったり、 その話になると黙り込んで動かなくなるような場合も、このパターンの可能性もあります。
このパターンでは、とにかく安心させるコミュニケーションが必要です。
もしこのパターンに強くハマっている時には、信頼関係から築き直すことが必要なこともあります。
◎親が落ち着いた状態で話す
◎子どもの言い分を最後まで聞き、それに沿った話を進める
◎子どもを応援している気持ちが伝わるコミュニケーション
(YES,and など)
◎日頃からマイナスなことについても、落ち着いて話せるような関係性を作る
(子どもの良いところはちゃんと言葉で認める、親が言い過ぎた時にはあとからでも謝るなど)
 また、発達の抜けがあると、「怖い」が強くなっていることがあります。
また、発達の抜けがあると、「怖い」が強くなっていることがあります。
思春期の成長期やストレスでその傾向が強く現れることも、今はめずらしくはありません。
でもご安心くださいね
この場合でも専門的な対応で改善できますので、講座などで個別にご相談ください。
「怒られるのが怖い」は結構多岐に渡る影響がありますので、そのままにはしないのがおすすめです
参考:「怒られるのが怖い」を絶対にそのままにしてはいけないワケと抜け出し方
常日頃から「失敗してはいけない」と捉えていると、上記のように失敗を見れなくなります。
「失敗してはいけない」は強く怒られたり、結果ばかり求められることで持つパターンもあれば、
 「失敗させなすぎ」で過干渉することで裏のメッセージとして伝わることで持つパターンもあります。
「失敗させなすぎ」で過干渉することで裏のメッセージとして伝わることで持つパターンもあります。
子どもが失敗しないように、親が先回りすることが多いと、子どもには失敗して回復する経験が少なくなってしまいます。
そうなると、ちょっとした失敗でも怖くてパニックになります。
「失敗させないように」という先回りや、子どもに頼まれてないのに親が察して動くことを繰り返していると、子どもは逆に、どんどん失敗に向き合えなくなるので、気をつけたいですね。
既にこのパターンにハマっている場合には
◎失敗を重大なことだと捉えるのを、まず親がやめて、一つの改善できる体験だとして扱う
◎失敗に対して感情的に怒るなど、圧をかけることをしない
安心できるコミュニケーションを日頃から。
◎察してちゃんを育てるようなことはしない
参考:気づかずに我が子を「察してちゃん」 にしないコツ:思春期の子育て
 自己肯定感が低いと、「自分には無理」とすぐに逃避するようになるので、ちょっとした失敗や努力が必要な課題に向き合えなくなってしまいます。
自己肯定感が低いと、「自分には無理」とすぐに逃避するようになるので、ちょっとした失敗や努力が必要な課題に向き合えなくなってしまいます。
失敗の内容に目を向けて改善することまでできずに、ただ謝ってその場をしのいだり、ただ落ち込んで自分や他人を責めたりする方に行きがちです。
いくら落ち込んでも改善には繋がらないのは、既に見てきたとおりです 😐
自己肯定感は、自分で色々なことを決めてやれた、という体験が少ないと、育ちにくくなります。
なんでも言うことを聞いてもらったり、先回りしてもらうことが多かったり、または行動の指示命令が多いと、自己肯定感は育たないのです。
どうしても先回りしてしまう場合には、お母さん・お父さんが「失敗が怖い」のかもしれません。
それをリリースするところから始めれば、余裕を持って子どもを見守れるようになり、本当に必要な対応ができるようになります
(^^)
 また、特に思春期には高い理想と今の自分を比べては凹むので、世界のどの国でも思春期には自己肯定感が一時期下がります。
また、特に思春期には高い理想と今の自分を比べては凹むので、世界のどの国でも思春期には自己肯定感が一時期下がります。
ただ、他の国はその後上がっていくのですが、日本はずっとその低い自己肯定感のままになってしまうことも多いのが特徴です。
それは自他ともに「長所を褒める」「人より抜きんでる」を良しとしない文化の影響もかなりあります。
●ちょっとでも褒めたら「いい気になる」から、ダメ出しで奮起させないと。
●良いことでも「目立ちすぎるのはよくない」「出る杭は打たれる」「みんなと同じが一番」
という人もまだまだいます。
しかし、本来人は「希望と自信」で動くものです。
「やりたい、やれそう」その2つは自己肯定感がある程度あってこそ感じられます。
 ダメ出しで奮起するタイプも0ではないですが、もっと効率がいいのは、本人が自分で「やりたい、やれそう」と思って自ら動く方です。
ダメ出しで奮起するタイプも0ではないですが、もっと効率がいいのは、本人が自分で「やりたい、やれそう」と思って自ら動く方です。
困難や辛い経験からも成長できますが、うまく行ったことや楽しかった経験からも同じくらい学べるのです。
良いところに目を向けずに、わざわざ必要以上にダメ出しをするのは、子どもの自己肯定感を下げるばかりです。
改善してほしいことがある場合には、先にしっかりOKを出せることについて認めてからがオススメです!
他にもいっぱい、自己肯定感を日頃から上げるコツはありますので、講座やキンドルもご活用ください
◎子どもにどうしたら良いか考えるチャンス、自分で決めるチャンス、自分でやてみるチャンスを与える
◎日頃から勇気づけをする
(2)同じ失敗の繰り返しから抜け出そうとするモチベーションを呼び覚ます
 失敗に意識が向けられる段階ならば、次はそのループから抜け出そうとするモチベーションがあるかどうかのチェックです。
失敗に意識が向けられる段階ならば、次はそのループから抜け出そうとするモチベーションがあるかどうかのチェックです。
子どもにそのモチベーションがないと、いくら周りで「いい加減にして」と言っても、その子の行動は変わらないですね 🙄
大人からすると不思議でも、子どもは「今の状態で困ってない」と捉えていることがあります。
 ●期日ギリギリでも提出できているから良い
●期日ギリギリでも提出できているから良い
●遅刻しても怒られないから大丈夫
●自分の成績はこんなもの
「ちゃんと計画的に宿題に取り組んだほうが良い」
「遅刻すると信用をなくすから、時間は守った方がいい」
「もっとやればできるのに・・・」
そんな大人とは話がすれ違ってしまいますね。
こう言う場合には「すべきでしょ」「別に困ってない」の応酬になるのが、一番もったいないですね 🙄
このようなパターンでは、「良い悪い」ではなく、まず現状について客観的な共通の認識を持つところから始めるのがおすすめです。
数値か図で表現できるものはそれを使いながら、分かりやすく説明します。
 無駄な時間の使い方をしているなどの、本人が思っているより現状のデメリットがあることと、改善した場合のメリットも、わかりやすく伝えます。
無駄な時間の使い方をしているなどの、本人が思っているより現状のデメリットがあることと、改善した場合のメリットも、わかりやすく伝えます。
本人はできていると思っていて、「朝〇〇時に起きていることが多い」と言うようなケースなら、そこから1週間、実際の記録を付けるのも有効です。
そしてここがポイントなのですが
「だから~~しなさい」と言うのではなく
「これについてどう思う?」を必ず挟むのをお忘れなく!
誰でもすぐに「だから~~しなさい」と行動指示されれば、げんなりして、やる気が無くなってしまいます。
まずは本人の思いを十分に聞くことが大事です。
聞いた上で、リフォームが必要な思い込みがあればそれをリフォームできるように対応できます
(^^)/
 「自分も失敗したけれど、それにはワケがある」と子どもが思っているときには、まずその話をしっかり聞いて受け取ることが大事です。
「自分も失敗したけれど、それにはワケがある」と子どもが思っているときには、まずその話をしっかり聞いて受け取ることが大事です。
納得できないこととしては、子どもの思い込みによるものがあります。
「あの場合には~~すべきだったからしょうがない」などと不適切に思い込んでいるような場合でも、子どもの話をしっかり聞ければ、それをリフォームすることを手伝えます。
また、子どもが納得できないワケが正当なこともあります。
とてもわかり易い例としては、「自分はA君を叩いてしまったけれど、その前にA君からしつこく嫌なことをされていた」というパターンがあります。
「叩く」のはもちろん良くない、失敗だったとわかっています。
 でもその自分の行為だけを怒られるのでは、「自分も嫌だった」という気持ちの処理ができないままになります。
でもその自分の行為だけを怒られるのでは、「自分も嫌だった」という気持ちの処理ができないままになります。
そこに納得感もすっきり感もないのに、自分の非だけを認めることができるようになるのには、自分で自分の気持ちをなだめることができて、清濁併せ呑めるようにまで成長していることが必要です。
そしてそのような成長を遂げるには、始めは誰かに自分の気持ちをなだめたり、清濁合わせて飲んでもらうことが必要なのです。
真っ直ぐな子どもに「大人になれ」と言いますが、その前にその子が大人の対応をしてもらってないと、そもそもそれがどういうことなのかわからないのです。
実際に社会に出れば、色々と一部だけ切り取って怒られたり、一方的に決めつけられたりすることもあるものです。
それにポキっと折れてしまわないしなやかさを育てるのは、やっぱり一番は家族です。
日頃から、安心して自分の気持ちを言えるようなコミュニケーションをしておくのがベストです
(^^)
 失敗だ!と思った時に、「何が、誰が悪いのか」と原因探しをしてしまうと、肝心の失敗に向き合えなくなることがよくあります 😐
失敗だ!と思った時に、「何が、誰が悪いのか」と原因探しをしてしまうと、肝心の失敗に向き合えなくなることがよくあります 😐
原因探しを始めると、最終的には「自分」か「他人」か「できごと」のどれかに行き着きます。
そして「あれさえなかったら」とか「あの人が悪い」とずっと考え続けてしまうのです。
自分以外の「他人」か「できごと」をいくら原因特定しても、自分にはそれらを変えるのは難しいものです。
自分が直接変えられるのは自分だけなので。
自分の言動で他人かできごとが変わりやすくなるように関わることはできますので、それはやはり「自分の言動を変える」ことになります。
「あれが、あの人が悪い」にハマっていると、自分を変えて、同じ失敗を繰り返すことから抜け出そうとは思わなくなるので
ご注意です。
 そして「自分」に意識が向いても「自分が悪い」で終わってしまったら、肝心の失敗の繰り返しから抜け出すことまでたどりつけなくなります 😐
そして「自分」に意識が向いても「自分が悪い」で終わってしまったら、肝心の失敗の繰り返しから抜け出すことまでたどりつけなくなります 😐
「自分が悪い」と、どんなに落ち込んだり自分を責めても、自分の言動を変えない限り、失敗の繰り返しから抜けるのは難しいのです。
そのためには、「原因探し」をしたとしても、同じ失敗を繰り返しているという事実に目を戻して、抜け出すことについて意識を向けるのがおすすめです。
(3)具体的な失敗から抜け出す方法を見つける
同じ失敗を繰り返すことから抜け出すには、(2)で、まずしっかり子どもの言い分を聞いた上で、本人に改善しようという意欲ができたら、実際に失敗する時に何が起きているのかをチェックするところからスタートします。
 途中で「それはあなたも悪い」などと口を挟まずに、とにかく子どもに顛末を話させて、最後まで聞きます。
途中で「それはあなたも悪い」などと口を挟まずに、とにかく子どもに顛末を話させて、最後まで聞きます。
既に子どもに改善しようという意欲があるのですから、次は「次に同じような場面になったらどうしたら良いと思う?」とまた尋ねます。
親が「正解の行動」を先に言わないことが大事です。
その子どもの話を聞くことで、何が失敗の元になっているのかがわかります。
例えば遅刻の場合には、子どもが「準備の時間」を甘く見積もっていることがみつかることもあります。
忘れ物なら「チェック作業が甘い」かもしれませんし
テスト勉強が不十分なら「計画を立てるのが苦手」なのかもしれません。
いくつか要因を書き出したら、それを見ながら「どれから取り組む?」と聞いていきます。
そしてその具体的な取り組みについての思いも聞いてみます。
そうすることによって、具体的な方法が見つけられるのかないのかもわかります。
 親が始めから「こう改善しなさい」だと、子どもは自分で考える練習と自分の考えを改善するチャンスもなくしてしまいます。
親が始めから「こう改善しなさい」だと、子どもは自分で考える練習と自分の考えを改善するチャンスもなくしてしまいます。
また、行動の指示なので反発される確率も高いので、もったいないですね。
子どもがやがて自分で自分の失敗を一人でも改善できるようになるために、子どもがその作業を一人でもできるように導いていくのが「質問」です。
それが生きる力を引き出すコミュニケーションです。
親に何を考えているのかを報告させることが目的はないので、できるだけ楽しい雰囲気でコミュニケーションができるといいですね
(^_-)
時に、子どもの
*気が散りやすくて集中が苦手で失敗が多くなる
*言ったことを覚えておくのが苦手
*一つのことに集中すると、狭い範囲のことしか意識できなくなる
 *自分のこだわりに固執しすぎる
*自分のこだわりに固執しすぎる
*完璧主義で0か100かになる
*マイイペース過ぎて周りに合わせられない
*気持ちの切り替えが苦手
*怖がりで親の陰に隠れようとする
*助けてと言うのがとても苦手
*情報処理の得意/不得意に大きな凸凹がある
*感覚過敏
などが、同じ失敗を繰り返す要因になっていることもあります。
そのような場合には、身体→心→頭の順で整えていくと改善しますので、ご安心くださいね
講座で個別にご相談ください。
 今までにも多数、そのような特徴があった子が本来の力を発揮できるようになっています!
今までにも多数、そのような特徴があった子が本来の力を発揮できるようになっています!
(^^)/
同じ失敗を繰り返す子:おわりに
ちゃんと対応の順番と具体的な方法があったんですね 🙂
今日はそれがわかったので、かなり目の前が広がった感じです
文章で読むと長くなりますが、これらは既に数100のご家族が実践して結果を出しているコツなんです。
これまでと違う対応をする時は、始めは難しく感じることもあるかもしれませんが、多くの人ができているので、焦らずやってみてくださいね
もう一度順番にチェックしてみます!
なんだか子どもの反応が楽しみです
♡♡終わりに♡♡
 子どもが同じ失敗を繰り返すのを見ていると、親としてはイラっとしちゃいますね。
子どもが同じ失敗を繰り返すのを見ていると、親としてはイラっとしちゃいますね。
そのまま何度か経験させて、子どもが自ら改善するまで待つ場合でも
あまりに続くのでどうなっているのか関わってみようとする場合でも
親にはそれなりに自分のイライラとうまく付き合うことが必要になってきます。
そんな時には自分を整えるコツをお役立てください。
講座でも、ブログでも多数お伝えしています。
思春期の子どもとコミュニケーションをする時には、コツが掴めるまでは子どもの反応も芳しくないこともありますね。
ただ、その反応にうまく対応できるコツがつかめると、今度は子どもの反応がすっと素直なものに変わることもよくあります。
ここが大人同士とはずいぶん違うところだと、お母さんたちからの嬉しいご報告をお聞きするといつも思います 🙂
 役立つコツを手に入れて、子どもとのコミュニケーションが楽になると、子育ての大変さもうんと楽になります
役立つコツを手に入れて、子どもとのコミュニケーションが楽になると、子育ての大変さもうんと楽になります
(^^)/
合わせて読みたい記事:
人のせいにする子ども:5つのパターンと知っておきたい親の対応
動画バージョンはこちらです。
音声だけお聞きいただくこともできます。
このブログの、もう一つの動画バージョンもあります。
音声だけお聞きいただくこともできます。