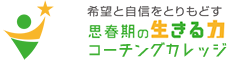謝れない子供:「反抗期だから」で済ますのはもったいない!
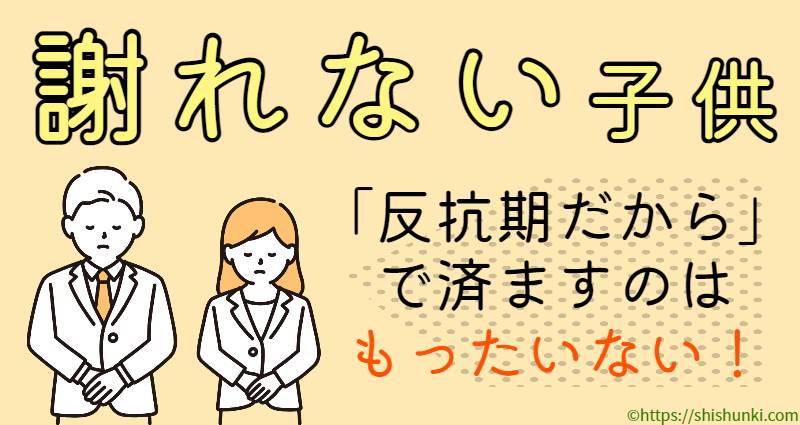
謝れない子供にイラっとすることはありませんか?
そうなると、ついそのイライラにまかせて、謝れないことを責めたり、謝らせようとムキにもなりがちです・・
それでは親子関係も悪くなるだけので、もったいないですね 😐
反抗期だからかと、大目に見ようとはしているんですが・・
このままじゃ人間関係も悪くならないかと心配です
「謝る」のはそれなりに勇気がいることです。
でも、必要な時にはちゃんと謝れることで、自分の失敗を成長に変えたり、相手との関係性をよりよいものにするチャンスにもできます 🙂
大人はそのようなことを経験から知っているのですが、子どもはそこまでの実感が持てない上に、「自分の気持ちや立場」に敏感なので、謝るのが苦手、嫌いな子も多いです。
謝らない子供にも、その子なりのワケがあります
そのワケを紐解いていけば、「謝らない子供」というお困りを親子で成長するチャンスに変えることもできますよ
(^^)
目次
なぜ、必要な時に謝れることが大事なのか
 始めに、「謝ることが必要な時」というのはどんな時でしょうか?
始めに、「謝ることが必要な時」というのはどんな時でしょうか?
「自分の過失で、誰かに好ましくない影響を与えてしまった時」になります
このような必要な時に、実害へのリカバリーをしても謝れないと
1)相手の「迷惑をかけられた」という気持ちが放置されたままになるので、相手に感情的なしこりが残る
2)自分も「失敗した」という嫌な気持ちにケリをつけられないので、ひきずってしまう
ということが起こります。
どちらにも嫌な体験として引きずりますね
そうなんです。
それではもったいないですね。
人のどんな行動にも、その裏にはその人なりのワケがあります。
謝れない理由を、自分でちゃんと言葉で説明できればいいのですが、子供はそうしないでただ謝らないという態度になりがちです
それでつい「謝る」「謝らない」という行動の話になってしまいます。
大事なのは子供の「謝らないワケ」なので、そこに大人が光を当てていくと、やがて子どもも自分から自分のワケを意識して扱えるようになっていきます
(^^)
子供が謝らない時にはワケがある
謝らない子供の7大ワケはこちらです
ピンときたものからお読み下さい 🙂
謝れない子供の7つの理由
(3) 「そんなつもりじゃなかった」にこだわっているので謝れない
(4) 自分のやったことにも正当な理由があると思っているので謝れない
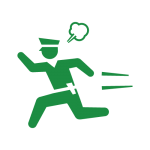 自分が過失(例:弟に手を出した)をする前に、弟が先に思い切り蹴ってきていた事実があったのに、自分が手を出したところだけを親に見られて、「手を出したことを謝りなさい」とすぐに言われたような場合です。
自分が過失(例:弟に手を出した)をする前に、弟が先に思い切り蹴ってきていた事実があったのに、自分が手を出したところだけを親に見られて、「手を出したことを謝りなさい」とすぐに言われたような場合です。
「弟が先に蹴ってきた」と言えるようならばまだいいのですが、(5)の頭が真っ白になっていたり、怒りの気持ちが強くこみ上げすぎていて、その時にすぐに言葉にできないような子もいます。
そのような子は「自分の事実」をその後も言葉にせずに「誰もちゃんとわかろうとしない」と黙り込んでしまうこともあります。
そうなると、「何度謝るように言われても謝れない子」と親から捉えらることになります。
そんなことが続くと、親は「困った。謝ることを覚えさせなくては」と力が入りますし、子供は「親は分かってくれない」とますます黙り込むことも起こります
大事な親子の信頼関係が崩れてしまうのはもったいないですね 😐
人はどうしても、「自分の見たこと」で状況を判断してしまうところがあるものです。
なので、子供の失敗を見つけた時には、謝ることを要求するより先に、「何が起きたのか、それについてどう思っているのか」などを双方から聞くことを心に留めておくのがおすすめです!
 自分がしたことを失敗だ、悪かったと思ってないので謝れない場合には、「本当にそう思ってない場合」と「多少やりすぎたと思っているが認めたくない場合」があります。
自分がしたことを失敗だ、悪かったと思ってないので謝れない場合には、「本当にそう思ってない場合」と「多少やりすぎたと思っているが認めたくない場合」があります。
例えば先程の弟への仕返しが過剰だったような場合です
対応としては、双方から起きたことと思いを聞いた上で、まずは「弟に蹴られて嫌だったね」と子供の気持ちを言葉にするのがおすすめです。
それによって子供の気持ちも落ち着くので、「やりすぎたと思ってる場合」にはトーンダウンしてきます。
「歳上なんだから少しくらい我慢しなさい」と言うのはNGです。
「我慢」じゃなくて「やめさせる」か「その場から去る」などの「対応」を教えるのが良いでしょう。
「やられたら倍返しで何が悪い」と思っている場合でも、落ち着いてきますので話がしやすくなります。
(4)のケースの対応に進めます (^^)
(3) 「そんなつもりじゃなかった」にこだわっているので謝れない
 本人がそうしようと思ってなかったことでも、結果的に過失になることもあります。
本人がそうしようと思ってなかったことでも、結果的に過失になることもあります。
例えば本人が食事の場で、誰かの動きに気を取られて自分が身体をねじってしまったら、ひじで水の入ったコップを倒して、誰かに水をかけてしまったような場合です。
このような時に「気をつけなさいっていつも言ってるでしょ!謝りなさい!」と言われても、子供は「わざとじゃないのに」と素直に謝れないこともあるものです。
また、自分の行為で誰かにダメージを与えてしまったショックから、(5)頭が真っ白になってしまうこともあります
どちらにしても、大声や責めるような口調は状況を悪化させるだけです。
それだと子供は「わざとじゃない」に固執しつづけてしまいます。
まずは状況のリカバリーを落ち着いて子供ができるようにサポートします。(水を拭くなど)
子供の気持ちが落ち着いてきたら、「やろうと思ってやったわけじゃないのは分かってるよ」と言葉をかけます。
 「わざとじゃない」という子供の主張を受け取ることはとても大事です。
「わざとじゃない」という子供の主張を受け取ることはとても大事です。
その上で、小学生以上ならば、物事には「意図責任と結果責任がある」という話をしてあげられるとバッチリです 🙂
~「わざとじゃない」という気持ちを伝えることはOKだけど、どんなつもりだったとしても、自分がやったことで相手にダメージを与えた場合には、「結果責任」として謝ることが大切~
ということを、ゆっくりと伝えれば、子供が成長するチャンスにできます
それを伝えてから、「相手の立場を想像する」事ができるように導きます。
あなたがわざとじゃないのはわかってるよ。
じゃあ次は、○さんとしてどう感じるかも想像してみてね。
座っていたら急に水がかかってきたら、どんなふうに感じるかな?
人は自分の気持ちが受け止められて始めて、他人の気持ちを受け止めたり、受け入れられる余裕ができます
(^^)b
![]() また、先程のようにちょっとした刺激が入ると身体が動いてしまうような場合には、発達の抜けが隠れていることもあります。
また、先程のようにちょっとした刺激が入ると身体が動いてしまうような場合には、発達の抜けが隠れていることもあります。
そのような動きだと、本人の意志ではコントロールできないので、「気をつけなさい」「落ち着きがない」と責めてもお互いにとって、良いことは何も起きません。
発達の抜けというと、大変なことのように思われるかもしれませんが、
実は家庭の日常のなかで埋めていけるものなので、ご安心くださいね 🙂
ピンときた方は思春期最幸家族講座等をご活用下さい
(4) 自分のやったことにも正当な理由があると思っているので謝れない
本人が自分のやったことには正当な理由があると思っている場合には、まず最後までその理由を言葉にさせて聞き切ります。
今までのその人との関係性や、本人が「~~ならしてもいいはず」という思い込みを持っている場合もあったりします。
途中で評価判断・アドバイス・要約はしないのがオススメです。
最後まで話を聞いたら、「理由」が「その行為をそこまでやって良い」と結びつくかどうかを丁寧に聞いていきます。
 「そんなの通用しない」と大人から言うのではなく、「なぜそれだと~~しても構わないとなるのか」とじっくり聞いて、本人の言葉で考えさせるのがポイントです。
「そんなの通用しない」と大人から言うのではなく、「なぜそれだと~~しても構わないとなるのか」とじっくり聞いて、本人の言葉で考えさせるのがポイントです。
「わからない」となったら、「じゃあ、明日の夕方また聞くら考えておいてね」と考えさせる時間を与えるのもオススメです
(^^)
自分で自分の理屈のつながりを言葉にしていくうちに、理屈がつながらないことに子ども自身が気づくこともありますし、偏った思い込み(「成績が良ければ人として上」のような思い込み)を見つけることもできます。
思い込みの偏りは、言葉にしないと頭で信じているだけでは、リフォームするのが難しいものです
本人が言葉にした時こそが、もっとフェアな思い込みにリフォームするチャンスです!
 自分が予期してなかった事が起きてびっくりして頭が真っ白になることって大人でもありますね
自分が予期してなかった事が起きてびっくりして頭が真っ白になることって大人でもありますね
また、その場で自分の中に色んな感情がいっぺんに湧いてきたり、自分の言いたいことが色々あるけれど、どうやって順序立てて言葉にすれば良いのかわからなくて、フリーズしてしまうこともあります。
また、真っ白まで行かなくても、自分なりに言葉を探しているのに喋れていない状態でも、外から見れば「ただ黙っているだけで謝ってない」状態になります。
そこで親から「早く謝りなさい」「なにが起きたの、ちゃんと説明して❣」と被せられると「違う!」「ちょっと待って」と言いたい気持ちもさらに増えてしまうので、ますます言葉が出なくなってしまう・・ということも起こります。
固まっているなと感じたら、少しリラックスさせるのがおすすめです。
少し違う場所に移動させたり、相手の人に待ってもらうように声をかけたりすると、徐々に落ち着いてきます。
頭が白くなりやすい子は、そうやって「真っ白になったけど、落ち着いたら話せた」という体験が増えると、徐々に頭が白くなる傾向もなくなっていきます 🙂
(6) 謝ったら自分が悪い・負けだと認めることになると思っているので謝れない
 失敗を重大なことだと捉えていたり、自分の価値を結びつけていたり、「勝ち負け」で物事を捉えていると、このパターンになりやすくなります。
失敗を重大なことだと捉えていたり、自分の価値を結びつけていたり、「勝ち負け」で物事を捉えていると、このパターンになりやすくなります。
失敗は誰でもしたら嫌ですが、「うまく行かなかった一つの体験」に過ぎずに、「最終結果」ではないことが分かるように関わっていくのがおすすめです。
失敗を責めたり、怖がったり、不安ばかり選考させるような言葉を子供にかけてしまうのはNGです。
また、何にでも「成功か失敗か」「良いか悪いか」の二択しかないように思わせるのも、子供にとって良いことは起きません。
『失敗も続けていけば成功までの練習になる。失敗でやめれば結果になる』という言葉を残した有名人は多数います
スラムダンクでも安西先生が言ってましたね 😉
こちらも参考にどうぞ:子どもが「失敗するのが怖い」時:効果的な親の5つの関わり方
「失敗を負けだと捉えてしまう」子には、自己肯定感の低さがあります。
ちょっとした失敗で自分の価値がなくなると恐れているからです。
子供の自己肯定感は大事に育てたいですね
不登校や自分の思いどおりに物事が行ってないと感じている時にも、自己肯定感が低くなっているので、その反発として「謝らない」に固執することもあります。
そんな時には甘やかすのは逆効果になるのでご注意です。
子供の存在を十分に受け入れていることが伝わったり、子供自身の心身のエネルギーをしっかり増やせると、自然と不要な固執はなくなっていきます 🙂
 子供も小学生以上になってくると、人の目を気にするようになってきます。
子供も小学生以上になってくると、人の目を気にするようになってきます。
思春期になれば、さらに「他人からどう見られているか」がとても気になります。
でも親や先生は「謝らせること」と「相手への気遣い」を優先しすぎるあまりに、子供のそんな気持ちへの配慮を忘れてしまうこともあります。
子供が自分のやったことに向き合うには、それに集中できる状態になっていることが必要です。
人からどう思われているのかに気を取られている時には、たとえ「本当は謝る方がいい」と分かっていても、その通り行動ができなくなってしまいます。
「いや、それよりも謝るほうが先だ」と大人は思うのですが、子供にそれを教えるには「謝ったら自分も相手もスッキリした」という実体験が必要です。
体験のない理屈よりも、今感じている恥ずかしさのほうが優先されるのは、子供だとしょうがないところです。
まずは子供なりのメンツや恥ずかしさを無視せずに、子供が謝ることに集中できるような環境を作ることを優先させるのがオススメです。
そういえば、自分も子供の頃は多少はどれも経験したことがある気がします。
うちの子は口数が少ないタイプなので、もっと話を引き出さないと、本人の内側で起きてることはわからないんだなと思いました!
気をつけたい!謝れない子供への親のNGな5つの対応
次は、ついやってしまいがちな「謝れない子供」への親のNG対応を見てみましょう
①子供の言い分や事実確認をせずに、頭ごなしに子供を責める
「うちの子は謝れない」「ちゃんと謝れるようにしなくちゃ」という親心が先走ってしまうと、その勢いで子供を責めてしまうことがあります。
私も昔は、そりゃあ自分の勢いのまま行動したものです
(。>﹏<。)
ただ、子どもを思う気持ちからの行動でも、怒鳴ったり責めたりしてしまうと、子どもの方には「怒られた」という嫌な気もくしか残らないんです
人は「自分が安全だ」と感じられて始めて、話の内容を受け取れるようになります。
怒られたり責められたりすれば、怖い・嫌だが膨らむだけなので、肝心の話の内容をうけとることができなくなります。
「結局謝ればいいんでしょ」となるくらいなので、「なぜこの場面では謝ることが大事なのか」という肝心の内容が伝わりません。
そうなると、怒る人の目が届かないところでは、謝ろうとはしなくなります・・・ 😯
 また、子どもも自分の言葉で思いを話すことも難しくなりますし、子どもが黙っていれば親もますます感情的にヒートアップしがちになります。
また、子どもも自分の言葉で思いを話すことも難しくなりますし、子どもが黙っていれば親もますます感情的にヒートアップしがちになります。
大事な親子の信頼関係が崩れてしまうのはもったいないですね
②話を聞かずに「あなたが悪い」「あなたも悪い」と決めつける
誰が悪いという話ばかりしていると、子どもも悪いか良いかの2択しか考えられなくなってしまいます
「ここは良かったけど、こっちはもっと他のことができたね」という考え方ができないと、0か100かの極端思考になりますし、何かあるとすぐに「誰が悪いのか」と考えるようにもなってしまいます。
大事なのは「どうしたいのか」と「そのために何ができるのか」です。
「どうしたい、なりたいのか」がぼやけているのに、「何が悪いのか」を頑張って探しても、どこにもたどり着けないので、かなりもったいないことになります。
③とにかく「謝りなさい」と言う
 本来は、謝るのは『自分の過失でその人に好ましくない影響を与えたから』という場合に必要となります。
本来は、謝るのは『自分の過失でその人に好ましくない影響を与えたから』という場合に必要となります。
ただ、日本では「自分に過失がなくても、揉め事を回避させるために謝る」という振る舞い方があります。
大人はその方法をよく使うので、相手と揉めることを回避させようと、事実関係や子どもの言い分を十分に聞かずに、謝るのがアタリマエなんだからと、子供に「とにかく謝りなさい」と言ってしまうことがあります。
ただ、子供は「自分の納得感」や「負けてはならない」のような、自分のことでいっぱいいっぱいになりがちです。
「揉め事を回避させる」ことよりもそちらに意識が行ってしまっている子供に、大人の前提を押し付けてしまっては、お互いに理解できないママのすれ違いになるだけです。
本当は自分に非があるわけではない場合でも、日本では謝ることで話を進めるという使い方が有効な場合もありますが、そういうこともある、と子供には教える必要もあります。
④事実確認をせずに、相手の感情などを損なったことに謝るように言う
 相手が怒っていたり、泣いたりしていても、それが正当なものかどうかは別の話になります。
相手が怒っていたり、泣いたりしていても、それが正当なものかどうかは別の話になります。
その子の過失が実際にそのようなダメージを相手に与えたかどうか、が大事なポイントです。
それを確認せずに、ただ相手が怒っているから・泣いているからと、子供に謝るように言うのは、他人の感情の責任をとることの強要になってしまいます。
実際に、ある学校の部活で「下級生がコロナになったから上級生に感染って、試合に出れなくなって腹が立つから謝れ」と上級生とその親!が下級生たちに言ってきたという事例もあります 😯
そういう時に子どもを謝らせるのは筋の通ったことでしょうか???
(対応は慎重にする必要はありますが)
そういう、他人が怒っているからということだけで子どもに謝ることを強要してしまうと、子供は人の顔色ばかり見るような子になってしまいます。
そうなってしまったら、あまりにも残念ですね 😐
⑤人目を気にして、子供の気持ちや立場を気にかけない
これは、謝れない子供の理由(7)と同じですね。
 日本ではどうしても他人の目を気にするところがありますので、ことを大きくしない、終わらせよう、揉めないようにと、謝ることで「この話は終わり」にしたがる傾向もあります。
日本ではどうしても他人の目を気にするところがありますので、ことを大きくしない、終わらせよう、揉めないようにと、謝ることで「この話は終わり」にしたがる傾向もあります。
ただ、それを繰り返してしまうと、その場は「終わり」にできたようでも、大事な親子の信頼関係が崩れてしまうので、もったいないですね
⑥子供が謝らないことで、次々と怒りを爆発させてしまう
謝るように言っても子供が謝らないと、親もだんだん腹が立ってきます
そうなると、「言うことを聞かない子供」に対しての怒りや、「前にも話をしたのに」などの怒りが次々と着火されてしまいます。
怒りは「この状況を壊すためのエネルギー」なので、乗っ取られてしまうと、「状況を変える」のではなく「子供にダメージを与える」ために、毒舌を繰り出してしまうことも起こります。。
 親だってイラっ、ムカッとすることがあるのもアタリマエです
親だってイラっ、ムカッとすることがあるのもアタリマエです
そんな時には、自分に気づいて一度タイムがとれれば大丈夫!
そして
子供が言う通りにしない時には、子供なりのワケがある
それを思い出して、そちらに意識を向けてみるのがおすすめです
無駄なバトルと後悔とはおさらばしましょう!
(^^)
謝れない子供が、必要な時には謝れる子になるために親のできること
 自分の過失にも謝れない子供と今向き合っている時のサポートのステップは最大でも5つです。
自分の過失にも謝れない子供と今向き合っている時のサポートのステップは最大でも5つです。
1⃣ 自分と子供を落ち着かせる
ショック状態だと、親もうまく対応できませんし、子供も何かを言われてもうまく受け取れなくなります。
まず双方が落ち着くことから始めましょう
2⃣子供の話をしっかり聞く
子供の話を引き出していきます。
事実関係を聞きながら、時々その時の子供の気持ちを「びっくりしたんだね」などと言葉にしながら進めていくと、子供も安心して話ができるようになっていきます。
相手からも事実関係が聞けるとベストです
3⃣子供が謝る必要があると思った場合には、その理由について子供の思いを聞く
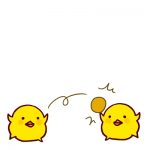 子供が謝ることに同意すればOK
子供が謝ることに同意すればOK
4⃣子供に謝る必要があると思うケースでも謝れない場合には、「謝れない子供のワケ①~⑦」をチェックして対応する
5⃣必要に応じて、親も一緒に謝るのもアリ
子供を尊重しながら、謝れない理由や謝る必要をお互いに理解していくことで、謝るのが苦手な子供でも、徐々に自分から必要な時には謝れるようになっていきます
(^^)
「謝れない子供」というお困りを、親子で成長するチャンスにしよう!
 今謝ることが必要な場面じゃないの日常のなかでも、「謝れない子供」を「必要な時には自分から謝れる子」に成長させるのに役立つコツが3つあります。
今謝ることが必要な場面じゃないの日常のなかでも、「謝れない子供」を「必要な時には自分から謝れる子」に成長させるのに役立つコツが3つあります。
ⅰ子供の自己肯定感を育てるようなコミュニケーション
・日頃から子供の良いところや愛情を言葉で伝える
・子供の話だけを聞く時間を持つ(5分でもOKです)
ⅱ失敗への対応を教える
・失敗は嬉しいものではないけれど、そこから改善ポイントを見つければせいちょうできる
・失敗への対応を教える
失敗への対応は「相手がいれば謝る」「原状回復」「次に同じことが起きないようにするにはどうしたら良いかを考え出す」の3点です。
それがしっかりわかっていれば、無駄に失敗を恐れることはなくなります。
ⅲ日頃から「ごめんね」をさらっと言う
 ちょっと家の中で腕がぶつかったり、親が時間に遅れたときなどに、さらっと「ごめんね」を言えていると、子供も自然に謝れるようになります。
ちょっと家の中で腕がぶつかったり、親が時間に遅れたときなどに、さらっと「ごめんね」を言えていると、子供も自然に謝れるようになります。
人は他人の「言っていること」よりも「やってること」から大きな影響を受けます
ⅰⅱⅲが日常でアタリマエにできるようになれば、親としても気持ちが楽になります
(^^)
子供を「改善しなくちゃ」と悪いところにばかり目を光らせているのは疲れます
子供の良いところを無理矢理にでもⅰ日1個でも見つけようとすれば、楽しい発見が増えてきます
失敗を恐れて心配したり、引きずるよりも、そこから何かを掴もうとする方が気が楽です
必要な時にサラッと謝れれば、心に不要な罪悪感も溜まりません。
「謝れない子供」というお困りにであったら、子供も親も成長して楽になるチャンスに変えてしまいましょう!
(^o^)/
謝れない子供:終わりに
何度言っても変わらないし、反抗期だから待つしかないのかと思っていましたが、子供にも色んな理由があるんだとわかって、子供の見え方がずいぶん変わりました。
うちは口数が少ない子なので、親の方が喋りすぎでした。
子供なりに話せるようにやってみようと思いました!
ちょっとした見方と接し方を変えるだけで、子供は敏感に反応します
ぜひ、反応を楽しみながらやってみてくださいね
♡♡あとがき♡♡
 謝るというのは、自分の非を認めることなので、嫌な現実にも向き合うための勇気がいりますね
謝るというのは、自分の非を認めることなので、嫌な現実にも向き合うための勇気がいりますね
子供がそんな勇気を持てるようになるには、「自分は失敗しても安全だ=居場所がある」という、自己肯定感の基盤が必要です。
そのためには
・失敗を過剰に悪いことだと捉えない
・子供の話を聞く
のがとても効果的です。
特に子供の話をしっかり聞くことは、子供の「自分を説明する意欲と力」を育てます
これからの時代を楽しんで自分らしく生きるためにとても大事な力です
(^^)/
合わせて読みたい記事:
人のせいにする子ども:5つのパターンと知っておきたい親の対応
話を聞かない子どもにはどうしたらいいの?思春期だからと諦めないで
このブログの動画バージョンはこちらです。
音声だけお聞きいただくこともできます。