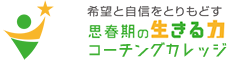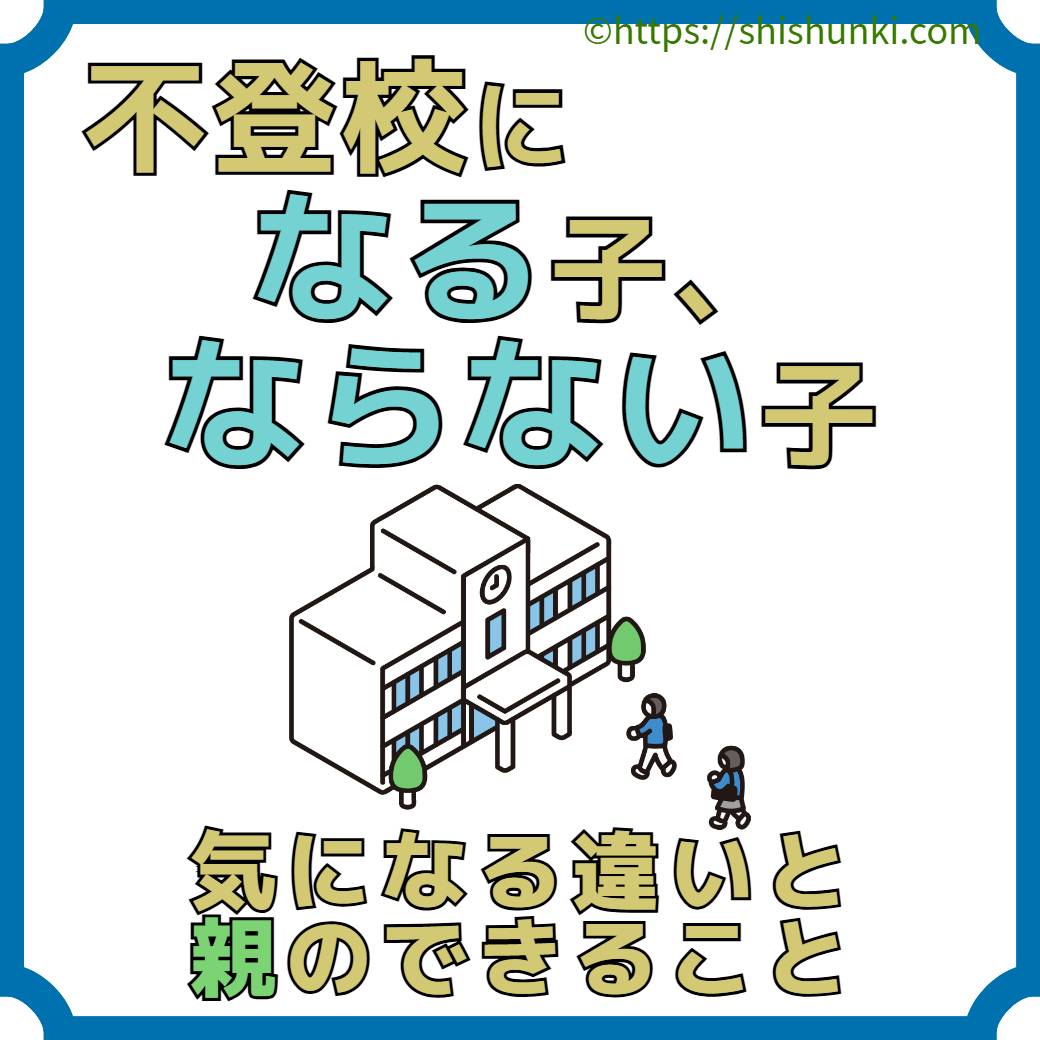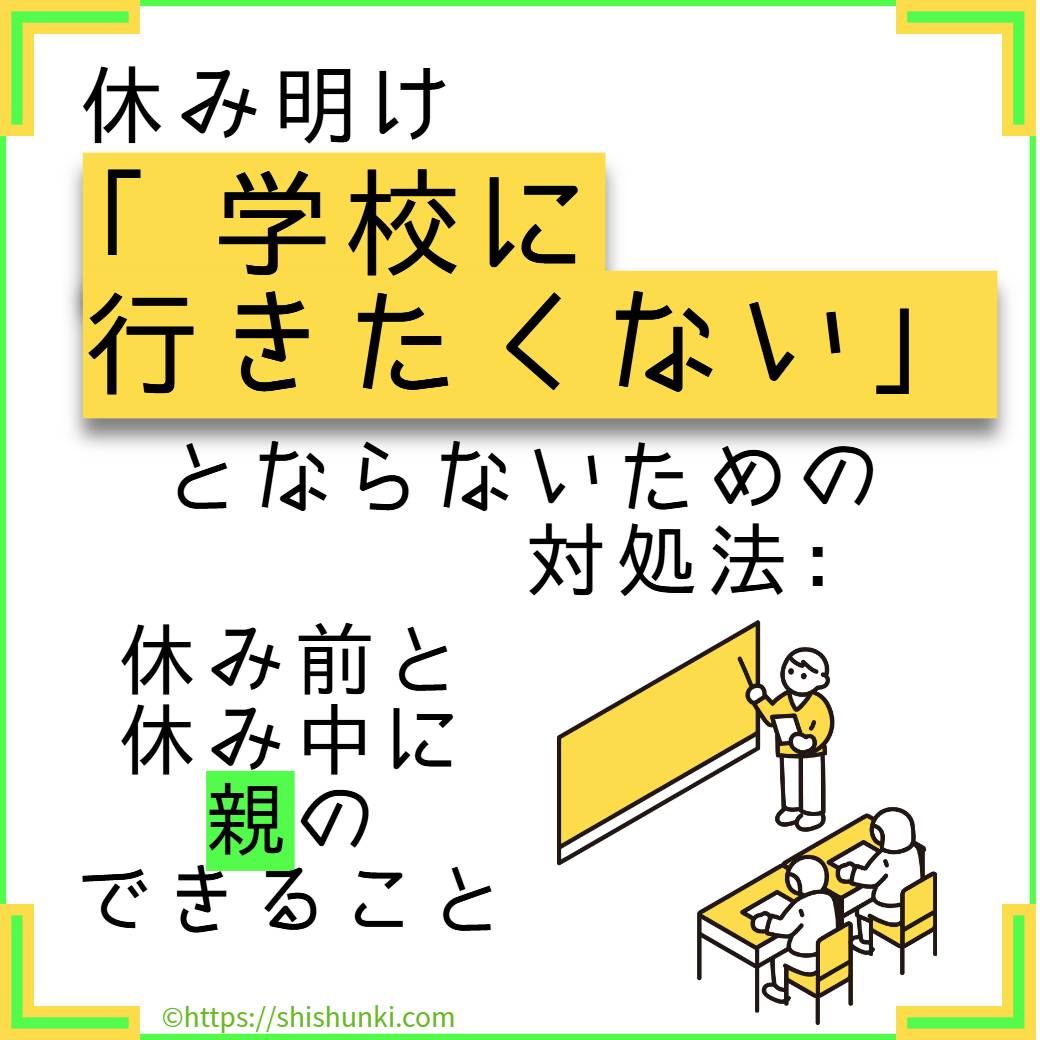新しい環境に慣れるまで:5つの知っておきたいこと、親のできること
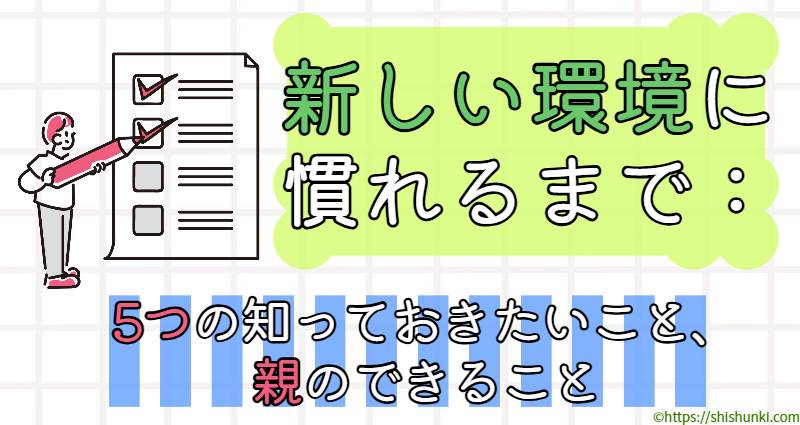
新しい環境に慣れるまでには、誰にでも多少の不安と緊張があります。
それが嬉しい変化でも、新しい環境には「まだわからない部分」があるので、やっぱり不安や緊張はあるものです。
本来子どもは好奇心が旺盛で、変化には柔軟に対応します。
ただ最近は「不安」が強いお子さんが増えている傾向があります 🙄
お子さんの不安が強いと、親としてはつい「大丈夫よ」と励ましたくなりますが、逆に嫌がられることも多いもの。。
今回は「新しい環境に慣れる」ことについて、5つの知っておきたいこととできること、親のサポートのコツのご紹介です 🙂
慣れるまで毎回かなり時間がかかります。
結局は新しい環境に慣れて
楽しく過ごせるのですが
なんとなく登校したくない様子や
暗い顔になるのが毎回なので
私も落ち着かなくなります。
慣れにくいのは性格だから
治らないでしょうか
毎回不安が強いのは
お子さんもお母さんも大変ですね。
それはお子さんが小さい頃からでしょうか
クラス替えがある新学期には
不安そうな子どもを見るのもストレスですし
どうにかしてあげられないのもストレスです 😐
そうなんですね 😐
でも、ご安心ください!
「不安」について詳しく知れば
不安を自分のために役立てることができます。
また、新しい環境に対して「用心深い傾向」は
持って生まれたものでもありますが
その傾向を和らげることもできるんです 🙂
もっと詳しく知りたいです。
では、ご一緒に
「新しい環境に慣れるまで」についてと
親御さんのサポートのコツを見てみましょう
目次
新しい環境で辛くなる時に、起きていることとは?
新しい環境に慣れるまで、「未知のもの」への不安を感じるのは自然なことです。
ただ、その不安を大きく感じ続けていると、不安で毎日が塗り込められて、辛くなってしまいます 😐
未知なものへの当たり前の不安を
その時になるまで感じるのは自然なのです。
ただ、その不安を知らずに自分で
大きくしてしまっていることをやめれば
不安が拡大して辛くなることはなくなります。
なるべく、不安を少なくできるといいですね。
不安をやめるのではなく、無駄な不安を増やし続けないことがポイントなんですね
そうなんです!
そして不安を多くしてしまうのは
●不安に巻き込まれて、不安にばかり意識を向け続けている
●不安を感じてはだめだ!と焦って、今すぐ解決しようとする
●それでも消せない不安を感じる自分(または子ども)を責めたり、無力だと思う → 自己肯定感の低下
を気づかないうちにやっているからです。
私も子どもも。。
不安は意外と巻き込む力が大きいので
ちょっと意識しないとなってしまいますよね。
私も、もちろんそうでした 😳
でもちゃんとうまく不安と付き合えるようになりますよ☆
はい、まずは次の5つのことを知っているだけで
気づかずに不安を大きくしてしまうことをやめられます。
新しい環境で辛くならないために、親子で知っておきたい5つのこととできること
不安を最小限にする、知っておくと良い5つのこと
はい、ではそれぞれを
具体的にどうしたらいいかも含めて
見てみましょう!
1)知らないことに不安を感じるのは当たり前:不安は味方!
新しいこと=知らないことがある場合に、それに対して「どうなるんだろう」と不安を感じるのは自然です。
すべての感情には、自分にとって役立つ行動を促すという目的があります。
不安にも、自分にとって役立つ行動をさせるという目的があります。
 不安は「考えられるリスクに、できる準備をしよう」と、自分に行動を促すための感情なんです。
不安は「考えられるリスクに、できる準備をしよう」と、自分に行動を促すための感情なんです。
「今自分ができること」に意識を向けるのが、不安エネルギーの最も良い使い方なんです 🙂
そうなんです!
それを知らないと不安を感じた時に
「こうなったら嫌だ」と
マイナスな可能性ばかり想像し続けたり
不安を感じてはいけない!と
無視しようとしてしまいます。
でも、そういうことが、実は不安は無駄に大きくしちゃうんです。
ああなったら嫌だな、と思ってるうちに、どんどん不安になります。
また、無理にポジティブに考えようとしても
ついつい頭にまた浮かんできちゃうんですよね。
そうなんですよ~
不安を感じたら
「今自分は未知のものへ不安を感じているんだ」と気づいて
それ以上考えるのは一度やめて
まずは深呼吸いたしましょう!
不安は自分の味方なので、落ち着くところから始めましょう!
先ほど、新しい環境に不安を感じるのは自然で
どんな人にも起こる、という話が出ましたが
 では、一般的に
では、一般的に
新しい環境に不安を手放せて慣れるのには
どれくらいの時間がかかると思われますか?
ふふ、私もそう思っていたんですが
実は新しい環境に完全に慣れるには
半年かかると言われています。
この頃には自分らしく過ごせるようになるのが
大人でも子どもでも平均的なんです。
4月から新しい環境になる場合だと
完全に慣れるのが10月くらいですか
もちろん個人差はありますが
意外と長い期間ですね。
つまり「新しい環境に慣れる」については
短距離走のイメージよりも
長距離走のイメージを持つことが
現実にマッチするんです。
長距離のレースを
単協理想だと思って走ってたら
途中で疲れたり、エネルギー切れになっちゃいますね
それで焦るのは
返って逆効果なんですね
はい、短距離走的に考えてしまうと
途中で苦しくなります。
そして、完全に慣れた状態の手前の状態
ある程度緊張せずにいられるようになるポイントは
3ヶ月経った頃です。
4月からの新学期だとすると
6月末とか7月の頭です。
新学期だと
クラス行事や定期テストをそれぞれ1回はやった頃ですね。
6月末や7月だと
長距離のイメージの方が近いです。
そうですね。
4月に10月をイメージするのは難しいでしょうから
ここまでの3ヶ月を
短距離のような全力疾走ではなく
長距離走のイメージで
7割位の力をずっとキープするイメージで行くのがオススメです。
長距離の視点を持つことって
とても大事なんです。
実際に
ここまで無理をして頑張っていたために
3ヶ月目くらいから疲れが出て来るケースが毎年結構多いです。
6月末や7月から学校が嫌になってきて
夏休みを挟んで
その後に登校しづらくなる子が
どの学年でも一番多いです。
そうなんです 😐
また、4月にものすごく不安や緊張が強いと
3ヶ月も持たずに
5月の連休明けに
「またあの緊張に戻りたくない」と
身体がNOとなって、動けなくなることもあります 😐
無理しながら登校では
テンション(気合だけで頑張る)を高くするので
その後必ず疲れてしまうんです。
 友だちを作るのにも
友だちを作るのにも
4月はお互いに不安と緊張があるので
他の子の本来の姿も、まだ十分にはわからないものです。
徐々にその子らしさがでてくるなかで
「自分と合いそうかも」と思える出来事も増えてきます。
私の中のイメージを変えて
子どもが3ヶ月で徐々に安定して慣れていけるようにサポートすることにします
不安は味方であることや
慣れるのは長距離走だとわかってきたら
不安にも、だんだん焦らないようになってきたと思います。
そしてここでもう一つです!
それは、小さい頃から今まで
自分が新しい環境に慣れていった体験を思い出すことです。
不安があるとつい
「うまく行かなかったらどうしよう」
「あの時も最初は大変だった」と
経験の嫌な部分ばかり思い出してしまうものです。
 でも、「最終的には楽しく過ごせた経験」
でも、「最終的には楽しく過ごせた経験」
もあることを思い出してみれば
「絶対にうまく行かないわけじゃない」とわかります。
ただそのプロセスを無理なく早めたり
辛い時間を減らせば良いだけだとわかります。
また、うまく行った経験から
自分が今できることが見つかることも多いです 😉
うちの子も結局は馴染んでいるので
うまく行っている理由もあるはずですね!
うん、私もだいぶ落ち着いてきました
落ち着くことができると
今感じている不安について
もっと詳しく知ることができます 🙂
自分は「何について不安を感じているのか」を
とりあえず大きなことから小さなことまで
全部書き出してみます。
お子さんもお母さんも、それぞれご自分の目線で感じることでOKです。
 もう無い!思うまで書き出したら
もう無い!思うまで書き出したら
次に「それがどうなったらいいか」も全部書き出します。
そうすると、今自分ができることと
その時が来ないと行動が決まらないことがはっきりします。
そうなんです!
そして、その時が来ないと行動しようがないことは
その時に起きそうな状況を
考えられるだけ書き出します。
ここは、悪い可能性だけでなく
良い可能性も同じ数だけ書くのがポイントです!
つい、悪い可能性ばかり考えてしまいますけど
同じ確率で良い可能性もあるんですよね。
そうなんです 🙂
案外、調子よくラッキーに物事が進むことだって同じ確率で存在しています。
それを知っていると
「絶対悪いことになる」と自分を追い込んで
不安を増やすこともなくなりますね 🙄
そして今自分が対応できることと
対応がわからないことを分ける、
というのが大事なポイントです。
 もし、対応がわからないことがあれば
もし、対応がわからないことがあれば
何か良いアイデアがないか調べたり
他の人に聞くことができます。
もちろん、当カレッジには
膨大なこれまでの経験で良い結果が出た実績がありますので
周りに聞いてもわからない時には
ぜひご相談ください!
自分や周りに聞いてもヒットするものがないと
「もうだめか」と思ってしまいがちですが
実績ある専門家に聞けば必ず方法があるんですね。
はい、「寄り添う」「共感する」も大事ですが
具体的に「できること」を見つけることはとても大事です。
「現実」は最終的には「行動」で変わるからです 🙂
5)不安を感じた時には、何をすればよいか、何はしないほうが良いかを何度も思い出す
不安を感じた時には
その不安に巻き込まれて
焦ったり、不要な言動をしないことが最も大事です。
落ち着いて適切なことをすれば
不安はなくなります。
 なぜなら、不安は「リスクに対して行動することを促す」感情だからです。
なぜなら、不安は「リスクに対して行動することを促す」感情だからです。
ただ、不安はとても強力に人を巻き込むことがあります。
気づかないで焦って、変な言動をしてしまうことは
私も今でもチョイチョイ起こります。
なるべくそんなことを減らすためには
不安を感じた時にはここまでみてきた4つを
何度でも思い出しましょう!
まずは「不安を味方だと捉えること」
そして「慣れるのは長距離走」
「自分はこれまで慣れてきた体験がある」
ことを思い出します。
 そして落ち着いたら
そして落ち着いたら
自分が感じている不安を味方に付ける作業をします。
不安を感じているポイントを知って
今自分ができることを見つける
でしたね (^_-)☆
どうしたらいいかわからない時には
ぜひ知っている人の力を借りましょう。
あなたの時間にはそれだけの価値があります。
もっと明るく、本当にやりたいことに向けて使うためにあるのですから。
新しい環境に不安な子への親のNG対応
ここで、親御さんのサポートについてまとめましょう。
まずは、うっかりやってしまいがちなNG対応です。
親のNG対応
既にこれまでに出てきましたように
不安は無視したり 感じないようにしても
感じないようにしても
自分にくっついて離れません。
そしてちょっとしたことでブワッと出てきます。
夜寝る前の布団の中
ぼんやりしている時。。。
そうなると、いつでも不安に悩ませられてしまいます 🙄
また、子どもに
「自分の感情を尊重するな」という指示にもなってしまいます。
自分の感情がわからなくなると
「幸せ」「好き」も分からなくなるので
最も避けたいことですね。
不安は味方、そう思って
ちゃんとあることを認めて
それに落ち着いて向き合うのがおすすめです。
 そう言われて「そうね」と思えるくらいであれば
そう言われて「そうね」と思えるくらいであれば
それほど不安はもともと強くない場合です。
特にイマドキの子、思春期の子は
「納得」することが大事なので
ただ「なんとかなる」と言われて
「そうですか」とはならないと思っているのがおすすめです。
なぜ、大丈夫なのかを
一つでも理由をつけて伝えてみる方がずっと伝わります。
自分から簡単に話しかけられない
何をどう話せばいいの
返事がなかったり、沈黙になったらどうするの・・
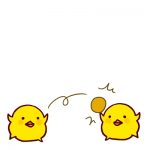 そんな不安を子どもがその後に話せて
そんな不安を子どもがその後に話せて
それについて一緒に話せるのならば良いですね。
ただ、大雑把なアドバイスだけで
子どもの気持ちを変えようとするのはNGです。
同じような言葉に
「気持ちを強く持って」というのもありますね。
気持ちを強く持つって、具体的にどうすることなのか?
そんな話ができればいいのですが・・
抽象的なアドバイスのみなのは
相手をただ困らせるだけなのでNGです。
 子どもが不安になっているので
子どもが不安になっているので
気分をはらさせようと
好きなことをやらせたり
どこかに連れて行くこと、
そのものはまずいことではないのですが
それは子どもが本当にそれで不安を解消できたり
「ま、いいか」と思える場合だけ有効です。
それでも消えない不安である場合には
好きなことをやり放題にさせたり(ゲームなど)
欲しいものを買い与えたり
遊びにだけ連れ回すを繰り返しても
不安を味方にしない限り
不安に取り込まれてしまいます。
その時一瞬の笑顔なのかを見分けるのがポイントになります。
 また、子どもの気持ちに寄り添うのではなく
また、子どもの気持ちに寄り添うのではなく
子どもの機嫌を親が取ろうとする姿勢が繰り返されると
子どもは自分で自分の機嫌を取ることができなくなります。
それは結構恐ろしいことなのでご注意です。
参考:”子どもの気持ちに寄り添う”への、よくある誤解と5つのNG対応
今わかったので、気をつけます
子どもが暗い顔をしていると
親はつい、なんとかしてあげようと思っちゃいます。
はい、私もそうでした
思った途端に動いてました
(^^)>
でも、子どもの不安は原則的には子どもの課題です。
自分で自分の課題を乗り越えられるようにサポートするのが親のお役目です。
 実はサポートするよりも
実はサポートするよりも
自分でやるほうが楽なことが多いです。
そしてつい、自分がなんとかしてあげようと
やたらアドバイスをしたり
親が代わりに先生に
「なんとかしてください」と言いに行ったりしてしまいます。
でもその結果が
子どもの成長のチャンスを摘むことになったり
子どもの学校生活の環境を乱すのではあまりにも残念です。。
アドバイスは望むかどうか尋ねて
望まれたら情報提供で十分です。
一緒に情報を調べるのもいいですね。
「できそうにないけど、どうしたらできるようになるかな」
と言われたら
それをその子ができることまでに
リフォームするのを一緒に手伝うくらいです。
 それでも解決できない場合には
それでも解決できない場合には
自分がなんとかしよう、とこだわるよりも
当カレッジにご相談ください。
ずっと安全、簡単にその子が成長できるヒントが手に入ります。
でも「できない」って言われるので
直ぐに他のアイデアを探したりして。
自分がなんとかしてあげなくちゃって思ってました。
はい、まさに私も同じタイプでした。
アドバイスの言いっぱなしは
あまり役立たないと
私も身を持って経験した一人です。
子どもが新しい環境に慣れるまで、親の有効なサポート
次に、親ができる、有効なサポートについてです。
1)落ち着いて、目的を思い出す
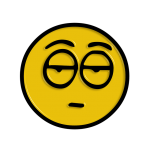 実は、不安は伝染しやすいんです。
実は、不安は伝染しやすいんです。
特に課題の分離があやふやだと
子どもの不安に、簡単に親が不安になってしまいます。
そうなると子どもも更に親の影響で
不安が強くなる・・という悪循環になりますのでご注意です。
落ち着くには先程の「5つの知っていること」を思い出すのがおすすめです。
深呼吸もいいですね 🙂
親の役割は
子どもが長距離を安定的に走れるように
サポートすることだと思い出して
身体・心・頭へのサポートに注力してみてくださいね
きっと良い結果に繋がります 🙂
 子どもが不安を味方につけて
子どもが不安を味方につけて
新しい環境に楽しく慣れていくことを経験するには
身体にエネルギーがしっかりあることが前提になります。
身体がエネルギーが不足だと
そもそもマイナス思考になるので
不安がとても強くなります。
エネルギー不足だと
「自分にもできそう」と思えることが
少なくなるので
あれこれ不安に感じたり
「できそうな感覚」が持てなくなります。
身体のエネルギーを上げるには
睡眠・生活リズム・栄養、そして運動です。
身体のエネルギーは生化学的なものなので
本人の意志に関わらず
この4つがあればしっかりたまります。
(運動はある程度エネルギーが溜まってから
その量に合わせて進めていきます)
 また、物理的な側面からいうと
また、物理的な側面からいうと
「学校」が新しい環境になることに
不安を持ちやすい場合は
習い事や塾、ボランティアの集まりでも
なにか継続している「場」があるのも役立ちます。
一つしか属する「場」がないと
それが新しくなると
自分の全部が落ち着かなくなりますが
「ここは変わらない」という場があると
そこで落ち着くことができるので
不安にもちゃんと向き合いやすくなります 🙂
心のエネルギーアップは
勇気づけと
感じている感情をそのまま外に出すサポートです。
 勇気づけは
勇気づけは
新しい環境に関わらないことでもOKです。
ちょっとした子どものできていることや
頑張っていることに
「見ているよ」というサインを送るつもりでするのがおすすめです。
落ち込んでいるから
気分を変えさせようとか
「~~させよう」モードだと
すぐに見抜かれて逆効果になります。
いつも気にかけている
応援している
そんな気持ちが伝わればOKです。
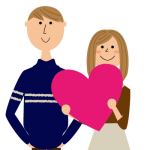 自分には安全基地があることを感じられれば
自分には安全基地があることを感じられれば
落ち着いて不安とも向き合えます。
子どもが感じている感情をそのまま外に出すサポートは
マイナス感情でも
「何が気になってるの?」
「どう感じているの?」と
責めたり解決しようとせずに
子どもが自分の感情を言葉にして外に出せるように関わることです。
それは「不安に共感すること」が目的ではなく
子どもに「自分はこう感じている」と
ただそのまま表現させることが目的です。
その環状や出来事への
評価判断・アドバイスは要りません。
「そうなんだね」とただ
子どもがそう感じている、という事実を受け止めるので十分です。
 そこでアドバイスを求められたら
そこでアドバイスを求められたら
「それがどうなったら良いのか」を聞いて
「自分ではなにかアイデアはある?」とか
「似たようなことでうまく行ったことは?」などと
話を進めていければ、バッチリです。
「5つの知っておくと良いこと」の
4)何に不安を感じているのかを知る
を、子どもができるようにサポートしていきます。
思春期になると
「なぜ大丈夫なのか」
「なぜゆっくり慣れれば良いのか」などへの
納得できる答えを欲しがります。
なので、「5つの知っておきたいこと」を
話すのも役立ちます。
 具体的な不安を一緒に特定して
具体的な不安を一緒に特定して
それに役立つ具体的な方法を見つけるのもいいですね。
身体に元気があって
心が安定していて
頭で理解すれば
不安を味方につけることができます。
だんだん、子どもが長距離を安定して走るために
私ができることがイメージできてきました!
新しい環境への不安がとても辛い子:そのタイプと親のサポート
多くの場合には
ここまでのサポートで
新しい環境に自分らしく慣れていきます。
ただ、子どもの中には
新しい環境への不安がとても強くて、辛さがとても大きい子もいます。
ここでは、よく見られる5つのタイプと有効なサポートのポイントについてもご紹介します。
(その他の場合にも個別にご相談ください)
新しい環境への不安がとても強い子
 クラスで「ちゃんとしている」
クラスで「ちゃんとしている」
「良い子」だと思われたい子は
友達と楽しそうにやっている自分でないとならないと
思っていることがあります。
以前「友達100人できたかな」という
歌がありましたが
*友達は多いほうが良い
*人気者通い
*クラスカーストの上位に入るには友達が必要
という思い込みがあるのかもしれません。
そういう場合には
どんな子とも
自分で適切な距離感を
その時時で決めて良い、と教えてあげると
ものすごく驚くことがあります。
 自分はどんな人と
自分はどんな人と
どんな時に
どんな距離感でいれれば
一番心地よいのかを見つけられるといいですね。
自分に自信がないので
誰かに頼っていたい思いが強い子は
早く頼る(自分が隠れる)対象を見つけようとすることがあります。
まずは身体・心・頭へのアプローチで
基本的な自信をつけることが大事ですね。
そして「対等な関係」が築けるように
サポートしていきます。
 そしてどんな子でも
そしてどんな子でも
何もかも自信がないわけではないので
その子の自信を育てることも役立ちます 🙂
3)感覚過敏の子・怖がりの子・疲れやすい子・発達課題がある子
感覚過敏の子(HSPと呼ばれることもあります)は
特に新しい環境のざわざわした感じを辛く感じやすいです。
怖がりの子も
ちょっとしたことに不安を感じやすいので
「知らない」事が多い新しい環境には
とてもナーバスになります。
また、心身のエネルギーが少なくて
疲れやすかったり
イライラしやすい子も
新しい環境は苦手です。
 何らかの発達課題がある子も
何らかの発達課題がある子も
環境が変わるのが苦手で
自分の不安にうまく対応できないことも多いです。
これらのタイプは身体の課題の影響が大きいので
心や頭に働きかけるだけは
改善が難しかったり
感覚の問題なので
本人がうまく言葉で説明しづらいところがあります。
半端な言葉がけや
説得で改善させようとするのは
逆効果になることが多いので
気をつけてたいところです。
でも、ご安心ください。
 感覚過敏もエネルギー不足も
感覚過敏もエネルギー不足も
疲れやすさ、イライラしやすさも
身体へのアプローチで
土台から改善できるんです!
ピンときた方は
当カレッジにご相談ください。
コミュニケーションの苦手さについては
本人が意識している場合と
していない場合があります。
小中学生だと
自分がなぜ相手とうまく行かないのかが
よくわからずに
ただ、自己肯定感を落としてしまっていることも多いです 😐
 また、逆に
また、逆に
「自分はコミュニケーションが苦手だ」と
抽象的に思い込んで
身動きが取れなくなっている場合もあります。
こちらは中高大生に多いです。
でも、こちらも大丈夫!
何が苦手なのか、を具体的に見つけて
その部分に何をすればいいのかが分かって
それをやってみて
「うまく行った」という体験が作れれば
ちゃ~んと全員改善します。
こちらも個別の対応が大事なので
ピンときた方はご相談ください。
 これまでの体験で
これまでの体験で
友達関係や先生や部活の指導者との関係で
つらい経験がある場合には
新しい環境への不安がとても強くなることがあります。
友達関係は思春期には
本能的に大事なものなので
それを強く求める部分と
辛かったので避けたい部分の葛藤が
かなり強くなります。
また、先生や部活の指導者だと
立場の違いから
かなり精神をえぐられていることもあるので
こちらも辛いです。。。 😐
 でも、こちらも個別対応で
でも、こちらも個別対応で
トラウマを過去にすることができますので
ご安心ください!
トラウマは過去の記憶に
強い、辛い感情が結びついたものです。
強い、辛い感情を
リリースすれば
それは「過去の体験」になります。
こちらも個別にご相談ください。
感覚過敏や怖がりも改善できるんですね!
うちの子は小さい頃から怖がりなんです。
「性格」だと思ってましたが
改善できたら
うんと楽になりそうです!
はい、今の状態がどんなものであれ
強すぎる傾向は改善することができます。
希望を持ってご相談ください 🙂
実例:環境の変化が毎回辛かった子
Aさんは小さい頃から怖がりでしたが
思春期になって
特に中学生になった時から
春の環境の変化をとても辛く感じるようになりました。
 小学校の5年、6年のクラスに
小学校の5年、6年のクラスに
馴染みにくかったので
中学での生活にとても期待していたのですが
頑張りすぎて
夏休み前から登校渋りが始まり
2学期からは登校できなくなっていました。
家でずっと過ごしているうちに
徐々に元気になってきたので
2年生の春からは登校しようと
思っていたのですが
いざ登校してみると
緊張することが多く
5月の連休前から
また登校できなくなりました。
 5月の終わり頃に
5月の終わり頃に
当カレッジでサポートを始めることになりました。
始めはセッションは絶対に嫌!と言っていったので
お母さんがお子さんへの対応を
バージョンアップさせたり
身体・心へのアプローチを始めるところからのスタートでした。
1ヶ月もすると
家でとても元気になってきて
徐々に学校に行く話をするようになりました。
少しずつ本人の
「また登校したい」という意欲が
表に出てくるようになったので
小さなチャレンジをしながら
自信もつけていきました。
 やがて自分から
やがて自分から
「セッション受けようかな」と
言うようになって
ズームでお会いすることができました。
自分の思いを沢山話してくれるうちに
「中学を楽しみたい。」という気持ちが
膨らんできて
登校を始めることになりました。
そして夏休みには
勉強やコミュニケーションの不安へも
準備をして
夏休み明けから
登校を始めました。
 始めはゆっくりペースでしたが
始めはゆっくりペースでしたが
ゆっくりでも進むことができたので
徐々にクラスにも授業にも慣れていくことができました。
焦らずにいられたので
ゆっくりと、同じ趣味の友達も見つかって
毎日朝から晩まで登校できる
体力・気力がついていきました。
それから約1年と少したって
この春に
大好きな部活がある高校に
合格して通うんです!と
嬉しい報告をいただきました。
 今は新しい環境に
今は新しい環境に
不安が0ではないけれど
部活にはもう既に参加しながら
新学期を自然体で楽しみにしているそうです。
こんなに落ち着いて
春を迎えられるのは初めてです、と
お母さんも笑っていらして
私もとても嬉しかったです 🙂
新しい環境に慣れるまで:おわりに
子どもの顔が暗くなるので
私もどうしたらいいのかと不安でした。
「性格」だから諦めるしかないのかと思ったり
でもずっとこれで
この先大丈夫なのかと心配したり。。
でも今日は、どんな状態からでも
もっと楽に過ごせるようになれる事がわかって
本当に嬉しいです!
実は家でできる有効なことって
たくさんあるんです
なんとかしたいと思いながら
自分なりにあれこれやっていましたが
効果が出なくて・・
何をするのはNGか
何をすると効果がでるのかを
今日はちゃんと分かってよかったです!
次はもともとの怖がりについて
またご相談させてください
❤❤あとがき❤❤
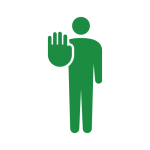 世の中には「変わらない」とされていることが多いです。
世の中には「変わらない」とされていることが多いです。
でも実際には
「この世で変わらない
”変わり続ける”ということだけだ」
というJonathan Swiftの名言があるように
よくも悪くも変化は常にあります。
「性格」だって同じです。
どうせなら
「幸せに楽しく生きる」方向に
変化を進めていきたいですね。
また、変化を
急激に大きなものばかりだと
捉えるのも避けたいものです。
 特に「成長」は
特に「成長」は
一日一日、毎日続いているのですが
その一日一日の変化は気づきにくいです。
特に土台や中身が
変化成長している時には
外から見えにくいことも多いです。
ある日ふと
「こんなに成長している」とわかります。
私はかつて
せっかちで直ぐに結果を求めていました。
でも色々痛い目?にもあいながら
一番確実なことは
日々ちょっとずつ積み重なることだと
気づくようになりました。
 そしたら日々の中の
そしたら日々の中の
小さな変化にも気づけたり
それを喜べるようにもなりました。
今、小さな変化があるということは
この先にもっと大きな変化につながることだと
想像するのも楽しいです。
人間の子育ては
特に長い時間を要します。
子育ての結果やかけた愛情は
わかりやすくないですが
一番確実に深いところを成長させていると思います。
あなたの日々の子育てを
いつも応援しています
(^^)
合わせて読み大記事:
子育ての悩みは『個別サポート』で手放せる!
不安が強い子どもの親御さん必見!効果的な対処法とNGな関わり方
思春期に「発達障害かも?」 と思ったら:危険な二次障害にはご用心