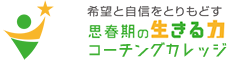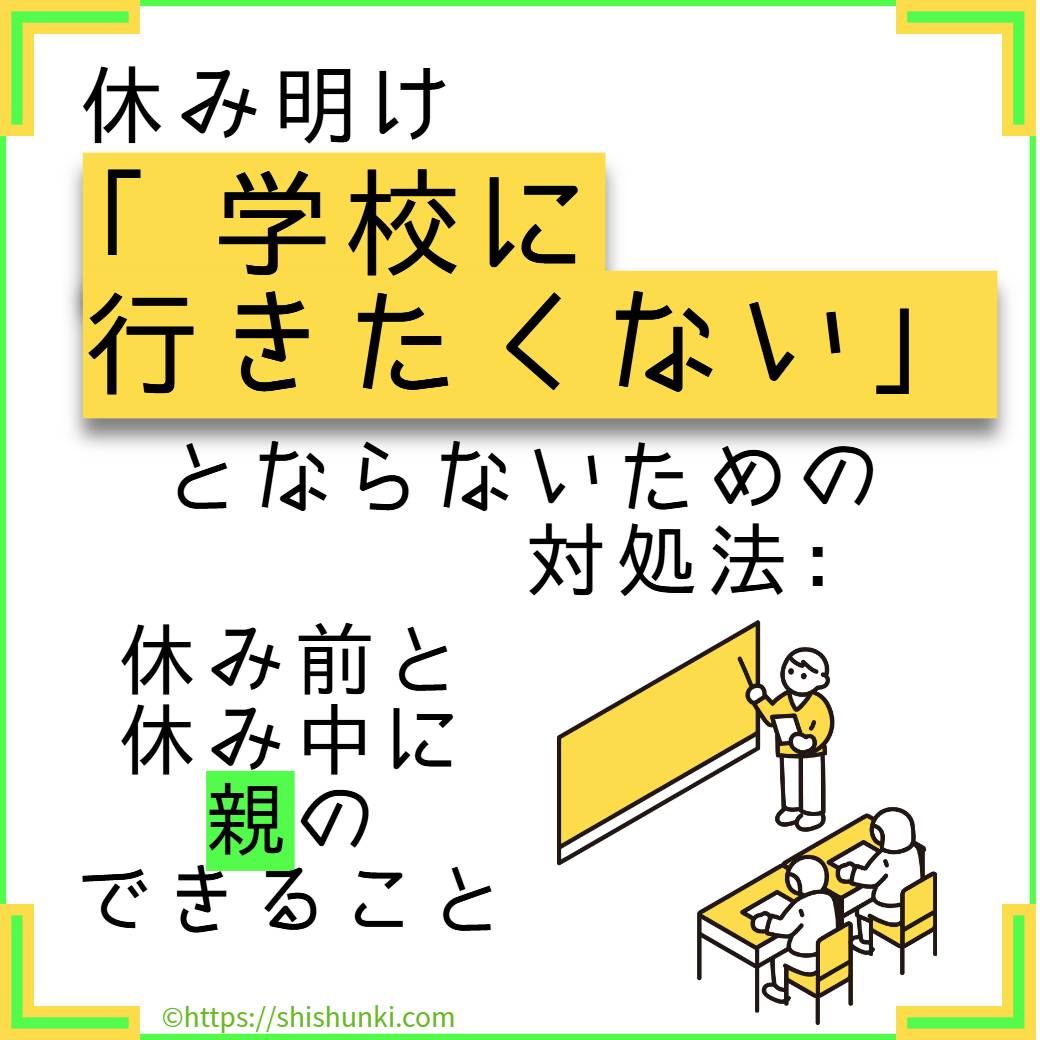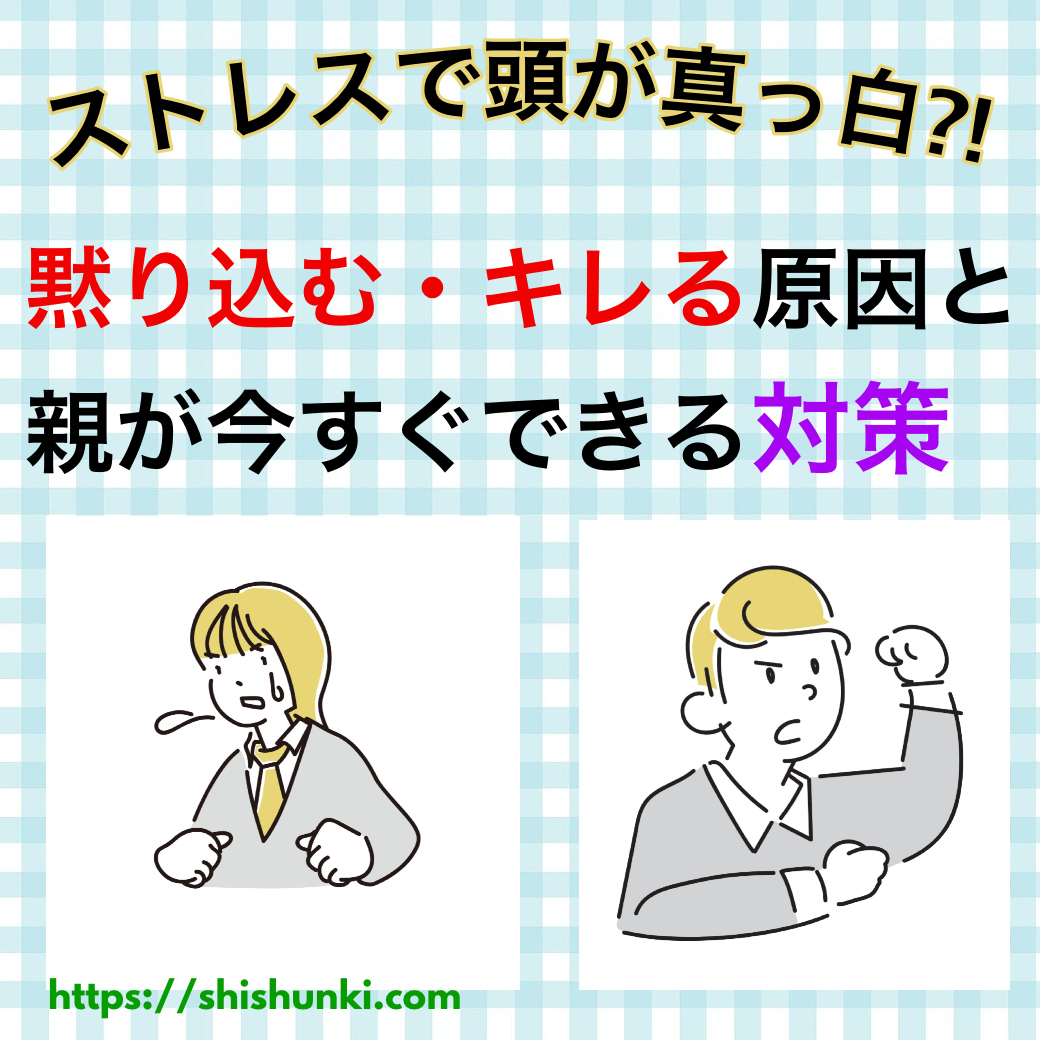やりたくないことはやらない子:性格だからと受け入れる?
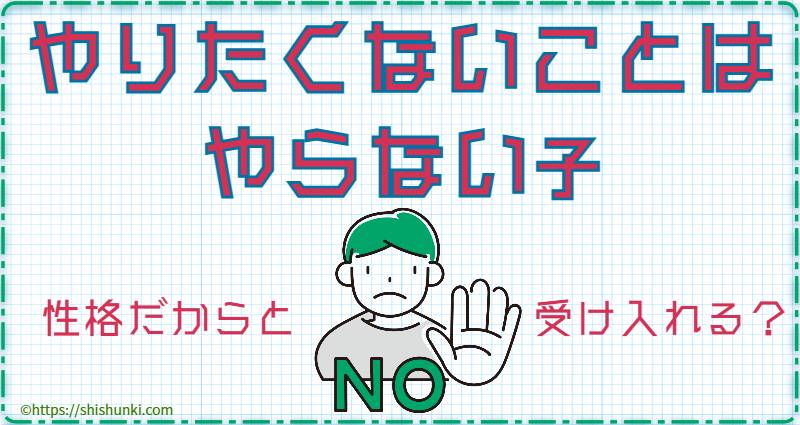
「やりたくないことはやらない」子が増えています。
子育てをしていると
「子どもの気持ちを尊重して」
「自主性を大事に見守って」などと
親が言われることも多いので
子どもの「やりたくない」を
どう扱ったらいいのか迷うこともありますね。
「やりたくない」「嫌だから」と言い出すと
頑としてやらないので手を焼いています。
子どもによっては
もともと主張が激しいタイプの子も
おとなしめ目の子もいますね。
主張できるのはある意味
「表現できる」とも言えますが
年齢とともに
周りに理解してもらえるような表現の仕方や
「人の話を受け取る力」も必要になってきます。
ちょっとしたことなら
「嫌だから」でもいいんですが
年齢が上がってきたら
それでは通らないことも増えてます。
ただ、「とにかくやりなさい」と脅したり
「我慢しなさい!」と言うのも
何か違う気がするんです。
おっしゃるとおりですね 🙂
今やりたくないことにも
必要ならば
向き合えるようになってほしいと思っています。
ただ、それをどう伝えたり
どこからどうサポートすれば良いのかがわからないので
ずっとモヤモヤしています。
今日はそんなご相談で伺いました。
分かりました!
では、「やりたくないことはやらない」子の
生きる力を伸ばすコツについて
ご一緒に見てきましょう 🙂
目次
要注意!子どもの「やりたくない」への親の2大NG対応
まず初めに、よくありがちな
2大NG対応を知っておきましょう。
「もしかしたら、やってるかも!」と思ったら
すぐにその対応はやめるのがおすすめです!
1つ目は「やりたくないを無視してやらせようとする」
2つ目は「結局”やりたくないことはやらない”を許す」です。
 1つ目の
1つ目の
「やりたくないを無視してやらせようとする」は
「とにかくやるべきことなんだから、やりなさい」
「つべこべ言わずにやりなさい」などがありますね。
かつてはそういう
「大人・親・先生の言うことは聞くべし」
という考え方が多かったので
親世代では、子どもの頃に
そう言われてきた方は
「自分が言われてきたように」
そんな言葉で対応していることがあるかもしれません。
ただ、今は社会環境も変わってきています。
小さい頃から動画やSNSを見て
「いろいろな考え方がある」ということを
子どもは既に知っています。
 また、ネットの「好きなようにやる」動画が
また、ネットの「好きなようにやる」動画が
無責任で楽しそうに見えて
「自分もそうしたい。そうできないのはおかしい」
と、思っている子も多いです。
なので、頭ごなしに
「いいから、とにかくやりなさい」と言われることに
強く反発する子が今はたくさんいます。
その反発を親が力や罰で抑えようとすると
親の力が強い間は(小学生くらいまで)
しぶしぶそれをやったとしても
子どもの内側の不満はずっと残ったままになります。
そしてそれが、のちの親子関係に影響してしまうことがよくあります 😐
 中学生以上になったら
中学生以上になったら
大事な進路選択の時や
何か問題が起きた時に
親子で話し合うことができなくなってしまったり
今度は子どもが
親を怒鳴ったり反発することで
主導権を握ろうとするパターンもあったりします。
「いいからやりなさい」と
言われて育ったので
その後大事な話を親にしなくなってました。
それが嫌だったので
子どもに頭ごなしにやらせるのにも
違和感があるんです
そうだったんですね。
子どもには
自分の「やりたくない」をただ我慢するのではなく
それと向き合って
現実と折り合いをつける方向に
進んでもらいたいですね。
また、無理にやらせようとすると
子どもが反発を諦めて
自分の気持ちを感じたり
自分で考えることを諦めてしまうというパターンになることもあリます。
 「何を言っても無駄。
「何を言っても無駄。
大人しく言うことを聞いているのが一番」
となってしまうんです。
でも、今は進路選択や就活でも
「自分が選んだ理由」を詳しく聞かれます。
「自分で選んだ」軸がないと
入ってもすぐにやめたり
不適応になることが多いからです。
そうなんです。
子どもの「やりたくない」を無視すると
その場では子どもが言われた通りにやったとしても
今の「自立」を求められる社会では
すぐに子ども自身に大きなツケが回ってきてしまいます。
気をつけたいですね。
2つ目の親のNG対応は「結局”やりたくないことはやらない”を許す」です。
主張が強い子
言い出したら簡単に引かない子に
対応し続けるのは
根気と時間が要ります。
 親も忙しいですし
親も忙しいですし
他の兄弟姉妹がいれば
その子だけに時間と手間をさけないこともありますね。
それで、ある程度
「ダメ、ちゃんとやりなさい」と言っても
子どもが引かないと
「もう、しょうがないわね」と
親が根負けして
結局、子どもの「やりたくないことはやらない」を
許し続けてしまう状態なっていることも意外と多いんです。
そしてさらに、「やらない」結果必要となった
学校や塾への連絡などの後始末まで
親がやってしまう・・
というループに親子でハマっているパターンも結構あります。
 親としては
親としては
「これでこの件は片付いた」と思うのですが
子どもがそれで学習するのは
「やりたくないことはやらない」を主張し続ければ
結局親がなんとかしてくれる
になります 😯
そして、それ以降ますます
子どもは簡単には「やりたくないことはやらない」を
譲らなくなるので
更に親はめんどくさくなって・・
という強力な負のループができちゃうので
これも要注意なパターンです!
ずっと子どもの
「やりたくないことはやらない」の尻拭いを親が続けても
子どもが成長すれば
親が手を出せないことも増えてきます。
 そうなると、やっぱり
そうなると、やっぱり
子ども自身が家の外ではうまく行かなくなります。
「やりたくないことはやらない」ばかりだと
「逃げ癖」がついてしまうので
家の中に引きこもってしまうこともあるんです。
始めは私も「やるべきことはやりなさい!」と
子どもに言うんですが
子どもが折れないので
結局途中でこちらが折れちゃうんですよね。
それもよくないな、とは思うのですが
どう話したら良いのかもわからないので
同じパターンを繰り返しちゃってます。
そうですよね。
「代わりにどうすればいいか」がわからないと
別の対応に変えるのは難しいものです。
これから「代わりの対応」についてお話していきますが
ここで2大NGに共通することをサクッとまとめますね。
どちらも
「やりたくないことはやらない」の「やるかやらないか」に注目しているのが共通点です。
つまり「結果」ですね。
 大事なのは「やりたくない」に注目することです。
大事なのは「やりたくない」に注目することです。
子どもの「やりたくない」には、その子なりの理由があります。
それを無視して
「やるか、やらないか」だけに焦点が当たり続けると
子ども自身も
「なぜ自分はやりたくないか」という大事なことに目を向けないままになります。
ひたすら「やりたくないのでやらない」と言い続けてしまうんです。
「なんでやりたくないの?」と聞くことはあったんですが
「やりたくないから」
「めんどくさいから」って返ってきて。。
それで終わりにしてました。
はい、そういう流れになっているご家庭も多いです。
こういう場面では
「引き出すコミュニケーションのコツ」を知っていると役立ちます。
次は子どもの「やりたくない理由」に目を向けてみましょう
子どもの「やりたくない」理由に目を向ける
子どもに「なぜやりたくないの?」と聞いても
子ども自身がうまく答えられないことはよくあります。
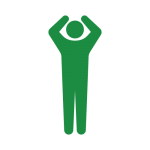 あまり自分の感情とちゃんと感じたり
あまり自分の感情とちゃんと感じたり
言葉にするのが得意ではない子もいます。
ずっと「やりたくないから」
「嫌だから」が家の中で通っていれば
それ以上自分の「やりたくない」の理由を
意識しないですみますので
練習が不足しているんです。
そしてそういう子ほど
「やりたくないからやらない」をそのままにしておくと
ますます自分の感情と向き合えなっていきます。
家の中だけであれば
「やりたくないからやらない」で通っても
学校や友達関係、部活などでは
そうは行かないことが増えてきます。
そういう時には
どんなに拙くても
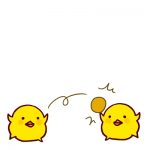 自分なりの「やりたくない理由」を言葉で相手に伝える必要があリます。
自分なりの「やりたくない理由」を言葉で相手に伝える必要があリます。
他者に
「自分のやりたくない理由」を説明せずに
都合よく察してもらって
フォローまでしてもらうことを期待するのは変ですね。
自分から、相手が納得する理由を伝えて
必要ならば
フォローをお願いできるようになる力は
人とつながるには欠かせません。
小学生3,4年になれば、家でも
「やりたくない」「嫌いだから」を
「やらない理由」にせずに
相手にわかるような理由を
言葉にする練習が必要です。
 もちろん、誰でも自分の気持ちを
もちろん、誰でも自分の気持ちを
わかりやすく人に伝えるのは難しいものです。
ただ、少しずつでもやってみることで
上達するのは確かです。
(やらなければ何も変わりません)
また、不十分な説明しかできなくても
自分なりに表現しようとする姿勢を見せれば
それが相手に伝わることもあります。
相手がコミュニケーション上手だと
うまく引き出してくれることもあるでしょう。
ただ、相手が他人だと
「そんなよくわからないこと言って 😡 」と
怒られる可能性もあるので
まずは家の中で練習するところから始めるのがおすすめです 🙂
私の方が先に諦めてましたが
もうちょっと粘って
引き出してあげるといいんですね
そうですね 🙂
大人も忙しいので
すぐに時間がとれなければ
「夕食後に聞かせてね」でもOKです。
簡単に「やりたくないから」「嫌だから」で
話を終わらせないことが大事です。
今まで自分の気持ちの土台にあるものに
目を向けてこなかったら
始めはぎこちなかったり
うまくできないこともあるでしょう。
 でも、焦らずに
でも、焦らずに
少しずつ進めていけば
必ず徐々にできるようになります!
それは、これまでの当カレッジで
数多く見てきた実際の親子さんが教えてくださった事実です 🙂
ちょっとしたことでも
自分の気持ちについて話すことができれば
たとえそれが屁理屈でも
そこにある「思い込み=〇〇がこうだから」に気づくこともできます。
気づけばそれをリフォームするチャンスにもできます!
そして、自分の「やりたくない」理由に気づけば
その理由を外してやってみることも考えられますし
逆に「こうならやれる!」というものを
見つけることもできます 🙂
ちゃんと、完璧に説明できなくても構わないんです。
 まずは少しずつでも
まずは少しずつでも
子どもの「やりたくない」の理由を引き出してみましょう。
「やりたくない」の3大要因と対策
これには3パターンあります。
①やったことがないことや、今までとは違う条件だから、うまくやれるかわからない。やれないかもしれないのは嫌
②前に何度かやったけれど、うまくやれなかった
③以前やってみて、傷ついたことがある
 どれも、うまくやれなさそうだから「やりたくない」と
どれも、うまくやれなさそうだから「やりたくない」と
思っているパターンです。
①やったことがないことや
今までとは違う条件(メンバーや場所が違う)に
うまくやれないだろう・・という不安を感じています。
このパターンへの対策は
お子さんの個性と状況に合わせていくつか考えられます。
例えば実際にやってみると
徐々に慣れていって
やがて不安なくできるようになる場合もあります。
「やってみればできる」なので
「やりたくないからやらない」で
手を付けないのはもったいないですね。
 また「新学期の友達作り」への不安を
また「新学期の友達作り」への不安を
3月4月に感じている場合には
毎年5月になれば
それなりに友だちができているなどの
自分の成功体験を思い出すことで
少し不安が和らいで
「やらない」から「もう少し続けてみよう」になることもあリます。
そこで「自分は新しい環境が苦手だけど
慣れれば大丈夫」と感じることができれば
その後も、簡単に「やらない」にはならずにすみますね 😉
また、何か条件があれば「やりたくない」度合いが下がる場合もあります。
例えば登校したくない場合でも
お母さんに校門まで送ってもらえばOKだったり
朝クラスに一番早く入っていればOkということもあります。
 そういう「やりやすくなるヒント」が見つかれば
そういう「やりやすくなるヒント」が見つかれば
「やらない」を手放すこともできますね。
このようなヒントは
これまで似たような経験を乗り越えた時を
思い出すと見つけやすくなります 🙂
さらに「予期不安」が強すぎる場合には
不安への考え方を教えるのも有効です。
不安が強い子どもの親御さん必見!効果的な対処法とNGな関わり方
また、怖がり度合いがとても強い場合には
身体へのアプローチが有効です。
本能的な「怖がり」を自然にリリースする方法がありますので
ピンときた方は
思春期最幸家族講座か個人セッションでご相談ください。
 ②前に何度かやったけれど、うまくやれなかったので
②前に何度かやったけれど、うまくやれなかったので
「やりたくないからやらない」となっている場合では
別のやりかたを見つければ
うまくやれることは案外多いです。
例えば勉強して成績を上げるのもその一つです。
今の勉強方法が自分にあってないだけで
その子に合う勉強方法にしたら
偏差値が10上がった、ということは
当カレッジでは珍しくはありません。
また、定期テストや受験などでは
計画を立てるのが苦手で
良い結果が出せてないこともあリます。
こちらも計画の建て方を身につけたら
志望校がワンランク、ツーランクアップしたこともざらにあります 😉
 その子の情報処理の特性を踏まえた勉強方法を
その子の情報処理の特性を踏まえた勉強方法を
知りたい方は個別にご相談ください。
③以前やってみて、傷ついたことがある場合には
そのトラウマをリリースして
自然にチャレンジできるようになることができます。
当カレッジのカウンセリングでは
様々な方法がありますので
その場面を思い出すことさえ難しくてもOKです。
自分の納得感が大事な子は
納得できないことをするのが大の苦手です。
そして自分から
「ここが納得行かない」と言える子もいれば
言えずに黙って不満を抱えることもいますね。
 言える子はまだわかりやすいです。
言える子はまだわかりやすいです。
本人の言い分の前提になっている
思い込みを引き出しやすいです。
例えば
「ゲームの使用ルールを決めるなんてやりたくない。
学校を休んでゲームをしている子もいるんだから
自分もそうしても良いはず」などです。
気をつけたいのは
親が安易に
「他の子もそうしているんだ。じゃあ、しょうがないわね」と
飲み込まれてしまわないことです。
本当にそれが我が子のためになるのかや
その言い分が
家の外や、学校や社会で通用するのかを踏まえて
対応するのがおすすめです。
もし、すぐにいい言葉が浮かばなければ
ちょっと考えてから返事するね、でもOKです。
 納得したい子には、穏やかに
納得したい子には、穏やかに
もっと筋の通った理屈を返して
冷静に考えさせるのが一番効果的です。
怒鳴ったりすると、言葉の内容よりも
感情的にヒートアップして
売り言葉に買い言葉・・の応酬になりやすいので
誰にとっても良い結果にはなりません。
効果的な伝え方がわからない場合には、個別にご相談ください。
これまでにもたくさんの成功事例があります 🙂
また、子どもの身体のエネルギーが少なすぎると
自分は屁理屈ばかり言うけれど
正当な理屈を理解しようとしないこともあります。
「2」のパターンの裏に
「3」が隠れている状態です。
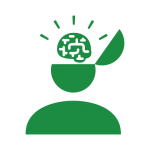 エネルギーが少なすぎると
エネルギーが少なすぎると
人間脳(理屈や客観性)が使えずに
本能的な目先の欲求だけに流されやすい状態なるんです。
大人でも疲れていると
理性的な判断が難しくなりますね。
この場合には身体から見直していくと
とても早く子どもの状態が変わるので
「別の子みたい」に話しやすくなります。
また、タイプによっては
「とにかく最初はNO」がコミュニケーションの癖になっている子もいます。
これも裏に「怖さ」があるのですが
人間関係で最も誤解されやすく
損をしやすい癖ですね。
 この癖を持っていることで
この癖を持っていることで
先生や顧問、指導教授、上司に誤解されて
追い込まれていた子どもや大人も
結構いるんです。
できるだけ早くにリリースするのがおすすめです。
「3」身体のエネルギー切れ
睡眠不足、生活リズムの乱れ、栄養不足などで
そもそもしっかり動けたり
やる気を持って活動できる状態でないことがあります。
身体のエネルギーが少ないと
イライラしたり
マイナス思考になったり
0か100思考にもなりやすいので
すぐに「やりたくないからやらない」と
なってしまうことはよくあります。
 また、身体のエネルギーが不足しているために
また、身体のエネルギーが不足しているために
「学校に行く意味」とか
「生きる意味」を考え出してとまらなくなり
「2」の”納得できないことはやらない”に
なっていることもあるので
ここは適切な判断が必要です。
思春期には特に成長のために
身体のエネルギーが大量に必要です。
足りないとわかりやすく身体に出ることもありますが
精神面に強く出ることもあります。
例えば「やる気」がない状態が続く場合には
身体のエネルギー不足をチェックするのがおすすめです。
子どもによっては
自分の気持だけでなく
身体の状態に気づきにくい子もいます。
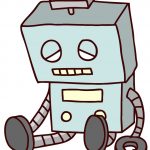 そういう子はぎりぎりまで動いて
そういう子はぎりぎりまで動いて
ある日パタッと動けなくなることがあリます。
お子さんの状況に合わせて
身体のエネルギー状態チェックもありますので
ピンときた方は講座や個人セッションで
個別にご相談ください。
子どもが「やりたくない」と言った場合に
親がしばらく「やらないとダメでしょ」と言っても
子どもがやらないままにしていることがあります。
その時に、親の方が忙しいので
つい、「しょうがないわね」などと
子どもの代わりにその「やりたくないこと」を
結局やってしまうパターンです。
例えば中学生以上になれば
塾へのお休みの連絡などは
(重病の時以外は)
本来子どもが自分で連絡すべきです。
でも「やりたくない」からやらないでいれば
親が勝手にやってしまうパターンが繰り返されるうちに
「別にこれでいいんだ」と子どもが学習してしまうのです。
子のパターンの親ごさんは
自分は一応「やりなさい」と言っているので
「うちの子は言い出したら聞かないから」
過干渉ではない、と思っていることが多いです 😐
でも実際は
子どもの課題を親がやってしまっているので
子どもからすれば
「言い出したら聞かなくても困らない」ので
そうなっているのです。
このパターンは
不登校で起きやすいです。
子どものペースで、とか
子どもの自由に、等が念頭にあると
そうなりやすいです。
そしてそのパターンが
不登校の長期化の一つの要因になっていることはよくあります。
もし、このパターンになっていると気づいたら
子どもの課題を親がやってしまうのではなく
子どもがやるまで声をかけたり
「やらない結果」を子どもに体験させることを
親御さんが勇気を持って始めるのがスタートになります。
そして、あれこれ急に子どもの課題を全部返すのでは
子どもも混乱してしまうので
最も重要なことひとつから取り組むのがおすすめです。
「でも、家が散らかっているのは我慢できない」
と思うこともあるかもしれません。
そんな時には
子どもの尻拭いをずっと続けるか、
しばらくの間散らかっているのを我慢するか
どちらかを、親御さんがまず選びます。
「やりたくないことはやらない子」の力を伸ばす親の関わり方
では、「やりたくないことはやらない子」が、
自分の「やりたくない」という気持ちに向き合って
賢い行動の選択が自分でできるようになるための
親の関わり方のコツをまとめましょう。
 「やりたくない」気持ちを我慢したり
「やりたくない」気持ちを我慢したり
気づかないふりをするという
受け身・被害者ポジションではなく
自分の「やりたくない」の思いと現実の折り合いを
自分で決めて行動できば、バッチリです。
 これは子どもが今「やりたくない」と思っている、という事実を受け入れることです。
これは子どもが今「やりたくない」と思っている、という事実を受け入れることです。
これは「やりたくないなら、やらなくていい」と、同調することと違うのは、ここまで見てきたとおりです。
「あら、そうなのね」などとひとまず子どもの言ってることをちゃんと受け止めたというサインを出しましょう。
子どもの「やりたくない」という気持ちや意見の存在を認めることで、それと現実をどうする合わせるかという次のステップに進めます。
「やりたくない」の下にある、その子の理由を引き出します。
「何が気になっているの?」
「もしやったらどうなると思う?」
 などと、できるだけ子どもの言葉で本人に話させます。
などと、できるだけ子どもの言葉で本人に話させます。
うまく話せなくても、ニコニコ待っているのでOKです。
自分の理由は言いきった、と子どもが思えるまで話しきれれば、バッチリです!
ここで「自分はどうせ勉強しても成績が上がらないから」などの
不適切な思い込みが見つかったら
次の(3)の「どうなったらいい?」とともに
リフォームをしていきます。
身体のエネルギー切れが大きな要因になっている場合には
まず身体のエネルギーを整えることから始めます。
ある程度エネルギーがないと
理論的な会話さえ難しいことがあるからです。
(3)「本当はどうならいい?」を引き出して
「やりたくない」との折り合いの付け方をサポートする
 十分に「やりたくない理由」を出し切ったら
十分に「やりたくない理由」を出し切ったら
この状況が「本当は動なら良い」と思っているのかを
やはり子どもの言葉で話すように引き出します。
始めはノラリクラリと
本心を言わない子でも
じっくり話しを聞いていると
少しずつ話すようになることはとても多いです。
「本当はこうだといい、こうしたい」が出てきたら
そのためにできることを見つけます。
0か100かではなく
0よりも30でも50でも良い、と心がけるのがポイントです。
具体的な場面での工夫の仕方は
先程の「3大理由」や
当カレッジブログにもたくさんありますので
ぜひお役立てください。
 また、講座や個人セッションで
また、講座や個人セッションで
個別にご相談いただけば
個性と状況に合う「できること」を詳しくお伝えいたします。
(1)~(3)でとても重要なのは
子ども本人に言葉にさせることです。
親が
「このままだとーーーとなるでしょ、だから〇〇しなくては」
と喋ってしまうと
子どもはその結論までたどり着く思考ができなくなります。
結局「こうすればいいんでしょ」と
最後の行動だけやったとしても
それは子どもの成長にはあまり役に立たないんです 😐
親のサポートは
やがて、子どもが一人でも
自分の「やりたくない」という気持ちに向き合って
「本当はこうなら良いのに」を見つけて
そのための行動を自らするようになるためです。
 今、その行動をやらせるよりも
今、その行動をやらせるよりも
やがて子どもが自分で
自分の気持と現実に折り合いをつけられるようになる方が
何十倍も価値があリます。
子どもが「やりたくないからやらない」と言っていたことに
考えてみて「やってみたこと」には
必ず見ていたよ、サインを送るのがおすすめです。
それが成功したら
「やらないと思っていたことでも
やってみたらできた」という
良い体験になります。
そには子どもの喜びがありますので
それに「ちゃんとと見てたよ」とサインを出すと
子どももより嬉しくなります。
 また、もしやってみた結果が
また、もしやってみた結果が
思ったほど良くなかったとしても
自分で考えてやってみて
「やりたくないと思っていたことをやれた」
という体験は
その子にとっては大事な経験です。
結果だけを見るのではなく
それへの工夫やチャレンジに光を当てていくと
「せっかくやったのにだめだった。
やらないほうが良い」
という極端な思考にハマりにくくなります。
「やれた」という経験を
さらなる工夫やチャレンジにつながるように
ぜひ、「みてたよ!」サインを子どもに送りましょう。
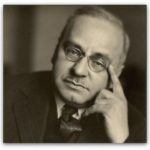 それをアドラー心理学では
それをアドラー心理学では
「勇気づけ」と言います
(^^)
(6)「やりたくないならやらなくていい」という環境を保持しない
これは、すでに
「やりたくないならやらなくていい」という
環境が家庭でできあがっている場合です。
親御さんが忙しくて
テキパキ片付ける力がある場合には
子どもがすぐに動かないと
親御さんが代わりに子どものやるべきことをやってしまいたくなります。
ただそれがパターン化すると
いくら大きな声で注意しても
子どもは「やりたくないことはやらなくていい」と
学習してしまったら
黙って親がやるまで放置します。
なので、一時的には根比べになりますが
子どもの課題は子どもに返していきましょう。
やりたくないことはやらない子:おわりに
言い出すとしつこいので
もやもやしながらも
結局私ががそれを認めてたので
変わらなかったんだとハッとしました。
なにか別の対応を・・と思っていても
代わりにやることが見つからないと
そのままになってしまうことは
もちろん、私にもあります 🙂
自分が子どもにどうなって欲しいのかを
改めて自分で
言葉にすることができたのも良かったですし
具体的にやれることがわかったので
眼の前がスッキリして
気分も明るくなりました
また詳しくご相談させていただきますね
♡♡あとがき♡♡
子どもによって、主張が強い子も
おとなしい子もいますね
どうしても子育ての日々のなかでは
主張が強い子の気持ちを尊重しながら
上手に話を持っていく余裕がないこともあるものです。
ただ、時には時間をとって
子どもと向き合ってみると
子どもが自分で自分の気持ちに気づいて
うまく現実との折り合いをつけられるようになることは
案外多いものです。
 中学生でも高校生でも
中学生でも高校生でも
子どもは大人が思っているよりも
まだ成長途中なので柔軟です。
必要な良い刺激をポンと入れるだけで
ぐんと成長して驚かせてくれることもよくあります。
当カレッジでは
お子さんへの直接セッションも多いので
「こんなに成長しましたね!」と
お母さんと嬉しい驚きを分かち合うのも
コーチの喜びの一つです。
(^^)
合わせて読みたい記事:
思春期の、自分で決めることの大切さと、親が知っておきたい落とし穴
”子どもの気持ちに寄り添う”への、よくある誤解と5つのNG対応
よかれと思ってやったのに・・親子コミュニケーションがうまく行かない時
動画バージョンはこちらです。
音声だけお聞きいただくこともできます。