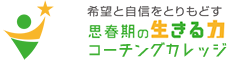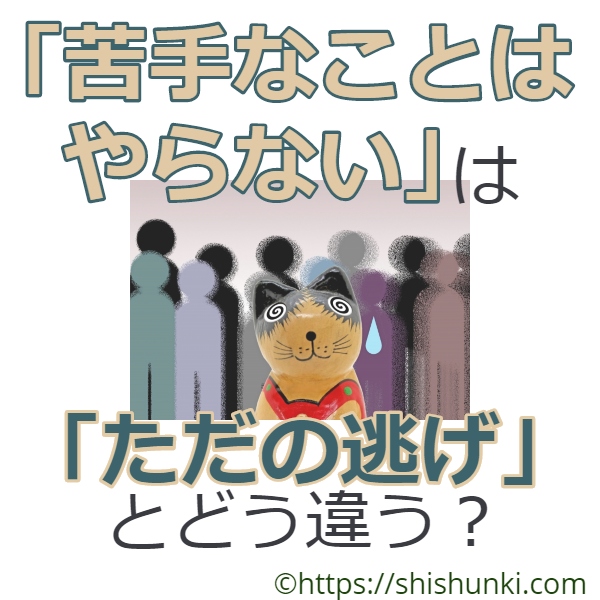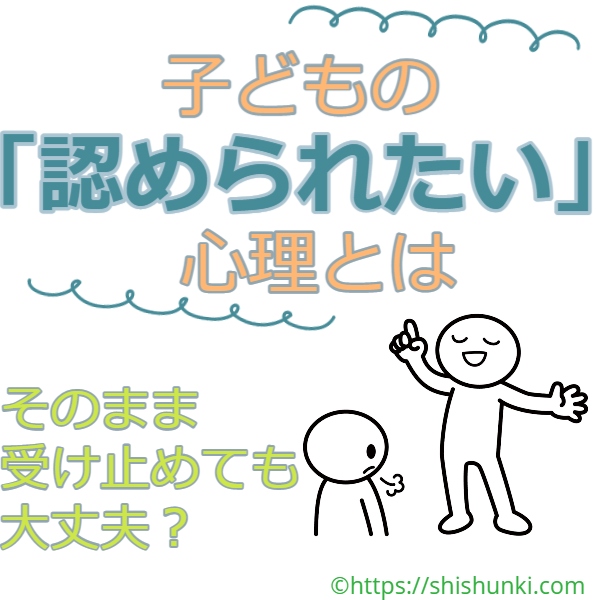不登校の進路について考える時:知っておきたい2つのこと

不登校だと「今学校に行けるのか」だけでなく、その後の進路についても気になってきます。
何をしていてもしていなくても、日本の学生は時間の流れとともに、次の環境に進むことになっているからです。
ただ、不登校の場合には、新しい環境になるのは一つのチャンスにすることもできるんです!
無理に行かさずに見守ってるんですが、時々「この先の進路はどうなるんだろう?」と私も不安になります。
イマドキではフツウに学校に行ってても、進路選びが難しくなってると聞くので、うちのような場合にはもっと大変じゃないかと心配です
不登校がどんなものでどうやって回復していくのかがわからないと「今」についても不安でいっぱいなのに、学生はどうしても「次の進路」について考えることも必要になってしまいますね 😐
当カレッジでは不登校を心身のエネルギー不足と捉えてます。
その子の心身のエネルギー漏れをなくして、十分にネルギーを満たすことで、これまでにも数多くの回復をサポートしてきました。
その子の「今」の心身のエネルギー不足状態によって、その子が身体に元気を、心に希望と自信を取り戻すまでにかかる時間はそれぞれです。
そしてその回復までの期間のどこで次の進路への準備がどう必要になるか・・・というのは、いつも大事なポイントになります。
「進路を選ぶ」のは思春期の子どもにはどこかで出てくる課題ですし、とても大事でそれなりにエネルギーも準備も必要です。
 不登校そのものは、そのようなイベント?がなくて、ただ回復に専念できれば最短で進む・・というところもあるんですが、どうしても「進路」について、どこかで考える必要も出てくるのがリアルです
不登校そのものは、そのようなイベント?がなくて、ただ回復に専念できれば最短で進む・・というところもあるんですが、どうしても「進路」について、どこかで考える必要も出てくるのがリアルです
(^^;)
ただ、この「進路を決める」ことを、不登校の子の心のエネルギーを回復させるチャンスにすることもできるんです!
はい、ではご一緒に、不登校の進路について考える時に役立つコツについてみてみましょう!
目次
不登校の進路について考える時に大事な2つのこと
まず、不登校の進路について考える時に大事な2つのことを押さえておきましょう!
(1) 過去と今の延長線上に未来を決めない:最幸未来から考える
 「進路」は「未来をどう過ごしたいか」で決める、進みたい道のことです。
「進路」は「未来をどう過ごしたいか」で決める、進みたい道のことです。
なので、進路選択で一番初めにすることは、「なんの制約もなかったらどんな未来を過ごしたいのか」に意識を向けることなんです。
ところが私達は「今までこんな状態だから、その延長線上で考えると未来はこんなもん」というところから、進路を考えようとしてしまうことがあります。
今不登校だから、行けるところは・・って。
はい、誰でも気づかないうちに、そう考えてしまうことってありますよね。
では、ちょっとイメージしてみてください。
今東京にいるとして、パリに行きたいとしたら、「どこから東京に来たのか」は関係ないですよね。
パリという目的地と東京という現在地が分かれば、あとは「東京からパリにどうやっていくか」を考えれば良いだけです 😉
また、もう一つよくあるのが「今居る東京が嫌だから、どこでも違うところに行きさえすれば良い」って進路を選んでしまうことです。
今が辛いとそう思いたくなるのも分かりますが、「パリ」とか「シンガポール」とか「宮崎」とか行き先を決めないと、どこにも行けなかったり、適当なところに行ってあとから後悔することになる確率は高いです 🙄
まずは「なんの制約もなかったら行きたい未来」=最幸未来から考えるのがとても大事なポイントです。
でも、「今不登校」というのは考慮しなくて良いんですか?
はい、それはその次のステップです。
「今不登校」というのは、「今東京で熱を出してる」のと同じ、「現在地にどんな状態で居るか」ということです。
なので、行き先が決まったら、具体的に「今の状態で現在地から目的地に行く方法」を具体的に考えていきます。
そこでは「今東京」「今不登校」は大事な現実です。
「今不登校」という現実は、望む未来を手にするには「不登校ではない」状態よりは工夫と戦略が必要なことはあるでしょう。
でも「今不登校」だということが「その未来には進めない」ことにはなりません。
それについてより詳しくは、あとからの「中学編」「高校編」で見てみましょう
(^^)
 まず大事なのは、「今不登校だから」と「今行けそうなところだけ」を進路の選択肢にしてしまわないことなんです。
まず大事なのは、「今不登校だから」と「今行けそうなところだけ」を進路の選択肢にしてしまわないことなんです。
「東京」から「パリ」に行く方法って、自分では「飛行機」「船」しか思いつかなくても、実は様々な方法があります。
チケットの買い方だって様々です。
実際の方法は探せば良いんです。
今自分が知っている方法だけから進路先を決めるのではなく、まず「なんの制約もなかったら行きたいところ」から考える・・というのが、とても大事なポイントです。
その子が「本当に行きたい」と思う進路が見つかれば、希望とやる気が出てきます。
それは不登校からの回復に必要な心のエネルギーの回復にも繋がります。
過去と今の延長線上に未来を決めずに、最幸未来から考えましょう!
(2) 「正解」は一つだと思いこまない
 「このままではマズイ」という恐怖や不安が強くなると、「完璧な正解」が今すぐ欲しくなります。
「このままではマズイ」という恐怖や不安が強くなると、「完璧な正解」が今すぐ欲しくなります。
失敗してまた苦しむのはどうしても避けたい・・と思うのも本能で、人は不安になると視野が狭くなりがちです 🙄
そんな時にはぜひ、望む未来への進み方=進路は
*「一直線の最短コースだけでもない」し
*そもそも「子どもの望む最幸未来もより良いものがこの先に見つからるかもしれない」
ことも、思い出してみるのがおすすめです。
東京-パリなら直行便があるけど、山形-パリには直行便がないから、今山形に居たらパリに行けないってことはないですよね。
直行便があれば最短でいけますが、なくても「経由」していけば望む未来に行く方法はいくらでもあります。
同じように子どもの進路にも「経由」というアイデアもあるんです!
「今すぐ」真っ直ぐに望む場所に行けなくても、経由すればどこにでも行くことができるんです!
 今の子どもたちは「人生100年時代」を生きます。
今の子どもたちは「人生100年時代」を生きます。
もし経由にその1/5を使ったとしても、あとの4/5が最幸になる道を選ぶこともできるんです
(^^)
また、子どもの最幸未来についても、「絶対の正解」を見つけなくては!と思わなくて大丈夫です。
最幸未来がはっきりしてなくても、そのエッセンスを引き出す方法もありますし(講座でもお伝えしています)、そもそも子どもの成長や時間の経過とともに「進みたい未来」さえ変わることもあるのがアタリマエです。
特にイマドキでは、毎年毎年、新しい仕事や幸せを感じるものがたくさん出てきています。
今はまだ無いけれど、3年後に現れるものが、もしかしたらお子さんが最幸に好きで得意で人の役に立てる仕事や趣味なのかもしれません。
かつてのように、時の流れがゆっくりで社会の変化がそれほどなかった頃には、「この進路を進めばこのような未来が手に入る」というのが、ある程度の確率で予測できたこともありました。
でも今ではどの仕事もどの道具も10年後も大丈夫と言えるものは本当に少なくなっています。
 イマドキは「ずっと変わらないもの」ではなく、「数年先の最幸未来」をイメージしながら進んでいく時代です。
イマドキは「ずっと変わらないもの」ではなく、「数年先の最幸未来」をイメージしながら進んでいく時代です。
社会に出てからも何度も転職や進路選択をするのがアタリマエなんです。
次の進路選択に「正解」を選ばないと大変!と思わなくても大丈夫❣
ただ「自分で進路を選ばない」と、社会の変化が早いだけに、どんどん周りに流されてしまうことにもなってしまいます。
全世界の95%の人が死ぬ時に思うことは「もっと自分の好きなように生きればよかった」だそうです。
こんなに様々な選択肢がある時代に、最後にそう思うのではあまりにももったいないですね
(T_T)
自分の進路は「今不登校」ということや「~~と人に言われたから」と決めるのではなく、自分で方向性を決めることがとても大事です。
「パリ」まで決められなくても、「ヨーロッパ」まで分かれば、ヨーロッパに行ってみれますし、そこで何に自分がトキメクのかもわかります。
「仮ぎめ」でもOKなんです。
イマドキは「仮ぎめ」をしながら社会の変化とともに進んでいく時代です。
なんだか肩の荷が下りました
難しいと感じたら、最幸家族講座や個人セッションもご活用ください
では、次に不登校の進路について、中学生編と高校生編をざっくりとみてみましょう
不登校の進路について:中学生編
 中学生の場合には、まだ社会についての情報が多くはないので、「最幸未来」がそれほど先までイメージできないことも多いです。
中学生の場合には、まだ社会についての情報が多くはないので、「最幸未来」がそれほど先までイメージできないことも多いです。
それでも「将来~~になりたい」と思っている子もいますし、「高校ではこんなことができたらいいな」とか「これを学ぶのは面白そう」というイメージを持っている子も居ます。
そのような子の場合には、それが実現できる計画を具体的に立てていきます。
当カレッジではより詳しくそれぞれを進めていきますが、ここでは概要をご紹介します。
 その子が今望んでいることは、「高校で実現することなのか、その先の進路で実現することなのか」をはっきりさせていきます。
その子が今望んでいることは、「高校で実現することなのか、その先の進路で実現することなのか」をはっきりさせていきます。
無理に「将来の仕事」がイメージできなくてもOKです。
「高校では思いっきり好きなテニスをする」でも大丈夫!
その子が今感じられる「望む未来」を扱うほうが心にエネルギーが満ちてきます。
そして、何があったら「その望む未来が手に入ったと感じるのか」なども、より具体的に見つけます。
始めは①で見つけた「外せない条件」を満たす学校をすべてリストアップしてみましょう。
「今不登校だから全日制は無理」などと言わずに、望む未来を叶えられる学校をすべて出します。
また、「通信なら美奈同じ」でもありませんので、個別に詳しく調べるのがおすすめです。
「受かるかどうか」「実際に通い続けられるかどうか」は次のステップで考えますので、このステップではとにかく「どの学校なら望む未来が過ごせるか」だけを考えます。
校風や学費、通学時間や部活などについて詳しい情報を手に入れます。
 その学校の卒業生の進路実績も忘れずに。
その学校の卒業生の進路実績も忘れずに。
タイミングとその子の状態が合えば、できるだけ実際の学校に行ってみるのもおすすめです。
部活については指導方法や先輩後輩の関係性、実際の練習日数や練習時間なども、できる限り情報を入れましょう。
そしてある程度絞れたら、それぞれの進路先に実際に行けるまでの条件(いつどのようにエントリーするのか、何を重視して、何は問われないのかなど)についての情報も、できるだけ早く詳しく手に入れます。
以前よりかなり早くから合否を出すところもありますので、情報は早めに集めておくのがおすすめです。
今は高校もいろいろな形で受験することができますし、「裏情報」もある場合もあります。
今在籍している中学の担任の先生も、子どもに伝えてくれる情報以上のものを、親御さんが尋ねれば教えてくれることもあります。
同じように塾の先生にも、子どもからだけでなく、親からも聞いてみるのがおすすめです。
「良いな」と思ったところは簡単に諦めずに、詳しく調べてみてください。
イマドキの受験は一つの学校についても様々な情報が必要なので、親御さんも情報集めはサポートしてあげるのがオススメです。(これは不登校でなくても同じです)
私の頃とは違いますね
古くからある学校でも、校風や学力などがかなり変わっていることもありますので、最新情報を手に入れてくださいね
そして親と話し合いながら、最終的には子ども自身が複数の候補を決めます。
(決めるについてはこちらもご参照ください:
思春期の子どもが決められない時: 気づかれにくい悩みとワケ)
②で複数の候補を出したら、次は実際の戦略を立てていきます。
ここからは「今のその子」の体力・気力・学力の3つの視点から、候補の進路先に優先順位をつけたり、それぞれにどのように挑戦していくのかを具体的に決めていきます。
ここで大事なのは「今のその子の体力・気力・学力で行けるところ」を選ぶのではなく、「今から進路決定の日までにどれくらい、それぞれが伸びるか」をベースにして進路の候補と戦略を決めることです。
今がどんな状態でも、子どもの体力・気力・学力をそれぞれ具体的に伸ばしていくアイデアは豊富にあるので、ぜひそれらを活用していきましょう!
 当カレッジでは3ヶ月で「これまでとは全く違う体力・気力・学力になる子」も珍しくはありません。
当カレッジでは3ヶ月で「これまでとは全く違う体力・気力・学力になる子」も珍しくはありません。
まずは合格のために必要な体力・気力・学力をつけて、その先に通い続けて十分に活動できるような体力・気力・学力をつけることを目指します。
受験時に完璧に回復してなくてもいいので(できるならそれが一番いいですが)、試験までには合格できるラインまでもっていくのがポイントです。
今がどんな状態でも、それで諦めてしまうのではなく、しっかりと戦略を立ててチャレンジしてことで、進路が大きく変わった子たちはたくさんいます
リアルでは、中学生でもすでに何年も学校に行ってないなどで、学力が望む学校の進路決定の試験日までに上がりきらないと予測される事例もあります。
その子の状態によっては、身体がそれなりの基準まで変化するに時間がか必要なこともありますし、その変化に合わせて親の接し方も変えていくなどの、必要なステップを踏む時間もあります。
そうですね 🙂
そしてこのような場合には、「高校受験までに望む未来を100%叶える」だけでなく「高校の先で叶える」ことを設定する方法もあります。
とにかく諦めないことが大事です。
今までの事例からみると、不登校の子が自分の行きたい進路に向かう場合には、体力・気力・学力を回復させることにとても積極的になります。
今の学校に戻ることよりも、行きたい高校に進むためにならエネルギーが湧きやすい子も多いんです。
なので、予想していた以上に早く回復することもよくあります
(^^)
また、子どもが高校やその先での「望む未来」がわからない場合もありますね。
当カレッジの講座では、そのような場合でも引き出す方法をお伝えしていますが
*どんな高校生活を過ごしたいのか(毎日の過ごし方)
*高校の先に学びたいことややってみたいことはあるのか
という漠然としたイメージから、行きたい高校の条件(男女共学なのか、校風など)をいくつも出してみて、上記のように①②③と進めることもできます。
大事なのは、はっきりとしていなくてもその子の「望む未来」のエッセンスを軸に選ぶことです。
「不登校だから行くところが限られるでしょ」では、子どもの自己肯定感は下がるばかりです。
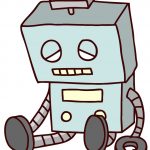 不登校で一番残念なのは、「学校にいけないこと」よりも、そこからその子の自己肯定感が下がって、自分をあきらめるようになってしまうことです。
不登校で一番残念なのは、「学校にいけないこと」よりも、そこからその子の自己肯定感が下がって、自分をあきらめるようになってしまうことです。
そしてそのためには、必ず『頑張れ』という「声がけや見守るだけ」ではなく、子どもの体力・気力・学力を上げる具体的なサポートとセットで受験参略を進めてください。
効果的な方法で子どもが「自分もやれる!」と手応えをつかめれば、その子の自己肯定感も自信も上がります。
また、進路選択で専願や受験日が同じで絞ることが必要な場合には、それぞれに実際に行ったらどんな毎日なのか・・・を具体的に想像しながら、子どもとそれぞれの進路先の「良いところ」と「気になるところ」を書き出してみるのがおすすめです。
その時には「何が充実しているのがその子にとって大切なのか」という視点を忘れずに 😉
部活なら部活をどう楽しみたいのか、勉強なら何ができたら嬉しいのかなど。
アレコレ細かく考えすぎてしまうと、決めるのが難しくなってしまいます。
先程でてきたように「正解はたった一つ」ではないし、「どこに行っても予想しなかった良いこともそうでないこともある」ので、『ここで絶対にベストを出さなければ』と思いすぎないことも大事です。
 ここで深刻になりすぎてしまうと、後に何か『困ったこと」が起きた時に「やっぱりもう一つの方にすればよかった」と引きずることにもなるのでご注意です
ここで深刻になりすぎてしまうと、後に何か『困ったこと」が起きた時に「やっぱりもう一つの方にすればよかった」と引きずることにもなるのでご注意です
(^_-)
不登校の進路について:高校生編
高校生の進路選択は、中学生よりも多くの選択肢があります。
大学に行く、専門学校に行く、仕事をする、etc.
たくさんあるので迷いやすいかもしれません。
それでも最幸の進路選択の進め方の概要は同じです。
 すでに「望む未来」がある場合にはそれをより明確にしていきます。
すでに「望む未来」がある場合にはそれをより明確にしていきます。
その子に「こんなことをしてみたい」という具体的な望むものがある場合にはそれを軸に考えていきますが、高校生ではまだ「社会」や「仕事」についての情報が十分ではないこともよくあります。
「したいこと」や「仕事」がはっきりしていない場合には、「未来にどんな生活を送っていたいのか」からイメージするのでもOKです。
その子が5年後、3年後、2年後にどのような生活を送れていれば嬉しいのかのイメージから始めるのもオススメです。
まだ進路を考える時間がある場合には、自分の好き・得意などからこれまで気づいていなかった「最幸未来のエッセンス」を見つけるのもオススメです。
そしてそのエッセンスが満たされることを調べたり、可能性を感じる場に行ってみるなど体験してみることで、より自分のエネルギーが上がるものが見つけられるようになります。
いま不登校で、今の学校には行けなくても、自分の興味の有りそうな場には行ける子も案外多いです。
高校生の場合には、中学生の進路選択よりもより具体的に考えるのがポイントです。
 大学・専門学校・就職など、高校よりもより専門性が高いので、場によって「自分にあう合わない」がよりはっきりします。
大学・専門学校・就職など、高校よりもより専門性が高いので、場によって「自分にあう合わない」がよりはっきりします。
「不登校でも入れるところ」などで選んでしまうと、自分に合わない場に進むことにもなりかねないので、高校を選ぶ時よりも、自分の望みをできるだけはっきりさせるのがおすすめです。
進みたい未来のヒントが見つかったら、そのための情報集めをします。
その大学や専門学校に進んだ人たちや、仕事場に就職した人たちなど、先輩方のその後の進路などについての情報も忘れずに。
候補について調べたり、体験できるものは体験してみるのが一番です。
大学も昔と今では随分とシステムも変わりましたし、同じような学部の名前がついていても学べる内容は学校やその時の教授によって大幅に異なることもあります。
受験方法もさまざまなので、最新情報をしっかり集めるのがオススメです。
 中学生の場合と違って、高校生の進路についてはより多くの戦略のバリエーションがあります。
中学生の場合と違って、高校生の進路についてはより多くの戦略のバリエーションがあります。
戦略のたて方を学んだり、家族では難しい場合には、コーチという専門家と一緒に戦略を立てるのもおすすめです。
その先で違う選択肢を選んでやり直すよりも、この①~③に時間などを投資するのは効果は大きいです。
例えば、その子が「望む進路に進みたい」と決めた時の状態と、高校卒業までの期間によっては、高校卒業時には望む進路に進める状態にまで整えられないこともありますね。
中学生の場合には、そのような時には「高校で望む未来を実現する」のではなく、その先で実現することを目指すのがオススメでした。
でも高校生の場合には大きく二通りあるんです。
一つは高校卒業までにその子が最大回復して行ける場所に進み、その先で望む未来を実現する方法。
もう一つは浪人して、望む大学に直接進む方法です。
どちらが良いのかは、その子の気質もありますので、その子に合うと思われる方を決めるしかないところです。
 ちなみに私は、高校時代までは偏差値30台から、望む未来を見つけて最終的には2年浪人して東大に入った事例を二つ知っています。
ちなみに私は、高校時代までは偏差値30台から、望む未来を見つけて最終的には2年浪人して東大に入った事例を二つ知っています。
どちらも「望む未来」→「自分にあう勉強方法と戦略」を見つけたことから変わりました。
どちらの方も起業して、現在は大きな会社をそれぞれ経営をされてます。
はい、その子の進みたい未来への方向性と、その子にあう戦略があればいいんです。
様々なケースがあるのでここでは詳しくご紹介しきれませんが、子どもの体力・気力・学力をあげるアイデアはとてもたくさんあります。
子どもは深く落ち込むのも早いですが、逆に必要なサポートがあれば、回復する力も大人よりもずっとあります。
周りにそんな事例がないから・・
学校やお医者さんなどに「変わらない」と言われたから・・
そんなことで子どもの未来を諦めてしまってはもったいない!
望む未来に舵を切れば、子どもの心にエネルギーが湧き出します
ヽ(^o^)丿
不登校の子が自分の進路について考えられる状態になっていない時
・・でも残念ながら、まだうちの子とは、進路についてしっかり話ができる状態じゃないんです。
先のことを話そうとすると嫌がります 😐
こんな状態からでもなんとかなるものでしょうか
そのような場合には、お子さんがまだ不登校の「ショック期」か「安静期」なのかもしれません。
(参考:不登校からの回復過程:長引かせないための親の接し方のコツ)
また、順調に安静期を過ごせていないことで、「不登校になった自分」を責めたり、周りの目を気にしたりしてどんどん動けなくなってしまったり、勉強に遅れが出たことで『どうせ無理』だと希望を失ってしまっていることもあります。
そのような状態では、お母さん・お父さんともコミュニケーションを取らないで、一人でぐるぐる考えてしまうので、家にいても心身のエネルギーが回復しずらいこともあります。
このような状態のままでは、進路の話を論理的に進めるのは難しいですね。
でもご安心くださいね。
子どもがそのような状態の時には、子どもの身体・心・頭へ具体的にサポートをしながら、子どもが一番近くにいるお母さん・お父さんとコミュニケーションができるようになるのを目指すところから始めればいいんです!
 お母さん・お父さんとが難しい場合には、先にコーチと話すのでもOKです。
お母さん・お父さんとが難しい場合には、先にコーチと話すのでもOKです。
有効な新しい情報を入れずに、一人でぐるぐる考えているのは、「考えている」のではなく「悩んでいるだけ」です。
数日一人で考えても良い案が浮かばない場合には、新しい情報を入れる事が必要です。
子どもが新しい情報に耳を傾けられるような状態を心身から作るところから始めましょう!
そして子どもの身体にエネルギーが溜まってきて、誰かと信頼関係を築けてコミュニケーションができるようになると、外からの情報も取り入れられるようになりますので、一人でぐるぐる考える状態から解放されて、視野も広がります。
コミュニケーションが進めば、自分にもまだまだ可能性がいっぱいあることにも気づきますので、自分を責めたり絶望することから抜け出せるようになります。
そして更にエネルギーが溜まってくれば、子どもが自分から、学校や進路についても話題にするようになってくる「回復期」に入っていきます (^^)
子どもには回復する力がありますから、それがしっかり働けるようなサポートをしていけば大丈夫です!
そして進路についても、イマドキでは特に、いつからでもどんな状態からでも舵を切り直すことはできますので、必要なステップを焦らずに進めていけばOKです!
今までにも数多くのご家族がそうやって笑顔になられました 🙂
不登校の場合には、進路を考える前に、子どもが理性的に話せたり考えられる状態になるための準備期間が必要なことがあります。
進路には決定したり提出したり、受験する「タイムリミット」がありますので、それに間に合うように、できるだけ早く子どもの状態を整えるのがオススメです。
もちろん、いつからでもどんな状態からでも、子どもの変化をサポートすることはできるのですが、あえてそれを遅らせることのメリットは見つかりません。
進路についてもできるだけ子どもの最幸未来に最適な選択をするための準備はしたいですし、そもそも不登校という状態は子どもにとっても「不本意で不自由な状態」です。
「学校に行けてないから」ではなく、そのような不自由な状態からは早く抜け出すのがオススメです。
長引かせることで、子どもが自分を嫌いになったり、他者とのつながりが持てなくなってしまえばその後の人生にも響いてしまうからです。
不登校という体験や進路について考える体験を通して、子どもがその前よりも心身ともにエネルギーが上がって、その後も自分の心身の整え方を手にすることができれば、それらの体験を成長のチャンスにすることもできます。
「不登校になったから」何もかもまずくなるのではありません。
「不登校になったこと」よりも、その後に本人や周りがどう行動したり考えるかが大事です。
不登校の進路について考える時:おわりに
でも、不登校も進路の選択も、焦らずに一つ一つ進めていけば大丈夫なんだと思うことができました!
より具体的な進め方をまたご相談させてください。
まずはお子さんの一番近くにいるお母さんが「大丈夫なんだ」と思えることで、お子さんも落ち着けるようになっていきます。
♡♡あとがき♡♡
 日本では、不登校は珍しくも特別なことでもなくなってきています。
日本では、不登校は珍しくも特別なことでもなくなってきています。
それが良いことなのかどうかはわかりませんが、就活でも「不登校だったからダメ」という状態から、「不登校という体験を通して何を学んだか」を問われるようになってきています。
進路について考えることで、自分の望むものに目を向けるチャンスにもできます。
人は下を向いて「自分のだめなところ」について考えばかりだと、どんどん自分のことも嫌いになってしまいますが、「自分の好きなこと」「望むもの」に意識を向けられるようになれば、そこからエネルギーを取り戻していくことはよくあります。
そして「今は好きなことなんて考えられない状態」だとしても、そこから回復する方法だってあるんです!
 色んな情報がとびかうイマドキこそ、ショックな情報に惑わされずに、希望と自信を取り戻す未来に顔を上げていきましょう❣
色んな情報がとびかうイマドキこそ、ショックな情報に惑わされずに、希望と自信を取り戻す未来に顔を上げていきましょう❣
顔を上げれば視野も広がって、いろんなチャンスがあることにも、あなたを助けたいと思っている人にも気づきます
ヽ(^o^)丿
合わせて読みたい記事:
「子供に期待しない 」のが大事?親の期待は子どもをダメにする??
子供の自立に大切なことは?イマドキの思春期の子育てと進路選択
小学生の不登校:知っておきたい学年別の原因と必要な対応、NGな対応
高校生の不登校:全日制と通信制、それぞれでの必要な対応、NGな対応
このブログの動画バージョンはこちらです。
音声だけお聞きいただくこともできます。