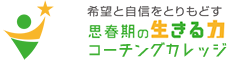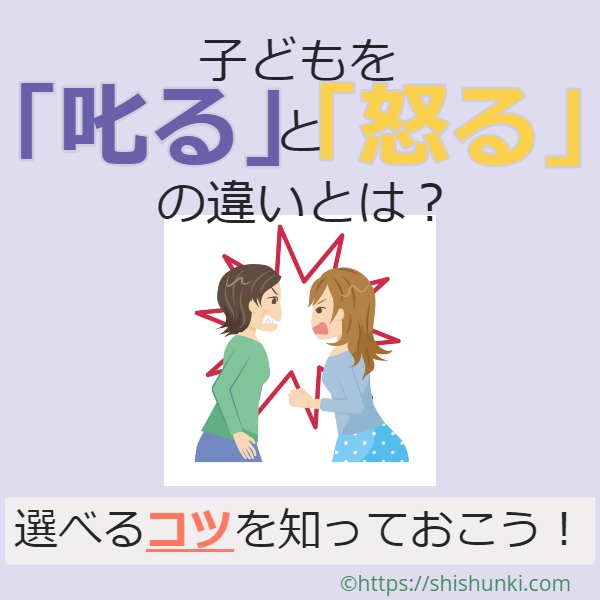増えている隠れ不登校:親が気づくのが大事なワケと接し方のコツ
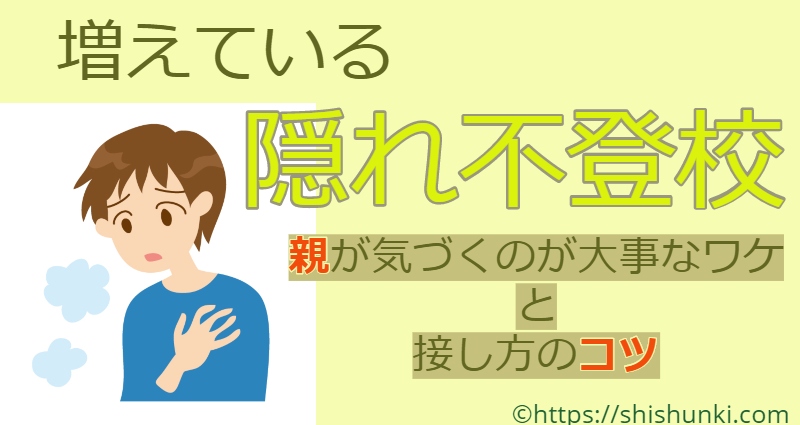
「隠れ不登校」という言葉をご存知ですか
文科省の定める「年間30日以上の欠席数がある=不登校」にはあたらなくても、『本当は学校に行きたくない、クラスに行きたくない』と思っている状態のことです。
隠れ不登校は中学生の5人から4人に一人が当てはまると言われていて、年々増加傾向です。
毎日登校はしてますが、足取りがどんどん重たくなってる気がします。
このままでは長期休みのあとなどに、登校しなくなるのではないかと心配です。
隠れ不登校の子は「本当は学校に行きたくない」と思いながら、頑張って登校しています。
そんな子は土日や夏休み等の長期休みになればホッとして、少しは緩むこともできます。
でもその間に「行きたくないワケ」が解消されたり、十分に心身のエネルギーが溜められなかった場合には、また登校を始める時に頑張りきれなくなってしまうこともあります。
一度止まってから再び動き出す時には、大きなエネルギーが必要になるからです。
休み明けに不登校が増えるのにはそんなワケがあるんです。
(T_T)
話を聞こうとしても何も言ってくれないので、腫れ物に触るようにしてしまいます
私も心配で辛いです
お子さんに尋ねてもうまく話が進まないのは辛いですね。
それでもお子さんがが隠れ不登校かもと、気づかれたのは素晴らしいです!
気づけばお子さんに必要なサポートを見つけるステップに進めます
(^^)
ではご一緒に「隠れ不登校」についてと、接し方のコツを見ていきましょう
隠れ不登校の実態は?
 隠れ不登校は文科省の定める不登校の定義=年間30日以上の欠席がある状態ではなくても、学校やクラスに行きづらい、行きたくないと思っている状態のことです。
隠れ不登校は文科省の定める不登校の定義=年間30日以上の欠席がある状態ではなくても、学校やクラスに行きづらい、行きたくないと思っている状態のことです。
隠れ不登校についての最近のデータは2つあります。
一つは2019年5月に実施されたNHKの取材班による、LINE上での約18000人の中学生へのアンケートです。
このアンケートからは、不登校は約4.5%、隠れ不登校は23.6%という数字が出ています。
またその隠れ不登校を、部分/教室外登校(保健室や一部の授業に参加する子 14.3%)と仮面不登校(通常登校しているようだかが、ほぼ毎日登校したくないと思っている子 9.3%)に分けています。
この調査では隠れ不登校が文科省の基準による不登校の5倍以上いることになります。
もう一つは2018年10月に行われた日本財団による不登校傾向にある子どもの実態調査です。
こちらでは、中学生は不登校の子が約10万人、隠れ不登校は不登校の3倍強の10.2%の33万人という数字が出ています。
また、こちらでは隠れ不登校に
・文科省定義外の不登校(1.8% 約6万人)
年間欠席数が30日未満だが、1週間以上連続で欠席がある
・教室外登校 保健室などクラス外当校
・部分登校 教室にも行くが授業参加が少ない子ども
・仮面登校(授業不参加型) 基本的にクラスに行くが別のことをしている
・仮面登校(授業参加型)(4.4% 約14万人)
皆と同じように登校・勉強しているが、登校したくないと思っている
という分類もしています。
小学生や高校生も加算すると、かなり大きな数字になります。
特に今は小学生の不登校や隠れ不登校が増大傾向です。
それは私も2010年から思春期コーチ™として活動していての実感とも同じです。
不登校や隠れ不登校に低年齢化と増加傾向があるんです。
これらの調査から見えてくるのは「学校に行っているかどうか」や「出席日数」が問題の本質ではないということです。
登校しているかどうかは誰にでもわかりやすいので、「とりあえず子どもが登校している」と親御さんも先生も安心してしまうのは、私も一人の親としてよく分かります。
確かに「登校している」のは、「苦しくても登校できるだけのギリギリのエネルギーはある」わけなので、それ以下の状態よりはマシだと言えなくもありません。
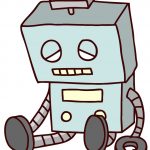 ただ、そんなギリギリの状態で毎日登校し続けてしまうばかりだと、やがて子どものエネルギーが枯渇してしまったり、休み明けに登校を開始することが難しくなることも出てきます。
ただ、そんなギリギリの状態で毎日登校し続けてしまうばかりだと、やがて子どものエネルギーが枯渇してしまったり、休み明けに登校を開始することが難しくなることも出てきます。
身体の病気も本格化する前に手当をすると早く回復するように、不登校もできるかぎり「隠れ不登校」のうちに必要なサポートを得られると早く子どもも元気になります。
もちろん当カッレジでも今までに、様々な状態から希望と自信を取り戻されたお子さんがとてもたくさんいらっしゃいます。
不登校になってから数年たっていた方も珍しくはありません。
ただそれでも、できるだけ早いうちに必要なサポートを得られれば、お子さんもご家族も辛い時期が短くなります。
隠れ不登校のうちに手が打てればそれに越したことはありません。
でも残念ながら、子どもが「登校できない状態」になってから、親御さんが慌てるという状況が多く見られるんです。
ただ、そうなってしまうのにもワケがありますから、次はそれについて見てみましょう!
隠れ不登校のうちにサポートされることが少ないわけ
 隠れ不登校が、不登校になるまで気づかれにくかったり、サポートされにくいのにもワケがあります。
隠れ不登校が、不登校になるまで気づかれにくかったり、サポートされにくいのにもワケがあります。
国では不登校についての数字は公表していても、今まで隠れ不登校の調査をしたという発表はありません。
隠れ不登校にはまだ光が当てられていない上に、まだ現場の学校でも不登校への対応もまちまちな状態です。
対応方針がはっきりしていないことに加えて、先生たちが頑張ろうとしても、隠れ不登校まで細かくサポートできないという現実もあります。
 そして残念なことに、国が動き出すまでにはとても時間がかかります。
そして残念なことに、国が動き出すまでにはとても時間がかかります。
「不登校には休ませることが必要なケースが有る」と国が公に認めたのは2016年になってからです。
それまでも不登校数はどんどん増加していたのですが、「学校には登校させるべき」という指導がずっと続いていたんです。
そして国が指針を変えても、実際に現場レベルまで行き渡るのには更に時間がかかります。
今でも残念ながら学校や先生から「とにかく登校するように」と指導されることもあるのが現実です 😯
そして「休ませて良い」という指針以外には、親御さんに向けての、どのような具体的なサポートが必要なのかについての情報は殆どありません。
たしかに、不登校でも隠れ不登校でも、その子に必要な具体的なサポートは細かく言えば異なります。
それでも大まかな指針が見えないと、家でどのように子どもを休ませたら良いのかと、親ごさんも不安になってしまうのも当然です。
・休ませるというのは、何も言わずに放っておくことなのか
・不登校の子どもは叱ってはいけないのか
・気持ちを聞くように言われても、話しかけても答えてくれない・・(子どもも苦しそう)
 実際に私も子育て中には、そんな迷いをたくさん抱えて毎日を過ごしてました 🙁
実際に私も子育て中には、そんな迷いをたくさん抱えて毎日を過ごしてました 🙁
不登校にさえこのような状態なので、隠れ不登校までの対応の指針が出るまでには、まだまだしばらく時間がかかりそうです。
また、学校の先生は「クラス運営と授業の専門家」でも、「不登校や隠れ不登校を数多く回復させてきた専門家」ではないことがほぼほぼです。
優秀で真面目な先生ほど、忙しい中でも親身に相談にのってくださいますが、「その子の回復」について効果的なサポート方法をご存知かどうかは違う話です。
不登校や隠れ不登校の具体的なサポートについては、今すぐに国や学校のリーダーシップを期待するのは難しいと言わざるを得ないでしょう。
でも思春期の子どもにとって、1年、1月、1週間はとても貴重な時間です。
不登校でも隠れ不登校ででも、学校と協力してサポートするのは大事ですが、話を具体的に進める主体や、見守っているだけでよいのか、どんなサポートが必要なのかは、親御さんが主導で行うしかないのが現実です。
 思春期になってくると、子どもは自分の気持ちを親や大人に表現することをためらうことが増えてきます。
思春期になってくると、子どもは自分の気持ちを親や大人に表現することをためらうことが増えてきます。
よく親御さんからお聞きするのが『不登校や隠れ不登校で担任の先生に相談したら、学校では楽しそうにやってましたと言われました』という言葉です。
それは先生方がただ見逃しているというのではなくて、思春期の子どもは内心どんなに辛くても、できるだけ元気そうなフリをしがちなことも大きく影響しています。
その理由は
・他の人に自分の気持ちを知られたくない
・自分で解決できないことが恥ずかしい
・みんなと同じじゃないと知られたくない(他の子は楽しそうに行けてるから)
・親に心配させたくない
・どうせ相談しても何も変わらない
などなどと、さまざまなものが挙げられます。
 思春期になると、「自分のことは自分でやりたい、やるべき」「大人に頼るのはかっこ悪い」という思いや、「自分らしく在りたいけれど、周りと”同じ”でもありたい」という思いが強くなります。
思春期になると、「自分のことは自分でやりたい、やるべき」「大人に頼るのはかっこ悪い」という思いや、「自分らしく在りたいけれど、周りと”同じ”でもありたい」という思いが強くなります。
それで小さい頃のように素直に自分の悩みや嫌なことを親や大人に表現することがぐっと少なくなります。
子どもなりに『ここで先生に異を唱えたら自分の立場が悪くなるかも』『親は今とても忙しそう』などと考える力も出てきます。
また、子どもなりに気持ちや考えも複雑になる(自分は苦しいけど、友達を悪く言いたくないなど)のですが、それをうまく言葉にする力が足りなくて、飲み込んでしまうこともあります 😐
また、先生や親などに
*自分の気持ちや言い分をちゃんと聞いてくれない。
*上から一方的に命令する
*時に理不尽なことも言うのに、自分が質問してもちゃんと答えてくれない
と感じた経験があると、大人への不信感を持ってしまい、大人に頼るのを諦めてしまうこともよくあります。
 そうなると、大人が『何でも言ってね』と声をかけたとしても、すぐには相談してこなくなってしまうんです 😐
そうなると、大人が『何でも言ってね』と声をかけたとしても、すぐには相談してこなくなってしまうんです 😐
このような場合には、子どもとの信頼関係を強くしていくというステップが必要です。
より、言いやすい関係性を作ることが必要なんですね
親としては「なんで今さら?」と思うかも知れませんが、思春期には再度親子の信頼関係を大切にすることがとても重要になります。
でもそれは愛情を伝えるなど、ちょっとしたことからできるんです。
そして、もしとてもこじれたように思える関係でも、そこから信頼関係を育てることはできますから、ご安心くださいね。
親が隠れ不登校に気づきにくのは、ひとつは忙しさもあります。
忙し毎日では、つい子どもの表情や動きをじっくり見ることも少なくなりがちです。
②で見てきたように、子どもからも自分の悩みを表現しないのもあって、親は子どもが多少元気がないかな?と思ったとしても、普通に学校に行っているから大丈夫だと思ってしまうことも起こりがちです。
 また、子どもが苦しそうだなと思っても「どう接したらいいのか分からない」のでただ見守ってしまうことや「不登校になったらどうしたらいいのか分からない」ので、なんとか登校し続けるうちに回復してくれないかと願ってしまうことも挙げられます。
また、子どもが苦しそうだなと思っても「どう接したらいいのか分からない」のでただ見守ってしまうことや「不登校になったらどうしたらいいのか分からない」ので、なんとか登校し続けるうちに回復してくれないかと願ってしまうことも挙げられます。
助けたい、元気になってほしいと思っても、どう接したら良いのか分からなければそうなってしまうというのは、私もとても良く分かります。
私にもそんな時期がありましたから・・
私が思春期の頃には周りに不登校の子も居なかったので、私は不登校とはどのようなものなのかや、どう接したら良いのかというイメージも全く持てていませんでした。
なので、子どもが学校に行きづらくなっていることに気づいてからも、自分なりに話を聞くようにはしましたが、その次にどうしたら良いのかや、どう学校に相談して良いのかもさっぱりわからずに右往左往してばかりでした。
子どもを休ませたほうが良いと分かっていても、本人に『登校したい』と言われれば、そう言いつつも玄関でうずくまって動けない子どもの背中をただ見ているしかなかったこともありました。
 私なりに「専門家」と言われる方にできる限りコンタクトをとったのですが、もう15年以上前のことなので、当時は情報も少なく、私は「うちの子」を元気にするための良いサポート方法を手に入れることができませんでした。
私なりに「専門家」と言われる方にできる限りコンタクトをとったのですが、もう15年以上前のことなので、当時は情報も少なく、私は「うちの子」を元気にするための良いサポート方法を手に入れることができませんでした。
それでも自分なりに精一杯あれこれ本を読んでは試したりもしましたが、今思春期の専門家として振り返ってみれば、悲しいかな、当時の私は逆効果のこともかなりしてたのです 🙁
そのように、親が精一杯なんとかしようと思っても、「うちの子の場合にどうしたらいいのかわからない」と、隠れ不登校を見逃したり、気がついても必要なサポートができなくて親子とも苦しくなってしまうことも起こります。
現場では「うちの子の場合にどうしたらいいのか」を見つけることが一番大事です。
大まかなサポートの指針も公には出ていない現状では、それを一緒に見つけてくれる、回復事例をたくさん持っている専門家に相談するのが一番の早道と言えるでしょう。
もし「何もせずに見守っている」ことで子どもの状態がマシになったとしても、根本的な課題が解決していなければ、周りの状況が変わったり、他のストレスがかかった時に、また隠れ不登校や不登校になってしまうこともよくあります 😐
専門家なら、その子の根本的な課題解決に必要な情報をちゃんと伝えてくれるでしょう。
隠れ不登校や不登校が増えてるワケは?
文科省の2019年12月発表の資料 によると、
によると、
小校の不登校児童数は44.841人で前年度から約28%の増加
中学生は119.687人で前年比9.8%の増加
高校生は52,723人で6.2%の増加となっています。
過去6年間でも不登校の人数と割合はどちらも増加していますし、高校生では中途退学も減少傾向から増加に転じています。
そしてとても残念で悲しいことに、小中高生の自殺数もこの5年で、横ばいから増加に転じてしまっています。
日本ではようやく成人を含めた全体の自殺者数が減少しているのですが、そのなかでも児童生徒の数が増えていることは、本当に大問題だと言えるでしょう
このように、悩んでいる子ども達が増え続けていること、特に不登校や隠れ不登校が増えているのには、どのようなわけがあるのでしょうか?
 イマドキでは子どもも小さい頃からYoutubeや漫画やサイト、時にはゲームから、さまざまな考え方や個性があることを無意識で知っています。
イマドキでは子どもも小さい頃からYoutubeや漫画やサイト、時にはゲームから、さまざまな考え方や個性があることを無意識で知っています。
今子どもたちに人気なのは「みんなで力を合わせて協力して宝や望みを手に入れる」というパターンのストーリーです。
そのような世界では、各人の特徴や個性を活かして認め合う姿がよく見られます。
昔のように「清く正しい主人公」と「どうしようもない悪の権化」という単純な対立ではなくて、仲間にも敵にもいろんな性格や特徴があって、そこに良い点もまずいところもあるけれど。。というパターンがほとんどです。
仲間でも敵でも、時に対立しながらも、立場を超えて話し合ったり理解しながら友情を深めていくというストーリーがよくあります。
そして実際の社会では「善悪」「集団一致行動」という単純なことばかりでないですから、イマドキの漫画などの方がよりリアルに近いと言えるでしょう。
ところが学校という場では、まだまだ「学校や先生や部活の指導者の言うことが絶対に正しい」という「絶対的な良い・悪い」が幅を利かせすぎている場面もよく見られます。
ある一つの基準に「集団で一致して合わせる」ことや、「学校や先生・部活の指導者は絶対的な善なので、とにかくそれに従うこと」や、「細かな必要性が分からないやり方まで指示されたとおりにやること」を求められる場面も多いのです。
 そこにイマドキの子どもたちは違和感を感じることが増えてます。
そこにイマドキの子どもたちは違和感を感じることが増えてます。
昔のように「皆で同じことをする」や「先生や大人の言うことにはとにかく従う」「必要性がわからないことをする」が難しくなっているのです。
もちろんどんなコミュニティでも、その目的を成し遂げるために定められたルールや秩序を守ることはとても大事です。
それでも思春期の子どもは特に「自分なりの納得感」を大事にします。
それは小さい頃のように大人に言われたことをそのまま受け取るのではなく、「自分で考える力」を育てるために必要な成長のステップです。
(大人からすれば、イチイチめんどくさいと思うこともありますが 😉 )
納得感にこだわる子ほど、ちゃんと納得できればガッツリルールも秩序も受け入れます。
忙しい中でも、ちょっとひと手間をかけるだけで、子どもは納得して笑顔になることも多いんです。
でもその「納得感を求める気持ち」をないがしろにされるような、昔ながらの『とにかくこうしなさい』『アレコレ言わずにやりなさい』という一方的な指示命令だけでは、いつまでも違和感と不信感を持ち続けてしまうことが多いんです。
残念ながら、まだ学校の先生や部活の指導者のなかには自分が「上」だから子どもの人格を否定するような言動をしても許されると思ってる方も0ではないのが現実です。
社会でならパワハラと言われるようなことでも、学校のなかでは許されていることもよくあります 😐
そのような態度を見聞きすることで、子どもが学校や部活に行きたくない・・と悩み始めてしまう事例はとても多いです。
文科省が発表している「不登校になった原因・きっかけ」は「家庭生活に起因」「いじめを除く友人関係をめぐる問題」「学業不振」がベスト3なんですが、先に上げた民間の調査などでは「教員との関係」「いじめ」「学校の決まりに納得できない」がベスト3です。
ここからも、学校と実社会のズレが整えられるのには、時間がかかりそうに思えてしまいます
(T_T)
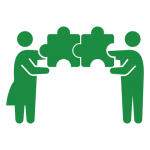 学校の体質改善を求めることも大事ですが、今お悩みの子どもを救うには、「学校は大事だけど一つのコミュニティに過ぎない」ことを親と子がしっかり共有することも大事です。
学校の体質改善を求めることも大事ですが、今お悩みの子どもを救うには、「学校は大事だけど一つのコミュニティに過ぎない」ことを親と子がしっかり共有することも大事です。
日本の思春期の子どもは学校に居る時間がとても長く、部活や塾もその延長線上にあることが多いです。
そうなると「学校が世界のすべて」のように思いやすいので、学校が嫌なところになると、子どもは自分の世界に居場所がない、追い詰められと思い込みやすいんです。
学校がどのような目的を持ったコミュニティで、違和感を持った相手はどのような人なのかを、ちゃんと距離をおいて捉えられるように、その上で適切な協力関係を持てるようにすることはとても大事です。
なぜなら社会に出れば、そのような力がどうしても必要になるからです。
学校や学歴を盲信するのではなく、「自分」を軸に付き合い方を調節する力が大事です。
そしてできるなら、学校以外のコミュニティにも属せると子どもの心にも幅が広がります。
 どんな時代でも思春期の子どもは、親よりも友達を大切に思うようになります。
どんな時代でも思春期の子どもは、親よりも友達を大切に思うようになります。
それは自立に向けて、家庭以外の世界とつながる大事な成長のステップです。
それでもかつては、友達関係は学校から帰宅すれば一度中断されていました。
その間に子どもは一人でじっくり考えたり、他の人たちと触れ合うことで世界を広げることもできました。
ところが今ではSNSで、いつでも何をしていても特定の友達と繋がりあったままになってしまいます。
時には親が寝た後でも深夜にこっそり友達とやり取りをしていて寝不足になっている子も居たりします 🙄
そのような密な環境では、一度こじれてしまうと学校に行くのが辛くなることも起きてきます。
さらに今の即レス文化では、よく考えずに文面を見た瞬間の感情的な反応で返事を返してしまうこともよくありますし、短い文章ではニュアンスが十分に伝わらないことも起こります。
また、面と向かって相手の顔を見ながらだと、とても言えないようなキツイことでも、SNSだと伝えられてしまうこともあります。
 さらに相手が直接自分に情報を送ってこなくても、インスタなどで相手が誰と遊んでいるかなどを知ることができるようにもなっています。
さらに相手が直接自分に情報を送ってこなくても、インスタなどで相手が誰と遊んでいるかなどを知ることができるようにもなっています。
そのようなことから、イマドキの友達関係は密にもなりやすく、こじれも起きやすいんです。
思春期の子どもにとっては友達はとても大事な存在なので、特定の友達関係だけが密であれば、それがうまく行かなくなった時には「世界の終わり」のように感じてしまいます。
友達への思いが強い子ほど、別のコミュニティにも属したり、ある程度幅広い友達関係を築いておくことは大事です。
SNSが悪影響を与えているからと言って、子どもの世界からそれを取り上げることは根本的な解決にはなりません。
子どもはすでに「それらがある世界」に住んでいるからです。
それらがある世界で楽しく行きていくためには、友達やSNSとの付き合い方も自分が主導で決めていくことが必要です。
 自分を中心にして、色んな友達やSNSとの距離感をうまくとれるようになることが大事です。
自分を中心にして、色んな友達やSNSとの距離感をうまくとれるようになることが大事です。
(参考:仲良しグループがしんどい!思春期の友達関係と親のできること
ここまで見てきたように、イマドキの社会の変化から子どもたちが違和感やしんどさを感じて、隠れ不登校や不登校になることが増えてますが、一方では子どもたちにも敏感な子が増えていて、違和感やしんどさを強く感じやすくなってもいるんです。
考え方の違いから一方的に指示命令されるのが嫌な子も多いのですが、他にも相手の高圧的な「言い方」や「態度」に強い違和感や不快感を持つ子も増えてます。
怒られるのがとても怖かったり、大きな声や騒がしさ、匂いやざらついた空気感などの五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)に過敏さがあることから、色んなタイプの人が集う学校生活に苦痛を感じる子もかなり増えてます。
 給食やお弁当などの匂いが交じるのが苦手だったり、男子でも同じ男子たちがふざけあっているのを見ているだけでも辛くなる子もいたりします。
給食やお弁当などの匂いが交じるのが苦手だったり、男子でも同じ男子たちがふざけあっているのを見ているだけでも辛くなる子もいたりします。
(参考:「怒られるのが怖い」を絶対にそのままにしてはいけないワケと抜け出し方)
このような感覚的な辛さは、とても個人的なもので、本人にとってはそれがアタリマエだけど他の人とどう違うのかわからないために、子どもが説明しようがないこともあります。
そしてそのような状態は、他の人にはなかなか理解されないのもさらに子どもの辛さを深めます。
『そんな騒がしさは普通じゃないの?』
『もっと気持ちを大きく持たないと』
などと言われても、本人にはどうしようもないんです。
見守れたり、辛さに共感されて話を聞いてもらうだけでは解決できないこともあるんです。
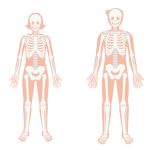 でもご安心下さいね。
でもご安心下さいね。
このような場合でも、発達の抜けを埋めるなどの身体へのアプローチで楽になることができるんです!
敏感さは治らないという説もありますが、当カレッジでは今までもそこから笑顔を取り戻していった事例もたくさんあります。
心に寄り添ったり、言葉がけだけでは解決しなかったことにも、身体からのアプローチはとても有効です。
そして過敏さが調節できるようになることで、本来のその子のエネルギーを読み書きや他の身体の動きにも使えるようになっていくので、社会性や学習能力や身体能力が上がった事例もたくさんあります。
講座や個人セッションでは、敏感な子どもが増えているワケや身体からの最新のプローチも沢山ご紹介しています。
ピンときた方はご活用下さい。
つい自分の思春期の頃を参考にしがちですけど、その違いも踏まえることは大事ですね。
それに思春期について最新の情報を手に入れるチャンスも殆どありません。
どうしても自分の体験や周りを参考にしがちです。
私もそれで随分と辛い時間を過ごしました。
大事なのは「今うちの子の場合にどうしたらいいのか」を知ることです。
隠れ不登校のうちに親が気づいて対処するには?
 なるべく隠れ不登校のうちに早期発見をして必要なサポートができると、不登校になったりこじらせることが少なくなります。
なるべく隠れ不登校のうちに早期発見をして必要なサポートができると、不登校になったりこじらせることが少なくなります。
大事な思春期の時間を親子とも楽しく過ごしたいものです。
残念ながら子どもは、先程見たようになかなか自分から『辛い』『助けて』と言ってこないので、親御さんが隠れ不登校に気づけるといいですね。
そのためには次のようなことが役立ちます。
![]() どうしても子どもが思春期になると、「身体も大きくなったし、もう大人並みね」と思いがちです。
どうしても子どもが思春期になると、「身体も大きくなったし、もう大人並みね」と思いがちです。
子どももいっぱしのことを言うようにもなりますので、親の『これくらいはできるでしょ』という期待も上がります。
でも、まだまだ子どもの「物事を客観的に考える」「長期的な視野に立つ」「感情に引っ張られない」「人の立場や気持ちにも配慮する」という機能を司る、脳の前頭葉という部分が育ち切るには時間がかかります。
思春期の子どもには「できるところ」と「まだまだなところ」が、びっくりするほど混在しているのが普通です。
(参考:脳科学で納得!イマドキの思春期には子育てにコツが必要なワケ)
でも親の方はつい期待を高くしてしまうので、子どもの「できない」「やれてない」「そもそも理解できてない」ところを見つけると、ものすごくがっかりしてしまいます。
そうなると、ついそんなところばかり子どもに注意することも起きがちです。
そして期待が高い分だけ、子どもがやれてることや頑張ってることはスルー・・・・
 それでは子どもからしたら、「いつも文句を言われている」「できないことばかり言われてる」と受け取ってしまいます 😯
それでは子どもからしたら、「いつも文句を言われている」「できないことばかり言われてる」と受け取ってしまいます 😯
思春期になるとただでさえ、子どもは友達と自分を比べたり、高い理想と自分を比べては、自己肯定感を下げてしまいがちです。
強がりと言ってても、内心では自信のない子がとても多いのが日本の思春期の子どもの特徴でもあります。
ぜひ、日頃からちょっと気をつけて、子どものやれてることや、頑張ってることにも言葉で触れておくのがオススメです。
褒めるというよりは、ちゃんと見てるよというサインを出し続けるのがポイントです。
お母さん・お父さんが結果やできないことばかりでなく、自分なりにやっていることを認めてくれることが、子どもの自信と信頼関係を作ります。
そしてそのような下地があると、もし本当に辛いと思った時には、子どもも自分から「ちょっと最近・・」などと声をかけてくることも増えてきます。
 大人だって忙しい毎日ですが、一日5分だけでも良いので、その子とだけの時間をとってみるのがオススメです。
大人だって忙しい毎日ですが、一日5分だけでも良いので、その子とだけの時間をとってみるのがオススメです。
スマホやテレビのながらではなく、ちゃんと身体と心をその子だけに向けることで、子どもの毎日の変化にも自然に気づきます。
子どもの好きなことについての話を聞くだけでも良いですし、足裏や手のひらなどのマッサージをしたり、してもらってもいいでしょう。
大事なのは時間の長さではなくて、その子にしっかり向き合う時間を少しでもいいので積み重ねることです。
この時間を持つことで、子どもの変化にも早く気づきますし、信頼関係も自然にぐんと強くなります。
そして子どもの自己肯定感も、びっくりするくらい上がります。
兄弟の多いご家庭ではちょっと大変かもしれませんが、ぜひやってみて下さい。
兄弟が多いお子さんたちほど、その効果がすぐに分かります
(^^)❤
 思春期の子どもは「自分の納得感」が大事です。
思春期の子どもは「自分の納得感」が大事です。
でもその話し方が未熟で、何が言いたいのかよく分からなかったり、感情的すぎたりすることも多いので、つい大人は子どもの話に『もういい』と言いたくなったり、『とにかく〇〇しなさい』と言いたくなることも多いです。
はい、私もしょっちゅうそうでした (^^;)
思春期は反抗期でもあるので、反抗のための屁理屈をぶつけてくることもありますが、それでも、子どもが本気で納得感を求めていること、大事な疑問や本音をぶつけてくることもあるんです。
このような場合には子どもの真剣さが違います。
もしそのような状態に気づいた時には、ぜひ時間をとって、子どもの言い分を最後まで聞いてみるのがオススメです。
その時に十分な時間が取れない時には、『〇〇ならしっかり話を聞けるから待って』と声をかけてみて下さい。
子どもは自分なりに大切にしている考え方や価値観を話したい、分かってもらいたいと思っているからです。
お父さん・お母さんに伝えることを望んでいる、諦めてない瞬間です。
 もちろん、子どもの話にはよくわからないことや理屈がおかしいことも多々あるでしょう。
もちろん、子どもの話にはよくわからないことや理屈がおかしいことも多々あるでしょう。
でも、そんな時には細かく言い返さずに、とにかく最後まで子どもの話を聞ききるのがオススメです。
子どもはちゃんと聞いてもらったことで、自分を認めてもらったという気持ちが持てるので、自己肯定感も信頼関係も上がります。
また、自分で話している内に、つじつまが合わないことがあれば自分でそれに気づくこともあります。
自分の思いを話しきることで、子ども自身が自分が何にこだわっているのかに気づいたり、隠れ不登校のワケが子ども自身の中で解消されたという実例もいくつもあります。
そしてもし子どもの言い分が正しくて、お母さん・お父さんがミスをしてたなと思う時には、サクっとそれを認めて謝るのがオススメです。
親だからミスを認めない、完璧であろうとする必要は全くありません。
 そして一度言葉にしたことだって、相手の話を聞くうちに、自分の意見が変わることだってあるんです。
そして一度言葉にしたことだって、相手の話を聞くうちに、自分の意見が変わることだってあるんです。
親がそのようにあっさり振る舞うことは、子どもにとても大きな影響を与えます。
子どもも自分が完璧でないことを認められるし、間違いったら直せばいいんだと学ぶんです。
でも、それが子どもとの関係を大きくこじらせたり、自分自身を追い詰めることになってたんです。
色んな体験や学びをしたことから、「親も一人の人間で、これからもっと成長していくよ」と思えてから、ずっと肩の荷が下りて楽になりました。
自分の親への思いも楽になりました 🙂
親が自分の不完全さも受け入れて、ありのままで居るようになると、子どもも自分のありのままで居られるようになります。
そうなれば、もし辛いことがあれば子どもも『辛い』と言いやすくなります。
(1)~(3)で下地を日々作っておくと、子どもの変化にも早くに気づきますし、子どもから話を引き出しやすくもなります。
そして『これは隠れ不登校かも?』と思ったら、子どもに更に詳しい話しや気持ちを聞いてみることもできます。
 子どもがそれ以上話さなかったり、『もう少し自分で頑張りたい』と言う場合には、しばし見守ることも大事ですが、1週間以上たっても子どもの様子が上向かない時には、何らかのサポートが必要な状態です。
子どもがそれ以上話さなかったり、『もう少し自分で頑張りたい』と言う場合には、しばし見守ることも大事ですが、1週間以上たっても子どもの様子が上向かない時には、何らかのサポートが必要な状態です。
再度子どもに声をかけてみたり、学校での様子を学校側にさりげなく尋ねてみてもいいでしょう。
このような時には「引き出すコミュニケーション」が大活躍します。
そして親子で作戦をたてるのもいいですが、そこから1週間過ぎても良い変化が現れない時には、専門家に相談するのがオススメです。
思春期の子どもはどうしても「一人で頑張ろう」としすぎて、いつまでもぐるぐる思考をしがちです。
出口が見つからない状態で、いつまでも新しい情報を入れずに考え続けても、それは「考えている」のではなくて「ぐるぐる思考にハマっている」状態です。
何らかの新しい刺激が必要です。
(参考:一人で抱え込む癖は変えられる⁉知っておきたいリスクと可能性
ぐるぐる思考の対処法:思春期にこそ7つのステップを知っておこう!)
 思春期の子どもは柔軟なのですが、一定以上のストレスにはガクッと弱くなって、あれよあれよと状態が悪くなることもあります。
思春期の子どもは柔軟なのですが、一定以上のストレスにはガクッと弱くなって、あれよあれよと状態が悪くなることもあります。
必要以上に長引かせてしまうことが、回復を遠ざけてしまうこともあるんです。
身体の不調の場合には、私達はお医者さんという専門家に相談するのですが、隠れ不登校の場合には、専門家に相談するのがどうしても遅くなりがちです。
それは「身体と違って、心のことを相談するのは恥ずかしい」とか「子どもの不登校は子育ての失敗」などという考え方がまだ残っている影響もありそうです。
でも、隠れ不登校や不登校はさまざまな要因が重なってなる”状態”ですし、「子育てのせい」というような単純なものではありません。
そして身体の不調と同じように適切なサポートさえあれば、どんな状態からでもちゃんと回復します。
こじらせないうちの、早めのサポートが有効なのも同じです。
「どうしたら良いのかわからないから見守る」「いつか子どもが自分で回復するんじゃないか」だけでは、状態が悪化してしまうことがあるのは、身体の不調の場合と同じです。
 専門家は「理論」を語る人よりも、実際に子どもの回復をサポートした実績がたくさんある人を、始めは複数当たってみるのがオススメです。
専門家は「理論」を語る人よりも、実際に子どもの回復をサポートした実績がたくさんある人を、始めは複数当たってみるのがオススメです。
「うちの子に合うサポート」を見つけることが大事だからです。
実際に話を聞いて比べてみて、ご自分が信頼できそうな人を選ぶのが一番です。
『親のせい』とかいう人は選ばないことをおススメします。
「増えている隠れ不登校」のおわりに
わからないことだらけで不安でした。
それに励ましや見守るだけでなく、身体へのアプローチで回復することがあるっていうのにもびっくりしました。
「どうしたらいいのかわからない」ままだと、せっかく隠れ不登校かもと気づいても、ただ不安なままで過ごすことになってしまうのが一番残念です。
まずは子どもとの信頼関係を強くしながら、子どもから話が聞けそうかやってみます。
そして身体からのアプローチもあることも子どもにも伝えてみます。
子どももびっくりしそうです 🙂
❤❤あとがき❤❤
隠れ不登校の数が急増しているのに、まだ思春期や不登校についての具体的な情報やサポート方法があることが広く知られていないのがとても残念です。
これからも、必要とされている方にお届けしたいと願っています✿
また、本文では書ききれなかったのですが、学校生活を大事にしながらも、子どもが自分の好きで得意なことを見つけて、それを伸ばしていくのもとてもオススメです。
実際の社会では、学校生活では測れない「人を楽しませる力」や「〇〇についてとても詳しいこと」などでも、十分楽しく経済的にもしっかりと生活することができます。
むしろ自分なりの好き・得意が分かっていないことで、学歴が高くても社会に出てから迷うことが多くなっているのがイマドキです。
好きで得意なことで学校以外の人やコミュニティにも繋がれれば、楽しみながら子どもの世界もうんと広がります。
学校でストレスを感じても、「それが世界の全てではない」子は、余裕を持ってストレスにも向かえます。
ぜひ、お子さんの「好き」に注目してあげてくださいね。
子どもの「好き」に光を当てることは、子どものエネルギーを増やして、希望と自信を取り戻すのにも効果的です。
回復にも予防にもとても役立ちます
(^^)/
合わせて読みたい記事:
知っていれば安心!思春期の不登校をこじらせる4つの原因と関わり方