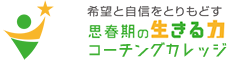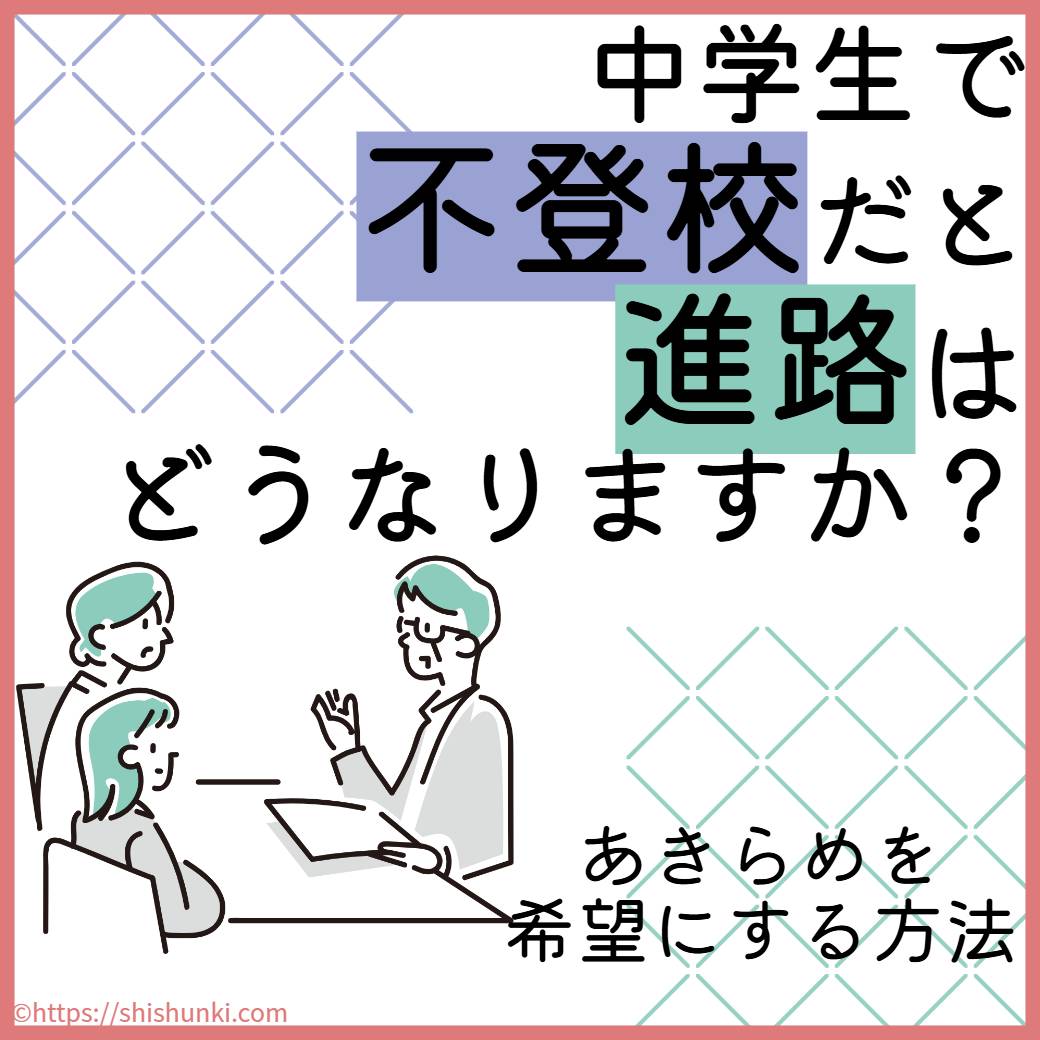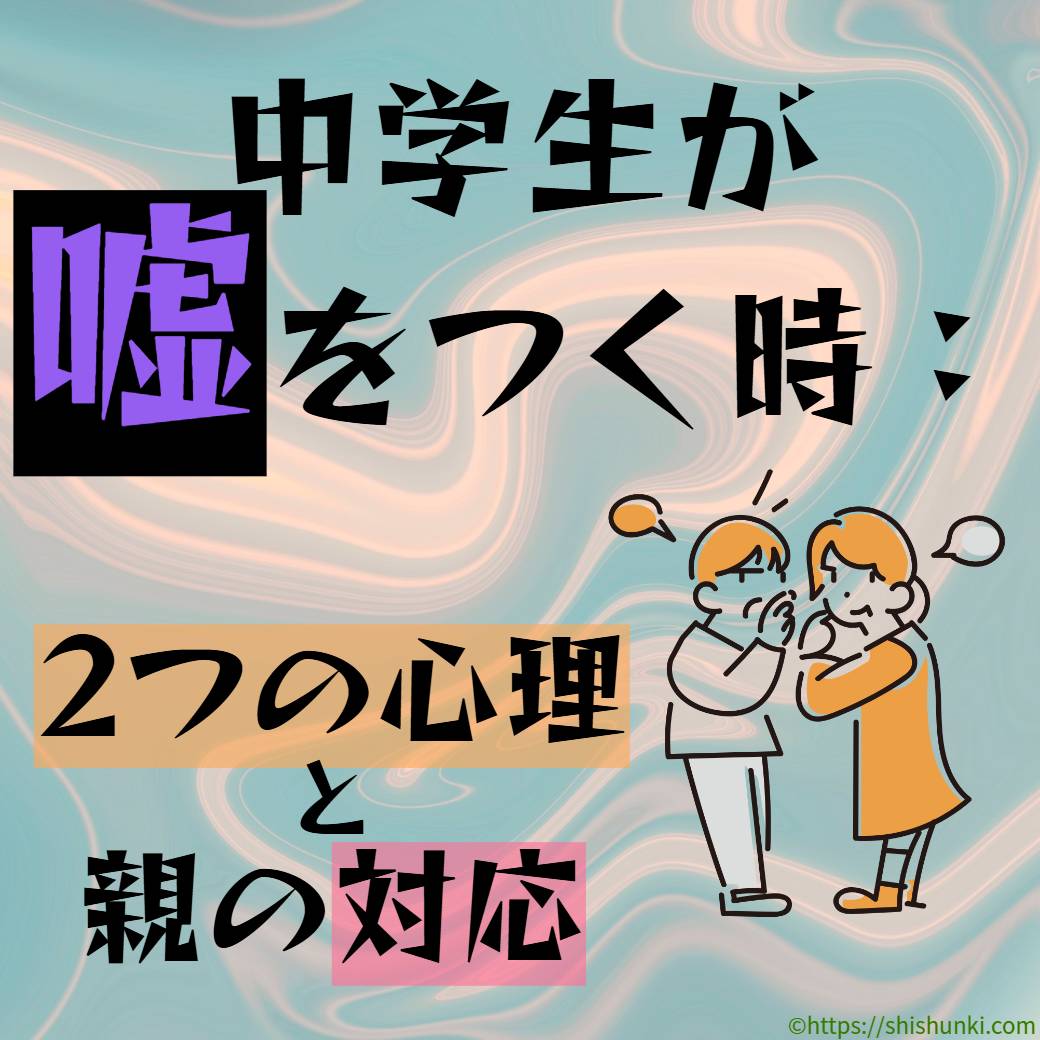思春期のやりたいことと進路選択:可能性を引き出す親の関わり
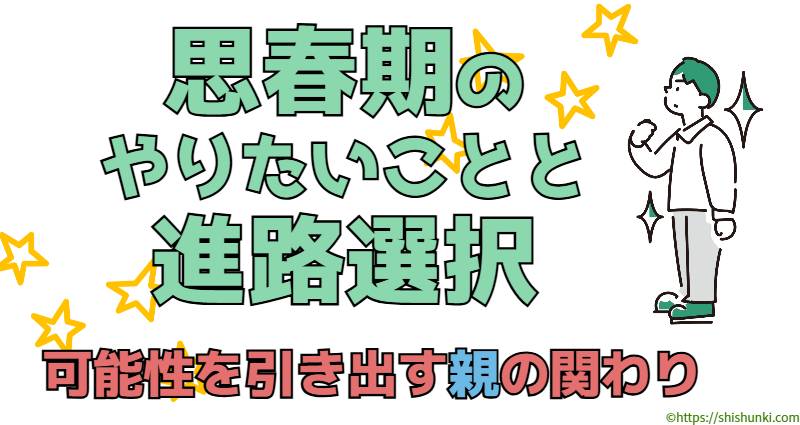
思春期には何度か進路選択の機会があります。
以前の進路選択の基準メインは
「偏差値」だったのですが
社会が大きく変わった今では
本人の「やりたいこと」を無視して選んでも
どこかで行き詰まってしまうパターンが増えています 😯
なので、どうやって
「やりたいこと」を見つけたら良いのかが
今の進路選択では大事なテーマになっています。
「将来何になりたいの?」と聞くのですが
「わからない… YouTuberかな」と
ぼんやりした応えしか返ってこないので
このままでいいのかと不安です。
そうなんですね。
今は進路選択にも
選択肢がとても増えていて
また、1校ずつの特色も強くなっているので
良く比較検討して選ぶことが大事ですね。
でも、うちの子はなんだか他人事みたいで。。
小さいころからやりたいことが
はっきりしている子もいますが
実はそういうお子さんはとても少ないんです。
東京大学とベネッセが2万人の子どもを10年間追跡した調査でも
小学生の73.7%、中学生の55.8%が、
進路について深く考える経験をしていないと出ています。
そうなんです。
そして、3人に1人(35%)は小5から高2まで
同じ職業希望を持ち続けますが
それ以外の65%の子どもは途中で希望が変わるのです。
それがずっと続くかどうかはわからないんですね。
そうなです。
「YouTuber」という答えは
2015年は圏外でしたが
2024年には小学生で4位にランクインしています。
ただ、この答えの中には
「本当にやりたいことがまだ見つかっていない」ので
身近で思いついたことを言葉にしただけ
ということも多いのです。
なので、問題は、
子どもが深く考えていないことではないんです。
深く考える機会や方法を知らないことなんです。
では、どうしたら考える機会や方法を
持てるようになるんでしょう
家でできることはありますか?
はい、もちろんあります!
ではご一緒に
お子さんのやりたいことを引き出して
可能性を開く進路選択のために
家でできることをご一緒に見てみましょう
目次
気づかずにやっている親のNG「進路サポート」
まず最初に、やってしまいがちな
進路についての親のNG関わりから見てみましょう
NG1:「具体的な職業」を決めさせようとしている
「医師は?」
「公務員は安定してるよ」
親は自分が良いと思う職業を
おすすめしてしまうことがあります。
でも、今の小学生が社会人になる頃には
もう存在しない職業がたくさんあるのは
最近のAIの目覚ましい進化で明白ですね。
 大切なのは「何になりたいか」ではなく
大切なのは「何になりたいか」ではなく
「どんなことに興味があるか」
「何をやりたいと思うか」なのです。
NG2:親の価値観で「現実的な選択」を押し付ける
「YouTuberなんて現実的じゃない」
「プロスポーツ選手になれる確率、知ってるの?」
「医者なんて、あなたの頭じゃ無理。お金もないし」
親は「安全」「確実」を目指してほしいので
ついこんなことを言ってしまうこともあります。
でも実際には調査データにもあるように
小5で「医師」を目指していた子が
高2で「化学系の研究職」という
独自の進路を見つけることもあります。
親が「非現実的」と子どもの思いを
頭から否定してしまうと
その子が本当の興味を探求する機会を
奪ってしまうことになるのでご注意です。
NG3:子どもの「興味」を「将来性のない趣味」として切り捨てる
 「ゲームばっかりして…」
「ゲームばっかりして…」
「YouTubeばかり見てないで勉強しなさい」
「絵ばっかり描いてないで」
しかし、これらの興味こそが
将来の進路につながる最も重要な手がかりになるんです。
当カレッジではそんなところから
「好きのタネ」をたくさん見つけます。
例えばゲーム好きでも
そこから「作戦を立てるのが好き」
「みんなと協力するのが好き」などの
やりたい事・興味のあることのタネが見つかります 🙂
そんタネを育てたことで
YouTube好きから
マーケティングを学ぶ学部に進んだり
サッカー好きから
チーム研究に進んだ事例も当カレッジにはあります。
 せっかくの子どもの興味を
せっかくの子どもの興味を
まるっと切り捨ててしまうと
子どもは
「やりたいことがわからない」状態に
なってしまうのでもったいないですね。
NG1をやってました!
今NGだとわかって良かったです。
進路を「深く考える」子どもになる5つのポイント
先ほどの調査データでは
進路意識が高い子どもの明確な共通点を示しています。
ポイント①:探究的な学びを経験している
「グループで考える」
「討論する」
「レポートにまとめる」などの
探究的な学びをしている子は
進路を深く考える比率が10ポイント以上高くなっています。
与えられた情報を覚えるだけでなく
そこから自分が何を感じたり思うのかを
自分でわかるようになる練習です。
ポイント②:親との会話の質が高い
 親子の会話が多いのは嬉しいですね。
親子の会話が多いのは嬉しいですね。
そして子どもの可能性を引き出すために
効果的な会話は
「テストの点数どうだった?」ではなく:
- 「このニュース、どう思う?」(社会への関心)
- 「将来、どんなことをしてみたい?」(夢の共有)
- 「どこでそう感じたの?」(思考の深掘り)
などの、子どもが
*自分の気持ちや思いに繋がれるような会話
社会と自分をつなぐような会話
がおすすめです。
調査でも
「将来や進路のこと」を話す家庭の子どもは
話さない家庭の子どもより
進路意識が約2倍高いことが示されています。
「考えさせなくちゃ」と難しく考えずに
ただ言葉をかけてみるのでOKです。
ポイント③:内発的動機づけと目標意識のどちらもある
進路を深く考える子どもでは
- 「新しいことを知るのがうれしい」
(内発的):77.2% vs 61.5% - 「希望する高校や大学に進みたい」
(目標):85.4% vs 72.6%
となっています。
 つまり、先に進路への動機と目的があるので
つまり、先に進路への動機と目的があるので
それに向かって学習意欲が高くなっているのです。
ポイント4:社会のニュースに関心を持つ
「社会の出来事やニュースに関心が強い」子は
進路を深く考える経験をしている比率が
15ポイント以上高いということも出ています。
なぜなら、社会への関心を持つと
「自分はこの社会で何ができるか」
という問いにもつながるからです。
農業問題のニュースを見たことから
それについて考えるようになって
経済学部に進んだ子もいます。
TVに出てきた時などに
お互いの意見や思いについて
話す機会が自然に持てるといいですね。
ポイント5:親が大事なことを伝える
 また、親が以下の大事な価値観を
また、親が以下の大事な価値観を
子どもに伝えていたり
実際に行動させていたりする姿勢があると
子どもの進路意識が高いことも出ています。
- 主体性(自分の考えを持つこと)
- 自信(自分に自信を持つこと)
- 教訓帰納(失敗から学ぶこと)
- 挑戦(新しいことに挑戦すること)
- 目標(将来の目標を持つこと)
先回りしたり過干渉だと
育たないことばっかりですね
気を付けます!
「YouTuber」と言うわが子の可能性を引き出す親のコーチング
コーチングという言葉は
分かっているようで
ピンと来てないこともあるかもしれません。
そんな時に分かりやすいのが
「ティーチング(教える)」と
「コーチング(引き出す)」を比べてみることです。
この二つには決定的な違いがあります。
ティーチングアプローチ:
子ども:「YouTuberになりたい」
親:「YouTuberは不安定だから、安定した職業を選びなさい」
→ 子どもの思考が止まってしまう。
 親に頭から否定されたことから
親に頭から否定されたことから
親子の会話が進まなくなる
コーチングアプローチ:
子ども:「YouTuberになりたい」
親:「へえ、YouTuberのどんなところに魅力を感じるの?」
→ 子ども自身が自分の思いについて考え始めます。
ティーチングは
親の決めた方向に進ませることが目的で
コーチングは
その子の世界を一緒に見て
視野を広げたり成長につなげることが目的です。
ありがとうございます 🙂
子育てではコーチングはとても役立ちます。
特に「決まった正解」のないこれからでは
とても大事ですね。
当カレッジでは
具体的に個性に合わせた親子コミュニケーションのコツを
沢山お伝えしています。
そのなかから、すぐにできる
親子コミュニケーションで役立つ
3つのコーチングスキルをご紹介しますね
 スキル①:聞く
スキル①:聞く
- 評価・判断をせず、そのまま受け止める
- 言葉の奥にある「感情」「価値観」を聴く
- 子どもの話を遮らず、最後まで聴く
スキル②:質問する
❌ 「どうして勉強しないの?」(詰問)
⭕ 「どんなところが面白いの?」
(引き出す質問)
⭕ 「もし失敗しても大丈夫だとしたら
何をしてみたい?」
視点を変える質問)
質問は相手から言葉を引き出せますが
質問は言い方や意図によって
詰問や誘導になってしまうこともあるので
ご注意くださいね。
 当カレッジでは講座や個別コーチングで
当カレッジでは講座や個別コーチングで
具体的にお伝えして
質問から親子関係が良くなったと喜んでいただいています。
スキル③:勇気づける
また、
「結果に関わらず努力したことも認めてくれる」環境だと
子どもの進路意識が高いことも出ています。
結果は結果として受け止めることは大事ですが
同時に親が
努力や工夫への声がけも心がけていると
子どもも結果だけを気にするのではなく
「何ができるか」
「どう工夫したらいいか」
に意識が向くようになります。
つまり「自分にはできそうに思えないこと」や
「少しでも失敗の可能性があること」を避ける、
という傾向が出にくくなります。
 (身体のエネルギー不足状態だと
(身体のエネルギー不足状態だと
なんでも”怖い”になりますので
その場合には身体へのアプローチの併用で改善します)
一つ、事例をご紹介しますね。
実践ケース:YouTuberから広がった進路
A君:「YouTuberになりたい。
動画を作るのが楽しいんだ」
親:「そうなのね 🙂 。
どんな動画を作るのが楽しいの?」
A君:「友達との日常とか」
親:「なるほど~。
作っている時には、どんなところが一番楽しいの?」
A君:「編集して、音楽つけたり、テロップ入れたりする時かな」
親:「そうなのね!素材を編集して
見る人が楽しめる形にするのが好きなんだね」
A君:「そう。どうやったら
もっと見たくなるかなと
想像しながら工夫するんだ」
 親:「おもしろそうね!
親:「おもしろそうね!
Youtube編集以外でも
そういうことをしてる人には
どんな人がいるのかな?」
A君:「映画の編集者?
テレビ番組のディレクター?」
親:「そうだね。最近は
企業のYouTubeチャンネルとか
教育系の動画も増えてるね」
A君:「あ、企業の動画マーケティングとか、EdTechとかもあるね!」
このような会話を日常で時々していたら
A君の興味は
映像制作・マーケティング・教育×テクノロジーなどの
多方面に広がっていきました。
今A君はマーケディングを大学で
とても熱心に学んでいます 🙂
わが子の可能性を引き出す親の「コーチング習慣」
大切なのは、日常生活の中で
コーチング的な会話を自然にすることです。
そのために役立つ
七つのやってみると良い習慣をご紹介します。
今日から始める7つの習慣
①週1回の「深い対話」タイムを確保する
できれば30分〜1時間
スマホを閉じて
子どもとじっくり話す時間を作ります。
「今週一番面白かったこと」
「最近興味を持ったこと」など
子どもが話しやすい話題でOKです。
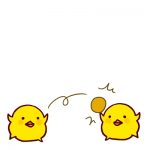 「親子で会話」が当たり前になります。
「親子で会話」が当たり前になります。
②社会のニュースを「わが子の視点」で一緒に考える
「このニュース、どう思う?」
「もしあなたがこの問題を解決するなら?」
などど、時々声をかけてみます。
すぐに返事が返ってこなくても
声をかけておくだけでもOKです。
③「なぜなんだろうね」「どうしたら?」を心がける
例えば子どもが「疲れた」と言ったとき:
❌ 「それくらいで?頑張りなさい」
⭕ 「何で一番疲れるの?」
そして「どうしたら疲れにくくなるかな?」
「~~しなさい」ではなくて
自分で改善に向けて考えるという
方向性を与えるのがおすすめです。
④子どもの「調べたこと」に心から興味を持つ
子:「YouTubeで見たんだけど、深海魚ってすごいんだよ!」
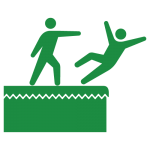 ❌ 「そんなの見てないで勉強しなさい」
❌ 「そんなの見てないで勉強しなさい」
⭕ 「へえ!どんなところがすごいの?」
子どもの「聞いて、面白いんだよ」という
気持ちをまず受け止めます。
話を聞いてみると
「え、そんな視点でみてたんだね」と
子どもを見直すこともたくさんありますよ~
⑤小さな挑戦を勇気づけ続ける
❌ 「100点取ったね、すごい!」(結果だけ)
⭕ 「難しい問題に挑戦したんだね」(努力、工夫)
言われたことに子どもの意識は向きます。
自分でも過程や工夫を考えるようになります。
⑥失敗を「学び」に変換する問いかけをする
 まず感情や出来事を
まず感情や出来事を
しっかり受け止めた後に
「何が起きたの?」
「次に似たようなことが起きたら、どう対応してみる?」
失敗にも理由があって
改善できる、ことを当たり前にします 🙂
⑦親自身が何かを学び続ける姿を見せる
子どもは親の「言葉」ではなく
「やっていること」を見ています。
親も学び続ける姿を見せることで
*学ぶのは当たり前
*学ぶことは自分のために一生続く
と、子どもも受け取ります。
ちょっと意識すればできそうです。
良かったです 🙂
日ごろから少しずつ
「当たり前になっていること」が増えていけば
子どもも日ごろから
社会をちょっと広い視野で見れるようになります。
そしていざ進路選択の時期に来た時でも
親子でそれを話題にする会話ができたり
好きのタネから現実的な選択ができるようになります。
終わりに:
なかなか進まないので
困っていました。
今日は
親の日ごろの関わりで
子どもが進路や社会について
意識を向けられるようになることや
子どもの考えを深めていくサポートが
私もできることなのが分かって
気持ちがとても軽くなりました!
調査の結果にもあるように
親の関わりで
子どもの進路への意識が
大きく変わります。
そして、より深い進路選択についての
会話のコツも知りたいので
またご相談いたします。
♡♡あとがき♡♡
今は同じような偏差値や校則でも
学校・コース・学部ごとに
とても個性のある時代です。
ぼんやり進路を選んだために
途中で投げ出してしまったり
学校や生徒と合わなくて
辛い思いをしている子も増えています。
ただ、それは
しっかり先まで考えて選べば
とても楽で楽しい環境になる、ということでもあります。
 そのためには
そのためには
♡親子で進路の話ができること
♡子どもの「やりたいこと」やその方向性がわかること
♡具体的な進路選択のための情報収集と整理ができること
が必要です。
そして親子の会話がスムーズに進むには
*元気な身体
*安定した気持ち
*考えられる力
が親子の両方に必要です。
疲れ切っていて、イライラしていたら
情報の整理も難しくなってしまいますね。
☆より個性に合わせた具体的なコーチング方法を知りたい
☆好きのタネ、得意のタネなど、役立つタネをたくさん見つけたい
☆情報整理の仕方を知りたい
☆身体・心・頭を良い状態にしたい
☆不登校や発達課題のある子のベストな進路選択をしたい
 ☆子どもに直接コーチングで引き出してほしい
☆子どもに直接コーチングで引き出してほしい
そんな時には思春期最幸家族講座や個人セッションもご活用くださいね。
このブログが、あなたとお子さんの
最幸未来につながる一歩になることを
心から願っています
(^^)/
あわせて読みたい記事:
中学生で不登校だと進路はどうなりますか?:あきらめを希望にする方法
子供の自立に大切なことは?イマドキの思春期の子育てと進路選択
「死人テスト」で親子コミュニケーションをバージョンアップしよう!