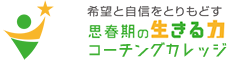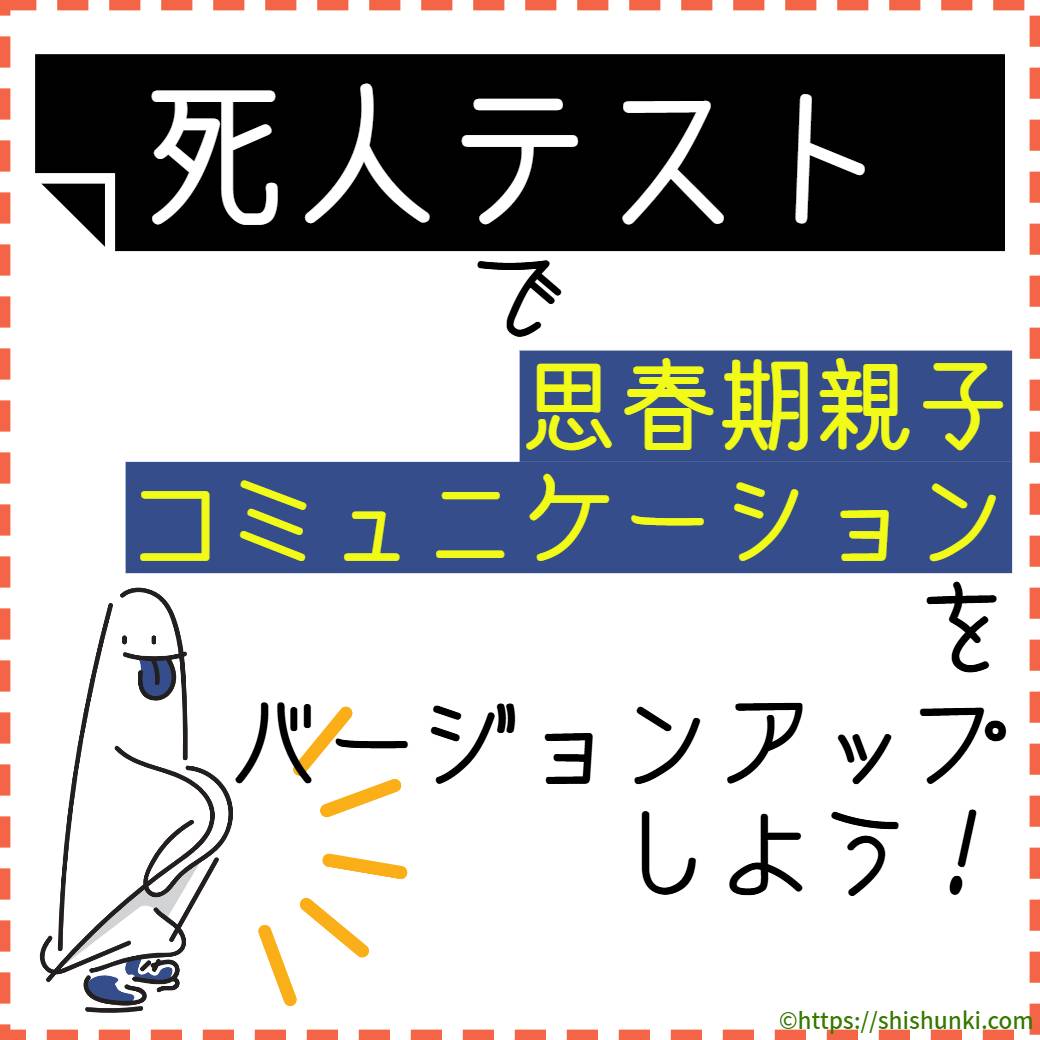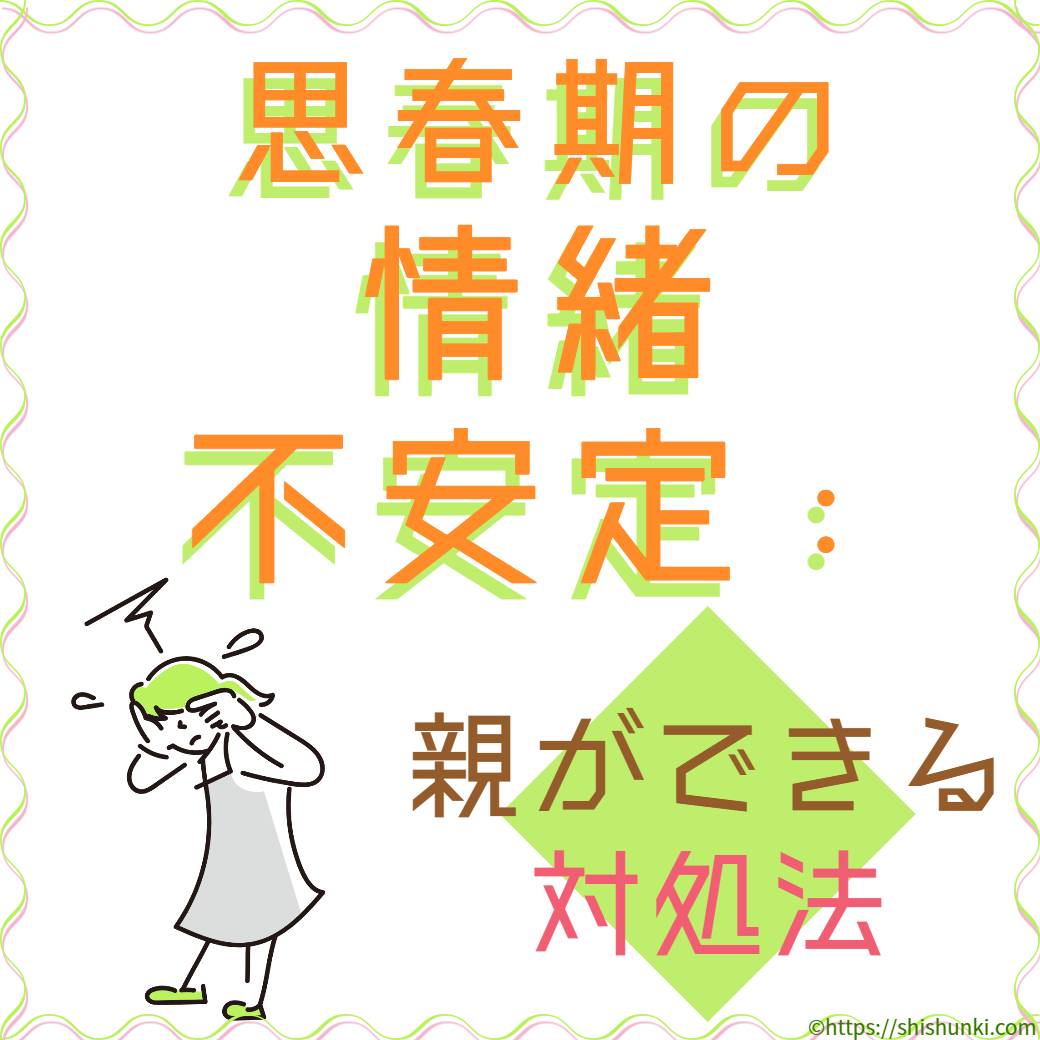不登校の夏休みの過ごし方のコツ:休み明けを笑顔で迎えよう!
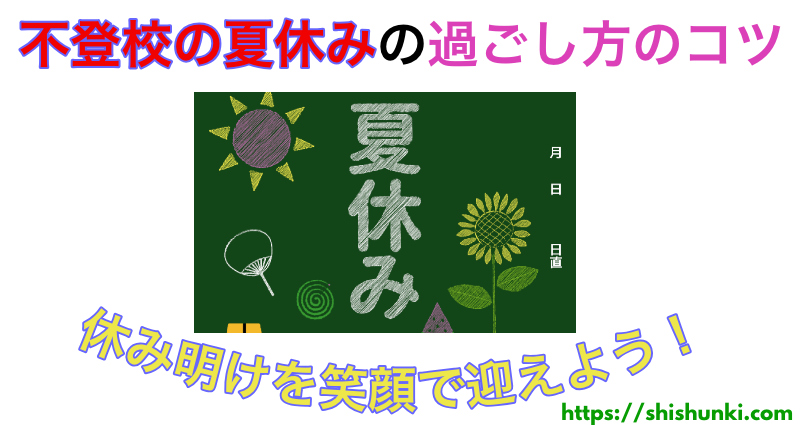
不登校に夏休みの過ごし方はとても重要です。
夏休みにはある程度の時間がありますし
子どもにも
「学校に行かなくちゃ」という
プレッシャーが減るので
サポートの効果が高まるチャンスです!
夏休み明け前に
登校できる状態に回復できれば
休み明けは笑顔で登校できますね 🙂
もうすぐ夏休みなので
気分が変わって
また休み明けには登校できるかと期待しています。
でも、夏休み明けはまた登校できないと
その先もずっと不登校になるのじゃないかと心配なんです 😐
夏休み明けの不登校も多いんですよね。。
そうですね
文部科学省の調査によると
夏休み明けの8月下旬〜9月上旬は
一年で最も不登校が増加する時期になっています。
特に中学生では
夏休み明けの不登校率が
通常の約2.5倍です。
この数字には
一学期は通常に登校していたのに
夏休み明けから不登校になった子も含まれています。
 でもご安心ください!
でもご安心ください!
夏休み前に不調がわかっている場合は
夏休みを上手に過ごして
その不調を休みのうちに
解決するチャンスにできるとも言えます。
休みの時間を有効活用すれば良いのです 🙂
普通の家庭でもできるんですか?
遊びに連れ出したり
好きなことをさせて
気分を良くすることくらいしかできないと思ってました
はい、不登校になるにもワケがあります。
そのワケをリリースすれば
不登校でいる理由もなくなります。
夏休みの間は
他の子達も”学校を休んでいる”ので
不登校の子も気持ちが少し楽になります。
その時間を上手に使って
子どもの生きる力を引き出しましょう!
目次
なぜ夏休み明けに、また不登校になるの?
夏休みの間は
他の子達も登校しないので
不登校の子は気持ちが少し楽になります。
毎朝「今日も登校できない」と
嫌な気持ちにならずに済むからです。
お母さんも同じように
ちょっと気持ちが軽くなります。
 しかし、夏やみ中に根本改善をせずに
しかし、夏やみ中に根本改善をせずに
夏休み明けが近づいてくると
また「登校」が現実的な問題として
目の前に浮かんできます。
そうなると
しばらく登校できてなかっただけに
「登校」へのハードルを高く感じてしまい
「嫌だな」「どうしよう」と
子どもの気持ちや思考がぐるぐるし始めます。
親も「休み明けに
行けなかったらどうしよう」と
不安になります。
その結果、親子とも
夜しっかり眠れなかったり
生活リズムが乱れたり
食欲不振になったりで
体調やメンタルを崩すことも少なくはありません。
気分が晴れたとしても
それが休み明けの登校につながるとは限らないんですね。
もちろん、夏休みに体力・気力を回復して
休み明けに登校できるくらいになることもあります!
それは、その子の
身体・心のエネルギーの低下が
それほど大きくなかった場合です 🙂
不登校になるワケは
その子のストレスの総量が
その子の心身のエネルギーの総和に
近づいてしまったことです。
特定の出来事は
「最後の一押し」
「きっかけ」であることがほとんどです。
 それが来る前に
それが来る前に
自覚症状のあるなしに関わらず
心身のエネルギー量が少なくなっていたために
そのきっかけで動けなくなる・・というのが不登校です。
うちもそのタイプです。
何か一つの大きなきっかけがなくても
様々なストレスが積み重なって
エネルギー切れになっている子も多いです。
では、そういう原因がわからない不登校でも
根本的に改善するんですね。
はい、大丈夫です!
その子が心身のエネルギーを
自分でしっかり作れるようになれば
不登校からも回復しますし
ストレスにも強くなります。
心身のエネルギーは
外から得るものではなく
自分で作るものなんです。
そして、多くのお子さんにそうなって欲しいのですが
残念ながら社会環境の変化と共に
ただ休んでいるだけだと
回復が難しいお子さんの数が年々増えています。
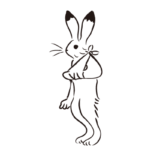 サポートが必要な状況だと
サポートが必要な状況だと
「時間が解決してくれる」
「本人が動き出すのを待つ」
というのは
一見優しそうですが
子どもをさらに困難な状況に
追い込んでしまうこともあります。
怪我をした時に
ただ安静に休んでいれば
自分で回復できる場合と
サポートが必要な場合があるのと同じです。
イメージがすっきりしますね!
はい 🙂
そして思春期の不登校は
・身体
・心
・頭
が、それぞれ変化する時期なので
(まだ成長途中なので拗れやすい面もある)
その3つを整えるのが大事なコツになります。
不登校の夏休みにやりがちな3つのNG対応
次は、夏休みやりがちな、不登校への3大NG対応について見ておきましょう。
「1」自由にさせるが逆効果になるケースも
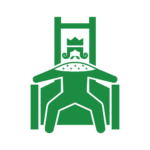 好きなことを思い切りさせれば
好きなことを思い切りさせれば
気分も晴れて
休み明けに登校する気になるのではないか?
そう思われるのも良くわかります。
ただ、思春期の子どもは
しっかりしているようで
まだ前頭葉が発達途中です。
自分の状況を客観的に見たり
長期的な影響まで考え抜いて
自分の行動を決めるよりも
時には自分の目の前の欲求や
好奇心だけで動いてしまうこともあります。
さらに、不登校になっていれば
それなりに気分も後ろ向きになっていたり
(その反動で学校以外のことには
ハイになることもあります)
 「怖い」「嫌だ」で
「怖い」「嫌だ」で
”避ける”ために動いてしまうこともあります。
考え方のもとになっているが
ネットでのガセ情報ということもあります。
ある程度の客観的で長期的な視点を持って
親のリードも必要な場合があることは
いつも覚えておくのがオススメです。
ただ好きにさせるのとは違うんですね
子どもが適切な判断ができる状態になるよう
サポートしていきましょう!
「2」「学校の話を避ける」ことが登校のハードルを上げるケースも
子どもが調子が悪い時には
学校の話をすると
不機嫌になったり黙り込むことがあります。
ただ、だからと言っていつまでも
「子どもの気分を悪くしないように」と
学校の話を避けるのはNGです。
子どもがショック期・安静期を経て
回復期に入ってきたら
少しずつ学校の話をするチャンスを作る方が
回復が早く進みます。
 子どもの状況の改善とともに
子どもの状況の改善とともに
学校や進路についての話題は
少しずつしていくのがおすすめです。
話す場合には
「いつから行くの?」という話ではなく
「学校でこんなことがあったそうだよ」とか
「進路についてこんな情報があるよ」などの
本人の行動そのもについてではないところから
始めるのがおすすめです。
学校の話をするのは当たり前になってきて
子どもの心身の状態も回復してきたら
この先どうするか、という
子どもの行動の話に移っていきます。
「3」勉強だけにフォーカスする危険性
 これまで休んだ分の遅れを
これまで休んだ分の遅れを
なんとか取り戻させなくちゃ!と
勉強ばかりさせようとすると
かえって回復が遅れてしまうことがあります。
脳の状態(身体)が整ってないと
勉強はただの苦痛になります。
やってもあまり頭に入りません。
身体→心→頭の順番が重要です。
今教えてもらってよかったです 🙂
子どもの「身体」を遠える夏休みの過ごし方のコツ
当カレッジではまず身体を整えるところから始めます。
それが、これまで16年間で最も最短で
また、逆戻りすることのない
回復に繋がると経験からわかっているからです。
身体には、脳や気分にも関わるホルモンも含まれます。
身体から整えることで
心や思考も安定しますし
実際に「学校に行きたい」と思った時に
それができる状態になるからです。
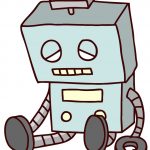 「学校に行きたい」と思っても
「学校に行きたい」と思っても
腹痛があったり
玄関で動けなくなっていては
登校が難しくなります。
そしてそんな状態が続くと
だんだんやる気も希望も失うことも起こります。
もったいないですね 😐
身体を整えるには
*生活リズム
*睡眠
*栄養
*運動
がキーポイントです。
生活リズムは、夏休みだからと
登校時と大きくずらしてしまうと
後から戻すことに大きな努力がいるようになります。
 特に睡眠サイクルについては要注意です。
特に睡眠サイクルについては要注意です。
人は就眠時刻と起床時刻の真ん中が
1.5〜2時間ずれると
ジェットラグ(時差ボケ状態)になります。
不登校でも、夏休みでも
ずれは大きくしないのがおすすめです。
栄養は、あまり広く知られていませんが
思春期は成長期のために
成長に必要な栄養が大量に必要です。
特に夏は炭水化物や水分過多になりやすいですね。
疲れやすい、やる気が出ない
考えが後ろ向き
集中力がない
イライラ、怒りっぽい・・
そんな状態は
身体に必要な栄養が足りていない可能性大です。
 当カレッジでは
当カレッジでは
難しい献立不要で
思春期の身体・心・頭を最も健康にする方法をお伝えしています。
これまで数百名の不登校が
根本から改善したばかりでなく
その子の心身から
本来の可能性を引き出した方法です。
ピンときた方は
思春期最幸家族講座や個人セッションでご相談ください。
身体が成長する思春期に
脳の前頭葉という部分が活発に発達します。
この前頭葉は25〜30歳まで
じっくりと時間をかけて発達するので
思春期の初めの頃には
本能脳(怖いなど)や欲求脳(今嫌、今やりたいなど)の方が
表に出やすくなることがあります。
 健康な子でも
健康な子でも
これらの脳に引っ張られやすいことがありますが
不登校になっていたら
よりその差が開きます。
逆に「怖い」「今やりたくない」「今やりたい」に
子どもの思考が引っ張られて
屁理屈を考えだしたり
実際に引っ張られた後に
自己嫌悪に陥ったりすることも多くなります。
脳は身体なので
生活リズム・睡眠・栄養・運動に
成長が影響されます。
脳も絶賛発達中なんですね。
子どもの「心」を育てる親の関わり方
子どもの心を健やかに整えて成長させるには
まず身体から整えることは必須です。
身体にはホルモン(気分)も含まれるからです。
そうですね。
更年期も同じように、ホルモンも乱れからイライラや落ち込みが生じることもあります。
でも、どちらも日常の中で、整えることができますので、ご安心くださいね。
更年期 vs 思春期になりそうでした 😉
身体を整えつつ、子どもが心に
安心と自信が持てるように関わっていきます。
そのために役立つのが
勇気づけコミュニケーションです。
”勇気づけ”は、アドラー心理学の言葉です。
子どもが安心して話しやすくなったり
自分のことを好きになるようなコミュニケーションの仕方です。
参考:子どもが伸びる褒め方は?思春期の子育てで知っておきたい勇気づけ
例えば、子どもと会話するときに
まず一つ、子どもを認める言葉をかけてから
「そして」で繋いで次の言葉を言う
Yes, and コミュニケーションもその一つです。
褒める、というよりも「認める」という方が近いです 🙂
子どもが何かをしたり言ったりした時に
「そうなんだね」と
一度受け止める言葉を言うだけでも「認める」ことになります。
子どもは受け止められたことに安心して
ずっと話しやすくなります。
はい、詳しくはこちらのブログもどうぞ。
子どもが伸びる褒め方は?思春期の子育てで知っておきたい勇気づけ
親世代までは
「親や先生の言うことは絶対」と言うコミュニケーションが通っていました。
ところが今の子達は
ネットで様々な情報を早くから得ているので
「親や先生の言うことがいつも正しい」とは
全く考えていません。
 しっかりこちらが伝えたい”内容”を伝えるには
しっかりこちらが伝えたい”内容”を伝えるには
まず子どもが
「話を聞こう」
という姿勢になっていることが必要です。
確かに思春期の反抗期もありますが
コミュニケーションのコツを使えば
子どもが安心して家族と会話するようになります。
家族との会話が安心んだと思えれば
本音を話すこともできます。
子ども自身が話すことで
自分の考えや気持ちを整理していくこともできます。
言葉で表現できるようになれば
イライラなどの感情を
ただぶつけることも減っていきます。
そうなんです!
当カレッジでは、その子とご家族の個性と状況に合わせた
コミュニケーションのコツをたくさんお伝えしています 🙂
家族関係が良くなったというご報告をたくさんいただいています。
家族関係が安定して
子どもが安心できると
不登校改善も思春期の発達もスムーズに進みます。
また、友達関係や勉強への不安など
未解消の「きっかけ」がある場合には
夏休みのうちに
「なんとかなりそう」と思えるところまで
対応ができるようになっていれば
休み明けに安心して登校しやすくなります。
 具体的にはそれぞれのケースで対応は異なりますが
具体的にはそれぞれのケースで対応は異なりますが
本人の「何に抵抗があるか」
「それがどうなれば良いか」
から始めるのが大事なコツです。
周りが思っているのと
本人が思っている望む未来が違うことはよくあります。
大事なのは、子どもが
「自分の課題を自分で乗り越えられた」という
感覚を持てるようにサポートすることです。
子どもの「頭」の可能性を引き出すためにできること
まず、身体を整えることと
コミュニケーションをバージョンアップさせることは
子どもの思考にとても大きな良い土台をつくります。
その上で頭を整えるコツもあります。
 不登校の子は
不登校の子は
「自分は他の子ができることができない」
「登校できない」
とネガティブな思考を常に持っています。
それが嫌で
現実逃避にゲームやデジタル
買い物や遊びに逃げてしまう子も少なくないのです 😐
表面的には平気そうだったり
屁理屈で強く見せても
それは外に向かっての自信がないために
せめて親だけでもコントロールしようとする
無意識の現れにすぎません。
先ほどの勇気づけのコミュニケーションで
小さなことでも、できて当然だと思うようなことでも
「いいね」と言うサインを
さらっと出し続けていくのがおすすめです。
褒めて動かそう、とするのではなく
ただ事実として「いいね」と思っていることを
伝え続けることがポイントです。
 子どもが不登校だと
子どもが不登校だと
親としても自信をなくしがちです。
(私も経験があります)
それで、子どもを改善しようと
ついダメ出し(改善点ばかり探す)ことにもなりがちです。
人は気になったところばかり目につくものです。
なので、意識して
ほんの少しでも良いことがあるのに
意識を向けていきましょう。
不思議なようですが、
お母さんがそうすると
子どもも自然とそうなってくるんです。
最も苦しいのは
「どうしよう」「でも何もできない」という
ぐるぐる思考を続けることです。
 ぐるぐる思考では
ぐるぐる思考では
「できないこと」ばかりに意識が向いてしまいます。
少しでも「できていること」が見つけられるようになれば
「できること」も見つけられるようになります。
身体と心を整えながら進めると
必ずぐるぐる思考から自然に抜け出せます。
そして、もう一つ
今の思春期の不登校にありがちなのが
親よりも達者な屁理屈を言うタイプです。
例えば一方的に
「自分は約束を守らないのは
親が守らないからだ」などと
激しく主張して
結局ゲームの使用ルールを守らない状態に
持っていくような状況です。
 親御さんの方が素直だったり
親御さんの方が素直だったり
何か子どもに「悪かった」と思うようなことがあったり
または子どもが「自傷してやる」と脅すような場合だと
親御さんが子どもの言いなりになってしまっていることもあります。
その関係性は不自然です。
家の外では通用しないので
子どもは外に行くことをより嫌がるようになってしまいます。
できるだけ早くの改善が必要です。
このような屁理屈力?のある子への対応は
一つ一つその屁理屈の根拠を潰していくことです。
具体的な方法はかなり個人の個性と環境によりますが
喧嘩や対立ではなく
子どもの屁理屈の威力を減らす方法はあります。
ピンと来た方はご別にご相談ください。
どう言い返したらいいのかわからないので
ぜひ、詳しくご相談したいです
はい、大丈夫です!
その他の不登校の夏休み過ごし方のコツ
⭐︎夏休み開始前から、身体・心・頭へのアプローチを開始します。
無理やりパワーで子どもを変えるのはなく
子どもが自然に変わっていくコツなので
毎日少しずつ改善します。
なので、早く始めれば早いほど
良い変化が積もっていきます。
 ⭐︎親の役割を常に意識する
⭐︎親の役割を常に意識する
子どもを変えよう、なんとかさせようと思って関わると
子どもは必ず抵抗します。
子どもには本来
自分が進むべき道を見つける力があります。
ただ、不登校になっていると
思春期の不安定さと共に
それに真っ直ぐに進めないことがあるのです。
特にここ10年で
社会環境の変化から
子どもの身体の力が大幅に落ちています。
「不登校は心の問題」だと決めてかかると
回復までに数年かかったり
社会に戻っても不安さが消えないことも増えています。
 身体・心・頭の順番に
身体・心・頭の順番に
子どもの生きる力が発揮できる状態になれば
親が〜〜させよう、としなくても
必ず子ども自らが自分のために必要な動きを始めます。
それはこれまでに
数百人で見てきた真実です。
⭐︎その子の個性に合わせて対応する
兄弟姉妹でも、個性は違います。
なので、コミュニケーションの仕方も
ちょっとしたコツがヒットする子もいれば
全くスルーの子もいます。
最近は兄弟姉妹で、時間差や同時に
不登校のご家庭も増えています。
一人の子にうまく行ったコミュニケーションパターンが
他の子にも響くとは限りません。
 そんな場合には、つい
そんな場合には、つい
「この子は性格が悪い」と
捉えてしまいがちですが
コミュニケーションのツボが違うだけなんです。
次に、これまでの改善事例をご紹介しますね。
実例公開:夏休み明けに笑顔で登校できた3つの成功事例
「1」中学2年生A君
A君は1年生の4月からの不登校で
当カレッジには2年生の7月に参加されました。
ちょうど夏休み前だったので
すぐに身体・心・頭へのアプローチを開始してもらいました。
 始めた頃は昼夜逆的気味でしたし
始めた頃は昼夜逆的気味でしたし
「もう学校なんて行きたくない」と
ぶつぶつ言うことが多かったのですが
徐々に夏休みの間に前向きになり
夏休み明けの8月末からは
投稿を開始しました。
ポイントは、無理に登校を目標にしたのではなく
思うように動ける身体作りから始めたことです。
今は高校受験に向けて、行きたい部活のために頑張っています。
「2」中学1年生Bさん
Bさんは小学校の頃から
保健室登校が多かった子でした。
4歳上のお姉さんも
一時保健室登校だった状態から
1ヶ月位で回復したので
 お母さんは同じように
お母さんは同じように
「見守って」いたのですが
Bさんはそれでは回復が難しかったのでした。
夏休み開始とともに
当カレッジに参加されて
身体・心・頭へのアプローチを始めたところ
夏休み明けには以前よりも
登校への抵抗も少なくなり
二学期からは徐々にクラスにいる時間が増えていきました。
二学期にはクラス行事にも
積極的に参加するようになり
三学期からは完全に通常登校をするようになりました。
2年生では
生徒会にも立候補して楽しく登校しています。
「3」高校1年生C君
 C君は中学の時には
C君は中学の時には
特にお困りはありませんでした。
しかし、高校受験で第一志望に入れず
それがきっかけとなって不登校になりました。
夏休みから身体・心・頭へのアプローチを始めて
同時にコーチングセッションで
彼が本当に望む未来像を明確にしました。
そこから身体のエネルギーと共に
心のエネルギーも湧き上がってきました。
まず夏休みには勉強を開始して
二学期からは登校も始めました。
その後志望大学、志望学部に合格して
今は希望のテーマを学んでいます。
要注意!登校再開時に出会いやすい壁と乗り越え方
 夏休みに身体・心・頭を適切に整えると
夏休みに身体・心・頭を適切に整えると
休み明けにはかなり良い状態になっていたり
回復に自信が持てるようになります。
それでも子どもの個性や
休んでいた期間の長さや状況
また、きっかけの種類や程度によっては
再登校の時に壁を感じることもあります。
よくある壁とその乗り越え方のコツもご紹介しておきますね。
壁1 身体の壁
休み明けに心身のエネルギーが
かなり溜まってきていても
久しぶりに家の外、学校に行く場合には
身体が緊張することもあります。
 それで腹痛や頭痛、吐き気などがある場合には
それで腹痛や頭痛、吐き気などがある場合には
無理をせずに
ゆっくりペースで登校するのがおすすめです。
「初日から完全に行かないと!」
と焦るよりも
数コマ遅れて行ったり
しんどくなったら早めに帰る
または保健室で休むのもOKにしましょう。
そうやって少しずつでも毎日登校していると
徐々に身体も「大丈夫だ」とわかってきます。
はい、そうです 🙂
「学校は安全」と身体が覚えればOKです。
避けたいのは
『やっぱりちゃんと行けなかった。
もうだめだ』
と親子で思い込んでしまうことです。
先ほどの実例「2」のBさんのように
じっくり戻って行っても良いのです。
壁2 友達関係の壁
休んでいた間に友達関係も変わっているかも。。と
不安になることもありますね。
それでも休み明けは
少し”仕切り直し”感もありますので
あまり深く考えすぎずに
堂々と?毎日投稿するのがおすすめです。
自分であれこれ考えすぎずに
毎日クラスにいるのが当たり前になれば
友達関係も自然にできてきます。
 無理に自分から声をかけようとしなくてもOKです。
無理に自分から声をかけようとしなくてもOKです。
ただ、自分から壁を作ることも必要ありません 😉
壁3 親の心配・ハラハラの壁
夏休み明けに登校を始めたら
子どもは久しぶりなので
登校して帰ってくるだけで
一杯一杯のこともあります。
親が心配だからと
「今日は何をしたの?
誰と話したの?」と
質問責めにしたり
「なんで早く帰ったの?
大丈夫?」
などと心配しすぎると
子どもはそれに反応してピリピリしてしまいます。
 身体・心・頭へのアプローチができていれば
身体・心・頭へのアプローチができていれば
必ず大丈夫なので
心配無用です 🙂
不登校の夏休みの過ごし方のコツ:終わりに
休み明けに行けなかったらどうしよう・・と
ずっと気になっていました。
考えてみれば
夏休みには時間がありますね。
その間にできることがわかって
かなり気分が楽になりました
思春期の子どもは
一定以上のダメージを受けると
いきなり状態が悪くなることもありますが
必要なサポートがあれば
大人よりも何倍も早くに回復します。
みなさん、驚かれるくらいです
安心できます。
次はより詳しく,うちの子への対応を教えてください
♡♡あとがき♡♡
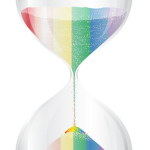 夏休みは短いようで長く
夏休みは短いようで長く
長いようで短いですね。
やることをシンプルに決めてやってみれば
思春期の子どもには
ちゃんと変化が出てきます。
思春期の子どものサポートが
うまく進むキーポイントは
身体へのサポートをしっかり実践することと
その子に適したコミュニケーションスキルです。
個性に合わせたコミュニケーションスキル、
といっても
それほど難しいものではありません。
 始めは、これまでに慣れている
始めは、これまでに慣れている
コミュニケーションと違うので
難しく感じることもありますが
みなさん実践していけば
ちゃんとお子さんの反応が変わるので
自信を持って対応できるようになります。
努力は「ただ頑張るだけ」では
結果に結びつかないこともあります。
大事なコツを押さえれば
思ったよりも簡単に
良い結果になることもあります。
ぜひ、夏休みの時間を有効活用して
休み明けにご家族全員で
笑顔になっていただければ嬉しいです
\(^-^)/
合わせて読みたい記事:
学校に行きづらい子の夏休み:しんどさも発達のぬけも解消するチャンス!