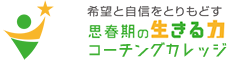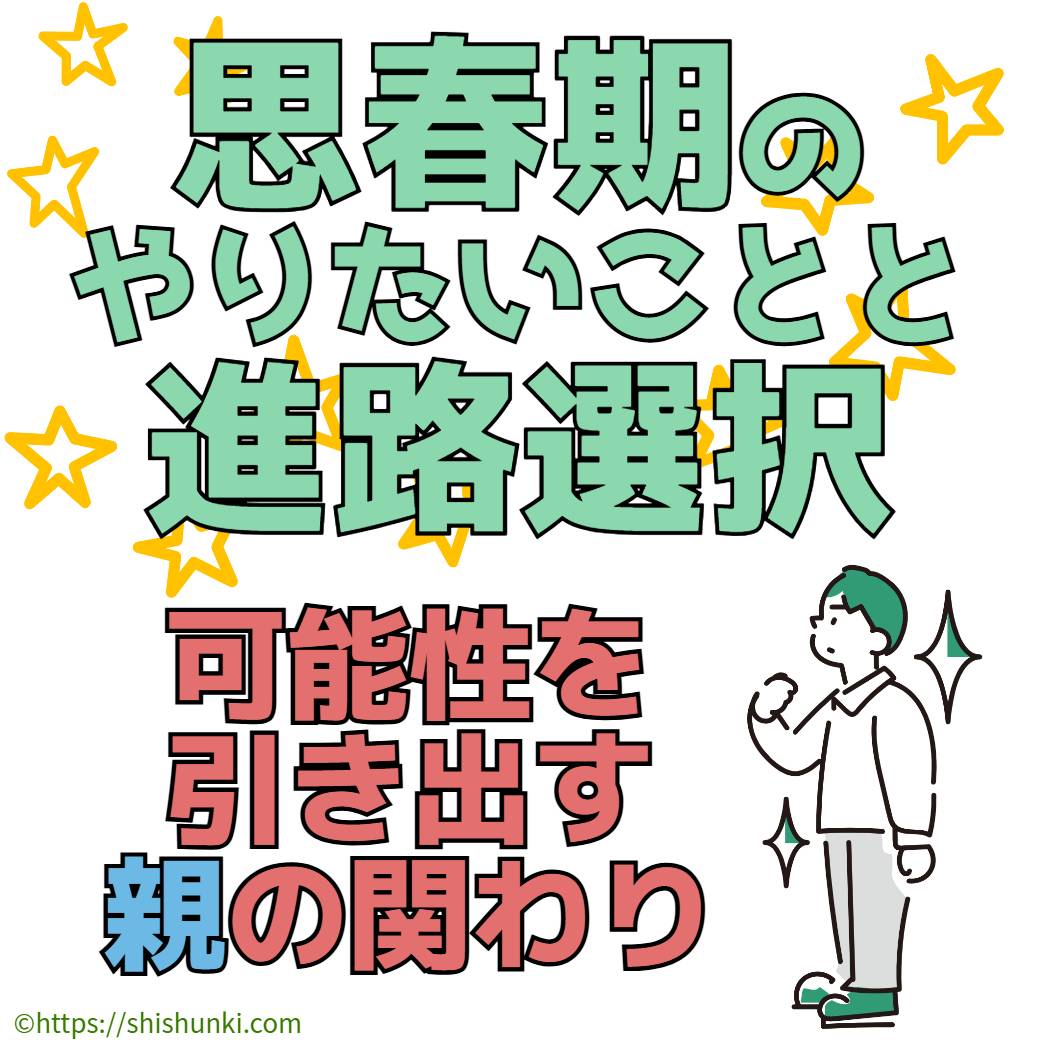中学生が嘘をつく時:2つの心理と親の対応

中学生が嘘をつくと、親としては
ショックで不安になります。
しかし、その勢いで問い詰めたり
または見逃したりしてしまうと
「嘘をつく癖」は習慣化する可能性が高くなります。
中学生が嘘をつく時の2つの心理と
成長につなげる親の関わり方をご紹介します。
正直に話してくれれば
失敗だって怒らずにすむのに
嘘をつかれたことで
私もカッとなってしまいます。
そうなると親子げんかみたいになるだけで
嘘の改善にはらないんです 😐
どうしたらいいでしょう
中学生が嘘をつくと
親は「何で嘘をつくんだろう」
「このまま癖になったらどうしよう」と不安になりますね
大事なことも隠されてしまいそうですし
友達や先生にもついてたらどうしようと
心配になります。
でも、もしかしたら私の育て方が悪かったからなのかもしれないとも思うんです。
そうなんですね。
実は中学生が嘘をつく時には
大きく二つの心理状態があります。
それぞれ必要な対応が違いますが
その心理状態についての
必要な情報と具体的な対応方法があれば
子どもは嘘をつくこともなくなります。
はい、もちろんです!
ではご一緒に、中学生が嘘をつく時の
2つの心理状態についてと
効果的な対応について見てみましょう
目次
気をつけたい、ついやりがちな親のNG対応
我が子の、中学生になって嘘に気づいた時に
親がうっかりやってしまいがちな対応があります。
そして、その対応が問題をさらに悪化させてしまいます。
 「なんで嘘つくの!?」
「なんで嘘つくの!?」
「正直に言いなさい!」
「いつから嘘をついてたの!? 他にも嘘があるんじゃないの!?」
嘘を発見した瞬間、怒りと不安が湧き上がって
つい感情的に問い詰めてしまう・・
これは、子どもを心配するあまりの素直な反応です。
けれど、子どもは親の感情的な
「変えよう」「否定しよう」
というパワーに圧倒されて
この瞬間は「攻撃されている」と感じられてしまいます。
感情的に問い詰められた子どもは
- さらに嘘を重ねて自分を守ろうとする
- 完全に心を閉ざし、黙り込む
- 「親には何も話せない」という確信を深める
こうして、「親に正直に話すことは危険だ」
という学習が強化されてしまうんです 😯
逆に、波風を立てたくない
子どもを追い詰めたくないからと
嘘に気づいても見逃してしまうケースもあります。
「まあ、今回はいいか」
「これくらいなら大したことない」
「問い詰めて関係が悪化するよりは…」
しかし、この対応も危険です 😯
子どもは敏感に親の反応を観察しています。
嘘を見逃されると、子どもは自然にこう学習します:
「嘘をついても問題ない」
「バレなければいい」
「親は本気で向き合ってくれてない
ごまかすのはチョロいが
自分にあまり関心は向いてない」
 結果として、嘘はエスカレートして
結果として、嘘はエスカレートして
嘘の習慣化や
親との信頼関係の崩壊など
より深刻な問題へと発展してしまいます。
そして、最もNGなのがこのパターンです。
新しい問題が起きるたびに
過去の嘘を持ち出してしまう。
「前もそうだったよね」
「この前も嘘ついたばかりじゃない」
「もう何も信じられない」
この対応は、子どもに
「やり直すチャンスはない」
「これから頑張っても無駄」
というメッセージを送ってしまいます。
人は、未来に希望が見えないとき
変わろうとする意欲を失います。
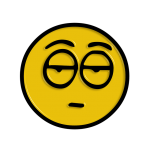 「どうせまた過去のことを言われる」
「どうせまた過去のことを言われる」
「もう信頼は取り戻せない」
「だったら、どうでもいい」
こうして、親子の間に修復不可能な溝が刻まれてしまいます。 (T_T)
ちゃんと分かってないと
行き当たりばったりで
どれもやってしまいそうです。。
こういう対応が子どもを
嘘の習慣化に追い込んじゃうとは
知りませんでした 🙁
そうですよね。
お子さんを思う気持ちがベースにあるのに
逆効果になってしまうのは
とてももったいない (T_T)
では、このような対応が逆効果になってしまうのはなぜでしょうか?
それは、どれも「嘘という行為」にだけ
焦点を当ているからです。
 その行為を直そう、変えようとすることに
その行為を直そう、変えようとすることに
意識が向いています。
つまり
「嘘をつくことになった子どものワケ」
に注目していないんです。
生えている雑草の
土から出ている部分だけを刈り取っても
根っこはそのまま・・では
雑草はまた生えてきますし
土の中では根っこを広げてしまうのと同じです。
嘘が出てくる「心理」「ワケ」を
見極めて
子どもがそれを手放せるように関わることが
子どもにも親にも最も良い未来に繋がります!
子どもが嘘をつくのは
★ごまかしたいから
★怒られたくないから
だと思っていました。
ただ、なぜごまかしたいとか
怒られたくない気持ちが
嘘に繋がったのかまで
意識したことはなかったです!
中学生が嘘をつく2つの心理パターン
中学生が嘘をつく時には2つの心理状態があります。
多くの子育て情報では
1つ目のパターンだけを扱っていることが多いですが
最近は特に2つめのパターンが増えています。
 子どもが何かを守りたいために
子どもが何かを守りたいために
防御手段として嘘をつくパターンです。
子どもが守りたいものは一つではなく
以下のうちの複数あるのがほとんどです。
(1) 親との境界線を守りたい
これは思春期の自立心の芽生えと親の支配への抵抗という心理です。
中学生は、自分の領域を確立したい本能が強い時期です。
親の過干渉や質問攻めから自分の心の内側を守るための境界線として嘘でガードすることがあります。
ひとつの「反抗期の態度」です。
(2)失敗や弱さを隠したい自己防衛
中学生は、他者からの評価を強く意識します。
テストの点数や友達関係の失敗など
「親に話せば、ガッカリされる・怒られる」
のを避けたくて
つい嘘をついてしまうことがあります。
私も中学生の頃には①があって
親にはこれ以上入ってこないでっていう気持ちがありました。
でもそれは忘れていたので、
子どもには理由②の
”怒られたくない”しか想像してませんでした
(3)心身のエネルギー切れから命を守る
中学生は身体・心・頭は急速に成長します。
その時には、それに見合うエネルギーがないと
心身のエネルギー切れになります。
そうなると、物事にちゃんと向き合ったり
チャレンジしたりするのがおっくうになります。
ただ、これは怠けではなく
向き合ったり考えたりして
これ以上エネルギーを使わないようにするための
自律神経の、命を守るための働きなんです。
神経生理学について知らないと
「ただ怠けているだけ」
「きちんとやらない」と
誤解されやすいのですが
かなりのエネルギー切れになると
段取りを踏んで何かをしたり
細かく説明するのが億劫で辛くなるんです。
寝る前のストレッチが億劫になることがあります。
そういうこと、ありますよね 😉
子どもがエネルギー切れになると
手を抜いてしまったり
何かを色々考えて説明するよりも
簡単な嘘をついてしまうこともあるのです。
そうなんです。
ただ、思春期の子どもは
自分の心身の状態にあまり気づけないこともあります。
不登校や腹痛などの
わかりやすいお困りが出てから
心身のエネルギー切れに気づくことも多いんです。
また、不登校の子がお風呂に入らなくなることもよくあります。
それは入浴して熱エネルギーの交換などで
疲れることを避けるためです。
そうなっていた子も土台から回復すれば
全員、ちゃんとお風呂に入りますので
ご安心くださいね。
 そして、この「1」防御の
そして、この「1」防御の
全てのパターンの裏には「恐れと辛さ」があります。
中学生はまだ脳の前頭葉が発達途中なので
長期的に考えれば
嘘がばれたり自分にデメリットが来るような場合でも
「今目の前の恐怖や辛さを避ける」ことを優先しがちです。
なので、「嘘をつくことの必要性」は
「恐怖や辛さ」ですから
その恐怖や辛さが無くなるように関われば
嘘をつく必要がなくなります。
「1」の防御パターンでは
何か守りたいものがあって
その手段として嘘をつきます。
裏には
「ちゃんとありのままに話せればいいのだけど・・」
という思いがあります。
 ところがこの「2」欲求追求パターンでは
ところがこの「2」欲求追求パターンでは
ちゃんと話さないことへの罪悪感は
あまり感じないのが大きな違いです。
例えばゲームの使用時間を
実際はかなり過ぎて使かった日に
「約束の時間以上に使った?」と聞かれて
「ううん」と答えたとしても
「1」では「今度からは気をつけよう」
という思いが裏にあります。
ところが「2」では
「やりたかったからやっただけ。
見つからなければ今度もやろう」
という心理です。
「自分がやりたいから」とか
「自分が嫌だから」が
自分の行動の中心になっていて
ルールや約束
前に説明された理由などは
あまりたいしたこととして捉えていない状態です。
重症のように思えます
そうですね。
「2」になってしまうのは
●小さい頃から
「嫌だ」がいつも通っていた
●「1」から始まった嘘が習慣化したから
●もともとあまり周りのことを気にかけない傾向が強い
等の理由があります。
何らかの理由で周りの親や大人が
子どものルール破りや嘘を見逃すことが多かったり
不登校で「かわいそうだから」と
好きなようにさせていたりすると
この「2」になってしまうことも多いです。
 また、発達の抜けがあって
また、発達の抜けがあって
「自分の欲求は通そうとするが
周りへの関心があまりない」傾向があることもあります。
「2」のパターンは
より「嘘をつく」ことが慢性化していて
「罪悪感」が少ないですが
「1」よりも身体・心・頭への関わりを
しっかり行うことで
改善や発達はもちろん可能です。
よかった 🙂
嘘をつく癖は“将来の人間関係”を壊す?
「まだ中学生だから、そのうち落ち着くでしょう
見守っていれば大丈夫」
そう思いたい気持ちはよく分かります。
しかし、残念ながら思春期の嘘の問題は
時間が解決してくれるものばかりではありません。
むしろ、思春期は「信頼関係の土台」が固まる最後のチャンスです。
子どもの嘘の全てに細かく
同じように関わる必要はありません。
まずは子どもの嘘の裏にあるワケ・心理を知って
必要な対応を必要なだけ行えばいいだけです。
 ただ、サポートが必要な状態なのに放置してしまうと
ただ、サポートが必要な状態なのに放置してしまうと
嘘は“自己防衛として便利すぎるので”
癖になってしまう可能性が高いのです。
そして嘘が習慣化すると、子どもには
「嘘をつかないと自分を守れない」
という思い込みと嘘をつく癖が確立してしまうのです。
中学生の嘘が習慣化すると起こる3つの深刻な問題があります。
① 友人関係・人間関係での孤立
中学生にとって、友達関係は本能的に大事です。
一度「あの子は嘘つき」とレッテルを貼られたら
SNSであっという間に広げられてしまうこともあります。
大人からすれば、思春期の友達関係は
大人になれば大きな影響はないと分かりますが
思春期の子どもにとっては
今の友人関係が大問題です。
 また、中学生での人間関係が
また、中学生での人間関係が
その後の人間関係のパターンに大きく影響することもあります。
ここで孤立を経験したことで
人を信じられなくなる元になることも
少なくはありません。
(ただ、そうなったとしても
いつからでも修復できますので
ご安心・ご相談くださいね)
入試や就活でも重要視される「信頼性」
社会に出てから最も求められる「ルールを守る誠実さ」。
これらは、思春期に基板が作られます。
② 嘘の習慣化による、物事に向き合えない態度
嘘が習慣化してしまうと
・自分の本音がわからなくなる
・物事に向き合えない態度の習慣化
というリスクがあります。
 嘘をつくことが癖になると
嘘をつくことが癖になると
自分の本音やものごとに
正面から向き合って
それを理解したり対応しようとする姿勢が
持てなくなります。
人にごまかしているうちに
自分の気持ちもよく分からなくなります。
逃げたりぼやかしているうちに
物事の本質に取り組むということも
分からなくなってしまいます。
表面的な「逃げ」
その場限りの「つくろい」
が癖になってしまったら
自分の成長もその喜びも
手にするチャンスが失われてしまいます。
もったいなさ過ぎます・・・
③ 親子の心理的距離の固定化
 最も深刻なのは、親子関係の決定的な断絶です。
最も深刻なのは、親子関係の決定的な断絶です。
思春期に親に本音を話せなくなった子どもは
大人になってからも親に心を開くことが難しくなります。
表面的な会話はできても
人生の重要な局面で相談しなくなってしまうのです。
就職、結婚、出産、仕事の悩み、人間関係の問題…
親が子どもの人生にどのように関わるかの土台は
思春期に築かれます。
その裏にある心理やエネルギー状態などの理由にも
目を向けることが大事なんですね
「嘘をつく」2つのパターンに必要な親の対応
まず、「1」防御パターンへの対応から見てみましょう。
ステップ0:
子どもが嘘をついたことに気づいたら
自分の心身の状態と
子どもの心身の状態をチェックします。
★身体が疲れている
★気持ちがイライラしていたり、落ち込んでいる
★頭がぐるぐるしていたり、他のことでいっぱい。。。
どちらかがそんな時には
すぐに長く話して、今嘘を手放させよう!としても逆効果です。
 今すぐ言わなくてはならないことだけ
今すぐ言わなくてはならないことだけ
コンパクトに伝えて
詳しい話は
もっと子どもと親の状態が良い時にします。
親がその場で深呼吸したり
水を飲んだりすれば落ち着けるのならばOKです。
心身の状態が慢性的に悪い場合には
どちらも身体へのアプローチが必要な状態です。
ステップ1:
落ち着いた、ゆっくりした声で話せるのならば
まずは子どもの言い分を聞きます。
「どうして嘘をついたの?」よりも
「何が起きて、そういう言葉になったの?」などの
「責める感じがない」言葉がおすすめです。
 人は恐怖を感じると
人は恐怖を感じると
すぐに防御態勢に入りますので
「大声や脅しで本音を引きだそう」
とするのは、百害あって一利なしです。
嘘をついたことと
嘘をついた出来事の両方があるので
今はどちらの話をするかをわけて
はっきりさせておくのも大事ですね。
嘘をついたことについてから話すのか
嘘をついた内容について話すのか
どちらでも優先順位が高い方からでOKです。
ステップ2:
子どもの言い分を意図通り聞いたら
「今、それについてどう思っているの?」と聞きます。
こちらも、嘘をついたことと
嘘をついた出来事についてはわけて話します。
ステップ3:
 今後の防止策を提案させます。
今後の防止策を提案させます。
本人が「ちゃんと正直に伝える」などと言えれば
「分かった。そう思っておくね」で終了します。
もし、何度も同じことを繰り返して
同じ防御策しか出てこない場合には
「同じことをこれ以上繰り返しても
同じ結果にしかならないので
ルールを決めましょう」
と、ルール決めをこちらから提案することもできます。
ルール決めについては
☆明確な判断基準
(嘘を1回ついたらなど)
☆結果見直しの日時
☆ペナルティ
を必ず決めます。
そして決めたルールは紙に書いて
全員が見れるところに貼っておくか
ネットで共有します。
子どもに言わせる、のがポイントですね!
はい、まさにそれが最も重要なポイントです!
次は「2.欲求追求パターン」への対応です。
こちらも、嘘が見つかった時の対応は
「1」と同じです。
ただ、ステップ2や3で
失敗や約束破りをしたことや嘘をついたことについて
子どもの思いを聞いても
「だってやりたかったら」
「だってやりたくなかったから」
「忘れた」
「めんどくさかったから」
 などの、感情・感覚的な言葉しか
などの、感情・感覚的な言葉しか
返ってこないことがよくあります。
そういう場合には
「失敗や約束破りをそのままにすると
どうなると思う?」
「嘘をつくことをどう思う?」
等と、本人に考えさせるような言葉をかけます。
そこで自分の未来や周りへの影響について
考えられれば防止策に進みます。
しかし、ここでも
「その場だけ逃れるために
適当なことを言う」子や
黙り込んで何も言わない子もいます。
適当なことを言う子には
実際に期限を決めてやらせてみて
うまくいくかどうかを見ようね、ということにします。
 そして必ず結果を記録しておいて
そして必ず結果を記録しておいて
見直す機会も決めておきます。
(たとえば1種間後に結果を一緒に見るなど)
それでできてなかったら
ルールを設定することにします。
黙って答えない子には
1時間後などの考える時間を与えます。
それでも答えないようであれば
ルール決めを提案して
反対意見がなければ
それを見直す期限を決めて実行します。
それらを試しても
嘘をつく、隠す癖が続く場合には
より本格的な身体・心・頭へのアプローチが必要になります。
基本的に「2」であれば
身体・心・頭へのアプローチが必要になります。
 その子の状態に合わせて
その子の状態に合わせて
土台から整えていけば
徐々に成長・発達していきます。
大事なことを本音で話せる関係を取り戻すために親のできること
中学生が嘘をついた時にできることは
ここまで見てきましたが
日常で本音で話せる関係を取り戻すために
日頃からできることをご紹介します。
(1)(2)(3)という
順番がとても大事なので
ここはしっかり守ってくださいね。
(1)身体を整える
睡眠、食事、運動、自律神経を整えて
安定した精神状態の物理的な土台を作ります。
子どもの心へ
気合いややる気を起こそうとしたり
説得やルールなどの頭への働きかけだけを行っても
身体のエネルギー不足や自律神経の乱れがあるままでは
ほとんど効果もありません。
まずは身体から整えましょう。
(2)心を整える
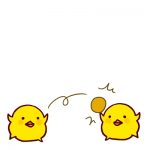 言葉や言葉の内容以外のトーンや表情
言葉や言葉の内容以外のトーンや表情
目線などでのコミュニケーションで
子どもに安心と個人としての尊重を与えます。
人は、身体と心が安定して初めて
他の人の話を聞くことができるようになります。
(3)頭を整える
身体と心が安定した状態で
しっかりと「考えさせる」ことが大事なポイントです。
大人は子どもに
「あれこれ教える、言う」ことが多いですが
子ども自身に考えさせて言葉として出させることがないと
のれんに腕押し
糠に釘になってしまいます。
「あんなに何度も注意したのに!」
となっている場合には
親の言葉の量が圧倒的に多いケースがほとんどです。
親の言葉の量 2
子どもの言葉の量 8
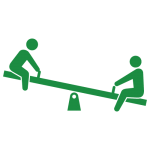 を目指しましょう!
を目指しましょう!
身体・心・頭への
お子さんの個性に合わせた
コンパクトに結果が出るのが早い関わり方は
思春期最幸家族講座やセッションでお問い合わせください。
「中学生の嘘」の事例
嘘が重なって完全に心を閉ざしてしまった中2女子の事例です。
Aさんの中2の娘・さくらさん(仮名)は
半年ほど前から頻繁に嘘をつくようになりました。
最初は小さな嘘でした。
「宿題やった」(実際はやっていない)
「友達の家にいる」(実際は別の場所にいた)
「テストはまだ返ってきてない」(実際は悪い点数を隠していた)
Aさんは最初、「思春期だから仕方ない」と思っていました。
しかし、嘘は徐々にエスカレートしたのです。
 学校から「最近欠席が増えている」と連絡があり
学校から「最近欠席が増えている」と連絡があり
驚いてさくらさんに聞くと
「行ってる」と嘘をつく。
部活動の顧問からも
「最近来ていない」と言われて
問い詰めると黙り込む。。。
Aさんは焦りました。
そして、感情的に問い詰めてしまいました。
「なんで嘘ばっかりつくの!?」
「もう何も信じられない!」
その後さくらさんは部屋に閉じこもり
ほとんど出てこなくなりました。
Aさんは後悔と恐怖に押しつぶされそうでした。
「私の対応が間違っていたのかもしれない」
「でも、どうすればよかったのか分からない」
「このまま娘との関係は終わってしまうのか」
眠れない夜が続きました。
 そのタイミングでAさんは講座に参加されました。
そのタイミングでAさんは講座に参加されました。
最初は半信半疑でしたが
「このままでは本当に取り返しがつかなくなる」
という危機感からの参加と行動でした。
Aさんは講座で初めて
「嘘の裏にある子どものワケ」に意識が向きました。
そして、具体的な対応方法を学び、その日から実践を始めました。
まず、身体を整えて
次に、感情を受け止めるように務めました。
最初は何を聞いても答えはなかったのですが
Aさんは焦らず、そして諦めませんでした。
日常でさくらさんが何か言った時にも
反射的に否定したりアドバイスせずに
「そうなんだね」と、まず受け取ることを心がけました。
 そして変化は、突然訪れました。
そして変化は、突然訪れました。
ある夜、さくらさんがリビングに降りてきました。
「お母さん、実はね…」
その声は震えていました。
さくらさんは、ぽつりぽつりと話し始めました。
友達からの仲間外れ。
学校に行くのが怖かったこと。
でも、心配かけたくなくて言えずに
嘘をついてしまったこと。
それでお母さんを怒らせてしまって
誰にも話せなくなってしまったこと。
Aさんは涙をこらえながら
ただただ娘の話を聞き続けました。
そして、話し終わったさくらさんに
こう言いました。
 「話してくれてありがとう。
「話してくれてありがとう。
一人で抱え込んでいて、辛かったね」
その瞬間、さくらさんは初めて泣きました。
そして、Aさんの腕の中で、子どものように泣き続けました。
Aさんが実践したのは、特別なことではありません。
講座で学んだ「身体・感情・思考を整える」ことを
焦らず毎日コツコツと実践しただけです。
そしてその「知識」と「具体的な方法」が
親子関係を根本から変えました。
現在、さくらさんは学校に通うことになり
新しい友達もできました。
以前のような嘘もなくなりました。
Aさんとさくらさんは、本音で話せる関係を取り戻したのです。
終わりに
「もう、嘘は悪いって分かっているはずなのに・・」と
嘘を止めさせることで
頭がいっぱいでした。
でも今回は
「嘘をつくのにも理由がある」ことが分かって
その理由にサポートすることが大事なんだと思いました。
目からうろこの気分です 🙂
「どうしたら子どもの嘘をやめさせられるか」から
「どうしたら、子どもが必要な場面で正直でいられるか」
という発想になれると
子どもへの対応も自然に変わりますね。
これからは、どんな言動にも
理由があることを忘れずに
子どもに接していきます!
次は、うちの子の個性に合わせた
より詳しい方法を教えてください
♡♡あとがき♡♡
中学生が嘘をつくと
「もう中学生なのに・・」
「今更手遅れじゃないかしら」と
親は不安になりますね。
ただ、どんな不適切な行動でも
そこにはワケがあります。
それはアドラー心理学では「目的」と呼ばれます。
今回の嘘のワケの「防御」なら
「自分を守るのが目的」
「自分を守ることで、安全でいたいのが目的」という感じです。
 その目的はその子・人にとっては
その目的はその子・人にとっては
「役立つ」と信じられているものです。
ただ、その方法が不適切だと
それがお困りに繋がってしまうんです。
なので、その人が求める目的を
もっと良い方法で満たせれば
不適切な方法はすっと手放せます。
むりやり脅したりして
変えようとするよりも
ずっとお互いにいいですね。
どんな状況でもいつからでも
誰もが望む最幸未来に舵を切れるんです!
(^_^)/
あわせて読みたい記事:
グレーゾーンの子どもの特徴と重要チェックポイントとは :思春期でも大丈夫!