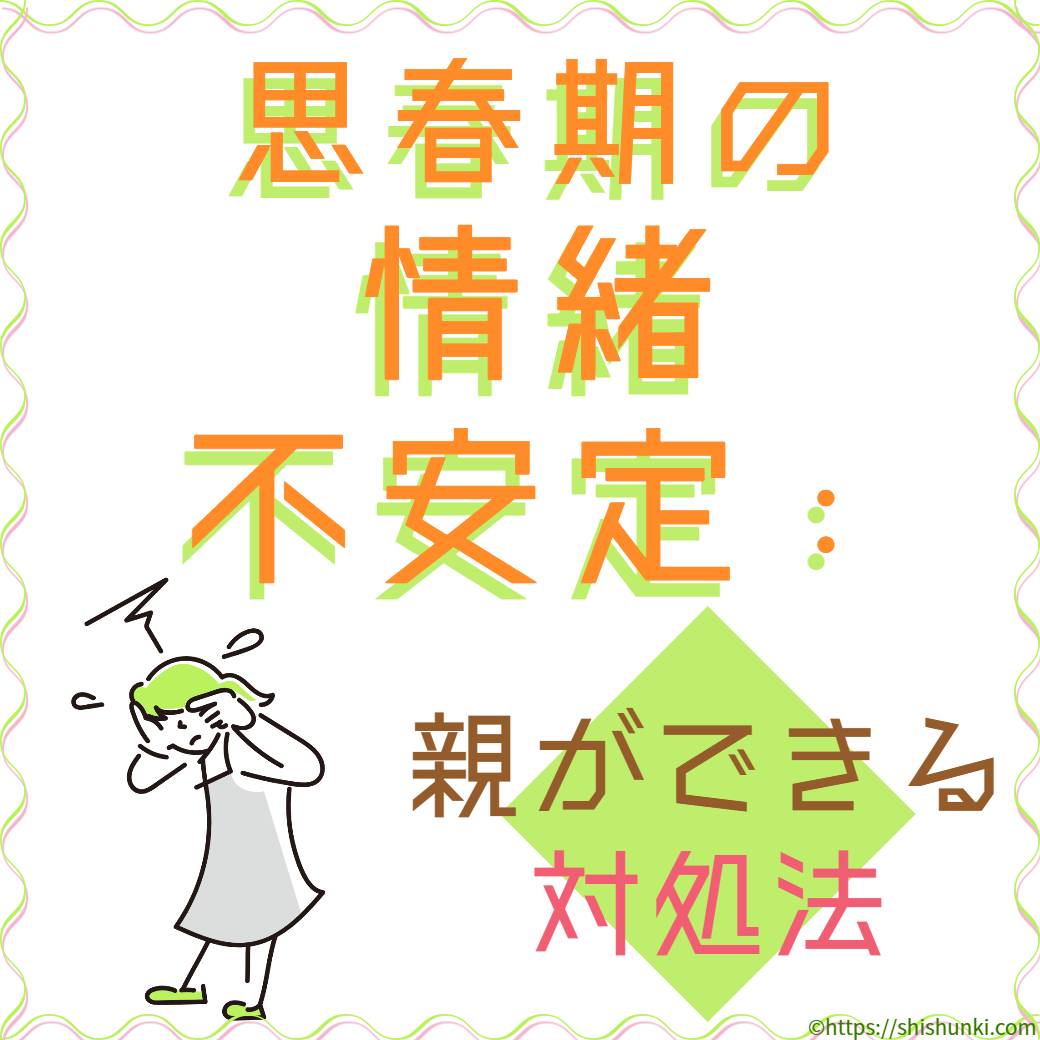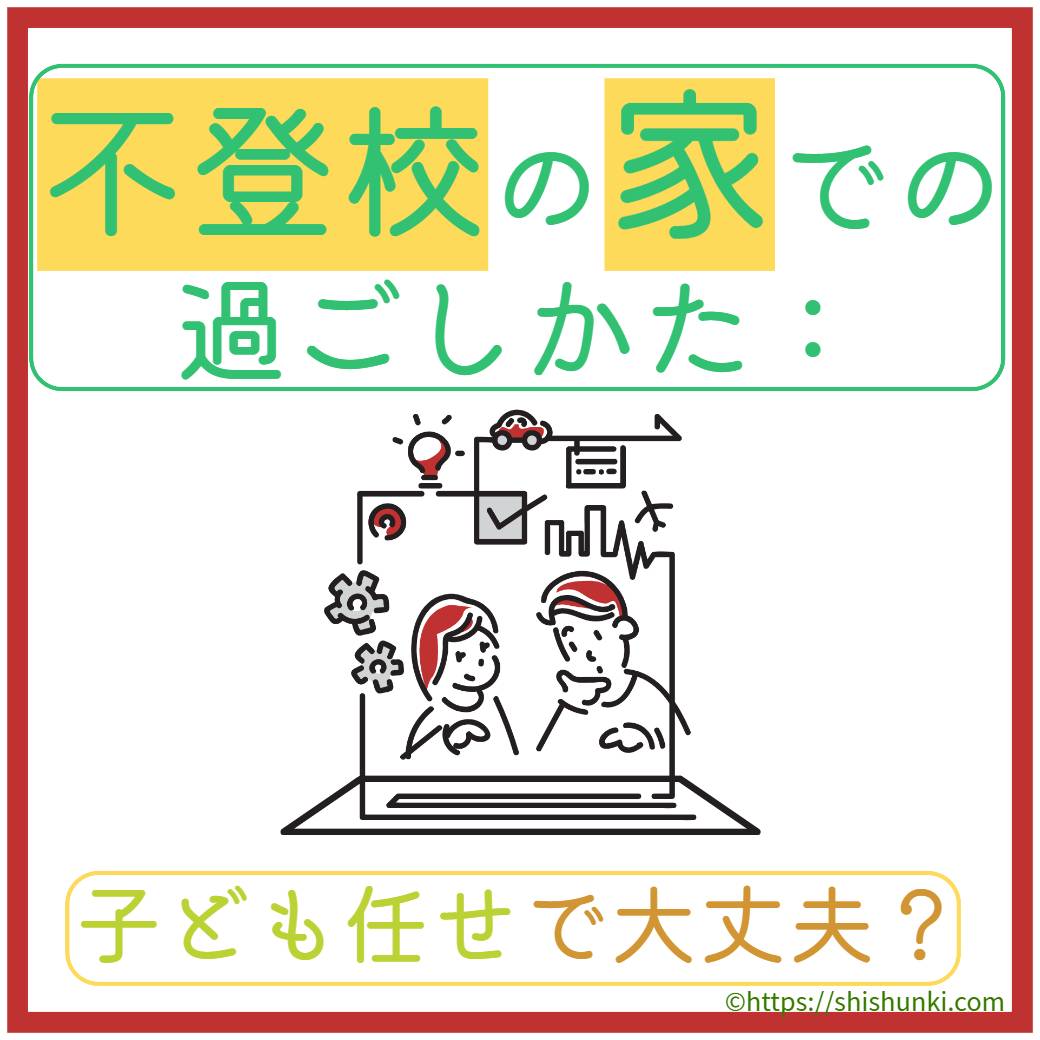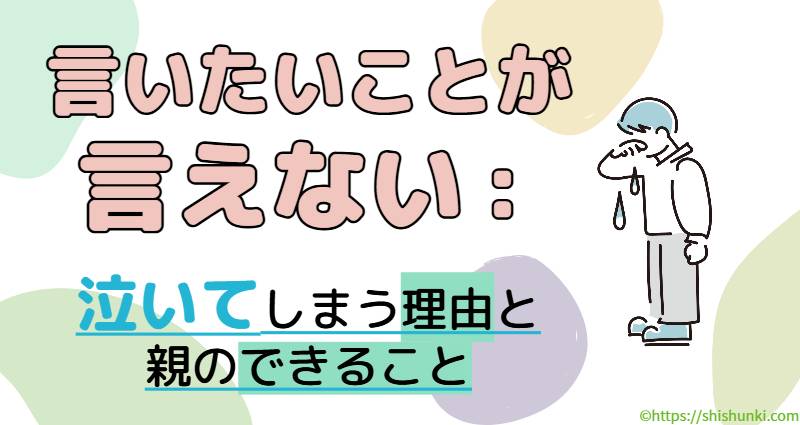
言いたいことが言えないで、お子さんが泣いてしまうと
お母さんは焦ったり
罪悪感を感じることもありますね。
特に「子どもの話を聞いてあげたい」
「気持ちを知りたい」と
声をかけた時にはショックです。
でも、ご安心くださいね。
お子さんが泣いてしまうのにも理由があって
その理由をリリースする方法もあるのです。
うちの子が、まさにそうなんです!
寄り添おうと話を聞こうとしても
子どもは何も話してくれずに泣いてしまいます。
本人は言いたくないわけじゃないのに
言えないで泣いてしまう、と言うんです。
なんだか、私が追い詰めたみたいになってしまって・・
このままでは親子関係も良くならないし
なぜそうなっているのかも
どう対応すればいいのかも分からなくて
行き詰りを感じてます
そうなんですね 😐
確かに、尋ねても何も言ってくれなかったり
お子さんからすれば
言いたいのに言えないのでは
お互いに困ってしまいますね。
子どもも思春期になったので
あまり細かいことは言わないようにしています。
ただ、進路選択などは
やっぱり親子で話し合う必要もあります。
お互いに本音で話し合せたら
心から応援したいと思っているのですが・・
それは素晴らしい思いですね 🙂
この言いたくても言えなくて泣く、
というパターンが
この先も繰り返されてしまうと
お子さんが「自分はうまく話せない」と
思い込んでしまったり
親御さんも「どうせまた泣かれる」と
会話を諦めてしまうことも起きがちです。
そんな風にお互いの心の距離ができてしまうと
本当に大切な話を共有できなくなってしまいます。
もったいないですね。
では、よい親子コミュニケーションをしたくても
子どもが言いたいことが言えずに泣いてしまうパターンを整えましょう!
ご一緒に、そうなってしまう理由と
整えるためのコツを見ていきましょう。
言いたいことが言えない子への、よくある3つのNG対応と、その裏にある思い込み
子どもが言いたいことを言えずに泣いてしまうパターンは
実は少なくはありません。
そして、そんな時にやってしまいがちな
親御さんのNG対応もあります。
知っていれば、すぐに止めたり、そもそもしなくてすみますね 😉
1)たくさん話を聞けば心を開いてくれる、と
なんとか話させようと頑張ってしまう

子育てをしていると
「子どもの話をよく聞きましょう」と
言われることも多いです。
確かにとても大事なことですが
「どのタイミングで」
「どのように」聞くかが重要です。
例えば子どもの感情が高ぶっている時に
なんとしても話をさせて聞こうとしても難しいのです。
感情的になっている時に活発なのは
話をしたり理解するために働く脳の前頭葉とは違う部分です。
まずは、その感情を落ち着かせて
前頭葉が働ける状態になってもらうことが重要です。
泣くほど感情を担う脳が活発化している時に
理屈で対抗しても
効き目がないのはそんな理由からです。
そうだったんですね!
うちの夫は子どもが泣くとイライラして
「泣いてごまかさずにちゃんと言いなさい!」
と怖い声で言うのですが
それは逆効果なんですね
はい、理屈っぽい言葉も
脅すような言葉も逆効果になってしまいます 😐
後ほどお伝えするコミュニケーションのコツを踏まえて
ゆっくりしたトーンや言葉で
安心感で子どもの感情を落ち着かせるのがおすすめです。
2)感情を受け止めれば解決するはず、とひたすら共感しようとする
「あなたの気持ちはわかるよ」
「辛かったね」といった共感の言葉は大切です。
しかし、思春期の子どもの場合には
感情を受け止めただけでは
根本的な解決にならないことが多いのです。
なぜなら、思春期特有の身体・心・頭と環境の変化から
感情のバランスが
根本的に不安定になっていることがあるからです。
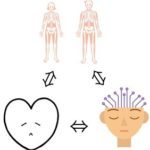
そんな場合は
メンタルだけでなんとかしようとするよりも
身体・心・頭と環境を整えるのが有効です。
つまり、共感だけ、感情面だけへの対応では
感情の乱れに対応できないケースもあるのです。
共感は万能だと思ってました!
目からうろこです 😯
3)思春期だから、しょうがない。。。とそのうち落ち着くのを待つことにする
「思春期だから仕方ない。そのうち落ち着くでしょう」
と考える親御さんも多いですが
これにはリスクがあります。
適切な対応をしないまま時間が経つと
親子 コミュニケーションパターンが固定化されてしまい
後から修正するのがより困難になってしまいます。
また、「うまく話せない」が本人のコンプレックスになってしまうことも多いのです。
そうなると、その思い込みが邪魔をして
友達関係や先生・部活の指導者との関係にも影響してしまいます。
うちの子も、泣いてしまうと
「自分はうまく話せないから」と
言うようになっています。
私も「そんなことないよ」と言うしかなくて。。
そんな時の対応も知りたいです。
そうですね、それも後ほど見ていきましょう!
言いたいことを聞いているのに、子どもが泣いてしまう理由と親のできること
次は、子どもが言い分を聞かれているのに
泣いて答えられなくなる理由と
それについて家でできることについて見てみましょう。
言いたいことが言えずに泣いてしまうワケと親のできること

実は、「子どもの言いたいことを聞く」時に
普通に尋ねているつもりなのに
気づかずにプレッシャーをかけてしまっていることがあります。
例えば、こんな声かけになっていたりしませんか?
「~~について、どう考えているの」
「どうしたいの」
そして泣いてしまったら
「どうしたの?何かあったの?」
「なんで泣いているの?」
これらの言葉は間違っているわけではないのですが
自分の言いたいことを言いにくい子どもにとっては
「すぐにちゃんと答えなければならないプレッシャー」
と感じられてしまう傾向があるのです。
真面目に、自分の思いをちゃんと伝えなくちゃ
早く言葉にしなくちゃ
でもうまく言えそうもない
自分はダメだ、どうしよう・・

そんな言葉ばかりがぐるぐるして
ますます焦って
「戦うか、逃げるか」反応に自律神経も陥ります。
交感神経優位な状態になるので
リラックスとは正反対の過緊張になります。
この状態では、ますます自分を冷静に
コントロールするのは難しくなってしまうんです 😯
自分の思いを言葉にしにくい子には
まず「安心感ましまし」でコミュニケーションを始めるのがおすすめです!
具体的な始め方などは、後ほどお伝えしますね。
思春期の脳はまだ成長途中です。
特に、論理的な思考を司る前頭葉の発達はゆっくり進むので
25~30歳にようやく完成します。

つまり、学生のうちは感情/感覚/欲求の方に
思考/言葉/理屈よりも強く
影響されやすいのです。
そして特に男子の場合には
脳の左右の発達の違いから
思ったことを言葉にする力が
中学生のはじめの頃に一時的に弱くなる傾向もあります。
皆さんも多分、中学生男子が
同じ年の中学生女子よりも幼く思えたこともあるのではないでしょうか
ちなみに、その傾向は
15歳くらいで男女差がなくなるのですが
その前に同級生女子や姉/妹に
徹底的に言い負かされた経験が続いてしまうと
その男子は
「自分はコミュ障だ」と
思い込んでしまうこともあるのでご注意です 😯
ちょっと話がそれましたが
子どもが言いたいことを言えずに泣いてしまうのは
甘えて、泣いてごまかそうとしているのでも
親御さんに反抗したいからでもなく
感情に飲まれやすい時期であることも影響があるのです。

「そういう時期でもあるんだ」と思えれば
少し余裕を持って見守りやすくなります 🙂
感情や思いは、ぼんやりした感覚に近いので
「言葉」を伴って
私たちの中に存在しているわけではありません。
赤ちゃんはお母さんの姿が急に見えなくなったら
悲しくて不安で泣きますが
その時に自分の気持ちが
「悲しい」「不安」
だとは理解していません。
では、どうやって人は
自分の感情や感覚に言葉をつけるのでしょう?
それは、周りの大人が
「あら、お母さんが見えなくて悲しくなっちゃったのね」
「不安になったの?大丈夫よ」
などと
赤ちゃんの感情を察して
その言葉を言うことからなんです。

そうやって人は感情を表す言葉を見つけていきます。
なので、例えば家庭であまり感情表現がなかったり
感情言葉が少なかったり
態度で表せば察してやってくれることばかりだったり
または赤ちゃん自身の
自分の感情と言葉の紐付け力が弱かったりすると
子どもは自分の感情を言葉にするのが苦手になることがあります。
特に、ある程度大きくなっても
親が過保護・過干渉だと
子どもは自分の思いを言葉で説明したり
お願いする練習が不足します。
子どもが言葉で表現する前に
親が察して先回りしてしまうからです。

このような状況だと、
表現されない感情は
その子の内側に溜まりやすくなります。
小さい頃は
「おとなしくて手がかからない、よい子」
であっても
溜まりに溜まった感情は
感情が敏感になる思春期になると
爆発してしまうことがあります 😯
また、小さい頃は思いが単純だったので
親が察したことは当たっていても
子どもが思春期になれば
親も、子どもの思いを察しきれないことも多々あるようになります。
そうなると子どもは
言葉で上手に表現できないので
相手を責める言葉や不機嫌、泣く
時には暴力などになることもよくあります 😯
最近ではコミュニケーションをしなくていい
ゲームやデジタルの世界に逃げ込む、パターンもあります。
あっ、うちの子はこのパターンかもしれません!
共働きで小さい頃から
上の子といることが多かったのですが
上の子が口達者で・・
下の子が何か言うと
すぐに強く言い負かされていました。
それで明るいけれど
自分の気持ちは表現しない子になってました。
そうだったんですね。
でも、ご安心くださいね 🙂
自分の思いを言葉にする力は
いつからでも、どんな状態からでも
育てることができます!
育ててみると
ものすごくおしゃべりになる子も
実は珍しくないんですよ
これまでに、自分の本音を話した時に
●強く怒られた
●馬鹿にされた
●無視された
そんな経験があるとショックです。
そこから「自分は本音を話すと危険」と
強い思い込みができている場合には
自分の思いを話そうとすると
その時のつらかった思いから
無意識に涙が出て
言葉は出てこない・・ということもあります。

大人は、子どもを怒ったり、からかったり
時にはスルーしても
それほど覚えていることはないものです。
でも、小さな子どもは
「家族の中でうまくやっていく」ことが
本能的な重大案件なので
そういう出来事はかなり強く心に残ります。
このような場合には
少しずつ安心な環境で
子どもの言葉を引き出していくことで
トラウマが徐々にリリースされることもあります。
それでも難しい場合にも
トラウマをリリースする方法は
当カレッジにはたくさんあります 🙂
直接トラウマを思い出してもらう方法だけでなく
徐々に薄れてなくなるような方法もありますので
お気軽にご相談ください。

思春期は成長期なので
ある意味不安定なだけに
バランスを崩しやすい側面もあります。
身体のエネルギー不足だと
前頭葉の発達が遅くなりがちですし
「ちょっと面倒でもやってみよう」という意欲も低下します。
なんでも「めんどくさい」のでやらない方向に行きがちだったり
なんでも簡単に諦めてしまうことも起こります。
また、身体のエネルギーの不足や
物理的な神経の圧迫などがあると
自律神経が乱れて
それほど悲しくなくても涙が出てしまうこともあります。
そんな状態になる原因には
そもそも身体が弱い場合もありますが
(代謝力が弱い、神経系の発達の抜けなど、要因は様々)
栄養不足、運動不足、睡眠不足
ストレス過多が挙げられます。

そこから思春期うつのような状態も起きやすいです。
当カレッジではその子の根本要因を
穏やかに整える方法のご用意があります。
ピンときた方は
講座や個人セッションをご活用ください。
どんな理由だとしても
ちゃんとリリースできるんですね!
はい、大丈夫です!
そして今
HSPという言葉がはやっていますが
HSPは感受性が鋭敏です。
そこから1)~5)どれも
当てはまりやすい傾向があります。
HSPだから、と扱わずに
その子の根本原因をリリースすれば
ちゃんと生きやすくなりますので
ご安心ください。
では次は、より具体的な接し方について見てみましょう
言いたいことが言えずに泣いてしまう子への話かけのコツ

言いたいことが言えずに涙が出てしまう子には
まず「安心感」がマシマシで必要です。
始めは「ここまでするのはめんどくさい」
と思われるかもしれませんが
子どもが「話しても安全、安心」と分かれば
それ以降は徐々にフランクにしていただいても大丈夫です。
お互いの気持ちが通じ合うコミュニケーションになります。
安心感マシマシの、子どもの言葉を引き出す5つのコツ
親がイライラ、不安、焦っている状態だと
子どもに安心感を与えるのは難しいですね。
 特に感受性が高い子は
特に感受性が高い子は
その様子だけで身構えてしまいます。
もし急に
「そうだ!子どもの意見を聞かなくちゃ」
と思いついた時でも
一度深呼吸したり間をおいて
落ち着いた状態になってから声をかけるとうまく行きます。
② ゆっくり始める
家族だと、ご自宅用コミュニケーションになりがちで
相手の状況にかまわずに
すぐに自分の言いたいことを切り出すこともあったりします。
でも、思春期になると
自分の世界に、いきなり
どかどか入ってこられるのは苦手です。
まずは「ノック」をしてみましょう。
「ちょっと話があるのだけど。 今、いいかな」

この一言で子どもは
「勝手に領土侵害された」とは思わずに
「個人として尊重されている」という感覚が得られるので
安心してコミュニケーションが始められます。
コミュニケーションのパターンとして
出来事のを最初から順番に話す癖がある方もいます。
それだと、子どもは
「一体、何の話だろう」と
イライラ・不安になるものです。
まずは、
「あのね、~~~という理由で
===について思っていることを教えて欲しいんだけど」
とコンパクトに始めましょう。
そして、それに対しての子どもの反応を見てから
必要な時には説明を足すのが
最も伝わりやすいコミュニケーションです。
子どもが反応し終わるまでは
こちらからさらに何かを言わないのも大事です。

落ち着いてコミュニケーションを始めても
子どもが先ほどの1)~5)の理由で
すぐには答えられないこともあります。
そのような場合には
「すぐには難しいなら
明日の食事の後に教えてね」などと
言葉にする時間をあげるのもおすすめです。
大人は忙しいので
一度話を始めたら
すぐに白黒つけたいと思うところもありますが
大事な話ほど、丁寧に進めることで
結局一番良いコミュニケーションになります 🙂
また、その決めた時間を
親も必ず守守ることは
その後の信頼関係にも大きく影響する大事なことです。
途中で子どもが言えずに泣いてしまった時の対応のコツ

子どもが泣いてしまった時には
感情があふれている状態です。
その時にはまず感情を静めることからですね 🙂
そのためには泣くことを否定するのではなく
一度泣いていることを受け入れます。
「涙が出ちゃうんだね」
「大丈夫、急がなくていいよ」とか
ただ黙ってそばにいるのでもOKです。
感情はすべて
一度そこにあることを認めると
自然に流れていきます。
泣いている人に「泣くな!」とか
「泣かないで 😐 」と言うのは
慰めているようで
「泣いてはいけない」というメッセージになります。

積極的に泣きたいわけではない時に
泣いてはいけないと言われたら
安心には繋がらなくなってしまいます。
お母さん・お父さんが落ち着いて
ただそこにいるだけで
子どももやがて落ち着きやすくなります。
また、以前から子ども自身が
「言いたいことを言えずに泣くのをなんとかしたい」と
言ってる場合には
「違うものに意識を向ける」ことをやってみるのも効果的です。
泣いている時には自分の内側で
感情が波打っていたり
グルグル思考をしています。
そんな時には自分の外側にあるものに意識を切り替えると
自分の内側が落ち着いてきます。
例えば、「今見える茶色の物」をゆっくり数えたり
部屋にある本の背表紙の文字を読む、
などすると
内側の感情や思考の興奮が治まります。

子どもから
「なんとかしたい」という話が出た時に
そういう方法があるよ、と話しておけば
いざ、そうなったらそれを一緒にすることもできますね 😉
子どもが徐々に落ち着いてきたら
「今少しずつ話せる?」と聞いてみて
まだ無理そうであれば
「じゃあ、明日の夕ご飯の後にまた話しましょう」と
次を約束して
言葉にする時間を与えるのも効果的です。
なるほど!
私は子どもに泣かれると
「どうして泣いちゃうの?
責めてるわけじゃないのに」
と自分の中でぐるぐるしていて
子どもをただ見ているだけでした。
こんな風に落ち着いて声をかけられれば
子どももプレッシャーも感じずに
早くに落ち着けますね。
そして言葉にする時間をあげれば
自分でゆっくり考えることもできるので
また話し合いもできますね
はい、なんでも焦るとうまくいかないものです。
私も基本せっかちなので
「急がば回れ」が身に染みたのは
子育て後半でした 🙂
先ほど「言いたいことが言えずに泣いてしまうワケと親のできること」でみてきたように
本音で話し合える親子になるためには
コミュニケーションの仕方だけでなく
〇リラックスして、論理的思考ができる身体
〇感情の高まりに対応できて、感情と思考を良いバランスで使えること
〇感情や思いを言葉にして表現する力

〇トラウマのリリース
などが必要なこともあります。
これらは日常で意識することで改善できることもあります。
そして、もし難しいな、と思ったら
当カレッジにもご相談ください。
お子さんとご家庭ができる方法をお伝えします。
こうやってみると、
自分の意志やコミュニケーションの仕方だけでなく
身体に関係している部分も多いですね。
そうなんです。
私たちの身体は、想像以上に
メンタルや思考に影響しています。
コミュニケーションや勉強、部活のパフォーマンスなどでも
身体から見直してみると
びっくりするくらい、よい結果になることは多いんです。
また、これらを行っていく上で
お母さん・お父さんが安定していることも
とても大事です。
敏感な子どもほど
お母さん・お父さんの言っていることよりも
どういう状態か、に反応します。
そういう意味でも専門家につながっていると
お母さん・お父さんご自身も安定するので
お子さんの成長も加速します。
【実例紹介】泣いてばかりだった子どもが変わった!
Aさん家族:中2娘との関係が劇的に改善したケース

Aさん(42歳・会社員)は、中学2年生の娘さんとのコミュニケーションに悩んでいました。
「娘が暗い様子だったので
気になっていました。
でも何か聞くたびに泣かれてしまい、
最後は『もういい!うざい!』
と言われる毎日でした。
娘が心配で声をかけているのに、
なぜこんなことになるのか全く理解できませんでした」
そんなAさんは、まずご自分自身の
「関わり方のクセ」を見直すことからスタートされました。
「私は娘が泣くと、すぐに
『どうしたの?』『何があったの?』
と質問攻めにしていました。
でも、これは娘にとって
余計にプレッシャーだったんですね」
アプローチを変えてから3週間後には
「娘が泣いたので、今度は何も聞かずに

『大丈夫よ、お母さんはあなたの味方だから
そこにいるから、落ち着いて話せそうなら声をかけてね』
とだけ言って、
少し離れたところで家事をしていました。
すると30分後、娘の方から
『実は...』と話し始めたんです。
それまで聞けなかった学校での悩みを
1時間以上話してくれました。
娘は話ができたことで元気になりましたし
それ以来、親子で本音で話せるようになりました。」
Bさん家族:不登校の息子との信頼関係を築き直したケース
Bさん(39歳・主婦)は、中学3年生の不登校の息子さんの反抗的な態度に悩んでいました。
「息子は私が何を言ってもゲームばかりで
『うるさい』『関係ない』と言うだけ。
昼間は偉そうに屁理屈三昧なのですが
時々、夜に一人で落ち込んでいることもあって...。
でも話を聞こうとすると余計に殻に閉じこもってしまうんです」

Bさんが実践したのは、
息子さんの「身体・心・頭」へのアプローチでした。
「まず息子の身体から、生活リズムを整えることから始めました。
特にゲームの使用ルールについては
最初は抵抗されましたが
ここが踏ん張りどころ、と
私の方が根負けしないように頑張りました。
そして適度な運動、十分な睡眠、
本当に必要な栄養とその摂り方も教えていただいて実践しました。
そして私自身も、息子に対する不安や焦りを手放すことを学びました」
2ヶ月後の変化です。
「ある日、息子が『お母さん、俺、実は...』と
受験への不安を話してくれたんです。
それまでは
『受験なんてどうでもいい
自分はもう道を外れたから』
と言っていたのに、
実は凄く心配していたことがわかりました。

今では進路のことも含めて、
色々なことを相談してくれるようになりました。
講座で進路選択の仕方も学んだので
今は自分が選んだ道に進む準備を
担任の先生にも自分でも相談しながら進めています 🙂 」
どちらも、本音で話ができるようになってよかったですね。
お母さんの晴れやかな笑顔が嬉しいです 🙂
どちらも「何を変えたか」より「どう変えたか」が大事ですね。
そしてこの二つの事例で共通しているのは
表面的なテクニックだけで
子どもを変えようとしているのではないところです。
子どもの状態をより深く理解して
親御さん自身の在り方を整えられています。
2番目のケースでは、
身体・心・頭を統合的にサポートする方法への理解があったからこそ、
劇的な変化を起こせていらっしゃいます。
2番目のケースは不登校だったんですね。
そこから自ら前を向く行動をするようになったのは
すごいですね!
言いたいことが言えない 終わりに
子どもに思いを聞いているだけなのに
泣かれてしまうので
とても困っていました。
思春期になると親に本音を言うのが
そんなに嫌なのかしら?
でも、ちゃんと話さないならないこともあるし
・・と、一人でかなり悩んでいました。
今回は、泣いてしまう理由もわかったので
とてもすっきりしました。
私ができることもたくさん
教えていただいたのもよかったです!
早速、家に帰って
自分ができることをまずやってみます。
はい、ありがとうございます。
やってみて、子どもの反応を見ます。
また詳しくご相談させてください
💛💛あとがき💛💛
 子どもも思春期になると
子どもも思春期になると
親子コミュニケーションが難しいと
感じることも増えてきます。
☑ 子どもに話しかけると、よく泣かれる
☑ 子どもが「もういい」「うざい」と言って話を打ち切ることが多い
☑ 子どもの本当の気持ちがわからない
☑ 子どもとの会話が表面的になりがち
☑ 子どもが問題を抱えていても、相談してくれない
☑ 親子で一緒にいても、お互い遠慮している感じがする
☑ 子どもの将来が心配で仕方ない
☑ 自分の子育てに自信が持てない
もしこれらに3個以上チェックがついたなら
親子コミュニケーションをバージョンアップするチャンスです!
多数あるブログや動画もお役立てください。
一人では難しいと思った場合には
思春期最幸家族講座や個人セッションもご活用くださいね。
 がっつり、最幸の結果が出るまでサポートいたします。
がっつり、最幸の結果が出るまでサポートいたします。
何時からでも、どんな状況からでも
幸せになる道があるのです♡
\(^o^)/
あわせて読みたい記事:
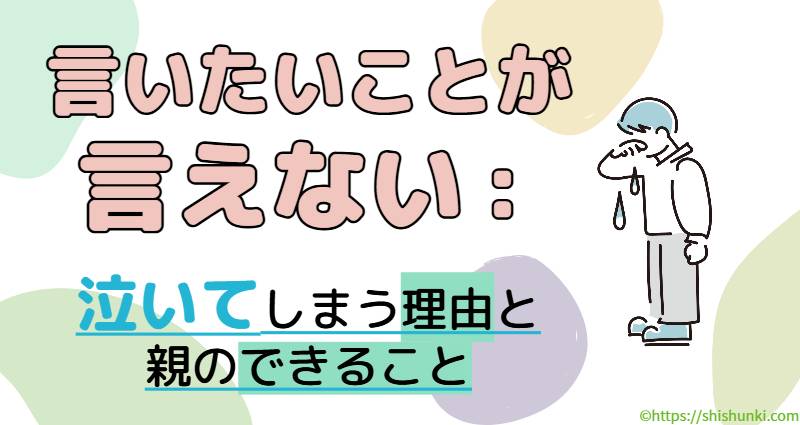
 子育てをしていると
子育てをしていると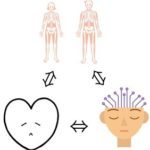 そんな場合は
そんな場合は 実は、「子どもの言いたいことを聞く」時に
実は、「子どもの言いたいことを聞く」時に そんな言葉ばかりがぐるぐるして
そんな言葉ばかりがぐるぐるして つまり、学生のうちは感情/感覚/欲求の方に
つまり、学生のうちは感情/感覚/欲求の方に 「そういう時期でもあるんだ」と思えれば
「そういう時期でもあるんだ」と思えれば そうやって人は感情を表す言葉を見つけていきます。
そうやって人は感情を表す言葉を見つけていきます。 このような状況だと、
このような状況だと、 大人は、子どもを怒ったり、からかったり
大人は、子どもを怒ったり、からかったり 思春期は成長期なので
思春期は成長期なので そこから思春期うつのような状態も起きやすいです。
そこから思春期うつのような状態も起きやすいです。 言いたいことが言えずに涙が出てしまう子には
言いたいことが言えずに涙が出てしまう子には 特に感受性が高い子は
特に感受性が高い子は この一言で子どもは
この一言で子どもは 子どもが泣いてしまった時には
子どもが泣いてしまった時には 積極的に泣きたいわけではない時に
積極的に泣きたいわけではない時に 子どもから
子どもから 〇トラウマのリリース
〇トラウマのリリース Aさん(42歳・会社員)は、中学2年生の娘さんとのコミュニケーションに悩んでいました。
Aさん(42歳・会社員)は、中学2年生の娘さんとのコミュニケーションに悩んでいました。 『大丈夫よ、お母さんはあなたの味方だから
『大丈夫よ、お母さんはあなたの味方だから Bさんが実践したのは、
Bさんが実践したのは、 今では進路のことも含めて、
今では進路のことも含めて、 子どもも思春期になると
子どもも思春期になると がっつり、最幸の結果が出るまでサポートいたします。
がっつり、最幸の結果が出るまでサポートいたします。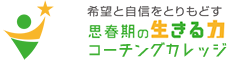



 落ち着いてコミュニケーションを始めても
落ち着いてコミュニケーションを始めても