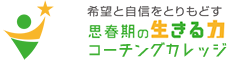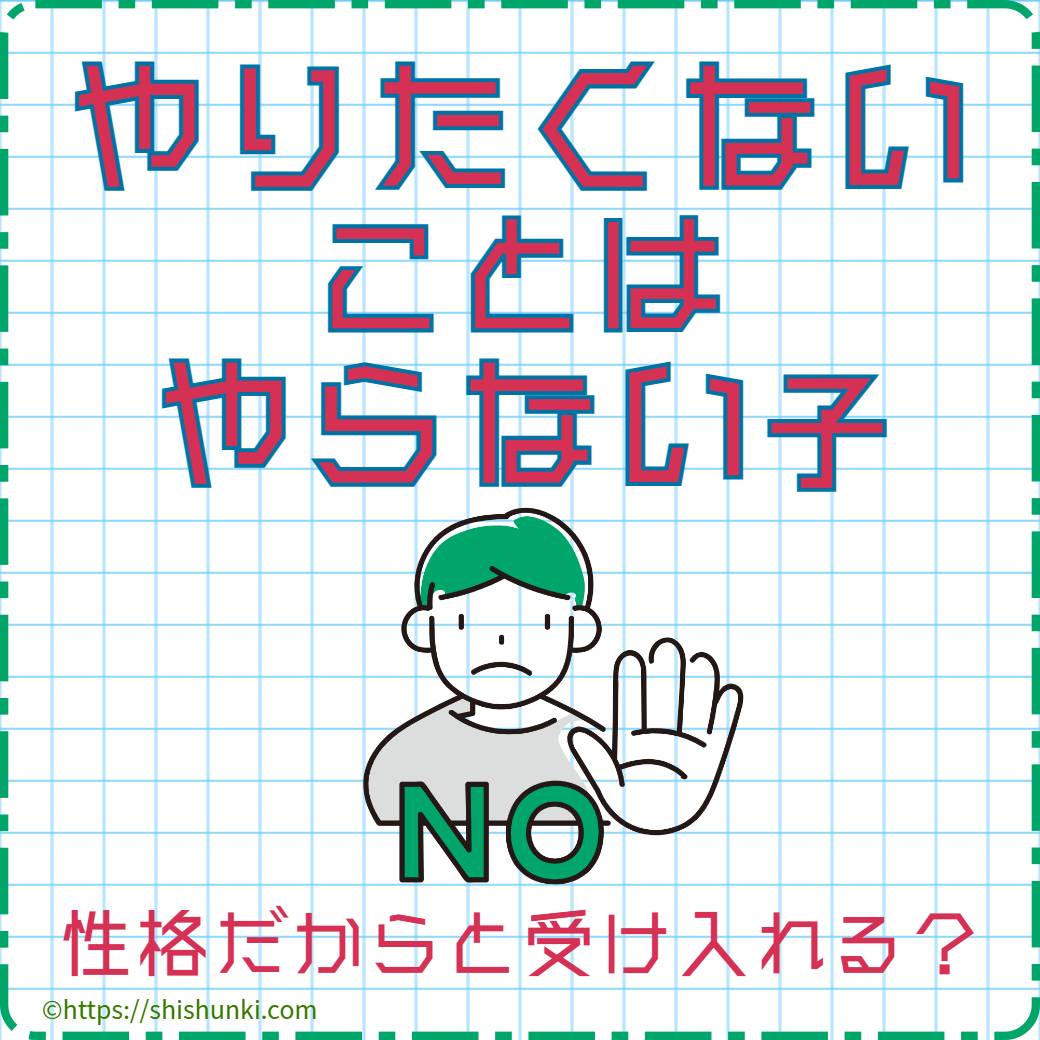ストレスで頭が真っ白⁈:黙り込む・キレる原因と、親が今すぐできる対策
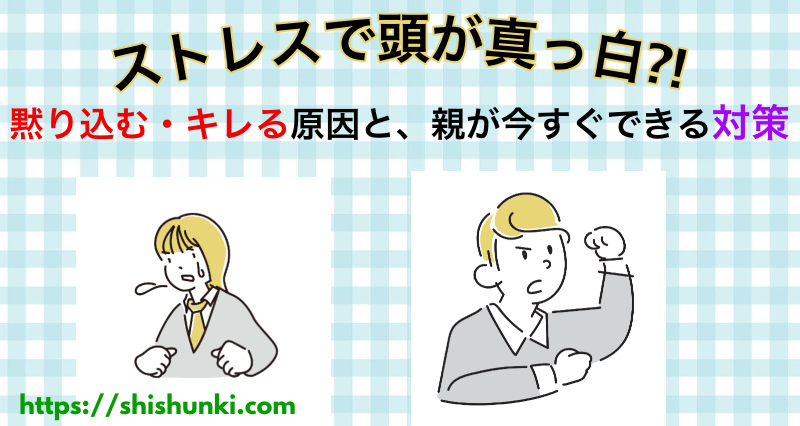
ちょっとしたストレスで、子どもが黙り込んだり、キレたりすることはありませんか?
実はその時、子どもはストレスで頭が真っ白になっているのかもしれません。
そしてそんな時に、やってはいけないNG対応があるのでご注意です!
自分が思っていたのと違うことが起きると
すぐに黙り込んでしまいます。
その時には
いくら話しかけても無言なんです。
ふてくされているようで
ますますイラッとしてしまいます。
話しかけても返事がないと
イラッとしちゃうものですよね
また始まった!とイライラして
こちらもつい声を荒げちゃって。。
でもそれでも何も変わらないので
私ばかり怒って終わるんです。
ダンマリばかりだと
子どもが何をして欲しいのかもわからないので
困ってしまいますよね。
そうなんですね。
実は、似たようなお悩みをお持ちのお母さん・お父さんは多くいらっしゃいます。
そして、ご安心ください。
その状態から抜け出す方法もありますし、
当カレッジでは、すでにその状態から抜け出しているお子さんたちもたくさんいます。
目次
頭が真っ白になる瞬間:子どもの脳で起きていること
自分にとっての困りごとが起きたり
予想外のことや思わぬ変化に直面したら
誰でもちょっと驚きます。
少しの間でも、ショックを受けて「ショック状態」になるんです。
そしてその状態がひどくなければ
すぐに落ち着いて
その事態に対応することができます。
 対応するというのは、
対応するというのは、
ステップ1:その課題に
・向き合って乗り越えようとするか
・今はその課題には取り組まなくて良いか
を判断する
ステップ2:決めた対応をする
自分なりに考えて決めて行動する、ということです。
例えば、クラスメイトにちょっと嫌なことを言われた場合に
違うよ、と言い返したり
ユーモアで返すのは
「乗り越えようとする」になります。
大したことじゃないので
取り合わなくていいと判断するのは
今は取り組まなくていい、と決めることになります。
どちらでも、場面に応じて
自分で適切に判断できれば良いのです。
 子どもでも大人でも、日常の中で
子どもでも大人でも、日常の中で
そうやってたくさんの物事に対応しています。
ところがその時に受けたショックが大きすぎると
「自分には対応できない」とパニックになってしまうんです。
パニックになると
人は脳の「前頭葉」が使えなくなります。
前頭葉は「論理的に考える力」を司っています。
なので、パニック状態だと
自分で適切に判断できない状態になるのです。
そういえば私も以前
全く思ってもみなかったことが起きた時にパニクって
おかしな動きをしたことがあります。
実家の祖母が危篤だと言われた時です。
パニックになって
自分のカバンに全く関係のない
お料理本を詰めて持っていってしまいました
そうなんです。
人はパニくると、いつもなら
しないような変な言動をすることがあります。
夜中の火事の知らせを突然受けた人が
お財布や携帯ではなく
枕を抱えて飛び出すことも珍しくないんです。
この状態を「脳がフリーズした」
「思考が飛んだ」
「頭が真っ白になった」と言います。
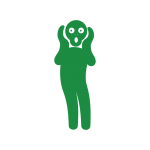 論理的思考が難しい状態なので
論理的思考が難しい状態なので
言葉が出てこなかったり
変な動きをしてしまいやすい状態なんです。
そして、このパニックへのなりやすさと
パニックの程度
(どれくらい思考が飛んだり
言葉が出てこないか)には
その人の「なりやすさ」があります。
パニック状態へのなりやすさと程度は人によって違うんです。
なりやすさ・パニックの強さは以下の要因に影響されます。
 自分の課題に自分で最後まで取り組んで乗り越えた体験が少ないと
自分の課題に自分で最後まで取り組んで乗り越えた体験が少ないと
ちょっとしたストレスにも
「自分には無理」とパニックになりやすくなります。
日頃から親や兄姉が過保護・過干渉にしてしまうと
ちょっとしたことでも
自分で取り組むのを難しく感じてしまうので
簡単に「無理」と言ったり思うようになります。
「どうやったらできるようになるか」と
考える癖がないので
パニックになりやすいのです。
真面目なのは長所なのですが
100できないとダメだ、という思いが強いと
100できそうにない時に
0か100かになって
「できない」と絶望に襲われてしまい
パニックになりやすくなります。
 できているところよりも先に
できているところよりも先に
できていないところを指摘されることが多いと
要注意です。
③うまくできずに強く怒られたり辛い思いをした体験があるとなりやすい
「失敗したらどうしよう」
「失敗が怖い」
思いが強いと、うまくやれそうにないと思った瞬間に
パニックになりやすくなります。
日頃から「失敗しないように」
「大丈夫なの?」と
声をかけられることが多いのは要注意です。
もともと怖がりや不安が強いタイプは
心身のエネルギー不足が考えられます。
 ある程度能力があって
ある程度能力があって
できることも多い子でも
どこかで、自分だけでは解決できない課題に
ぶつかることがあります。
「男の子でしょ」
「お姉ちゃんなんだから」
「もう中学生だから」
「なんでも一人でできるね」
と言われていると
困っても「助けて」と言えないので
密かにパニックになってしまうことがあります。
疲れている時、睡眠不足時、悩みがある時
そして思春期の栄養不足
エネルギー不足の時には
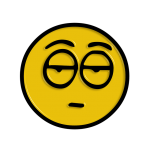 「自分が乗り越えられる」と思える範囲が狭くなるので
「自分が乗り越えられる」と思える範囲が狭くなるので
パニックになりやすくなります
もともと不安が強く、怖がりの子は
常にアラームを鳴らして警戒している状態なので
エネルギー不足になりやすいですし、
逆にエネルギー不足だと
不安が強く、怖がりにもなります。
不登校の時や
発達課題のある子は
身体のエネルギー不足であることがほとんどなので
すぐにパニックになりやすい傾向があります。
ちょっとしたことで、すぐに黙り込んでしまうのは
パニックになっていたからかもしれません
一度パニックになると
落ち着くまでは頭が働かなくて
なかなか言葉が出てこない状態になる子は結構いるんです。
親に反抗して黙っているのかと思ってました
外から見ると、区別がつきづらいですよね。
家族ならまだしも
先生や部活の指導などに誤解されてしまうこともあるので
なるべく早くに
パニックになりやすさは解消したいですね。
思春期は脳の前頭葉が発達途中です。
また、急激な成長期でもあるので
「バランスよく食べている」と
成長のために必要な栄養も不足しがちです。
 しっかり食べているようで
しっかり食べているようで
実は身体のエネルギーを
十分に作れていないお子さんも多いです。
成績や受験、部活、容姿で他の子達と比べられたり
友達関係で悩むことも多いのもあり
ストレスも受けやすい時期でもあります。
このように思春期には、頭が真っ白になやりやすい土台が実は多いんです。
そして、同じようにパニックなったら
誤解されやすい別の行動をとってしまう子もいます。
親は知っておきたい!キレるのは、パニックになっているからかも。。
パニックになって頭が真っ白になった時に
言葉が出てこなくて黙り込む子がいますが
同じような場面で
「キレる」子もいるんです。
 攻撃的になって、屁理屈も交えて
攻撃的になって、屁理屈も交えて
とにかく「NO」を言ってきます。
突然の予定変更や想定外の内容を
誰かに言われると
キレて突っかかってしまうのです。
思いついて何かを頼もうとすると
すぐに「聞いてない」とキレてくるんです。
このタイプは予想外のことに
キレて攻撃的になって
すぐに「NO」と強く主張します。
ちょっと落ち着いてからだと
受け入れられるようなことでも
想定外のことにはすぐに頭が真っ白になるので
反射的に「NO」を強く言うんです。
何か、理屈をつけることもありますが
それは「NO」のための理屈に過ぎなくて
じっくり考えた結果の屁理屈ではありません。
 でも、攻撃的で口調も強いので
でも、攻撃的で口調も強いので
言われた方はいい気分にはなりませんね。
やはり、家庭では大目に見てもらえても
家の外では、より強く誤解されてしまうことが多いです。
やっぱり早くにこのパターンからは抜け出したいですね。
すぐにNOを言います。
こちらもただ反抗期だからと思っていましたが
振り返ってみると
反射的にNOを言うのは
突然何かを言われた時がほとんどです
その対応は逆効果!ついやりがちな親のNG対応
親が、黙り込んでる・キレている子の状態について知らないと
「黙り込む」「キレる」は
ただ親をイライラさせる態度としか思えないですよね。
黙り込む子には
「理由を聞いているんだから、
何が起きたのかや
自分の意見くらいちゃんと言いなさい!」
「早く話しなさい!」
と言いたくなりますし
ただ不貞腐れているように思ってしまいます。
 そしてそんな場面が多いと
そしてそんな場面が多いと
「いつも黙ってばかりで逃げようとして!」とか
「なんで言えないの?」とさらに言いたくなり
最終的には
「もう、勝手にしなさい!
あなたには関わらないわ」
と見捨てるような言葉を、怒りの勢いで言ってしまうこともあるでしょう。
ただ、パニックで頭が真っ白になっている場合には
言葉の内容はほとんど伝わらないのです。
言葉の内容は前頭葉が拾うからです。
その時に活発になっているのは
脳の,、もっと原始的な部分
爬虫類脳の部分です。
この爬虫類脳はいつも
自分が今危険かどうかだけに注意を払っています。
 なので、前頭葉がパニックでブリーズしている時には
なので、前頭葉がパニックでブリーズしている時には
この爬虫類脳が
相手の言葉のトーンや大きさ
怒ったりイライラしている表情などだけを
情報として受け取るのです。
そして「今自分は攻撃されている」と判断すると
さらにストレスを感じて
パニックが悪化してしまうのです。
つまり、怒ったり、大きな声で何かを言うのは
さらに頭が真っ白になっている子どもを
追い詰めることになるんです 😯
今自分が説明しないから怒られている、と
自分の状況を理解することが難しい状態なので
この時間の記憶は
「自分は攻撃されて見捨てられた」になってしまうんです 🙁
攻撃してると受け取られちゃうんですか
そうなんです 😐
なので、顔色も青ざめて
表情がなくなっているような状態で
子どもが黙り込んでいる時には
声を荒げたり、できないことを指摘したり、突き放したりするような対応はNGです。
また、同じようにキレてくる子どもも
頭の中は同じ状態なので
声を荒げたり、できたいことを指摘したり、突き放すような対応はNGです。
 キレてくる子は、
キレてくる子は、
屁理屈を言ってくることも多いので
ちゃんと頭(前頭葉)は動いているだろうと思われがちですが
実はパニックで反射的に自分を守るために
闇雲に攻撃しているだけなのです。
正面からその屁理屈に対して
「そんなの通用しない!」とか
同じトーンの攻撃的な会話になってしまうと
このタイプの子は
どんどん頭に血が上った状態になって
ますますパニック状態になってしまいます。
そしてその結果
「それならもうどうでもいい!」
「もう志望校を受けない」とか
本心ではないことを捨て台詞で言い出すことも多いです。
 大人は怒っていても
大人は怒っていても
ある程度前頭葉が働きますので
その言葉を覚えてていて
後々「〜〜って言ったじゃない、その責任を取りなさい」などと
言いたくなることもありますが
そこは「今はパニクっているんだ」と
受け取って、言葉通りには受け取らないのがおすすめです。
どちらの場合も、パニックを増大させてしまうNGワードには気をつけましょう
「なんで黙っているの」
「いい加減にしなさい」
「早く言いなさい」
「いつまで不貞腐れているの」
「なんでそんなことで怒るの!」
「そんなことぐらいで」
「いい加減にしなさい!」
「またそんなこと言って!」
思春期の脳がフリーズしやすいと知っていないと
そういうことも起きますよね。
これからはイライラして声を荒げたり
子どもにつられて攻撃的にならなければ大丈夫です!
緊急対策マニュアル:その場で脳を再起動させる対策
子どもの脳がフリーズして
頭が真っ白になっている時には
なるべく早く、脳を再起動させることに集中するのがおすすめです。
 子どもが黙り込んだりキレた時に
子どもが黙り込んだりキレた時に
声を荒げたり責めたりするのは
パニックをさらに進めてしまうのでNGでしたね
まずは過敏になっている脳の爬虫類脳を落ち着かせることが大事です。
そのためには
言葉をかけるならば、ゆっくりと落ち着いたトーンで対応します。
黙り込んでしまっている子には
「良い言葉が思いつかない?」
「今、話すのは難しい感じ?」などと
ゆっくりと声をかけます。
返事が返ってこなくても、言葉の調子が伝わるだけでOKです。
そして声をかけても
「長く喋らない」
「説得しようとしない」のがポイントです。
 前頭葉がまだ動けない状態だからです。
前頭葉がまだ動けない状態だからです。
話をしなくてはならない場合には
「夕方にまた声をかけるから
それまでにゆっくり考えておいて」と
落ち着く時間を与えて
一度距離を置くのが効果的な場合もあります。
キレてくる子への対応は
つられてキレないことが最も大事です。
子どもが攻撃的なので
親もムッとしちゃいますが
一度深呼吸をしたり
「あとでまた話しましょう」と
距離を置くのでもOKです。
もちろん、子どもにキレられても
落ち着いて
「何が気になっているの?」と
声をかけられれればベストです。
そうなんです。
ついムッとしちゃうこともありますよね。
そうなったとしても
それに巻き込まれずに
安全だよ〜という雰囲気が伝わればOKです!
日頃から、子どもに予想外のことがあると
すぐにパニックになる癖があることを
お互いに話せておくと
よりスムーズにその場の対応ができます。
 その癖があることを責めたり
その癖があることを責めたり
「早く治さないと!」とするのではなく
ただそんな癖がある、という事実として
扱うのがおすすめです。
すぐに脳を再起動させたい時には
言葉で前頭葉に情報を受け取らせようとするよりも
身体の感覚を呼び覚ます方が
ダイレクトで早いです。
今過剰に敏感になっている爬虫類脳が
我にかえることができれば落ち着けます。
爬虫類脳が落ち着けば
徐々に前頭葉も働けるようになります。
爬虫類脳は「身体」に直結しているので
身体に感覚刺激を入れることで
我に帰りやすくなります。
どんなことが効果的ですか?
はい、一番簡単なのが深呼吸です。
お母さん・お父さんが、こっそり子どもの呼吸に合わせて呼吸をすると、子どもは早く落ち着けるようになります。
触らせてくれるならば
手を握ったり背中をさすってあげるのも効果的です。
もし、触らせてくれなければ
そばに静かに座ったり
目を見てにっこりするのも良いでしょう。
他にも、手や顔を水で洗う
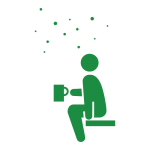 水やお茶を飲む
水やお茶を飲む
足の裏をマッサージする
少しぶらっと歩く
なども効果があります。
その状況とお子さんの状態に合わせて、お試しください。
日頃から、頭が真っ白くなりやすい傾向があることを
親子で共有しておければ
この対策も取りやすくなります。
根本改善への道
頭が真っ白になってしまった時の対策も大事ですが
そうなってしまう癖を根本的に手放せるのが一番良いですね。
 そのためには、なりやすさやパニックを強くしてしまう要因を排除していきましょう。
そのためには、なりやすさやパニックを強くしてしまう要因を排除していきましょう。
①自分でストレスを乗り越えた体験が少ないとなりやすい
→ 過干渉や過保護はやめて、小さな成功体験をたくさん積めるようにしていきます。
できた時や、工夫や努力していることへの勇気づけもたっぷりと!
②ちゃんとやらなくちゃ!という気持ちが強いとなりやすい
→ 良い結果でも悪い結果でも、結果だけにフォーカスして会話するのではなく、その前の意欲や工夫や努力にも声をかけていきましょう。
完全な成功でなくても「ま、いいか」と時には思える余裕が持てるように、日常での笑顔やユーモアがあるといいですね。
ダメ出しは極力控えて、改善したいところを伝えたい場合には、先に「YES」を伝えてからがおすすめです。
親御さんの完璧主義が強い場合には、そのリリースがおすすめです。(個人セッションで可能です)
③うまくできずに強く怒られたり辛い思いをした体験があるとなりやすい
 → 失敗を重いものだと受け止めすぎないようにしていきましょう。
→ 失敗を重いものだと受け止めすぎないようにしていきましょう。
失敗は、振り返りができれば、成功に続く「経験」になります。
親御さんの失敗への恐怖や不安が強い場合には、そのリリースがおすすめです。(個人セッションで可能です)
④人をうまく頼れないとなりやすい
→ 「⚪︎⚪︎だから、できるはず」と言う言葉はプレッシャーになります。
誰でも自分だけではできないこともあるものです。
この子ならできるだろうと思うことでも、
「いつでも声をかけてね、サポートするよ」と言う言葉や態度を日頃からかけておくのがおすすめです。
親も困ったと痔には人の相談する姿勢を見せておくのも有効です。
⑤不安が強い、心身のエネルギーが少ないとなりやすい
これは心体のエネルギー不足の解消です。
悩みがある場合には、それを引き伸ばさずに、早めにサクッとクリアにします。
コーチングはそれにとてもよく役立ちます。
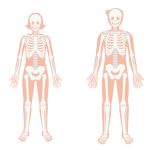 身体のエネルギー不足は、睡眠・生活リズム・栄養で根本的な改善が可能です。
身体のエネルギー不足は、睡眠・生活リズム・栄養で根本的な改善が可能です。
自分の身体で、十分なエネルギーを作るようになれば、多少のストレスにも怯むことはありません。
当カレッジのブログにもそれらについての情報がありますので、お役立てください。
より個別に、しっかり取り組みたい方は、思春期最幸家族講座や個人セッションをご活用ください。
また、より深いリラックスができて、ストレスに強くなるリセット体操など、そのお子さんに合う身体へのアプローチも多数あります。
不登校や発達課題の解消のサポートもありますので、ピンときた方は、思春期最幸家族講座や個人セッションをご活用ください。
事例紹介
事例1
大学院生で、指導教授とうまく行かずに進路が迷走している方でした。
とても優秀な学生だったのに、研究熱心だったあまりに生活リズムや栄養などが乱れていて、エネルギーが低下していました。
 そのために、自分でも気づかずに、本来の思考ができない状態になっていて、乱れた対応をしてしまうことがあり、それが指導教授との間に溝を作っていました。
そのために、自分でも気づかずに、本来の思考ができない状態になっていて、乱れた対応をしてしまうことがあり、それが指導教授との間に溝を作っていました。
ご本人に状況を理解してもらって、根本改善に取り組みました。
その結果、数ヶ月で本来の頭脳明晰さが戻ってきて、教授との関係も修復することができました。
事例2:
中学生男子で、不登校で家にいるようになったのですが
すぐにキレるので
お母さんが、
すぐに喧嘩になってコミュニケーションができないことにとても困っていました。
「性格」だと思って我慢しようと思っていたけれど。。という状態から
お子さん自身にも自分の反応の癖に気づいてもらったり
お母さんにもコミュニケーションパターンを変えてもらいました。
 徐々にスムーズなコミュニケーションができるようになり
徐々にスムーズなコミュニケーションができるようになり
並行して進めていた根本改善も
効果をあげたために
予想外のことにすぐにパニックになる癖は完全になくなりました。
今は高校受験も経て
友達もたくさんできて楽しんでいます。
終わりに
反抗期が強すぎるのかしら、と思っていましたが
ちょっとしたことでパニックになりやすいんだとわかりました!
いろいろ、思い当たることがあります。
今回はその癖が出た時の対応と
根本改善ができるとわかって
本当に良かったです
問題行動ではなく、ある意味
子どものSOSのサインだとわかると
親御さんも気持ちが楽になりますね
早速、子ども達にも話してみます。
次回は根本対策についてご相談させてください
❤️❤️あとがき❤️❤️
 子どもの話さない、キレてくるなどの
子どもの話さない、キレてくるなどの
行動は分かりやすく目につきますが
それがなぜ起きているのか?
がはっきり分からないこともありますね。
人はそんな時には
自分の想像でそれを埋めてしまうことが多いです。
そこから親子コミュケーションがずれてしまったり
信頼関係が崩れてしまうのは勿体無いですね。
パニックで黙ったり、キレている時の特徴は
柔らかさや融通性がない状態になっていることです。
 表情も硬いですし
表情も硬いですし
何かの言葉をかけても反応がなかったり
「何⁈」と、ちゃんと受け取れないことが多いです。
時には目が吊り上がったりして
いつもと違う表情になっていることさえあります。
子どもの様子がなんだかいつもと
だいぶ違う。。
そう思った時には
「〜〜だからかも」という想像を
一度手放してみるのがおすすめです。
 思っていたよりも
思っていたよりも
ずっと素直な、困っている子どもの姿が
見えてくることも多いです
(^-^)/
合わせて読みたい記事:
過干渉な親をやめたい!と思った時に大事な3つのコツ:チェックリスト付き
よかれと思ってやったのに・・親子コミュニケーションがうまく行かない時