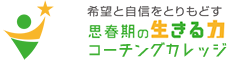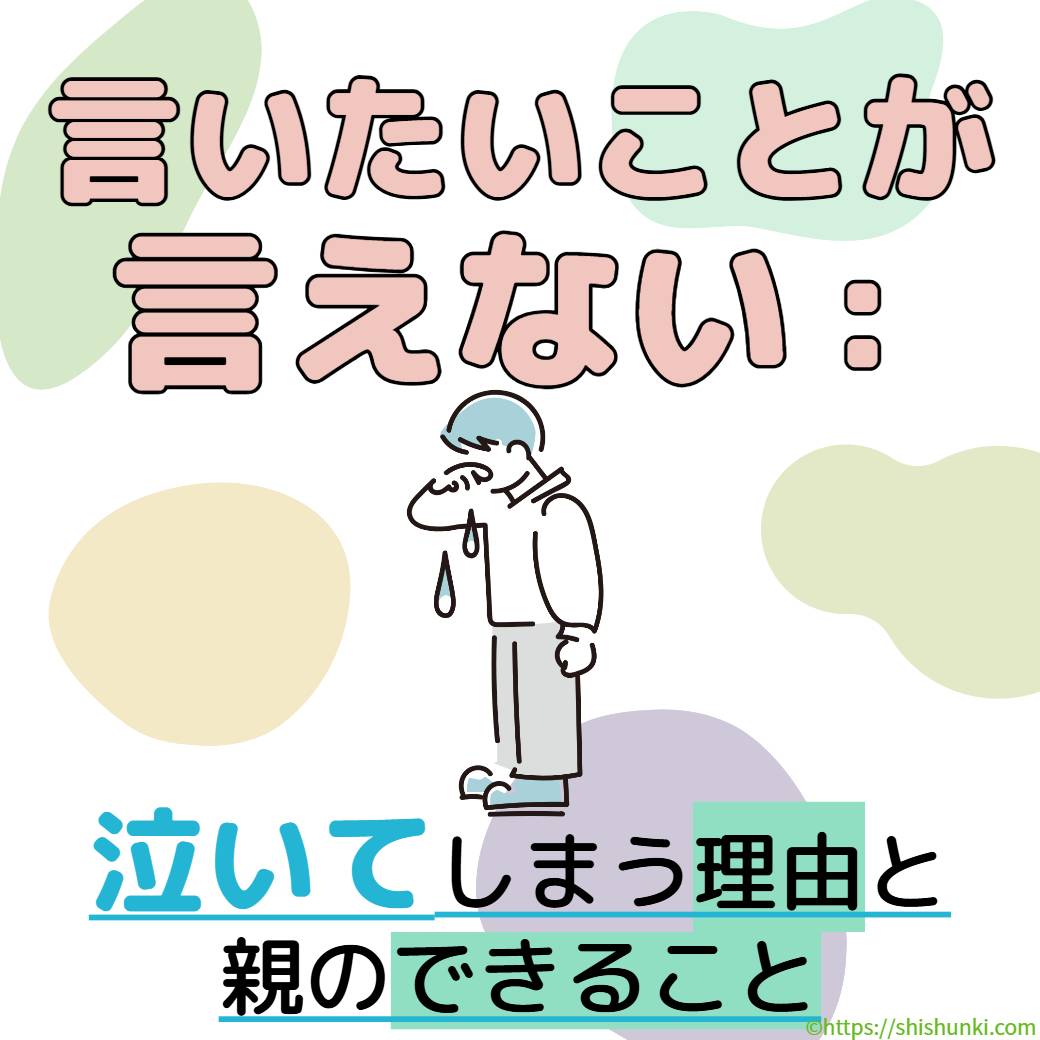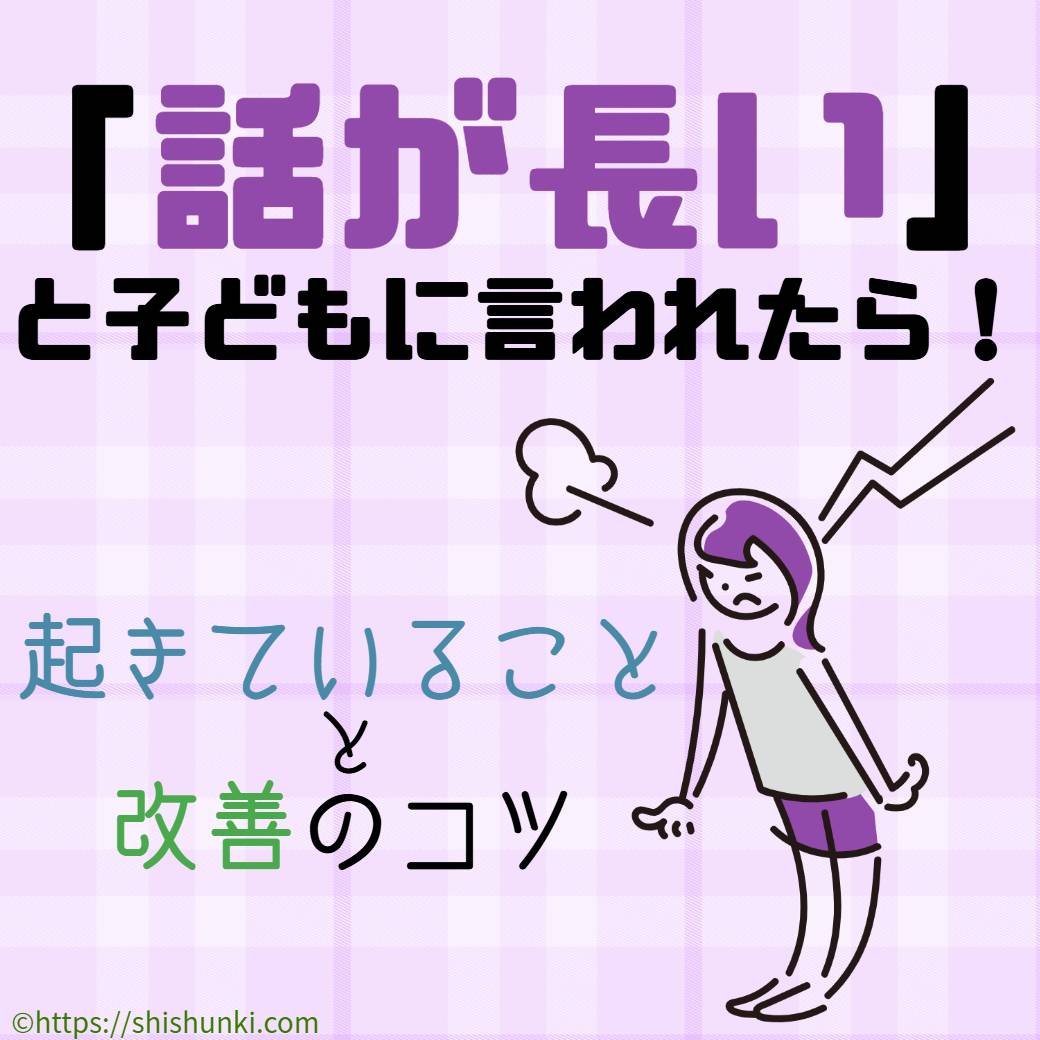不登校の家での過ごし方:子ども任せで大丈夫?

不登校の子はどうしても
家で最も多くの時間を過ごすようになります。
そうなると、家での過ごし方はとても重要です。
最近は不登校の長期化傾向がありますが
その回復までの長さと質に大きくかかわるのは
「不登校になった理由」よりも
「家での過ごし方」の方です。
なぜそう言えるかと言えば
「家での過ごし方」を
身体・心・頭の3つの側面から整えていくことで
どんな状態からでも
子どもは不登校から自ら抜け出して
本来の状態、充実した思春期を楽しむようになったケースが
当カレッジではすでに数百以上あるからです。
でも、家でどのように過ごさせるのが良いのか
よくわからなくて困っています
それはお子さんもご家族もショックですね
ただ
「じゃあ今私のできることは」?と考えてみたら
「家でどう過ごさせるかの指針をはっきりさせることからだ」と思ったんです。
「家では子どもにストレスを与えないように」
という話も聞きますが
子どもの自由にさせていたのに
不登校が何年も続いているケースも
数多くあるのも知っています。
家での過ごし方のポイントや
親の対応の指針が欲しいです
かなりのショックのなか
しっかり考えていらっしゃいますね!
本当に素晴らしいです 🙂
確かに、「不登校になった理由」と
「不登校を長引かせてしまう理由」は
別のものです。
家での過ごし方が後者にとても大きな影響があるのは間違いありません。
家で自由にさせても改善どころか
ますます長期化している 事例も多いのも
無理に学校へ行かせることも
効果的ではないのも分かっています。
でも、結局親としてどうすべきかがわからないんです。
そしてこのまま
時間だけが過ぎていくのが怖いんです。
子どもには受験というタイムリミットもありますから
家での過ごし方で
子どもの将来の可能性が減ってしまうのも避けたいです。
お子さんへの愛情と、だからこその不安ですね。
大丈夫です、ご安心ください!
不登校で家での過ごし方の指針はちゃんとあります。
それを踏まえて
お子さんの個性やご家庭の状況、
受験などの区切りのタイミグなど
個別状況にフットさせていけば
お子さんは以前よりも良い状態になることが多いんです。
不登校はピンチに見えますが
対応次第で
お子さんの可能性をより引き出すチャンスにもできるんです!
それを聞いて、心が軽くなりました 🙂
もっと詳しく知りたいです。
はい、では不登校の家での過ごし方での
よくあるもったいないパターンと
ピンチをチャンスに変えるために大事なことを
ご一緒に見ていきましょう!
目次
よく聞く「不登校は家ではストレスを与えずに自由に過ごさせましょう」は間違いなの?
不登校になったことは
子どもにも親にもショックです。
そして人はショック状態の時に
慌てて何かをしようとしても
ほぼ効果がなかったり
逆効果なことさえやってしまうことがあります。
なので、ショック期には
すぐに解決しようと焦るよりも
「なるべく安静にして
=ストレスを減らして
ある程度落ち着く状態になること」
が最優先です。
 これは子どもだけでなく
これは子どもだけでなく
親についても同じです。
興奮したまま
とにかく「登校させることばかり」に夢中になるのは
誰にとっても良いことにはつながりません。
その意味で
不登校になったばかりの頃に
「不登校にならないように」と
無理に登校させようとプッシュするのはNGですね。
ショック期に落ち着かせようと
子どもにかかるストレス
(登校や時に勉強など)を
減らすのは効果的です。
しかし、ショック期には
親御さんもショック期なので
その時に耳にする
☆子どものストレスを減らせて落ち着かせる
を↓
 ★子どもにストレスを与えてはいけない
★子どもにストレスを与えてはいけない
だから、子どもが「嫌だ」ということは
一切子どもにやらせないようにすべき。
子どもが「やりたい」「欲しい」と言ったら
全部やらせるべき。
☆今まで通りの生活ペースを優先するのではなく
今の子どものペースに合わせて行動させることを意識する
を↓
★子どもがやりたがった時だけ何かをさせる
子どもが「嫌だ」と言ったら
全くやらせなくていい
と、解釈してしまうことがあるのです。
実は私もウン十年前に
それに陥ってしまった時期がありました。
当時出ていた本を読んで
そう解釈したのです 😐
カウンセリングや相談室でもそう言われたのもありました
抽象的な話を具体的な行動に落とし込むのは
難しさがありますね。
 でも、そうなってしまうと
でも、そうなってしまうと
親が子どもの気分や顔色を見て
ご機嫌を伺うようになってしまいます。
親がびくびくしていると
子どもはわがままも通るので
嬉しいところもありますが
今困っている状態なのに
親に頼れない不安も同時に強く感じます。
実際私もその時期を抜けた後に
子どもからそう言われました。
そしてこれまでのお子さんとのセッションでも
同じような感想を話してくれたケースも多いです。
つまり、ショック期には
不要なストレスを減らして
なるべく早く落ち着くことが
回復へ第一歩なのは間違いないのですが
それを「子どもの好きにさせる」のと
混同しないことはとても大事なのです。
 そのためには
そのためには
「今、不要なストレスを減らすことの目的」
を見失わないことが大事です。
ショック期に不要なストレスを減らすのは
「ある程度落ち着かせる」ためです。
ある程度ストレスを減らして
状態を落ち着けて
安静期(意識してしっかり休む)と
その先の回復期に進められるようにするためです。
そして最終的には
また社会復帰して
楽しく充実した日々を送るためです。
それが分かっていると
子ども任せにして
★生活リズムや睡眠リズムをいくらでも乱したり
★食事をしない、好きなものしか食べない
★ゲームを毎日4、5時間もやり続ける
★家の中で王様・女王様のようにふるまう
(TVを独占するなど、姉兄姉妹に我慢を強いることをずっと許す)
 などはNGだと分かります。
などはNGだと分かります。
こんな状態が当たり前になってしまうと
不登校に慣れたとしても
次の安静期に進めません。
安静期は
睡眠・食事・生活リズムを徐々に整えながら
意識してしっかり休む時期です。
ケガの入院で例えれば
化膿しないようにケガを治療しながら
なるべく動かずに
回復にエネルギーを向かわせる時期です。
それを通過しなければ
さらにその次の回復期に
良い状態で進むことも難しくなってしまいます。
「ただ不登校という状態に慣れた子どもと親ごさん」
になるだけで
「ショック期をクリアした」とは言えないのです。
子どものペースを尊重する、は
ただ子どもの好きにさせる、とは
全く違うんですね。
登校や勉強など
「本来なら学生がやるべきこと」を
やらなくていいのは
回復が必要な状態だからですが
食事しない、昼夜逆転が
回復に役立つとは思えませんね
そうなんです。
睡眠が乱れて、食も乱れれば
身体のエネルギーはますます低下します。
身体のエネルギーとは
体力だけの話ではなく
食べたものから
必要なホルモンを十分作れたり
イライラや落ち込みから回復しやすい丈夫な神経系を
日々の代謝で作れる力も含んでいます。
それらがちゃんと作れないと
メンタルの不調や
脳の乱れや前頭葉の発達にも影響します。
不登校になった時よりも
イライラしたり不安定になったり
疲れやすくなったりすることもあるのですか?
はい、残念ながら
そういうことが起きているケースも多いです 😐
大事なのは
☆まずショック期には親子で
「ストレスを減らす」と
「子どものペースで過ごす」の意味を
間違えない
ことと
☆不登校のショック期、安静期、回復期、再活動期で
それぞれ家での過ごし方や
親のかかわり方を変えていくことです。
ケガの場合も
最初は安静にして
ある程度回復する力がついてきたら
今度はストレスを少しずつ与えますね
そうです 🙂
このリハビリで大事なのは
その人の回復状態や筋力に合わせて
徐々にストレスを強くしていくことです。
ある程度怪我が治ったのに
いつまでもギブス
いつまでもリハビリなしだと
どうなるでしょう?
むしろ、変な風に骨や腱がくっついて
他の部分にしわ寄せが行きやすくなったり
その部分も弱いので
また何度もケガをするかもしれませんね
はい、まさにその通りです。
逆に、しっかりとリハビリをしていけば
以前よりも周りの筋肉や腱を強くすることもできます。
その違いは、その人のその後の人生に
大きな違いを生みますね。
実際に、上記の二つを間違えたために
ずっと不登校だったり
少し登校する時期があっても
またすぐに行けなくなるのを
繰り返しているケースも珍しくはありません。
でも、それはお母さんのせいではありません。
私の頃は不登校への対応についての情報は
どんなに探してもほとんどありませんでした。
少しでも関連のある図書を見つけては
お手紙で質問させたいただいた時の気持ちを
今でも忘れることはありません。
 そして今は不登校についての情報が
そして今は不登校についての情報が
あまりにもたくさんあります。
なので、どれをどう
ご自分のケースに落とし込めばいいのかが
分からなくなるのも当然です。
「専門家」もたくさんいて
言うことがかなり違うことも多いので
ご自分もショック状態なのに
子どものために何かをしなければならないお母さんが
迷われるのも当たり前と言えます。
ですからこそ、
実際に数百名のお子さんが元気になった事例から
まとめた情報を知っていただきたいと思っています。
「子どもの好きにさせるだけ」で長期化すると、新たに生じる困りごと
不登校で家で自由に過ごしていたために
「不登校になった時」とは
別のお困り状態が生じることがいろいろあります。
今回は身体・心・頭に分けて
その一部をご紹介いたします。
「1」身体
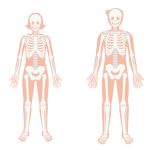 睡眠・食事・生活リズムが乱れたり
睡眠・食事・生活リズムが乱れたり
ゲームや動画・SNSばかりで
運動する(身体を毎日動かす)習慣がなくなって
長期間たつと
まず、身体の機能が衰えます。
それは
★エネルギー不足
(ちょっとしたことで疲れる、
何か活動をしたらその後や
翌日は休まなければならない状態など)
★身体の弱さ
・自律神経が乱れる
概日リズムが崩れてしまうと
脳と身体の日々のメンテナンス力も落ちます。
そのために
・腹痛・頭痛・花粉症などが起きやすい状態
・ストレスがかかると腹痛・頭痛など症状が出る
・定期テストなどに間に合う時間に
継続的に起きることが難しくなる
(遊びに行く場合には単発的には起きられることもあっても
1か月、2か月それを続けられるかは別の話です)
 ★前頭葉が十分に成長できない
★前頭葉が十分に成長できない
その時の気分で動いてばかりだと
自制力や自律力や
周りや未来への影響まで考える練習が不足します。
また、動かないことで
脳に適切な刺激も入らないですし
毎日ゲームばかりだと
リアル体験がないので
成長するチャンスが大幅に減ります。
★メンタルの弱さ
身体のホルモンや内分泌バランスの乱れから
すぐにイライラする、キレる、落ち込む
マイナス思考、攻撃性
自分の課題から逃げやすい傾向が習慣化することがあります。
長期化することで
その状態が「当たり前」になるのです。
困るのは、これらの身体の変化は
徐々に進むことです。
子どもも家族も
子どもの変化に気付きにくいので
「そういえば、すでにそうなっている」ことが多いです 😐
 長い時間をかけた繰り返しで
長い時間をかけた繰り返しで
できあがった状態は
良い状態に戻すには
ある程度時間をかけることが必要になります。
知論、かかった時間よりも
うんと短かい期間で回復することは
コツを押さえれば、ちゃんとできます!
そして例えば、新学期になって
気持ちが変わって
「今年度は登校しよう」と思ったとしても
身体を慣らしていく期間が少し多めにあった方が
うんと確実に登校できます。
本人は
「自分は毎日朝から最後まで登校できるから
練習なんていらない」
と思うのですが
生活リズムの差があまりに大きい場合には
最初の2週間から1か月くらいは頑張れたとしても
その後エネルギー切れになるというパターンも多いのでご注意です。
そこから自信を無くして
「やっぱり学校は無理」となるのはもったいないですね。
「2」心
 ★やる気、希望、意欲の低下
★やる気、希望、意欲の低下
身体のエネルギー切れになってしまうと
「やる気」が湧かなくなります。
なんでもいい、別に~が当たり前になります。
また、長期間不登校が続くと
「学校に行かないのが当たり前」になるので
希望や意欲も低下します。
★ストレス耐性も下がります。
ちょっとしたことにも
強く怒ったり悲しんだり、傷ついたりします。
★そして「好きなことしかやらない」
「嫌なことはやらなくていい」が
当然の生活が長くなると
なんでも「嫌だから」が理由になると
勘違いするようになる子は多いです。
 家の外の社会では
家の外の社会では
「嫌だから」は
ちゃんとした理由としては認められません。
嫌ならば、どこがどう嫌で
その結果、どうしてそれができないのか、を
相手が納得できるように
きちんと客観的に説明することが必要になります。
同じように最近は高校・大学・就活の面接でも
なぜ「~~が好きなのか」を
説明する力が問われることも多いです。
「嫌だから」「好きだから」で終わらせずに
より詳しく人に話せる力も必要です。
★親子関係のゆがみ
不登校で家にばかりいると
子どもの社会との窓口は
お母さんだけになることも多いです。
そうなるとお母さんを言い負かしたり
罪悪感に訴えたり
お母さんの言うことをスルーしておけば
 自分がやりたいことだけやる生活を
自分がやりたいことだけやる生活を
ずっと続けることもできます。
そうなると親子関係がおかしくなりますし
お母さんのストレスもかなりのものになってしまいます 😐
★「好きだから」「嫌だから」と
自分の気分や感情を
王様・女王様にしていると
理屈が分からなくなります。
いくら説明されても
「だってやりたくないんだもん」から
先に進めない状態になります。
人間関係に響きます。
「好きだから」「嫌だから」が
行動の理由になると勘違いすることの影響は
意外と大きいです。
★「すべてのタイミングを自分の気分次第にしている」と
決められた時間で行動したり
決められたことをやるのが
ものすごく辛くなります。
 そこで
そこで
「めんどくさい、やりたくない」となります。
「管理されたくない」
「コントロールされたくない」
「みんなと一緒に動きたくない」
などと言うことも多いです。
「集団生活が向いてない」という子もいますが
では、どうするのか、までを
自分で考える必要がありますね。
どんな仕事をするにしても
現実では他人との日時の約束はつきものです。
でもそれができない、嫌なので
家の中で王様・女王様でいたい
とにかく社会に出たくない、と
先のことまで考えずに
いつまでも家にいたがるようになってしまうこともあります。
★自信がない、不安が強い
 自分で自分の課題を乗り越えた、
自分で自分の課題を乗り越えた、
という経験がないと
自分に自信が持てません。
気分次第で自分の課題をほおっておいて
家族がそのしりぬぐいを繰り返していると
年齢が上がるほど
社会的に親が介入できないことの方が多くなります。
それで家の人には
暴言・屁理屈・脅しをかけるけど強い態度に出るけれど
外には出ないようになってしまうこともあります。
「3」頭
★前頭葉の発達不足
思春期は「人間脳」と言われる
前頭葉がもっとも発達する時期です。
その発達には
適切な量と種類の栄養と睡眠・運動
そして適切な刺激(考える練習)が必要です。
 気分次第になっていると
気分次第になっていると
「考える」必要がないので
前頭葉は刺激されません。
理屈や理論
未来への影響
他人への影響
について考えることが難しい状態になります。
思い付きで動くために
いろいろ破綻してしまうことが増えるのは
もったいないですね。
★日常で
「集中する」
「自分を律する」
「決断する」
「失敗があったらその責任をとる」
という経験が不足すると
それらが難しくなります。
 ★特にゲームやSNS・動画などは
★特にゲームやSNS・動画などは
すべて受動的な楽しみなので
自分から楽しいと感じることを探す姿勢を
忘れてしまう子もいます。
「暇」と言えば親が
何か自分を楽しませてくれるものを持ってきてくれると
勘違いしてしまうこともあります。
★そしてこういう子は
「人にものを頼む」「感謝する」ということが
すっぽり抜けていることも多いです。
自分がこんな状態だと匂わせたり
ただ黙って待っているだけで
「お願いします」「ありがとうございました」が
言えないのが共通するところです。
人間関係に響きます。
★どうしても長期休みになると
学習面でも抜けが生じやすくなります。
「自分にはわかることと分からないことがある」
という不安定さや自信のなさを
持っている状態が続きます。
 「安定した継続登校」のためには
「安定した継続登校」のためには
「学校に行く」とともに
「勉強のリカバリー」も必要になります。
当カレッジでは
効率的な勉強のリカバリーの仕方も
具体的にお伝えしています。
★情報社会で生きる力が育たない
点数や受験のためだけでなく
義務教育くらいの内容は
概要を理解しておくことはとても大事です。
これからますます情報過多の時代になりますので
その情報の真偽を見極める基礎力になります。
これらは、不登校が長期化した子が全部必ず持っているわけではありません。
もともとの気質や不登校になるまでの環境や
不登校になってからの過ごし方は
一人一人違うからです。
ただ、長期になるほど
多くのものが見られる傾向はあります。
 そしてこれらは
そしてこれらは
不登校になった時にはなかったり
あっても一時的や軽微だったものが多いです。
つまり、不登校になってからの
家での過ごし方によってできたり
増幅してしまったものと言えます。
不登校になったら
原因探しを続けるよりも
その後の家での過ごし方のほうが
回復とその後の人生には
ずっと重要なのです。
不登校というピンチをチャンスに変えるために最も必要なこと
ここまで見てきたように
不登校になった後の家での過ごし方はとても重要です。
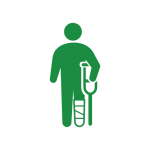 不登校は大けがをした時と同じように
不登校は大けがをした時と同じように
ピンチではありますが
同じように
そのピンチにうまく対応することで
子どもの生きる力を
身体・心・頭のすべての面で
前よりも強く成長させるチャンスにすることもできるんです 🙂
そのために最も必要なことは
子どもの状況に合わせて
親が子どものへの対応を変えていくこと
です。
不登校は
ショック期、安静期、回復期、再活動期、そして安定登校期という
段階があります。
それぞれをきちんと通過するためには
それぞれの段階で
クリアすべき目標があります。
「1」ショック期
 子どもと親御さんがまず
子どもと親御さんがまず
できるだけ落ち着くことです。
そのためには
不安をあおる情報とは距離を置いて
「不登校は、心身のエネルギー量が、受けているストレスの総和には不足している状態」
だということを
親子の共通理解にすることからです。
それによって
「学校を休むのは回復のためにしょうがない。
ただし、一番大事なのは回復だから
それに必要なことをする。」
という家での過ごし方の方向性がはっきりします。
「2」安静期
ショック期で回復に必要なことをする、という
共通理解ができれば
子どもは「学校に行かないこと」に
罪悪感を持つ必要がなくなります。
 ケガをして入院治療か自宅療養をしているのと同じです。
ケガをして入院治療か自宅療養をしているのと同じです。
親もわが子を恥ずかしいと思う必要もなくなります。
親子で無駄なストレスを減らせます。
そして、生活リズム・睡眠・食事から整えていきます。
生活リズムは
起立性調整津障害の場合には
少し対応が違うので
個別にご相談ください。
それ以外でも、安静期になったばかりだと
寝ても寝ても眠いこともあります。
その場合には
朝の起床時間を優先して
午前中に2時間開けてお昼寝タイムを設けるのがおすすめです。
詳しくは個別にご相談くださいね。
 安静期は、子どもの心身が元気になってきて
安静期は、子どもの心身が元気になってきて
落ち着いて動けるようになったら
回復期に進みます。
「3」回復期
子どもに少しエネルギーが溜まり始めた状態です。
この時期が一番子どもの個性が表に出てきます。
親の関わりが最も大事な時期です。
代表的なのは
少しエネルギーが溜まったからと
遊びや部活を登校よりも優先しようとするタイプと
エネルギーが溜まっているのに
とにかく何も変化を起こそうとしないタイプです。
上記のタイプには
親がエネルギーを使う方向性を導く必要があります。
放っておくと
遊びや部活でエネルギーを使い果たして
全く学校に意識が向かない子もいますので。
 全く動こうとしない子には
全く動こうとしない子には
やはり学校に楽しく行けるようになることが
ゴールだということを
意識させる必要があります。
お説教でとか
「登校刺激」ではなく
伝え方もありますので
ピンときた方は個別にご相談下さい。
回復期の家での過ごし方が
最もコツのいるところです。
「4」再活動期
本人の意識が登校にむいて
行動を始める時期です。
「登校」と「勉強のリカバリー」
「友達関係のリカバリー」が
課題になることが多いです。
焦らずに、自信をつけながら
進めていきます。
親も子どもの回復に合わせて
関わり方や家での過ごさせ方を
変えることが必要ですね
はい、「いつまでも好きなように過ごさせる」のは
ケガでいつまでもギブスを外さず
リハビリもしない、のと
とても似たような状態です。
しっかり自分で動けるようになるには
リハビリは不可欠です。
「優しさ」と「甘やかし」の決定的な違いとは
「子どもを大切に思うからこそ
何も言わずに見守っている」
愛情からだと、とてもよく分かります。
ただ、本当の優しさってどんなものでしょうか?
 「親の優しさ」は
「親の優しさ」は
子どもが幸せな社会的自立ができるように
今必要なことを適切にサポートすることです。
甘やかし:子どもの要求をそのまま受け入れ続ける
優しさ:子どもの成長に必要な適切な枠組みを提供する
例えば、回復期で
夜ふかしで朝起きられない子どもに対して:
**甘やかしの対応**
「起きたい時に起きればいいよ」
→ 生活リズムがさらに乱れて
ツケは子どもの身体・心・頭に生じる
**優しさの対応**
「朝起きるのは辛いと思うけど、一緒に少しずつリズムを整えよう」
→ 子どもに、朝起きることが重要だという
意識と理解を持たせて
協力することも伝える
→子どもの成長につながる
 子どもは不調な時ほど
子どもは不調な時ほど
今やっていることや状況を変えるのを
嫌がることが多いです。
ただ「子どもが嫌がるから」と
親が放置すれば
それはそのままになります。
伝え方にも子どもの個性や状況に合わせて
たくさんのコツがあります。
コミュニケーションにはコツがあるのです。
そんなコツを使ったことで
「あの時は反発したけど
ママに頑張ってもらって
本当に良かった」
となることは多いです 🙂
二度とない思春期という時間を大切に!
どう考えていけばよいのかが
とてもよくわかりました!
今までは「子どもに好きなように過ごさせる」のが
本当に良いのかどうか、を
ずっと考えていました。
でも、ケガからの回復と
似たようなステップを踏んでいけばいいんだ!
と分かって
とてもすっきりしました 🙂
人間は身体・心・頭のすべてで
バランスをとって生きています。
そして一時不調になっても
そこから回復する力があります。
その回復力が十分に発揮できるように
サポートするのが
周りの大人のお役目です。
不登校をわけのわからない特別な状態と
捉える必要はないんです
私が何とかしなくちゃ!と
いっぱいいっぱいになってたところもありました 🙂
ポイントを押さえていけば
子どもの力でより強い状態にもなれるんだ!
と思うと心も軽くなります。
また、個別の具体的な対応をご相談させてください。
なるべく貴重な思春期を楽しめる状態に
早くなってほしいです
♡♡あとがき♡♡
 「子どもにストレスを与えないように」と言われても
「子どもにストレスを与えないように」と言われても
いつまで、どうなったら、どう変えるのか
などの情報がないと
「ずっと、ストレスを与えてはいけないんだ」と
思ってしまうのも自然です。
特に20年くらい前には
子どもたちの身体の力が今よりも強かったですし
「学校には行くものだ」という概念が
良し悪しに関わらずみんなの当たり前だったのと
個人がスマホやゲーム機を持ってはいなかったなど
環境も今とはかなり違っていました。
その頃には
ショック期と安静期の期間が短くて済んだり
回復期に遊びに走ってしまうことも
少なかった状況でした。
 そして、子どもの気持ちというか気分が
そして、子どもの気持ちというか気分が
今のように大切だと
思われていることもなかったですし
子どもの個性も今ほど
はっきり表れてはいませんでした。
なので、「好きなようにさせている」と言っても
実際の不登校の子の家での過ごし方は
今とはずいぶん違っていました。
時代とともに
子どもの身体・心・頭の状態も
環境も変わってきています。
なので、不登校の家での過ごし方で
注意した方がいいポイントが
以前と同じではなくなっているのが現実です。
もし不登校になったばかりならば
ショック期のクリアポイントから押さえていけば
とてもスムーズに回復します。
 また、すでに長い期間の不登校でも
また、すでに長い期間の不登校でも
抜けている部分を埋めていけば
子どもが不登校前よりも
ずっと良い状態になることもできます。
もちろん、長い時間をかけてできた状態なので
そこからの流れを逆にするには
時間と手間はかかります。
それでもいつからでも、どんな状態からでも
”その子の生きる力を引き出す”ことはできるんです。
もし難しいな、と思ったら
当カレッジにご相談ください。
思春期最幸家族講座では
「現状把握」
「今の適切な目標設定」
「専門的で具体的なサポート」
があります。
不登校の数は増える一方ですが
その子たちが
前よりもずっといい状態で
その後の日常を楽しめるようになったら
世界もずっと輝くと思っています。
(^^)/
あわせて読みたい記事:
不登校と「甘やかしすぎ」の関係:要注意なのは不登校になってから!チェックリスト付き
「安全基地」の誤解!知らずに不登校や発達をこじらせていませんか