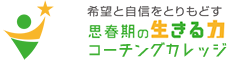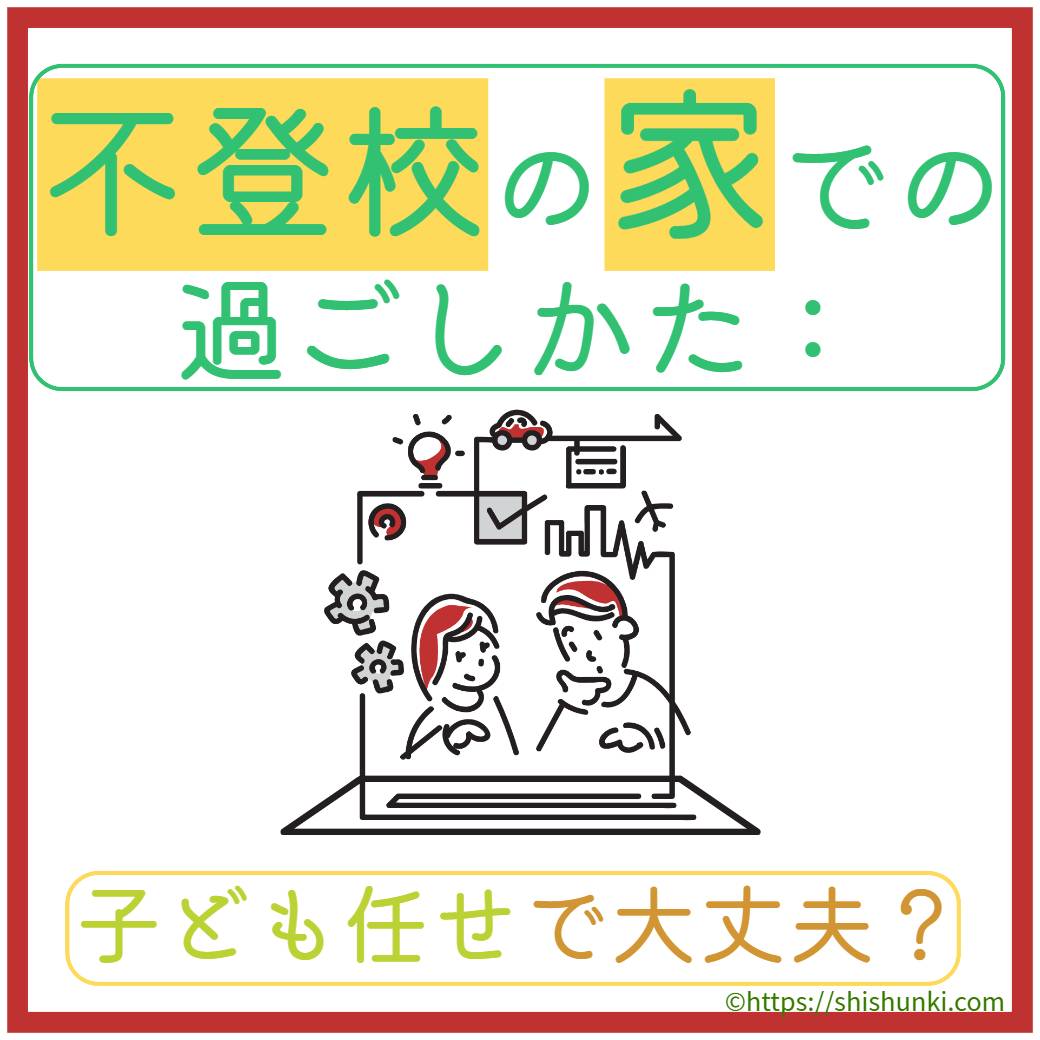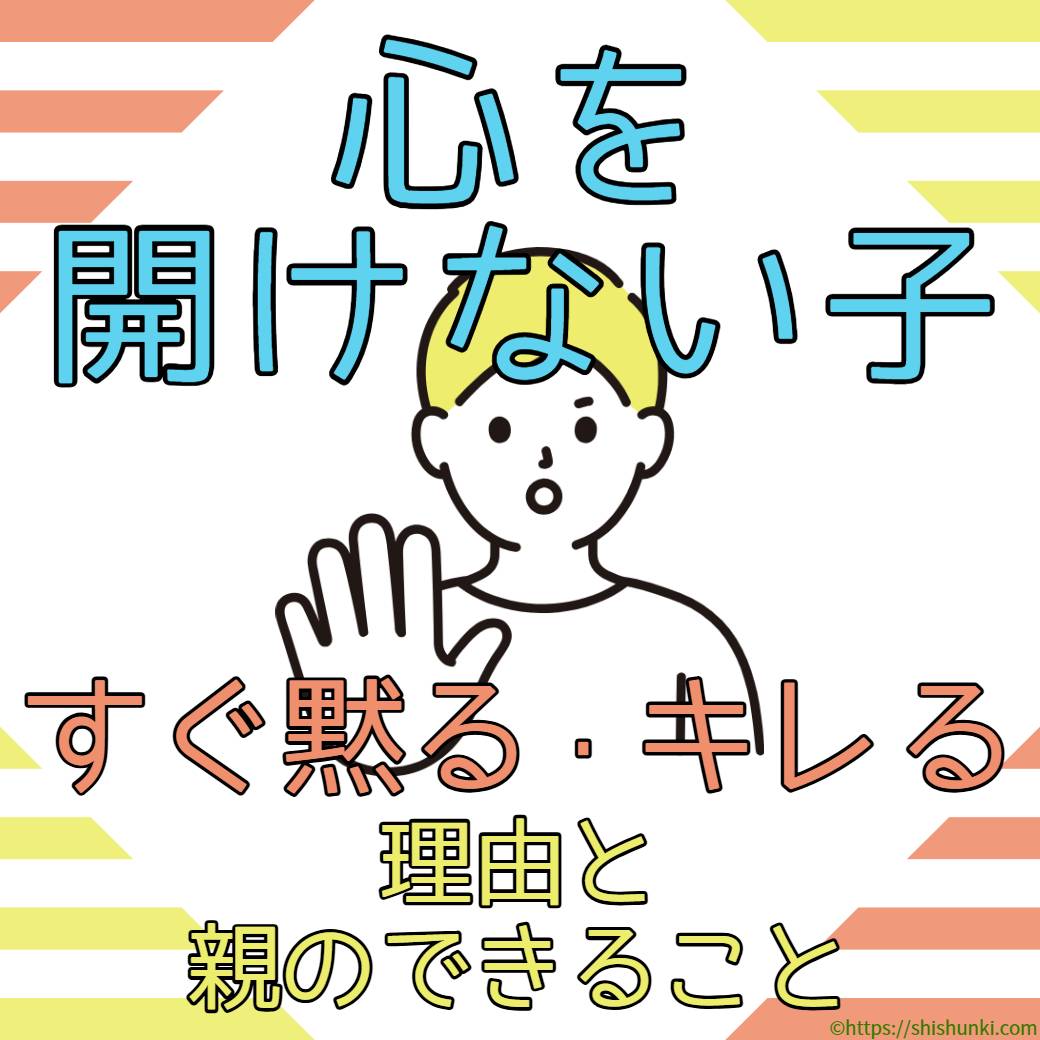「話が長い」と子どもに言われたら!起きていることと改善のコツ
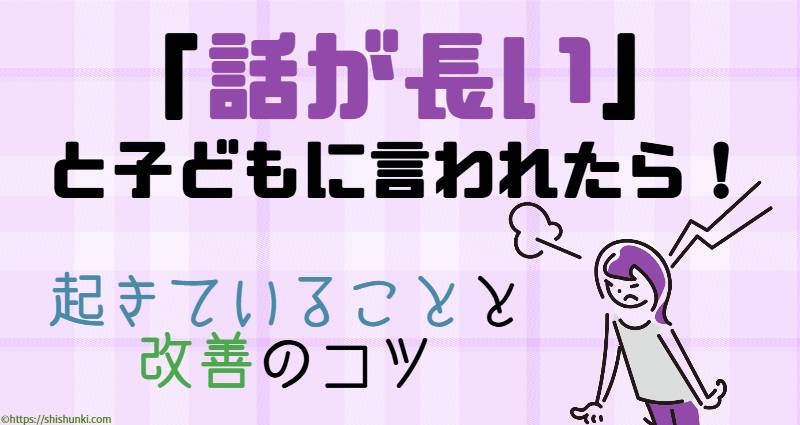
「話が長い!」と子どもに言われたことはありませんか?
そんな時には
「せっかく話しているのに、ちゃんと聞かれてない」
「子どもとコミュニケーションが取れない」と
がっかりしちゃいます。。。
ただ、そのピンチはチャンスに変えることができるんです!
ちゃんと分かってもらいたい!と
つい、たくさん話してしまうんです。
でも直そうと思っても
どこに気を付けて、どうすればいいのかもわからなくて
また繰り返しになってしまいます 😐
伝えようとたくさん話している時に
話の内容ではなくて
「伝え方」にダメ出しされると
伝わらないもどかしさもありますし
なにより、子どもの心が閉じたように感じてしまいますね。
でも、どうしたらいいのかもわからないので
このままうまくコミュニケーションできずに
親子関係が希薄になるのではないかと心配です。
自立の前の思春期には
親子で心が通じ合ったり
進路などの大事な話がしっかりできるといいですよね。
子どもから「話が長い」と言われる時には
話している親の理由と
子どもの理由の両方が考えられます。
そして理由は一つではなく
複数が原因になっていることもあります。
では一緒にそれぞれの内容と
できることを見てみましょう
目次
なぜ思春期の子どもは「親の話が長い」と思うのか。その理由と対応
思春期の子どもが親の話を長い、と言う時には
子どもがわのワケとして以下のような理由が考えられます。
それぞれの理由と対策がありますので
ピンときたところをご覧ください
思春期の子どもが「親の話が長い」と言いたくなる理由
 思春期になると
思春期になると
順調な自立に向けての発達として
自分が納得しないと行動しない傾向が出てきます。
小さい頃は
理由を説明されずに
ただ行動だけ指示されても
親の言うとおりに動くことが多いです。
これは小さい頃は
親の力が圧倒的に強いのと
自分の気持ちや考えを
自分でも言葉にして掴むことが
まだあまりできないからです。
思春期には自分の気持ちや考えに
敏感になってきますので
ただの行動指示には反発するようなるのも自然です。
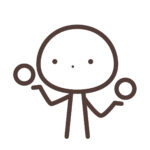 自分で「なぜこれが自分に必要か」を
自分で「なぜこれが自分に必要か」を
判断する力は育てたいですね。
ただ、ここで大事なのは
理由を親が一方的に長く説明しようとしないことです。
必要な行動について
「なぜこれがあなたに必要だと思う?」と
子ども自身に考えさせる質問をするのがおすすめです。
子どもが自分で考えることで
その理由に納得すればやるでしょうし
納得っできない時には
なぜ納得でき居ないのかも分かります。
納得できない点を話し合うこともできるので
無駄な「話が長い」で会話が終わることもなくなります。
 思春期にはまだ脳の前頭葉という部分が発達途中です。
思春期にはまだ脳の前頭葉という部分が発達途中です。
この前頭葉は
☆自分の感情をひとまず脇に置いて
物事を客観的に捉える力
☆情報や出来事の全体像を捉える力
を司ります。
なので、まだこの発達が途中だと
★感情的にイラッとしたら抑えられない
★情報量が多いと
全体として何が言いたいのかを分かりにくくなる
傾向があります。
 大人も幼稚園児には
大人も幼稚園児には
だらだらと長い話はしないですよね
無意識で、短い言葉で会話を繰り返しているはずです。
子どもが思春期になると
身体も大人びて
本人も「いっぱしの大人」のような言動をするので
つい勘違いしてしまいますが
彼ら彼女らはまだ「大人」ではないのです。
それを時々思い出すと
思春期の子育てもちょっと楽になりますのでおすすめです 🙂
思春期は
ホルモンバランスの影響で
感情的になりやすい時期です。
 また自分の考えや感情を尊重されたい気持ちも強くなります。
また自分の考えや感情を尊重されたい気持ちも強くなります。
一方親子関係は距離が近いので
どうしてもお互いに
「ご自宅用コミュニケーション」になりがちです。
自分の感情や思いを
他人ならオブラートに包んで表現するところを
ストレートに表現してしまうことも多くなります。
そこで子どもは親の話の内容よりも
親の圧や感情、言い回しなどに先に反応しやすくなります。
カチンときたら
そこからの話は耳に入ってこないので
だらだら続く音になります。
それで「話が長い」になってしまうこともよくあります。
 日々の家庭での会話で
日々の家庭での会話で
いつも落ち着く必要はないですが
子どもに何かを伝えたい
行動や考えを変えてもらいたい時には
大人が感情的にならないことが
とても役立ちます。
人の心身の状態はいつでも同じではなく
その時によって変化しています。
イライラしてた利、身体が重い時もあれば
なんだかウキウキしてたり
身も心も軽い時もあるものです。
そしてその時の心身の状態によって
同じことでも受け止め方屋感じ方が違ってきます。
 思春期には特にホルモンバランスの影響もあり
思春期には特にホルモンバランスの影響もあり
この心身の状態が変わりやすいです。
部活や塾で疲れている時
なにかで悩んでいる時などは
心身の状態はあまり良くはありません。
そういう時には集中力も落ちますので
長い話を聞くのは辛いものです。
子どもの機嫌をとるのではなく
相手の状態に注意を向けることで
お互いに良いコミュニケーションができますね。
ただ、そのイライラや落ちこみ
疲れている、集中力がなくなっている状態が
あまり回復せずに
数日間続くのであれば
 それは「慢性状態」なので
それは「慢性状態」なので
何かサポートが必要かどうかを
なるべく早めに判断する必要があります。
思春期は成長期で
ホルモンバランスも乱れやすく
睡眠・栄養。生活リズムの乱れも起きやすいです。
また、勉強や人間関係、部活、
容姿などで評価判断されて
成長を常に求められる時期でもあります。
心身の状態が良ければ
そのストレスを成長の糧にできますが
心身の状態が悪いと
そのストレスを乗り越えられない状態にもなります。
 そのような状態が続く場合には
そのような状態が続く場合には
自然治癒力(ホメオスタシス)が
うまく作用し切れていないのかもしれません。
そんな時にはサポートが必要です。
ただ回復を待っているだけだと
徐々に落ち込んだり乱れたりが
加速することがあるからです。
まずは身体の状態からチェックして
乱れがあるようならば
そこから整えるのがおすすめです。
睡眠不足、栄養不足、生活リズムが乱れていると
自分の自然治癒力(ホメオスタシス)が
ちゃんと働くことができません。
 判断や改善方法で迷ったら
判断や改善方法で迷ったら
思春期最幸家族講座や個人セッションでご相談ください。
必ずぴった利のサポートが分かります。
数十年前に流行った楽曲を聴いたことはありますか
きっと「なんだかテンポがゆっくり」だと
感じたのではないでしょうか
そうなんです。
デジタルの普及とともに
私たちの生活のテンポはとても速くなっています。
 それは便利で一面もありますが
それは便利で一面もありますが
同時に「待てない人」が増えている環境要因でもあります。
ボタンを押せば楽しい時間を無限にくれる
SNSでメッセージを送れば即レスが当たり前
動画さえ10分も見つづけるのが辛い
常にそんな状態に慣れていると
「すぐに相手が期待通りに反応する」
「簡単に分かる」
のが当たり前になっていることがあります。
今の大人たちよりも
子どもたちはずっと小さい頃から
そんな「当たり前」で日々を送っています。
 ☆じっくり相手の話を聞く
☆じっくり相手の話を聞く
☆変化を追って傾向をつかむ
☆時間をかけて育てる
のがめんどくさい
待てない人が増えています。
その傾向が強い場合には
その子が待てるぎりぎりのペースで
短い言葉をゆっくり話すと良いでしょう。
速いペースは速さを加速します。
ゆっくりペースは逆に落ち着かせます。
ただ、その子のペースよりも
あまりにも離れていると
ついて来れなくなりますので
その子のペースより
ややゆっくりと、落ち着いた声で話すのが効果的です!
 人が何かの情報を受け取るときには
人が何かの情報を受け取るときには
五感を使います。
五感は見る、聞く、触る、匂う、味わうですね。
会話では「聞く」、そして「見る」を主に使います。
「聞く」は音が順番に耳に入ってきます。
そしてその音は
録音でもしない限り残りません。
なので相手の話が長いと、
話の全体像をつかむためには
その始まりの頃の話を
ずっと覚えていないとなりません。
 この長い話の内容を覚えておく力が
この長い話の内容を覚えておく力が
個性の違いで強い子もいれば
あまり得意ではない子もいます。
大人でも違いがあります。
最近はこの続く言葉を
大量に覚える力が弱い子が増えています。
そうタイプの子は
話が長くなると
もう、何を話されているのか分からなくなることがあるのです。
このような場合に
「話が長い」と言われることがあるのです。
ただ、「話が長い」と言ってくれるうちは
まだ良いのかもしれません。
 わかりにくくて困るのは
わかりにくくて困るのは
①話全体がわらかないので
分かった部分の言葉で
印象に残ったものだけに反応する。
②説明されても分からないので
「結局==すればいいんだよね」
という理解だけになる。
の二つです。
①は話途中の
「あなたがーーーと言ったとき」などの
部分だけにこだわって
「ーーーなんて言ってない。
どうして作り話をするんだ」などと
怒ったり、黙ってそこだけため込んだりします。
 本当に言いたいことから
本当に言いたいことから
話がそれたり
子どもの記憶に残ることはありません。
②は「してほしい行動」を
その場ではとったとしても
その理由や必要性は伝わってないので
他の場面では全くやらない、と言うことが起こります。
ただ「これをやればいいんでしょ」
と思っているだけなので
応用が利かないために
似たような場面でもやりません 😯
実はこのタイプは少なくはありません。
 ただ、情報処理の特性からだとは
ただ、情報処理の特性からだとは
理解されにくいので
「ちゃんと伝えたのにやらない」
「わざとやらないのでは?」
と取られて
人間関係で誤解を生みやすい傾向があります。
もったいないですね。
もし当てはまってるかも?と思ったら
一度お子さんの情報の受け取り方を
チェックしてみるのがおすすめです。
そして伝えたいことは短い言葉で。
さらにその理由は本人に考えて言葉にさせるのがおすすめです。
ちゃんと理解できているかが分かります。
 そしてお子さんの情報の受け取り方と
そしてお子さんの情報の受け取り方と
効果的な対応のコツを使って
お子さんを成長させたい方は
講座や個人セッションをご活用ください。
身体・心・頭へのアプローチが有効です。
いろいろあるんですね
うちは1)2)3)と6)もありそうです
なぜ親の話は長いと感じさせてしまうのか:その理由と対応
次は親の方の理由と対策を見てみましょう
ピンと来たところをお読みください。
「話が長い」と子ども言われる親の理由
 子どもになぜそれが必要なのかを
子どもになぜそれが必要なのかを
理解させるためには
なるべく詳しく説明しなくては
という思いが強いと
話が長くなりがちです。
ただ、大人の仕事現場でも
「要件は短く。説明は順番に」
と言われるように
結論と理由を一緒に長く話されると
大人でも情報の整理にエネルギーをさかれます。
思春期の子どもには
子どもの理由1)2)がありますし
4)~6)があれば
長い話はより子どもに負担になります。
伝わりやすい話し方のコツは
後ほどまとめてお伝えします。
 「前にも言ったのに 👿 」
「前にも言ったのに 👿 」
「これくらい考えればわかるはず」
などと思うと
その怒りのエネルギーのままの口調で
しゃべってしまいがちです。
そうなると子どもの理由3)、
子どもは「言われた内容」よりも
先に「言い方」の方に反発してしまいます。
そして反発して感情的になると
もう、言ってることの内容は
あまり入っていかなくなります。
さらにその子どもの態度にムカッとして
また親も怒りが・・というパターンになると
本当に伝えたかったことではなく
「なんで素直に聞かないんだろう」
「なんでいつも圧をかけてくるんだろう」
しかお互いに残らなくなってしまいます。
もったいないですね 😐
 そういう場合にはどうしたらいいでしょうか?
そういう場合にはどうしたらいいでしょうか?
親だって子どもにイラっとして
つい責めたくなることもありますよね。
ただ、言葉や口調は
言った方はあまり意識していませんし
その後も自分で覚えてないのですが
怒りに任せると
本心からでない言葉も口から出やすくなります。
そして言われた方は
それを結構覚えているものです。
心に傷となって残ることさえあります。
なので、
「今は穏やかには話せない」と思ったら
その時にはすぐに言葉を発しないことです。
2,3回深呼吸をしたり
「これから何を伝えて
子どもにどうなって欲しいんだっけ?」
と思い出したりして
 一度落ち着いてから話すのがおすすめです。
一度落ち着いてから話すのがおすすめです。
すぐに治まらないようならば
「今落ち着けないから
あとで話すね」でOKです。
頭にきたら強く言いたくなりますけど
ひどいこと言い合いたいわけじゃないので。。
「黙る」なら何とかできそう!
今度からやってみます!
話しているうちに
前にも同じことがあったと思い出して
それについても話始めると
話は長くなる一方です。
話している方は
頭の中で関連が分かっていますが
子どもはますます趣旨が分からなくなる一方です。
そして頭の中では
「なんで今それを持ち出すの?」で
いっぱいになります。
親の言いたいことから
どんどん子どもの思考がずれていきます。
もったいないですね 😐
 一つのテーマ、一つの場面に絞って
一つのテーマ、一つの場面に絞って
話した方が
本当に言いたいことが伝わります。
ちゃんと説明しようとして
出来事を起きた順番に話す癖がある人もいます。
そうなると話が長くなって
どこに要点があるのかが
大人が聞いていても分かりにくくなります。
まずは、本当に伝えたい要点だけ
一文で先に伝えるのがおすすめです。
そうすれば相手は
「ああ、この話はこの説明なんだ」
と分かるので聞きやすくなります。
5)事実と自分の解釈を混ぜて話すなど、思いついたままに話す癖
 事実の話の中に
事実の話の中に
自分の想像や解釈を混ぜて話す癖があると
話は長くなりますし
聞いている方はかなり混乱してしまいます。
例えば
「またファイルを忘れたの?
いつもボケっとしているからでしょ」。
そう言われたら
「確かにファイルを忘れたけど
いつもボケっとしているとか
決めつけられたくない。
学校での様子は見てないでしょ」
などと、そこに子どもは反発してしまいます。
要らないひとことを
言いたくなる気持ちは
ものすご~く分かりますが
ご自宅用コミュニケーションにはご注意です。
そのままぶつけやすいです。
そうですね。
他人にはちゃんとオブラートに包んで伝えることを
どの親御さんもされているんです。
でも、わが子だと
包まずにそのまま渡しちゃう。
それがご自宅用コミュニケーションです。
そうなんです。
いつでもきっちり包装する必要はないですが
わが子だからと
自分の感情や思い付きを
なんでもぶつけていいわけでもないですね。
言われた思春期の子の方には
表向きは平気なように見えても
「いつもボケっとしている」
という単語が頭に残ってしまうこともあるのでご注意です。
「話が長い」と言われるのを放置すると・・
子どもに「話が長い」と言われたら
 ★本当に言いたいことが伝わらなかった
★本当に言いたいことが伝わらなかった
という、むなしさや無力感
★拒絶された感じ
がありますが
コミュニケーションがうまく行かないことが続いて
★子どもが心を閉ざす
★信頼関係が失われる
★大事な時にも相談してくれなくなる
は、最も避けたいところです。
思春期には進路選択という
親子で考えるべき機会が何度かあります。
まだ前頭葉が発達途中で
社会経験がない子どもが
情報不足で選択を間違ってしまうのは
とても残念なことです。
「子どもの気持ちを尊重する」のと
「子ども任せにする」のは違いますね。
 また、思春期の子どもには
また、思春期の子どもには
他にもいろいろな悩みがあるものです。
人間関係や恋愛、部活や習い事
もちろん成績についても。
自分なりに乗り越えることで
子どもは成長するのですが
時には乗り越えるために
少しサポートが必要なこともあります。
我慢強い頑張り屋さんほど
一人で何とかしよう、としますが
その見極めを間違うと
不登校や鬱になってしまうこともあります。
思春期の子どもは本来は柔軟で
ストレスに対応しながら成長します。
しかし、一定以上のストレスを受けると
急激にガクッとなることは
ホルモンの研究からも分かっています。
 そうなる前に
そうなる前に
親子コミュニケーションで
子どもの状態や思いを把握できるといいですね。
さらに、親子コミュニケーションが
うまく行けば
子どもへの愛情も伝わりやすくなります。
家の外で孤独を感じても
「自分には安全基地がある」と思えます。
それはとても大きなことです。
悩んでいる時に実際に相談しやすくなりますし
相談しなくても
心のよりどころになるのは確実です。
そして、子どもに悩みがあると分かった時には
親御さんが子どもの課題を
直接解決できなくてもよいのです。
むしろ第三者の専門家につなぐ方が
子どもが本心を話して
心や頭を整理できたり
専門家の視点から別の良い道を得ることもできます。
 ただ、お子さんの状態や変化を
ただ、お子さんの状態や変化を
一番見つけられるのはやはり親御さんです。
日々の中で短時間でも見て、聞いて、話すことで
子どもの状態をチェックする
そしてお互いの心がつながる♡
親子コミュニケーションは
ちょっとしたコツで
スムーズになります。
親子コミュニケーションが大事なんですね~
子どもに伝わりやすい話し方のコツ
ここでは、伝えたいことがある時の
親子コミュニケーションのコツを
ご紹介します。
 始めに、自分が落ち着いているかをチェックします。
始めに、自分が落ち着いているかをチェックします。
落ち着いていないならば
深呼吸したり水を飲むなどして
心身の状態を落ち着かせます。
これで無駄な感情バトルにはならずに済みます。
そして次に子どもの心身の状態をチェックします。
深いところは
ちゃんと観察や会話をしてみないと
分かりませんが
明らかにイライラしていたり
落ち込んでいる時には
まずそちらを落ち着かせたり
様子を見ます。
これで、相手の状態が悪いために
最初から拒絶モードになられるリスクが減ります。
今「どうなって欲しいので
何を伝えたいのか」を絞ります。
 ここがぼやけていると
ここがぼやけていると
途中から子どもの態度に
簡単に感情的になったり
本筋とは関係ないことを話し始めて
話が長くなって結局聞いてもらえないことが起こります。
雑談なら構わないのですが
伝えたいことがある場合には
一度思い出しておくと迷子にならずに済みます。
話しかける時には何でもいいので
子どもに「YES」を出します。
例えば
「今日は早く起きれてよかったね」とか
「最近部活頑張ってるね」でもOKです。
何も思いつかなければ
「今ちょっといい?」と
子どもにYESを言ってもらうのもアリです。
 YESが言える関係では
YESが言える関係では
意見が対立することがあっても
無駄なケンカにはなりません。
もしちょっとしたYESでも
言うのに抵抗があるならば
すでに対立的になっている状態です。
次に、決めたテーマについて
「こうしなさい」といきなりいうのではなく
「~~~について、どう思ってる?」などと
子どもの注意をそこに向けて
それについての言い分や思いを聞きます。
「まだ分かってないだ」
「また忘れてる!」
と決めつける前に聞いてみると
子どもなりの理由もあったりします。
 また、子どもも
また、子どもも
「今やろうと思ってた」も言いやすくなります。
いきなり「~~しなさい」と言ってしまうと
「今やろうと思ってたのに
言われてやる気なくなった」となるパターンは多いです。
また、自分が聞かれたことは
実際に答えなくても
子どもの頭の中では
「あ、忘れてた」とか
「やった方がいいよね」などと
考えが走ります。
親の方が
「これやりなさい
あなたにとって必要でしょう。
なぜなら~~~~~~」と
長く話しても
言われた方には
その内容はあまり伝わりません。
 「はいはい、やればいいんでしょ、やれば」
「はいはい、やればいいんでしょ、やれば」
になってしまう確率がとても高いのです 😯
子どもの考えや思いを聞くことで
初めてその内容が
その子にとって自分ごとになります。
伝えなくちゃ、
分からせなくちゃと
長々と説明していました。
本人に言わせることが大事なんですね
そうなんです 🙂
本人の言い分を聞くことは
ちゃんと尊重していることでもあります。
お互いの関係が良いものになる
一つのコツです。
そして話す時の1フレーズは短くするのが鉄則です。
子どもの理由での
今時の思春期の特徴1)2)5)がありますので
とにかく短く、伝えることは
1フレーズで1つにします。
 それ以上しゃべらないと気が済まない場合には
それ以上しゃべらないと気が済まない場合には
親御さんの方が興奮しているか
話す量がいつも多すぎる癖があるかです。
どうしてもその癖を変えられない場合には
一度ご自分が子どもに
伝えたいことを話している時に
スマホで録音しておくのもおすすめです。
あとからご自分が
「中立な聞き手」になって聞いてみると
分かりやすいかどうかを実感できます。
それをイメージしただけで
これからは気を付けられそうです 🙂
「話が長い」と言われていた3つの改善事例
事例1:
Aさんはもともと、言葉数が多い方でした。
そして一人っ子のB君はとてもおっとり
マイペースだったので
小さいころから
Aさんはあれこれと行動指示も多かったとのことです。
B君が思春期になってからは
いくらAさんが何度も何度も話しても
小さい頃のようには言うことを聞かず
マイペースに過ごしてばかりだ、というご相談でした。
詳しく伺ってみると
B君には
Aさんの情報量が多すぎて
(多くのことについて話していて
かつ、どれも話が長かったので)
 B君が話すことはほとんどなく
B君が話すことはほとんどなく
「話が長くてわからない」と言うくらいでした。
そしてその時には
「結局●●しろっていうことことでしょ」
としかB君の頭には残っていませんでした。
B君も思春期なので
行動指示されるのは嫌ですし
あれもこれも言われるので
自分がコントロールされているとしか
思えていなかったのです。
そして数多くのことを言われるので
どれから先にやればいいのかとか
何が一番重要なのかも
分からない状態にだったのです。
このケースでは
最初にお母さんの伝え方から
バージョンアップしていきました。
 始めは言葉を少なくすることが
始めは言葉を少なくすることが
難しかったAさんでしたが
徐々にできるようになってきて
B君の反応も良くなってきました。
もともと仲の良い親子なので
現在はとても良い会話ができるようになっています 🙂
事例2:
Cさんは高学歴のお母さんです。
Dちゃんに分かってもらおうと
「例えばなし」として
いつも自分の体験談を話していました。
しかしDちゃんも思春期になってからは
「今とは環境も違うのに」と思ったり
「どうせ私はお母さんのようにできませんよ」と
劣等感を持つようになってしまったのです。
「話が長いよ」というのが精いっぱいの抵抗でした。
 良かれと自分の体験談を話していたCさんは
良かれと自分の体験談を話していたCさんは
最初はショックでしたが
たとえ話には
その子の身近な体験からの方が
ずっとわかりやすいと
セッションを経て実感されました。
それからはとても
親子コミュニケーションも良好で
Dちゃんも自信がついてきました。
事例3:
Eさんはよく気が付くので
心配性なところがありました。
そこでF君が小さいころから
「▽▽になったら大変なのよ。
だからそうらないように
先に●●しなさいね。
絶対にちゃんとやるのよ」
という話を長々としていました。
 転ばぬ先の親心だったのですが
転ばぬ先の親心だったのですが
幼いF君には
避けるべき未来の大変さが
十分にイメージできないのと
「だから●●しなさい」がどう結びつくのか
話が長すぎてわかっていませんでした。
そんな状態でずっと来たので
F君は怖がりの指示待ち傾向が強くなっていたのです。
Eさんはそのお悩みのもとが
自分のコミュニケーションパターンからだとは
全く思っていなかったので驚きました。
もちろん、その要因は
Eさんのコミュニケーションの仕方だけでなく
F君の方にもあったので
二人ともバージョンアップのセッションをしていきました
それから1年たちましたが
今ではEさんの心配性も改善して
F君は生徒会長に立候補するくらい
リーダー力を発揮できるようになっています。
いろんな事例があるんですね
どの事例も
お子さんが思春期のうちに改善できて
良かったですね~
コミュニケーションの癖と
その影響は
案外気づきにくいです。
でも気づいて新しい癖に
バージョンアップすれば
とても良い結果につながります!
終わりに
コミュニケーションがしずらいと
感じることが増えてました。
「話が長い」と言われた時には
このまま離れていくのが自然なのかな?と
思いながらも不安でした。
今日は、「話が長い」と子どもが言う時には
親子それぞれに理由があって
私の方でも改善できることが
具体的に見つかってとても嬉しいです!
どんなお困りでも
たった一つだけの理由で
できあがってることはほぼありません。
いくつかの理由のなかから
早く改善した方がいいことや
影響が大きいものから扱っていくと
他の理由もなくなってしまうこともよくあります。
今日から私のコミュニケーションパターンを
バージョンアップします。
やってみて起きたことをまた
ご報告、ご相談させてください
♡♡あとがき♡♡
同じことを伝えようと思っても
伝え方次第で
相手の反応や
関係性が大きく変わることがあります。
親の話が長いのもその一例です。
家族のコミュニケーションを
難しく考える必要はないですが
特に子どもが思春期になると
押さえておいた方が良いコツはあります。
小さい頃は親の方が
圧倒的に強い立場なので
 コミュニケーションの仕方が
コミュニケーションの仕方が
あまり適切でなくても
子どもは親の言う通りに動くことが多いです。
でも思春期になってくると
そこに反発するのが
ある意味成長している証でもあります。
アジア、日本では
子どもは家のもので
親の言うことは聞くものという
傾向が長くあったので
親世代もその前の親世代も
威圧的に言われて終わりという
パターンで育ってきた方の方が
ずっと多いのです。
ただ、今ネットや移動技術の発達で
いろんな文化や意見が
どんどん交じり合っている状況になっています。
小さいころからたくさんの情報に
常に触れている子どもたちは
以前の思春期の子供たちのように
「大人しく」はなくなっています。
親が一方的に何かを言って
その責任をずっと取り続けるスタイルから
(そしていつまでも子どものことは親の責任)
とても早く変わり続ける社会で
幸せに生きるには
個人の力が必要になってきています。
その流れが良いのか、悪いのかは
断言できませんが
その流れに上手に乗りつつも
良い方向に変えるために
役立つことはしたいと思っています。
 未来が誰にとっても
未来が誰にとっても
もっと自分の幸せを感じられるものになるように♡
(^^)/
あわせて読みたい記事:
死人テスト」で親子コミュニケーションをバージョンアップしよう!
家族コミュニケーションを、思春期にバージョンアップしてますか?