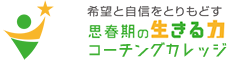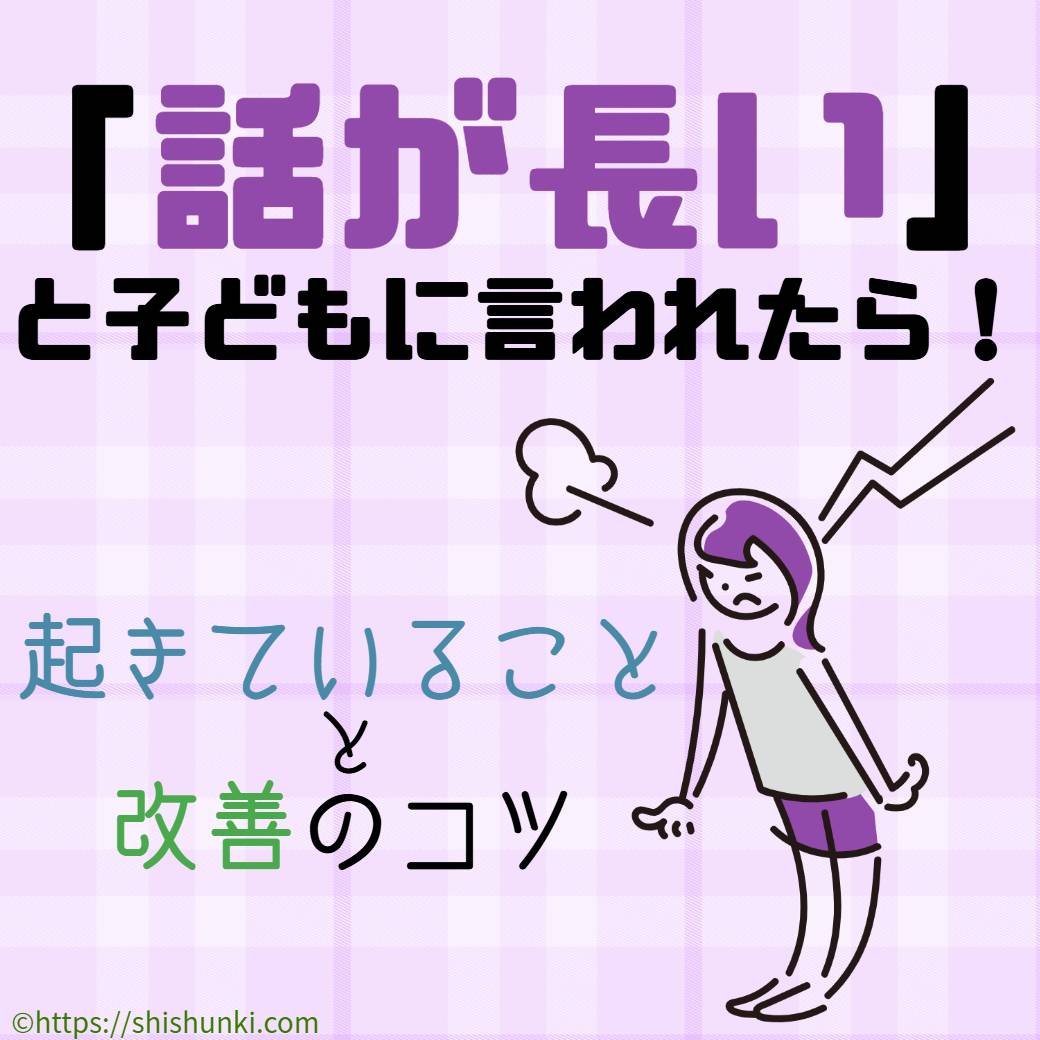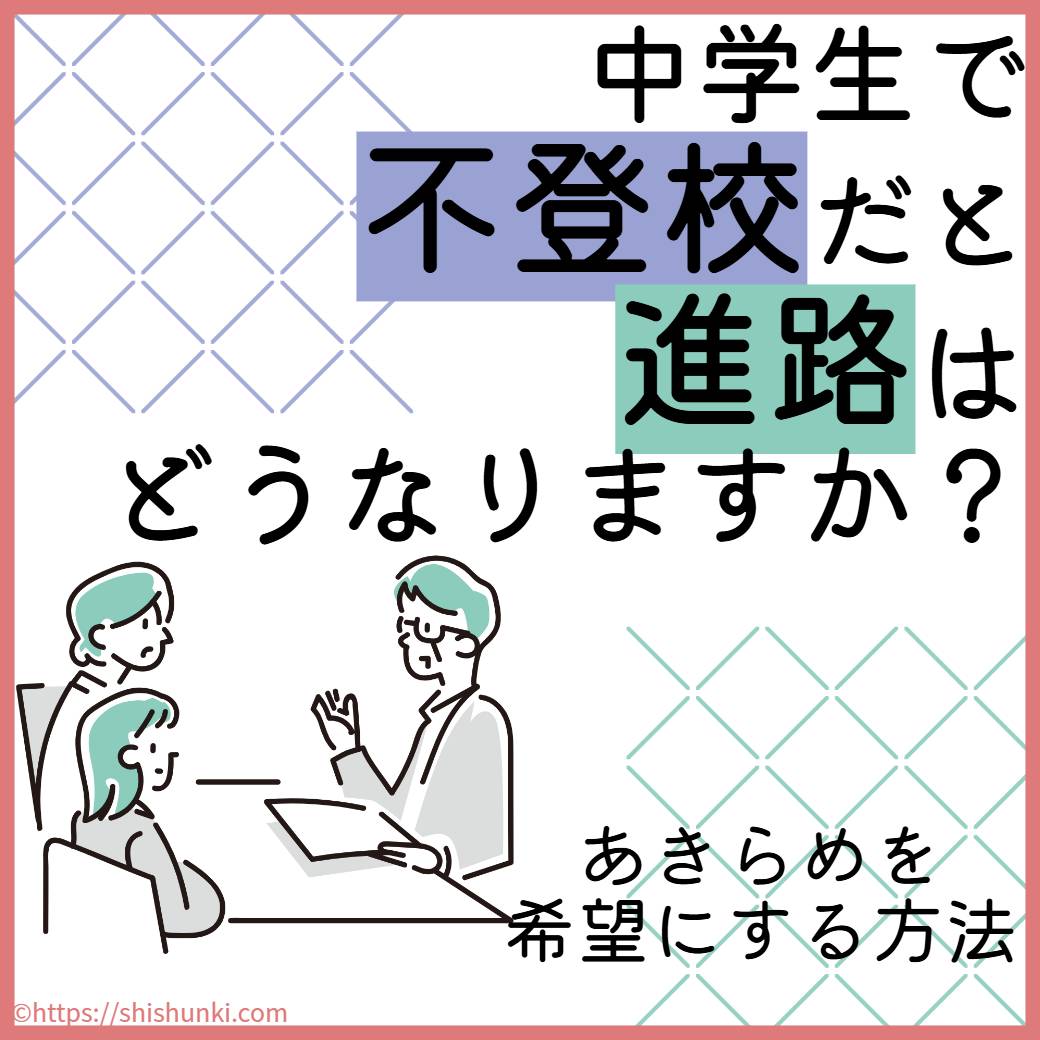心を開けない子:すぐ黙る・キレる理由と親のできること
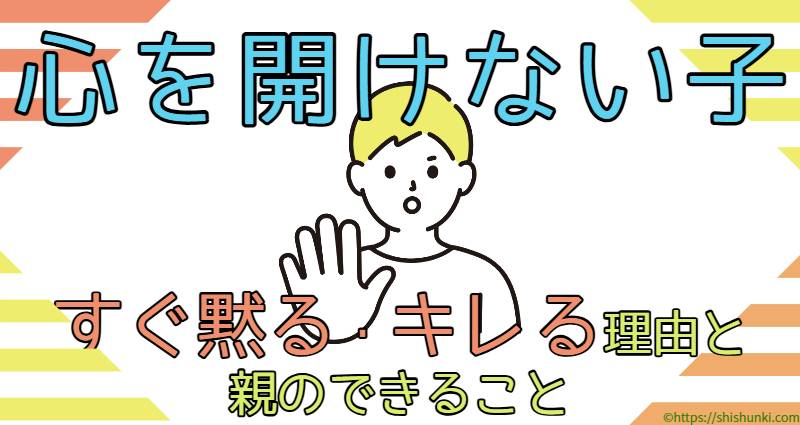
心を開けなくて
話しかけてもすぐに黙ったり
キレてしまう子には
どのような対応をしていますか?
「思春期だからしょうがない」
「そのうち落ち着くんじゃない?」
と放置していると
子どもの未来に思わぬ影響がでることもあるのでご注意です。
小さい頃は、学校の話も楽しそうに話してくれてたんです。
でも思春期になってからは急に口数が減りました。
こちらから話しかけても
「別に」「普通」「うん」といった短い返事でそっけないんです。
そうなんですね。
思春期になると話さなくなる子も結構いますね。
ただ、しばらく落ち込んでいる時や
この先の受験については
もっとちゃんと話したいんです。
話し合うことで
子どもの視野や可能性を
広げたいと思っています。
そうですね。
思春期は
「一人で頑張りたい」という自立心が
強くなる時期ですが
それが行き過ぎると
一人で抱えこんで苦しくなることもありますね。
うちの子は根がまじめなだけに
狭い視野で考えすぎないかが心配です。
でもなかなか心を開いてくれないので
どう関わったらいいのかわからなくて困っています。
思春期で日常の会話が減ったくらいだと
大きな問題ではないでしょう。
ただ、深刻な悩みや進路についての話にも
心を開けなくなっているのは心配ですね。
そして今、同じように
「子どもが心を開けなくなっている」状態として
お母さん・お父さんが話しかけても
すぐにキレて話にならない・・
というパターンも多いんです。
すぐにキレるのもダンマリみたいに
心を閉ざしているとも言えますね 😯
そうなんです。
子どもが親子の会話で
心を開けない状態になっている場合にも
そこには必ず理由があります。
その理由を紐解いていけば
改善すべきなのかの判断もできますね 🙂
ではご一緒に
その理由と親のできることを見てみましょう。
「子どもが心を開けない」──“思春期だから”で片づけていませんか?
コミュニケーションは
複数の人間の間の「やりとり」です。
そこでは必ず「情報のやり取り」と
「感情のやり取り」の両方があります。
コミュニケーションをすることで
相手の事情や考え、思いなどが伝わるので
お互いに理解しあったり
心が通じ合う、信頼できる関係性になります。
ところが、片方が心を開けないと
そのコミュニケーションができなくなります。
 そうなると親子関係に溝ができてしまいます。
そうなると親子関係に溝ができてしまいます。
もともと思春期には親離れのために
子どもが距離を開こうとして
会話が少なくなる傾向はありますが
深刻な悩みや進路選択・受験についてなど
子どもの将来にも影響することについても
親子でコミュニケーションがとれないのは
改善が必要な状態と言えます。
深刻な悩みや進路選択・受験は
子どもの課題ですが
親には「監督責任」や
「経済支援責任」もありますので
共通の課題になります。
また、思春期の子どもは
まだ実体験・経験の数も少ないですし
情報リテラシーも
脳の前頭葉も発達途中です。
 前頭葉は客観的に、長期的に
前頭葉は客観的に、長期的に
状況を分析して決定する部分です。
ここがまだ発達途中だと
思い込みや「こうしたい!」だけで
視野が狭く衝動的に行動してしまうことも起こります 😯
そして今は情報が玉石混合で溢れています。
情報リテラシー
情報の取り方と分析の仕方次第で
重要な案件ではその後が大きく変わってしまいます。
イマドキの子ども達はSNSや動画などで
簡単な情報を集めるのは得意ですが
まだその裏にある意図や
信憑性までをチェックする力は
十分には育ってはいないものです。
実際に志望校選択や受験について
子どもに直接セッションをしていると
情報の取り方や読み方が
とても浅いままになっていることも多いです。
そしてそれらを改善していくと
始めとはずいぶん違う選択になって
その子がぐんと成長することはよくあります。
進路選択をしちゃうのはもったいないですね。
そうなんです。
悩み相談?もネットには溢れていますが
本当に自分の状況に適切なものなのかの
判断は簡単ではないですね。
もちろん、子どもの課題なので
子ども自身が考えて
納得して最終決定をすることは重要なのですが
大事な案件ほど
その決定までの過程にサポートが必要になります。
そして、親子関係は子どもが自立するまでは
必要な「安全基地」ですから
そこがないと子どもは孤独で不安定になってしまいます。
 家の外に信頼できる相談相手が
家の外に信頼できる相談相手が
いればいいのですが
他にいない場合
特に子どもが不登校の状態だと
子どもは孤独になって
一人でぐるぐる思考に陥ったり
感情のやり場がなくなったりして
どんどん心身のエネルギーを失うことにもつながります。
だれにも自分の思いを伝えなければ
その思いの根っこにある思い込みが
間違っていたとしても
それに気づくことが難しくなるからです。
心を開けない度合いが強い場合には
無理にこじ開けようとすると逆効果ですが
適切な進め方での改善は必要です。
子どもの未来に直結している問題なんですね
よくあるNG対応には気を付けて!
まず、よくあるNG対応5つを知っておきましょう。
知れば、すぐにやめられたり
ついやりそうになってもとどまれます。
1) 根掘り葉掘り聞き出そうとする
 話しかけてもちゃんと返事をしないからと
話しかけてもちゃんと返事をしないからと
「学校どうだった?」
「友達とは何話したの?」
「テストの点数は?」——
どれかは答えるんじゃないかとの質問攻めは
子どもにとっては圧迫になってしまいます。
追い詰められたら
子どもはさらに心を閉ざしてしまいます。
やっと話してくれた!と勢いづいて
「だったらこうすればいいじゃない」
とすぐアドバイスしてしまう。。
子どもが始めに求めているのは
解決策ではなく
お母さん・お父さんが
ちゃんと自分の話を聞いてくれるかどうかを
自分で判断したいのです。
子どもの話を最後まで聞ききって
何を子どもが求めているのかを分かってから
それに答えるのがおすすめです。
 話しかけてもろくに答えない
話しかけてもろくに答えない
すぐにキレてくる・・だと
親も感情的になりやすいものです 😐
「なんで話してくれないの!」
「お母さんのこと信頼してないの?」
言いたい気持ちはよく分かるんですが
感情をぶつけてしまと
子どもは対応に困ったり
罪悪感を感じたり
攻撃されたと感じたりで
さらに距離を取るようになってしまいます 😐
ついやってしまうことあります。。
はい、もちろん私もムカッとすることあります 😐
でもその勢いのままを言葉にしないのが最善の策です。
感情がこみあげきた時には
一度深呼吸やタイムをとるのがおすすめです。
なんでこの子は・・という思いから
「お兄ちゃんはもっと話してくれたのに」
「○○ちゃんはお母さんとよく相談しているのに」
比較されるのは、思春期の子どもにとって
最も嫌なことの一つです。
 話してほしいがために
話してほしいがために
子どもが不機嫌そうにしていると
欲しいものを買い与えたり
甘やかしたりする。。
これは一時的には子どもの不機嫌が治っても
本質的な信頼関係は築けません。
むしろ、自分が話さなかったり
不機嫌になれば
おいしいことが起きる、という
不適切な学習をさせてしまうことになるので大NGです。
これらの5つのNG対応は、すべて
「親の不安」から来ています。
そしてその不安が
さらに子どもを遠ざけてしまっているのです。
時々やってることありました!
次からは意識してみます
心を開けない子どもの理由
次は、子どもが心を開けなくなっている
子ども側の理由からみてみましょう。
思春期になれば親と距離を置いて
同年代とつながりたい欲求が強くなります。
また「自分で考えて自分で決めたい」
というのも自立に向けての大事な欲求です。
 しかし、まだその欲求だけが強くなっていて
しかし、まだその欲求だけが強くなっていて
時と場合に応じての調節が
うまくできないこともあります。
基本としては
子どもの課題は子どもに任せて
自分で考えてやってみて
その結果から学ばせるのが最善です。
しかし、子どもの手に余る深刻な問題や
進路選択などの重要案件は
子どもが一人だけでは
適切な解決方法を見つけられないこともあるので
親がサポートすることも必要になります。
子どもにはなぜ親が決定前に
知る必要があるのかを伝えたのちに
まず子どもの思いや考えを聞きます。
そこで良いところをしっかりほめた後に
改善できる箇所があることを
一緒に考えていきます。
このような手順で
子どもがちゃんと反応するならば
それは大きな問題はない状態です 🙂
 もし、この手順でも
もし、この手順でも
ミュニケーションが進まない場合には
以下の要因が考えられます。
★親への反発が強くなっている
=親子関係がこじれている
★親子コミュニケーションが不適切パターンになっている
=
お互いの意見を対等に出して
それを踏まえての会話のやりとりがある状態になっていない。
★過干渉
★別の要因がある
(親子それぞれの心身のエネルギー不足など)
それぞれ、「子どもの要因」
2)感情優先状態、3)言語力、4)心身のエネルギー不足参照と
「親の要因」をチェックしてみてください。
 思春期には性ホルモンの働きで
思春期には性ホルモンの働きで
感情が強く揺れ動きます。
そして一方それを監督する
脳の前頭葉は発達途中です。
そのために
その時の「好き」「嫌い」で
重要な物事を判断することがあるので
そこにはチェックが必要です。
視野が狭い、経験不足
情報不足と解読不足もありますので
「もう思春期なのに」ではなく
「まだ思春期だから」と
おおらかな気持ちでサポートしていきます。
しかし、それでもうまく行かない場合には
★すでに親子関係がこじれていたり
 ★お互いにすぐに感情的になってしまっていたり
★お互いにすぐに感情的になってしまっていたり
★親子の心身のエネルギー状態が悪い
などの要因があるのでチェックします。
子どもが黙り込む、すぐにキレる場合には
言葉の力がまだ十分に育っていないこともあります。
思春期の10~15歳の間の一時期に
頭の中にあることを
パッと言葉にするのが苦手になる時期があります。
これは世界中で実験されていることですが
特に男子で起こりやすいんです。
(女子でもあります)
知っているはずの単語や言葉が
すらすら出てこないことがあるのです。
脳の発達の仕方の特徴からくるものだと言われています。
 外からはわからないのですが
外からはわからないのですが
本人としてはもどかしいですね。
そこでせかされると
イライラしたり、黙り込んだりしがちになりがちです。
そして加えて思春期には
自分の感情や考え、そして人間関係も複雑になります。
それをまとめて
分かりやすい順番で話す、というのは
それなりに力のいることです。
話が前後したり
まとまっていなくても
気にしないタイプの子はいいのですが
完璧主義、まじめな子は
「ちゃんと話さないと分かってもらえない」
という思いがあるので
「ちゃんと話せない」と思うと
黙り込んだり
「うるさい」「めんどくさい」とキレることがあるのです。
 このような場合には
このような場合には
子どもが答えやすいように
シンプルな答えやすい質問から順番にしていくと
安心して、だんだんたくさん話してくれるようになります。
当カレッジの個人セッションでは
「うちの子は話さないかもしれません」
と言われていたお子さんでも
いっぱい話してくれるのは
そんなヒミツがあるからです 😉
また、子ども(大人でも)によっては
自分の欲求には正直でも
自分の気持ちや身体の感覚
(疲れているなど)には
あまり気づけない子もいます。
これは発達の抜けがある状態です。
 そういう子は
そういう子は
日ごろから良くしゃべっているようでも
自分の気持ちや感覚を問われると
混乱して黙ったり
「うるさい」「ほっといて」などと
キレることもあります。
このような場合には
身体へのアプローチが有効です。
少しずつ自分の気持ちや感覚につながれるようになります。
そして逆戻りすることはありません。
また、家族のコミュニケーションパターンとして
誰かが一方的に指示命令して
それを他の人は受け入れる・・という
パターンになっていることがあります。
昔の上司から部下への指示命令みたいです。
そうなると子どもが
それ以外の「お互いやりとりして結論を出す」
というコミュニケーションができない状態になっていることがあります。
 子どもが小さい頃は
子どもが小さい頃は
まだそれでもなんとか表面上は回っていても
子どもが思春期になってくると
子どもにも自分のニーズや意見が出てきます。
そうなると、子どもが
自分のニーズを通そうとするには
キレて主導権を握ろうとするか
それが難しい子は
「どうせ言っても聞いてもらえない」と
だんまりで
相手にダメージを与えることで
主導権を握ろうとすることがあります。
封建的な?コミュニケーションパターンだったり
または
親御さんがとても忙しいご家庭で
起こりやすいパターンです。
このケースでも
コミュニケーションパターンを
お互いに好きなだけのボールを投げあう
千本ノックのようなコミュニケーションではなく
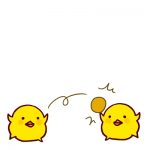 一つのボールでキャッチボールするように
一つのボールでキャッチボールするように
バージョンアップすれば
ちゃんと改善しますのでご安心くださいね 😉
子どもの心身のエネルギーが不足していると
子どもはイライラしたり
疲れて余裕がなかったり
感情的な言動や雰囲気に過敏に反応してしまうことがあります。
言語能力も落ちますし
感情的・反抗的にもなりやすいです。
このような場合には
身体的には
栄養・睡眠・生活リズム・運動
心・頭としては
悩み事(成績やテストなども含む)
に乱れがないかチェックして
必要なサポートをします。
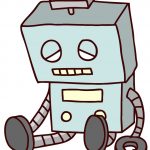 不登校で、家でしっかり休んでも
不登校で、家でしっかり休んでも
数週間で回復しない場合には
身体の乱れが深刻化していることが
ほとんどです。
また、発達の抜けが
小さいころからある場合や
(顕在化している場合も隠れている場合も)
思春期の成長期に見合う
身体・心・頭へのサポートが不足している時にも起こります。
そして当カレッジでは
どの場合でも身体へのサポートで
通常の何倍も速く、完全に回復しますので
ご安心くださいね
もっと単純だと思っていました!
子どもが心を開けなくなる親の理由
次は親御さんの方の理由を見てみましょう
 親ごさんに子どもへの愛情がたっぷりでも
親ごさんに子どもへの愛情がたっぷりでも
それを、その子に伝わるように伝えないと
残念なことに、伝わらない
または逆効果になってしまうこともあります 😐
例えば
★会話がキャッチボールになっていない
(一方的に話す
話が長い
すぐに遮るetc.)
★すぐに~~させよう、でいっぱいいっぱいになっている
(子どもの言い分や状態に合わせる余裕がない)
★良かれとすぐにアドバイスする
(アドバイスを必要としていないことは多い。
または子どもが自分で考えられるように導くことも必要)
★感情的になってしまう
などだと
思春期の子どもは
親子コミュニケーションが嫌になってしまいます。
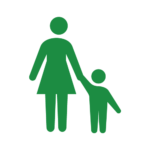 子どもが小さい頃は
子どもが小さい頃は
親の力と立場が圧倒的なので
これらの傾向があっても
表面的にはそこそこうまく行っていることもよくあります。
しかし子どもも思春期になれば
その考えが妥当かどうかは別ですが
自分なりの意見や感情に
気づくようになってきます。
その時に、もし子どもの意見や感情が
誤った情報からのものだとしても
コミュニケーションがうまく行かないと
そこに子どもを気付かせることも難しくなってしまうんです。
意見や感情が
間違った情報をもとにしているかどうかは
かなり子どもとその未来に影響することがあります。
それを放置して
表面的な行動の話ばかりでは
親子関係がこじれるばかりで
もったいないですね。
たくさんあります。
でも私がこれから
コミュニケーションの仕方を
変えられるのか不安です。
はい、もちろん大丈夫です!
コミュニケーションパターンは
ただの「習慣」です。
習慣は、今無意識で楽に
ついやってしまうことです。
なので、その習慣を変えようとする時には
「いつもの」の代わりに
「何をするか」をはっきりさせることが一つ目のポイントです。
そして二つ目は
「気づいたら置き換える」を繰り返すことです。
 誰でも「わかった」から
誰でも「わかった」から
「習慣」になるまでには
うまく行かない期間があります。
でも、それでも新しい行動を
気づいたら繰り返す・・とやっていくと
必ずそれが「新しい習慣」になるんです。
できないとへこんじゃって。。
自分を責めて
次にやる気をなくしがちだったんです。
でもそこを乗り越えれば
ちゃんと新しい方が習慣になるんですね 🙂
そうなんです!
逆上がりや自転車こぎと同じです。
「諦めたら試合終了」ですが
最初はできなくても
何度かやっているうちに
それが自然にできるようになりますよ~
気持ちよく、早く新しい習慣になります
感情との付き合い方って
あまり習うことはありませんね。
日本人は特に
自分の感情は表に出さない方がいいという
文化的な背景もあったので
学校でも家庭でも
「あなたはどう感じてる?」などと
聞かれることは少ないまま育っています。
ただ、感情は行動するためのエネルギーなので
ただ「嫌だ」だけでなく、
 「自分は何をしたいのか」
「自分は何をしたいのか」
「なぜそれをしたいのか」に
気づいていることが大事です。
*自分の本当の気持ちに気づけなかったり
*瞬間的な「嫌だ」に乗っ取られたり
*または我慢を美徳だとして
自分さえ我慢すればうまく行くと思っていたりすると
本当に自分が望む未来には行けなくなってしまいます 😐
逆に、その時だけの感情や気分に
振り回された行動になってしまって
本当に望んでいたこととは
違う結果になって
「こんなはずじゃなかった。。」と
なってしまうことが起きがちです 😐
親子コミュニケーションは
どうしても親子の距離が近いので
自分の感情をそのままぶつけやすいです。
 どんな人でも他人相手だと
どんな人でも他人相手だと
自分の湧きあがった感情に気づいて
それに対応しながらコミュニケーションしているのですが
親子だとそのままぶつけてしまいがちですね 🙄
なので、「できない」のではなくて
子どもにそうする「習慣がない」だけです。
そして子どもに対しては
家族だから失礼なことをしても許される
どうせ親子関係は崩れない
そんな思いがあるからです。
でも、親子でも関係性が
コミュニケーションで崩れることは
実際には珍しくはありません。
特に子どもが思春期になると。
 ご自分の感情を我慢するのではなく
ご自分の感情を我慢するのではなく
「この子とどうなりたいのか」
を思い出して
コミュニケーションができると
自然に伝わりやすいコミュニケーションになります。
どうしても感情が抑えられない時には
タイム、深呼吸がおすすめです
(^_-)
どうしても感情が不安定になる時や
爆発してしまう時には
その裏に
「~~すべき」が隠れていることが多いです。
|~~した方がいいのに」だと
期待はずれな場合には
がっかりしますが
相手を責めるような感情爆発までは
起こりにくいものです。
 ものすごく怒りや不安が強い場合には
ものすごく怒りや不安が強い場合には
「べき」が隠れていることが多いです。
そんな時には一度
「べきなのかどうか」を
チェックしてみるのもおすすめです。
「べき」があれば
それは「なぜべきなのか」を探っていくと
本当に求めているものにたどり着けます。
意外とそれが、大人でも
昔ご自分の親御さんに言われたことを
そのまま「べき」だと思っていたというケースも多いです。
ご自分だけで難しい場合には
もちろんコーチもお手伝いいたします💛
(個人セッション可能)
思春期になると親子の距離感を
親の方が意識して
徐々に離していくことも必要になります。
 ただ、この「徐々に」が
ただ、この「徐々に」が
個体差と状況によるのが難しいところですね。
基本的には
人間の子どもには
親離れの本能がありますが
親の方には子離れの本能がないのが
すれ違いが起きやすい理由でもあります。
人間は成長するのに
時間と手間がかかります。
動物のように
衣食住だけこなせれば
幸せに社会生活が送れるわけじゃないのが
もう一つの理由です。
いっぱしの大人ぶることもあるので
どこまで親が介入すればいいのかが
一番迷います。
そうですね。
子どもの身体・心・頭が
安定している状態ならば
「見守る」のが基本です。
ただ、それが乱れた状態が続くかどうかを
チェックし続けるのは忘れずに。
大人も忙しいので
直接手がかかることが減ってくると
つい、目も外しがちですが
毎日の変化チェックは大事です。
 あれ?と思う状況があって
あれ?と思う状況があって
今サポートが必要かどうか迷ったら
早めに専門家に相談するのがおすすめです。
楽に早く、確実にサポートができます。
こじらせてしまわないことが大事です。
実は意外と多いのが
親御さんの心身のエネルギー不足です。
そもそもエネルギー不足は
徐々に深刻化していくので
気づきにくいのです。
また、大人は子どもよりも
意志の力や
仕事などの他者が関わる
強制力が強いタスクがあるので
根性でぎりぎりまで
頑張ってしまうところもあります。
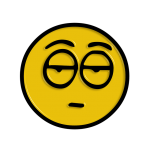 ただでさえ、思春期の子どもを持つ
ただでさえ、思春期の子どもを持つ
日本のお母さんの平均睡眠時間は
世界で最も短いと言われています。
子どもやほかの家族の調子悪ければ
そのケアも加わってきます。
お母さんはお疲れになっていることがほとんどなのです。。
人は心身のエネルギーが低下すると
身体も思い通りに動かなかったり
気持ちもイライラしたり不安定になりがちで
思考もまとまらないことさえあります。
子どもに余裕をもって
関わらない状態になっていることがあるんです。
なので当カレッジでは
まずお母さんの心身のエネルギー状態も上げていきます。
お子さんに余裕をもってかかわれる状態になることは
とても大事です。
 今でも十分頑張っている人は
今でも十分頑張っている人は
「もっとこうした方がいい」と分かっても
身体がついてこないこともあります。
気分が焦って待てないこともあります。
でもご自分の心身に余裕が出れば
子どもの考えや行動、成長を
ちゃんと待つこともできるようになるんです。
家族で笑顔になる早道です 🙂
心を開けない子どもの事例紹介
Aさん(仮名)の中学2年生の娘さんは
1年以上家族とほとんど口をきかない状態でした。
学校から帰ると部屋にこもり
食事の時も無言。
進路のことを聞いても
「別に」「どうでもいい」という返事ばかり。
Aさんは
このまま高校受験を迎えることへの不安で
押しつぶされそうでした。
 そんなAさんが
そんなAさんが
身体・心・頭へのアプローチを
学んで実践し始められました。
最初は大きな変化が起きてないように思われました。
でも、Aさんの身体が元気になり
コミュニケーションのコツを使ってみたり
自分の「べき」を問い直したりするうちに
Aさん自身の不安や焦りが
徐々に落ち着いているのを
感じるようになっていました。
そんなご自分に気づいたころに
娘さんの方から
「お母さん、あのね」とリビングに来て
話すようになったのです!
最初はとても短かった会話ですが
徐々に娘さんの話が長くなっていきました。
 始めは押し活のような
始めは押し活のような
個人的な話だけでしたが
やがて学校でのできごとや
将来やってみたいこと
高校選びについての不安などについても
話題に上がるようになっていきました。
その後、一緒に高校のオープンキャンパスに行ったり
高校情報を一緒に整理したりして
最終的には娘さんが
自分の意志で進路を決めることができました。
今ではとても楽しく高校生活を送っています。
『始めは思春期だからどうしようもない、
と思っていましたが
私にもできることが分かったので
そこから道が開けた感じです。
 今は本音を聞いても
今は本音を聞いても
ちゃんと答えてくれる関係になれたのが
とても嬉しいです。』
終わりに
思春期だからと諦めそうになっていました。
でもそのままにしておくのは
やっぱり子どもの将来に
大きく響くことがあると分かりました。
そして、自分ができることも
いろいろ見つかったので
まずそこから始めようと思います。
いろいろあると分かったので
私も落ち着くことができました。
次はやってみた結果をご報告して
さらに先に進みたいです
♡♡あとがき♡♡
一見同じ言葉で表現される状態でも
サポートが必要な場合もあれば
もう少し見守っていて
子どもの力で解決できるようにする場合もあります。
 子育てをしていると
子育てをしていると
その見分けが難しいと感じることも多いですね。
今何をすればいいのか分かると
すっと動けて
状況が改善することはよくあります。
大事なのは
今どこに何が必要なのかを
具体的に見極めるところです。
とても有名な話があります。
工場の重要な機械が故障して専門家が呼ばれました。
彼はネジを一本回すだけで直したのですが
その工場の管理者が
「たった一本のネジでなぜこんなに高いのか」と尋ねました。
その技術者は
「ネジを回す作業は1ドル
どのネジを回せばよいかを見抜く知識と経験が9999ドル」
と説明したそうです。
 当カレッジのブログでは
当カレッジのブログでは
なるべく多くの方に届くように
「どのネジを回せばよいかを見抜く知識」を
当カレッジの経験に基づいてお伝えしています。
ぜひ、ご活用ください。
そしてより個別な状況に合わせて
より詳しく知りたい時には
思春期最幸家族講座や
個人セッションもご活用いただけます。
また、ご自分がサポートしたい方には
思春期コーチ™養成講座もあります。
思春期の子育てでは
知っておくといい情報がたくさんあります。
みんなで笑顔をどんどん増やしていきましょう
(^^)/
あわせて読みたい記事:
「死人テスト」で親子コミュニケーションをバージョンアップしよう!
ストレスで頭が真っ白⁉黙り込む、キレる原因と、親が今すぐできる対策